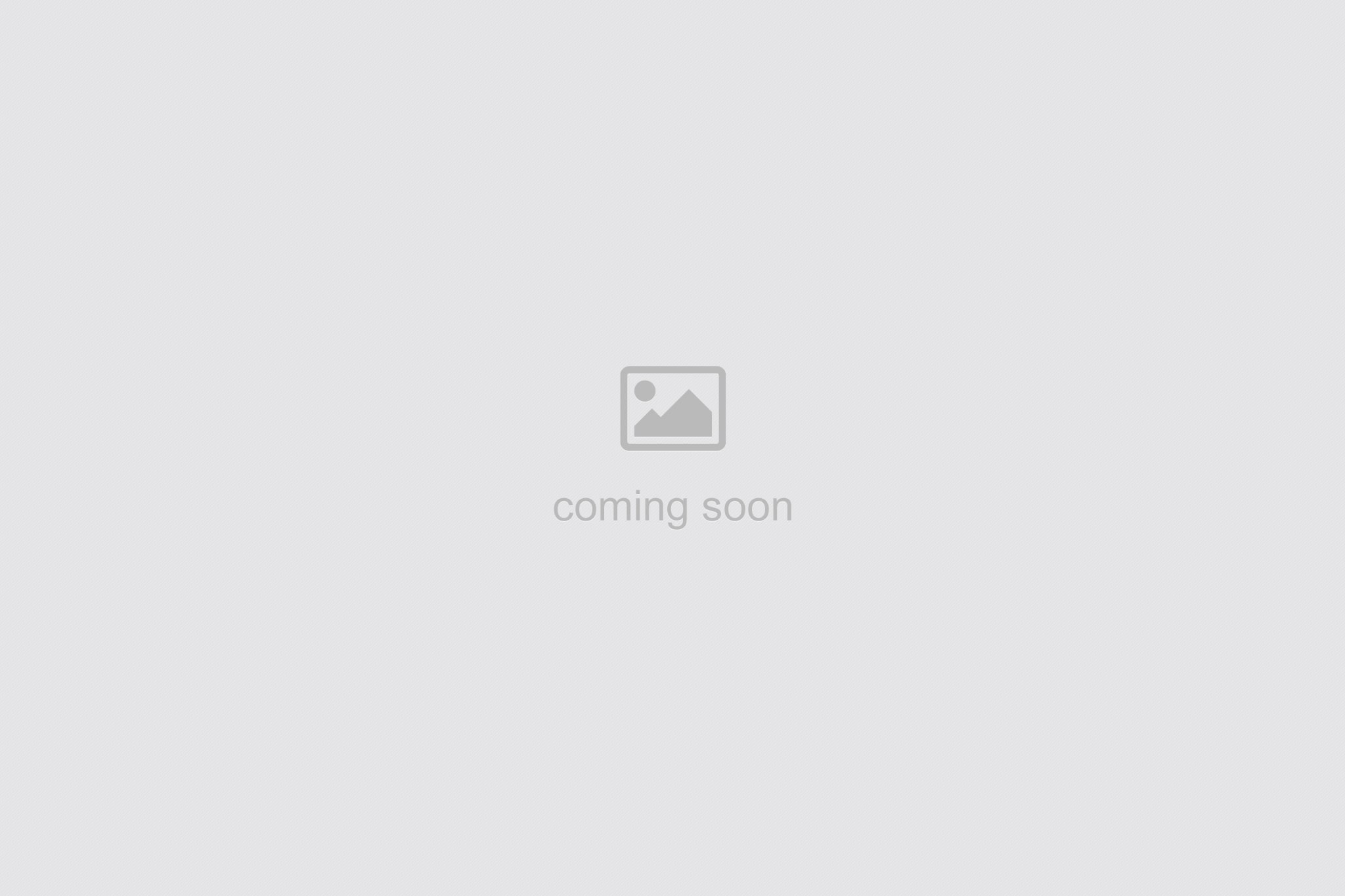短歌大会のご案内
本居宣長顕彰短歌大会について
松阪の生んだ偉大な国学者・本居宣長(1730~1801)は、広く日本の古典を研究し、人と歌との密接な関わりを明らかにし、歌を詠むことは、人の心を理解する上で最も大事なことだと考えました。何より、宣長にとって歌を詠むことは、大きな楽しみでもあり、その生涯に詠んだ歌は1万首を数えます。松阪の人にとって宣長は偉大な学者である前に、歌を楽しむごく身近な存在の人でした。
「本居宣長顕彰短歌大会」は、短歌を詠むことで、歌をこよなく愛した宣長の遺徳をしのぶとともに、歌に親しみ、また歌を通して日本の文化に触れていただこうとする行事です。
第69回本居宣長顕彰短歌大会開催要領
1.日 時 | 令和6年11月16日(土)13:00~ |
2.会 場 | 松阪市産業振興センター3F研修ホール(松阪市本町2176) |
3.当日運営 | 大会当日の参加は、事前予約が必要です。(大会当日参加予約申込は令和6年10月31日まで)入選者・投稿者を優先し、定員になり次第締め切ります。 |
4.主 催 | 本居宣長記念館 (後援 : 松阪市 松阪市教育委員会 三重県歌人クラブ 松阪短歌会 中日新聞社 夕刊三重新聞社 松阪ケーブルテレビ・ステーション) |
5.応募作品 | 一人二首まで(作品は返却しません) 未発表・自作で作者本人の投稿に限ります。 また二重投稿はお断りします。 |
6.応募方法 | 松阪市内の公民館、三重県内図書館等に設置してある所定の投稿用紙を使用してください。(コピー可) または、記念館ホームページの短歌大会チラシの裏面を印刷して使用してください。 投稿用紙には、住所、氏名、年齢、電話番号を必ず明記してください。 ホームページの投稿フォームに入力して応募することもできます。 メールでの投稿も受け付けます。メール本文に必要な項目を入力して送信してください。(件名は「短歌大会投稿」としてください) ※ホームページやメールでの投稿料の送金は、下記「11.送金方法」のゆうちょ口座を利用してください。投稿後一週間以内に入金が確認できなければ、投稿は無効となります。 |
7.提出先 問合せ | 〒515-0073 三重県松阪市殿町1536-7 本居宣長記念館 短歌大会係 TEL 0598-21-0312 Eメール info@norinagakinenkan.com |
8.募集期間 | 一 般 令和6年7月1日(月)~9月16日(月) 小中高生 令和6年7月1日(月)~9月10日(火) ※当日消印有効、休館日に直接お持込みは出来ません。 |
9.選 者 (講師) | 栗木京子(くりききょうこ) 先生(1954年名古屋市生まれ) 現代歌人協会理事長、歌誌「塔」選者、読売新聞、西日本新聞の歌壇選者。2013年「水仙の章」で斎藤茂吉短歌文学賞、2018年「ランプの精」で毎日芸術賞 |
10.投 稿 料 | 一首 1,000円(一人二首まで)。 ※小中高生無料 |
11.送金方法 | 1.ゆうちょ銀行を利用(手数料はご負担ください) ① 定額小為替(投稿作品に同封) ② ゆうちょ口座間で送金(投稿作品に『ご利用明細書』を同封) ③ 「電信振込み請求書・電信振替請求書」で振込み(投稿作品に『領収書』を同封) 口座番号 12250-6562341 公益財団法人鈴屋遺蹟保存会 ザイ)スズノヤイセキホゾンカイ 2.現金書留(投稿作品を同封) 3.現金(投稿作品とともに持参) |
12.各 賞 | 宣長賞3首 賞状・副賞 入選30首 賞状・記念品 |
13.作品集 | 応募作品すべてを掲載した作品集を、投稿者一人につき一冊進呈。 ただし、小中高校生で学校単位にてお申込みの場合は、1クラスにつき1冊の進呈。 学校単位以外の投稿者で大会当日不参加の方へは、大会終了後に一人一冊送付。 その他ご希望の方へは一冊300円で販売。 |
短歌大会の投稿は締切りました。ありがとうございました。
第69回本居宣長顕彰短歌大会チラシ
|
(5814KB) |
|
(605KB) |
画像をクリックするとPDFファイルが開きます
昨年度大会の様子
会場地図
松阪市産業振興センター
住所 松阪市本町2176
電話 0598-26-5557
【交通】
松阪駅(JR・近鉄) 徒歩12分
バス「松阪市役所」 徒歩3分
伊勢自動車道 松阪インター 12分
バス「松阪市役所」 徒歩3分
伊勢自動車道 松阪インター 12分
宣長学習作品展示会について
~小中学生「宣長学習」作品展示会を開催します~
郷土の偉人学習として松阪市内の学校で行っている社会見学や出前授業の後にまとめた作品の公開展示会を、開催します。
1 展示会の目的
作品展示会を通して「宣長学習」をさらに深め、郷土愛を育み自分の生活に活かすことと、作品の見学を通して、家族のふれあいと市民の記念館への親しみと理解を図るものです。
2 内容
子どもたちが「宣長学習」の事後学習としてまとめた記事や感想などを掲載した壁新聞やタブレット等を、公開展示します。
3 場所 桜松閣(本居宣長旧宅裏)
4 期間 令和6年2月17日(土)~2月24日(土) 9時~16時30分
※19日(月)は休館
5 参加校等
参加校 15校(小学校14校 中学校1校)
作品数 250点(個人作品 204点 班による共同作品 46点)
6 入館料
(1) 桜松閣での展示見学は期間中、一般の方も含めて無料となります。
(2) 作品を応募した学校の全児童・その家族の方は、期間中、本居宣長記念館入館料無料となります。一般の方の記念館入館料は有料となります。
展示の様子