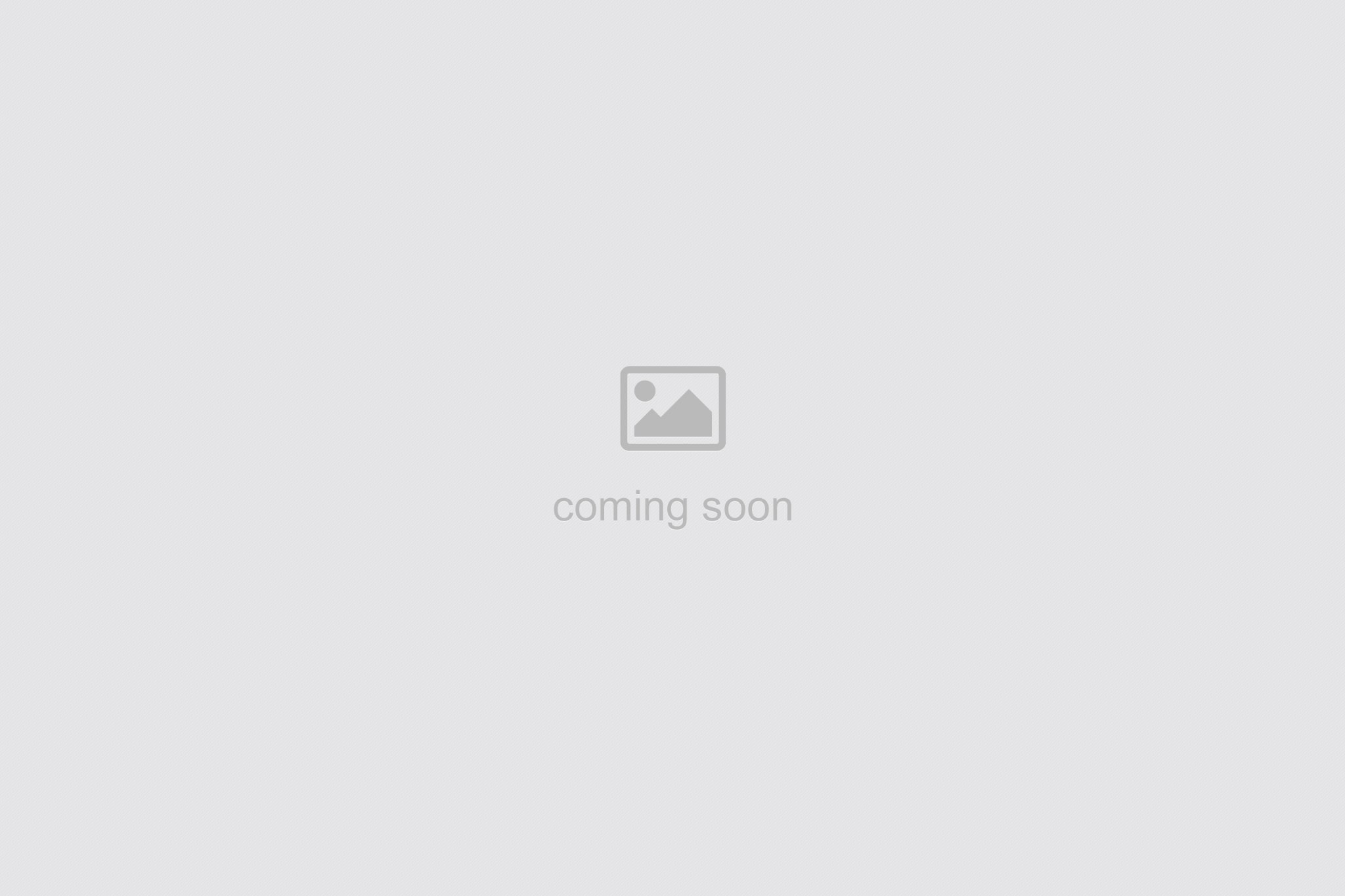『うひ山ぶみ』
歟底本は『本居宣長全集』を使用した。
う ひ 山 ぶ み
<イ>世に物まなびのすぢ、しなじな有て、一トやうならず、そのしなじなをいはば、まづ神代紀をむねとたてて、道をもはらと学ぶ有リ、これを神学といひ、其人を神道者といふ、又官職儀式律令などを、むねとして学ぶあり、又もろもろの故実、装束調度などの事を、むねと学ぶあり、これらを有識の学といふ、又上は六国史其外の古書をはじめ、後世の書共まで、いづれのすぢによるともなくて、まなぶもあり、此すぢの中にも、猶分ていはば、しなじな有べし、又歌の学び有リ、それにも、歌をのみよむと、ふるき歌集物語書などを解キ明らむるとの二タやうあり、大かた件のしなじな有て、おのおの好むすぢによりてまなぶに、又おのおのその学びやうの法も、教ふる師の心々、まなぶ人の心々にて、さまざまあり、かくて学問に心ざして、入そむる人、はじめより、みづから思ひよれるすぢありて、その学びやうも、みづからはからふも有ルを、又さやうにとり分てそれと思ひよれるすぢもなく、まなびやうも、みづから思ひとれるかたなきは、物しり人につきて、いづれのすぢに入てかよからん、又うひ学ビの輩のまなびやうは、いづれの書よりまづ見るべきぞなど、問ヒ求むる、これつねの事なるが、まことに然あるべきことにて、その学のしなを正(タダ)し、まなびやうの法をも正して、ゆくさきよこさまなるあしき方に落チざるやう、又其業のはやく成るべきやう、すべて功多かるべきやうを、はじめよりよくしたゝめて、入らまほしきわざ也、同じく精力を用ひながらも、そのすぢそのまなびやうによりて、得失あるべきこと也、然はあれども、まづかの学のしなじなは、他よりしひて、それをとはいひがたし、大抵みづから思ひよれる方にまかすべき也、いかに初心なればとても、学問にもこゝろざすほどのものは、むげに小児の心のやうにはあらねば、ほどほどにみづから思ひよれるすぢは、必ズあるものなり、又面 々好むかたと、好まぬ方とも有リ、又生れつきて得たる事と、得ぬ事とも有ル物なるを、好まぬ事得ぬ事をしては、同じやうにつとめても、功を得ることすくなし、又いづれのしなにもせよ、学びやうの次第も、一トわたりの理によりて、云々(シカシカ)してよろしと、さして教へんは、やすきことなれども、そのさして教へたるごとくにして、果してよきものならんや、又思ひの外にさてはあしき物ならんや、実にはしりがたきことなれば、これもしひては定めがたきわざにて、実はたゞ其人の心まかせにしてよき也、詮(セン)ずるところ学問は、ただ年月長く倦(ウマ)ずおこたらずして、はげみつとむるぞ肝要にて、学びやうは、いかやうにてもよかるべく、さのみかゝはるまじきこと也、いかほど学びかたよくても、怠(オコタ)りてつとめざれば、功はなし、又人々の才と不才とによりて、其功いたく異なれども、才不才は、生れつきたることなれば、力に及びがたし、されど大抵は、不才なる人といへども、おこたらずつとめだにすれば、それだけの功は有ル物也、又晩学の人も、つとめはげめば、思ひの外功をなすことあり、又暇(イトマ)のなき人も、思ひの外、いとま多き人よりも、功をなすもの也、されば才のともしきや、学ぶことの晩(オソ)きや、暇(イトマ)のなきやによりて、思ひくづをれて、止(ヤム)ることなかれ、とてもかくても、つとめだにすれば、出来るものと心得べし、すべて思ひくづをるゝは、学問に大にきらふ事ぞかし、さてまづ上の件のごとくなれば、まなびのしなも、しひてはいひがたく、学びやうの法も、かならず云々(シカシカ)してよろしとは、定めがたく、又定めざれども、実はくるしからぬ ことなれば、たゞ心にまかすべきわざなれども、さやうにばかりいひては、初心の輩は、取リつきどころなくして、おのづから倦(ウミ)おこたるはしともなることなれば、やむことをえず、今宣長が、かくもやあるべからんと思ひとれるところを、一わたりいふべき也、然れどもその教へかたも、又人の心々なれば、吾はかやうにてよかるべき歟と思へども、さてはわろしと思ふ人も有べきなれば、しひていふにはあらず、たゞ己が教ヘによらんと思はん人のためにいふのみ也、そはまづ<ロ>かのしなじなある学びのすぢすぢ、いづれもいづれも、やむことなきすぢどもにて、明らめしらではかなはざることなれば、いづれをものこさず、学ばまほしきわざなれども、一人の生涯の力を以ては、ことごとくは、其奥までは究(キハ)めがたきわざなれば、其中に主(ムネ)としてよるところを定めて、かならずその奥をきはめつくさんと、はじめより<ハ>志(シ)を高く大にたてて、つとめ学ぶべき也、然して其余のしなじなをも、力の及ばんかぎり、学び明らむべし、さてその<ニ>主(ムネ)としてよるべきすぢは、何れぞといへば、道の学問なり、そもそも此道は、天照大御神の道にして、天皇の天下をしろしめす道、四海万国にゆきわたりたる、まことの道なるが、ひとり皇国に伝はれるを、其道は、いかなるさまの道ぞといふに、<ホ>此道は、古事記書紀の二典(フタミフミ)に記されたる、神代上代の、もろもろの事跡のうへに備はりたり、此ノ二典の上代の巻々を、くりかへしくりかへしよくよみ見るべし、<ヘ>又初学の輩は、宣長が著したる、神代正語を、数十遍よみて、その古語のやうを、口なれしり、又直日のみたま、玉 矛百首、玉くしげ、葛花などやうの物を、入学のはじめより、かの二典と相まじへてよむべし、然せば、二典の事跡に、道の具備(ソナ)はれることも、道の大むねも、大抵に合点ゆくべし、又件の書どもを早くよまば、やまとたましひよく堅固(カタ)まりて、漢意(カラゴコロ)に、おちいらぬ衛(マモリ)にもよかるべき也、道を学ばんと心ざすともがらは、<ト>第一に漢意儒意を、清く濯(スス)ぎ去て、やまと魂(タマシヒ)をかたくする事を、要とすべし、さてかの二典の内につきても、<チ>道をしらんためには、殊に古事記をさきとすべし、<リ>書紀をよむには、大に心得あり、文のまゝに解しては、いたく古への意にたがふこと有て、かならず漢意に落入べし、次に古語拾遺、やゝ後の物にはあれども、二典のたすけとなる事ども多し、早くよむべし、次に万葉集、これは歌の集なれども、道をしるに、甚ダ緊要の書なり、殊によく学ぶべし、その子細は、下に委くいふべし、まづ道をしるべき学びは、大抵上ノ件リの書ども也、然れども書紀より後の、次々の御代々々の事も、しらでは有べからず、其書どもは、続日本紀、次に日本後紀、つぎに続日本後紀、次に文徳実録、次に三代実録也、書紀よりこれまでを合せて<ヌ>六国史といふ、みな朝廷の正史なり、つぎつぎに必ズよむべし、又件の史どもの中に、<ル>御世々々の宣命には、ふるき意詞ののこりたれば、殊に心をつけて見るべし、次に延喜式、姓氏録、和名抄、貞観儀式、出雲国ノ風土記、<ヲ>釈日本紀、令、西宮記、北山抄、さては<ワ>己が古事記ノ伝など、おほかたこれら、<カ>古学の輩の、よく見ではかなはぬ書ども也、然れども初学のほどには、件の書どもを、すみやかに読ミわたすことも、たやすからざれば、巻数多き大部の書共は、しばらく後へまはして、短き書どもより先ヅ見んも、宣しかるべし、其内に延喜式の中の祝詞(ノリト)の巻、又神名帳などは、早く見ではかなはぬ物也、凡て件の書ども、かならずしも次第を定めてよむにも及ばず、たゞ便にまかせて、次第にかゝはらず、これをもかれをも見るべし、又いづれの書をよむとても、<ヨ>初心のほどは、かたはしより文義を解せんとはすべからず、まづ大抵にさらさらと見て、他の書にうつり、これやかれやと読ては、又さきによみたる書へ立かへりつゝ、幾遍(イクヘン)もよむうちには、始メに聞えざりし事も、そろそろと聞ゆるやうになりゆくもの也、さて件の書どもを、数遍よむ間ダには、其外のよむべき書どものことも、学びやうの法なども、段々に自分の料簡の出来るものなれば、<タ>其末の事は、一々さとし教るに及ばず、心にまかせて、力の及ばむかぎり、古きをも後の書をも、<レ>広くも見るべく、又簡約(ツヅマヤカ)にして、さのみ広くはわたらずしても有リぬ べし、さて又<ソ>五十音のとりさばき、かなづかひなど、必ズこゝろがくべきわざ也、<ツ>語釈は緊要にあらず、さて又<ネ>漢籍(カラブミ)をもまじへよむべし、古書どもは、皆漢字漢文を借リて記され、殊に孝徳天皇天智天皇の御世のころよりしてこなたは、万ヅの事、かの国の制によられたるが多ければ、史どもをよむにも、かの国ぶみのやうをも、大抵はしらでは、ゆきとゞきがたき事多ければ也、但しからぶみを見るには、殊にやまとたましひをよくかためおきて見ざれば、かのふみのことよきにまどはさるゝことぞ、此心得肝要也、さて又段々学問に入たちて、事の大すぢも、大抵は合点のゆけるほどにもなりなば、いづれにもあれ、<ナ>古書の注釈を作らんと、早く心がくべし、物の注釈をするは、すべて大に学問のためになること也、さて上にいへるごとく、二典の次には、<ラ>万葉集をよく学ぶべし、<ム>みづからも古風の歌をまなびてよむべし、すべて人は、かならず歌をよむべきものなる内にも、学問をする者は、なほさらよまではかなはぬ わざ也、歌をよまでは、古ヘの世のくはしき意、風雅(ミヤビ)のおもむきはしりがたし、<ウ>万葉の歌の中にても、やすらかに長ケ高く、のびらかなるすがたを、ならひてよむべし、又<ヰ>長歌をもよむべし、さて又歌には、古風後世風、世々のけぢめあることなるが、古学の輩は、古風をまづむねとよむべきことは、いふに及ばず、又<ノ>後世風をも、棄(ステ)ずしてならひよむべし、<オ>後世風の中にも、さまざまよきあしきふりふりあるを、よくえらびてならふべき也、又伊勢源氏その外も、<ク>物語書どもをも、つねに見るべし、すべてみづから歌をもよみ、物がたりぶみなどをも常に見て、<ヤ>いにしへ人の、風雅(ミヤビ)のおもむきをしるは、歌まなびのためは、いふに及ばず、古の道を明らめしる学問にも、いみしくたすけとなるわざなりかし、
上ノ件ところどころ、圏(ワ)の内に、かたかなをもてしるししたるは、いはゆ
る相じるしにて、その件リ々にいへることの、然る子細を、又奥に別にくはしく
論ひさとしたるを、そこはこゝと、たづねとめて、しらしめん料のしるし也、
う ひ 山 ぶ み
<イ>世に物まなびのすぢ、しなじな有て、一トやうならず、そのしなじなをいはば、まづ神代紀をむねとたてて、道をもはらと学ぶ有リ、これを神学といひ、其人を神道者といふ、又官職儀式律令などを、むねとして学ぶあり、又もろもろの故実、装束調度などの事を、むねと学ぶあり、これらを有識の学といふ、又上は六国史其外の古書をはじめ、後世の書共まで、いづれのすぢによるともなくて、まなぶもあり、此すぢの中にも、猶分ていはば、しなじな有べし、又歌の学び有リ、それにも、歌をのみよむと、ふるき歌集物語書などを解キ明らむるとの二タやうあり、大かた件のしなじな有て、おのおの好むすぢによりてまなぶに、又おのおのその学びやうの法も、教ふる師の心々、まなぶ人の心々にて、さまざまあり、かくて学問に心ざして、入そむる人、はじめより、みづから思ひよれるすぢありて、その学びやうも、みづからはからふも有ルを、又さやうにとり分てそれと思ひよれるすぢもなく、まなびやうも、みづから思ひとれるかたなきは、物しり人につきて、いづれのすぢに入てかよからん、又うひ学ビの輩のまなびやうは、いづれの書よりまづ見るべきぞなど、問ヒ求むる、これつねの事なるが、まことに然あるべきことにて、その学のしなを正(タダ)し、まなびやうの法をも正して、ゆくさきよこさまなるあしき方に落チざるやう、又其業のはやく成るべきやう、すべて功多かるべきやうを、はじめよりよくしたゝめて、入らまほしきわざ也、同じく精力を用ひながらも、そのすぢそのまなびやうによりて、得失あるべきこと也、然はあれども、まづかの学のしなじなは、他よりしひて、それをとはいひがたし、大抵みづから思ひよれる方にまかすべき也、いかに初心なればとても、学問にもこゝろざすほどのものは、むげに小児の心のやうにはあらねば、ほどほどにみづから思ひよれるすぢは、必ズあるものなり、又面 々好むかたと、好まぬ方とも有リ、又生れつきて得たる事と、得ぬ事とも有ル物なるを、好まぬ事得ぬ事をしては、同じやうにつとめても、功を得ることすくなし、又いづれのしなにもせよ、学びやうの次第も、一トわたりの理によりて、云々(シカシカ)してよろしと、さして教へんは、やすきことなれども、そのさして教へたるごとくにして、果してよきものならんや、又思ひの外にさてはあしき物ならんや、実にはしりがたきことなれば、これもしひては定めがたきわざにて、実はたゞ其人の心まかせにしてよき也、詮(セン)ずるところ学問は、ただ年月長く倦(ウマ)ずおこたらずして、はげみつとむるぞ肝要にて、学びやうは、いかやうにてもよかるべく、さのみかゝはるまじきこと也、いかほど学びかたよくても、怠(オコタ)りてつとめざれば、功はなし、又人々の才と不才とによりて、其功いたく異なれども、才不才は、生れつきたることなれば、力に及びがたし、されど大抵は、不才なる人といへども、おこたらずつとめだにすれば、それだけの功は有ル物也、又晩学の人も、つとめはげめば、思ひの外功をなすことあり、又暇(イトマ)のなき人も、思ひの外、いとま多き人よりも、功をなすもの也、されば才のともしきや、学ぶことの晩(オソ)きや、暇(イトマ)のなきやによりて、思ひくづをれて、止(ヤム)ることなかれ、とてもかくても、つとめだにすれば、出来るものと心得べし、すべて思ひくづをるゝは、学問に大にきらふ事ぞかし、さてまづ上の件のごとくなれば、まなびのしなも、しひてはいひがたく、学びやうの法も、かならず云々(シカシカ)してよろしとは、定めがたく、又定めざれども、実はくるしからぬ ことなれば、たゞ心にまかすべきわざなれども、さやうにばかりいひては、初心の輩は、取リつきどころなくして、おのづから倦(ウミ)おこたるはしともなることなれば、やむことをえず、今宣長が、かくもやあるべからんと思ひとれるところを、一わたりいふべき也、然れどもその教へかたも、又人の心々なれば、吾はかやうにてよかるべき歟と思へども、さてはわろしと思ふ人も有べきなれば、しひていふにはあらず、たゞ己が教ヘによらんと思はん人のためにいふのみ也、そはまづ<ロ>かのしなじなある学びのすぢすぢ、いづれもいづれも、やむことなきすぢどもにて、明らめしらではかなはざることなれば、いづれをものこさず、学ばまほしきわざなれども、一人の生涯の力を以ては、ことごとくは、其奥までは究(キハ)めがたきわざなれば、其中に主(ムネ)としてよるところを定めて、かならずその奥をきはめつくさんと、はじめより<ハ>志(シ)を高く大にたてて、つとめ学ぶべき也、然して其余のしなじなをも、力の及ばんかぎり、学び明らむべし、さてその<ニ>主(ムネ)としてよるべきすぢは、何れぞといへば、道の学問なり、そもそも此道は、天照大御神の道にして、天皇の天下をしろしめす道、四海万国にゆきわたりたる、まことの道なるが、ひとり皇国に伝はれるを、其道は、いかなるさまの道ぞといふに、<ホ>此道は、古事記書紀の二典(フタミフミ)に記されたる、神代上代の、もろもろの事跡のうへに備はりたり、此ノ二典の上代の巻々を、くりかへしくりかへしよくよみ見るべし、<ヘ>又初学の輩は、宣長が著したる、神代正語を、数十遍よみて、その古語のやうを、口なれしり、又直日のみたま、玉 矛百首、玉くしげ、葛花などやうの物を、入学のはじめより、かの二典と相まじへてよむべし、然せば、二典の事跡に、道の具備(ソナ)はれることも、道の大むねも、大抵に合点ゆくべし、又件の書どもを早くよまば、やまとたましひよく堅固(カタ)まりて、漢意(カラゴコロ)に、おちいらぬ衛(マモリ)にもよかるべき也、道を学ばんと心ざすともがらは、<ト>第一に漢意儒意を、清く濯(スス)ぎ去て、やまと魂(タマシヒ)をかたくする事を、要とすべし、さてかの二典の内につきても、<チ>道をしらんためには、殊に古事記をさきとすべし、<リ>書紀をよむには、大に心得あり、文のまゝに解しては、いたく古への意にたがふこと有て、かならず漢意に落入べし、次に古語拾遺、やゝ後の物にはあれども、二典のたすけとなる事ども多し、早くよむべし、次に万葉集、これは歌の集なれども、道をしるに、甚ダ緊要の書なり、殊によく学ぶべし、その子細は、下に委くいふべし、まづ道をしるべき学びは、大抵上ノ件リの書ども也、然れども書紀より後の、次々の御代々々の事も、しらでは有べからず、其書どもは、続日本紀、次に日本後紀、つぎに続日本後紀、次に文徳実録、次に三代実録也、書紀よりこれまでを合せて<ヌ>六国史といふ、みな朝廷の正史なり、つぎつぎに必ズよむべし、又件の史どもの中に、<ル>御世々々の宣命には、ふるき意詞ののこりたれば、殊に心をつけて見るべし、次に延喜式、姓氏録、和名抄、貞観儀式、出雲国ノ風土記、<ヲ>釈日本紀、令、西宮記、北山抄、さては<ワ>己が古事記ノ伝など、おほかたこれら、<カ>古学の輩の、よく見ではかなはぬ書ども也、然れども初学のほどには、件の書どもを、すみやかに読ミわたすことも、たやすからざれば、巻数多き大部の書共は、しばらく後へまはして、短き書どもより先ヅ見んも、宣しかるべし、其内に延喜式の中の祝詞(ノリト)の巻、又神名帳などは、早く見ではかなはぬ物也、凡て件の書ども、かならずしも次第を定めてよむにも及ばず、たゞ便にまかせて、次第にかゝはらず、これをもかれをも見るべし、又いづれの書をよむとても、<ヨ>初心のほどは、かたはしより文義を解せんとはすべからず、まづ大抵にさらさらと見て、他の書にうつり、これやかれやと読ては、又さきによみたる書へ立かへりつゝ、幾遍(イクヘン)もよむうちには、始メに聞えざりし事も、そろそろと聞ゆるやうになりゆくもの也、さて件の書どもを、数遍よむ間ダには、其外のよむべき書どものことも、学びやうの法なども、段々に自分の料簡の出来るものなれば、<タ>其末の事は、一々さとし教るに及ばず、心にまかせて、力の及ばむかぎり、古きをも後の書をも、<レ>広くも見るべく、又簡約(ツヅマヤカ)にして、さのみ広くはわたらずしても有リぬ べし、さて又<ソ>五十音のとりさばき、かなづかひなど、必ズこゝろがくべきわざ也、<ツ>語釈は緊要にあらず、さて又<ネ>漢籍(カラブミ)をもまじへよむべし、古書どもは、皆漢字漢文を借リて記され、殊に孝徳天皇天智天皇の御世のころよりしてこなたは、万ヅの事、かの国の制によられたるが多ければ、史どもをよむにも、かの国ぶみのやうをも、大抵はしらでは、ゆきとゞきがたき事多ければ也、但しからぶみを見るには、殊にやまとたましひをよくかためおきて見ざれば、かのふみのことよきにまどはさるゝことぞ、此心得肝要也、さて又段々学問に入たちて、事の大すぢも、大抵は合点のゆけるほどにもなりなば、いづれにもあれ、<ナ>古書の注釈を作らんと、早く心がくべし、物の注釈をするは、すべて大に学問のためになること也、さて上にいへるごとく、二典の次には、<ラ>万葉集をよく学ぶべし、<ム>みづからも古風の歌をまなびてよむべし、すべて人は、かならず歌をよむべきものなる内にも、学問をする者は、なほさらよまではかなはぬ わざ也、歌をよまでは、古ヘの世のくはしき意、風雅(ミヤビ)のおもむきはしりがたし、<ウ>万葉の歌の中にても、やすらかに長ケ高く、のびらかなるすがたを、ならひてよむべし、又<ヰ>長歌をもよむべし、さて又歌には、古風後世風、世々のけぢめあることなるが、古学の輩は、古風をまづむねとよむべきことは、いふに及ばず、又<ノ>後世風をも、棄(ステ)ずしてならひよむべし、<オ>後世風の中にも、さまざまよきあしきふりふりあるを、よくえらびてならふべき也、又伊勢源氏その外も、<ク>物語書どもをも、つねに見るべし、すべてみづから歌をもよみ、物がたりぶみなどをも常に見て、<ヤ>いにしへ人の、風雅(ミヤビ)のおもむきをしるは、歌まなびのためは、いふに及ばず、古の道を明らめしる学問にも、いみしくたすけとなるわざなりかし、
上ノ件ところどころ、圏(ワ)の内に、かたかなをもてしるししたるは、いはゆ
る相じるしにて、その件リ々にいへることの、然る子細を、又奥に別にくはしく
論ひさとしたるを、そこはこゝと、たづねとめて、しらしめん料のしるし也、
<イ>世に物まなびのすぢしなじな有て云々、 物学ビとは、皇朝の学問をいふ、そもそもむかしより、たゞ学問とのみいへば、漢学のことなる故に、その学と分むために、皇国の事をば、和学或は国学などいふならひなれども、そはいたくわろきいひざま也、みづからの国のことなれば、皇国の学をこそ、たゞ学問とはいひて、漢学をこそ、分て漢学といふべきことなれ、それももし漢学のこととまじへいひて、まぎるゝところにては、皇朝学などはいひもすべきを、うちまかせてつねに、和学国学などいふは、皇国を外(ヨソ)にしたるいひやう也、もろこし朝鮮於蘭陀などの異国よりこそ、さやうにもいふべきことなれ、みづから吾国のことを、然いふべきよしなし、すべてもろこしは外(ヨソ)の国にて、かの国の事は、何事もみな外(ヨソ)の国の事なれば、その心をもて、漢某唐某(カンナニタウナニ)といふべく、皇国の事は、内の事なれば、分て国の名をいふべきにはあらざるを、昔より世の中おしなべて、漢学をむねとするならひなるによりて、万ヅの事をいふに、たゞかのもろこしを、みづからの国のごとく、内にして、皇国をば、返りて外(ヨソ)にするは、ことのこゝろたがひて、いみしきひがこと也、此事は、山跡魂をかたむる一端なる故に、まづいふなり、
<ロ>かのしなじなある学びのすぢすぢ云々、 これははじめにいへるしなじなの学問のことなるが、そのしなじな、いづれもよくしらではかなはざる事どもなり、そのうち律令は、皇朝の上代よりの制と、もろこしの国の制とを合せて、よきほどに定められたる物なれども、まづはもろこしによれることがちにして、皇国の古ヘの制をば、改められたる事多ければ、これを学ぶには、其心得あるべく、又此すぢのからぶみをよく明らめざれば、事ゆかぬ学問なれば、奥をきはめんとするには、から書の方に、力を用ふること多くて、こなたの学びのためには、功(テマ)の費も多き也、これらのところをもよく心得べし、さて官職儀式の事は、これももろこしによられたる事共も、おほくあれども、さのみから書に力をもちひて、考ふることはいらざれば、律令とはことかはれり、官職のことは、職員令をもととして、つぎつぎに明らむべし、世の学者、おほく職原抄を主とする事なれども、かの書は、後世のさまを、むねとしるされたる如くなるが、朝廷のもろもろの御さだめも、御世々々を経るまゝに、おのづから古ヘとは変(カハ)り来ぬ る事ども多ければ、まづその源より明らむべき也、なほ官職の事しるせる、後世の書いと多し、もろもろの儀式の事は、貞観儀式弘仁の内裏式などふるし、其外江家次第、世におしなべて用ふる書なり、されどこれも、古ヘとはやゝかはれる事ども多し、貞観儀式などと、くらべ見てしるべし、ちかく水戸の礼儀類典、めでたき書なれども、ことのほか大部なれば、たやすくよみわたしがたし、さて装束調度などのことは、世にこれをまなぶ輩、おほくは中古以来の事をのみ穿鑿して、古ヘへさかのぼりて考る人は、すくなし、これも後世の書ども、いとあまたあれども、まづ古書より考ふべし、此古書は、まづ延喜式など也、さては西宮記北山抄、此二書は、装束調度などの学のみにはかぎらず、律令官職儀式、其外の事、いづれにもわたりて、おほよそ朝廷のもろもろの事をしるされたり、かならずよくよむべき書なり、さて件のしなじなの学問いづれもいづれも、古ヘざまの事は、六国史に所々其事どもの出たるを、よく参考すべし、又中古以来のことは、諸家の記録どもなどに、散出したるを、参考すべし、さて歌まなびの事は、下に別にいへり、むかし四道の学とて、しなじなの有しは、みな漢ざまによれる学びなれば、こゝに論ずべきかぎりにあらず、四道とは、紀伝明経明法算道これ也、此中に明法道といふは、律令などの学問なれば、上にいへると同じけれど、昔のは、その実事にかゝりたれば、今の世のたゞ書のうへの学のみなるとは、かはり有リ、さてなほ外国の学は、儒学仏学其外、殊にくさぐさ多くあれども、皆よその事なれば、今論ずるに及ばず、吾は、あたら精力を、外(ヨソ)の国の事に用ひんよりは、わがみづからの国の事に用ひまほしく思ふ也、その勝劣のさだなどは、姑くさしおきて、まづよその事にのみかゝづらひて、わが内の国の事をしらざらんは、くちをしきわざならんや、
<ハ>志を高く大きにたてて云々、 すべて学問は、はじめよりその心ざしを、高く大きに立テて、その奥を究(キハ)めつくさずはやまじと、かたく思ひまうくべし、此志よわくては、学問すゝみがたく、倦怠(ウミオコタ)るもの也、
<ニ>主(ムネ)としてよるべきすぢは云々、 道を学ぶを主とすべき子細は、今さらいふにも及ばぬことなれども、いさゝかいはば、まづ人として、人の道はいかなるものぞといふことを、しらで有べきにあらず、学問の志なきものは、論のかぎりにはあらず、かりそめにもその心ざしあらむ者は、同じくは道のために、力を用ふべきこと也、然るに道の事をば、なほざりにさしおきて、たゞ末の事にのみ、かゝづらひをらむは、学問の本意にあらず、さて道を学ぶにつきては、天地の間にわたりて、殊にすぐれたる、まことの道の伝はれる、御国に生れ来つるは、幸とも幸なれば、いかにも此たふとき皇国の道を学ぶべきは、勿論のこと也、
<ホ>此道は、古事記書紀の二典に記されたる云々、 道は此二典にしるされたる、神代のもろもろの事跡のうへに備はりたれども、儒仏などの書のやうに、其道のさまを、かやうかやうと、さして教へたることなければ、かの儒仏の書の目うつしにこれを見ては、道の趣、いかなるものともしりがたく、とらへどころなきが如くなる故に、むかしより世々の物しり人も、これをえとらへず、さとらずして、或は仏道の意により、或は儒道の意にすがりて、これを説(トキ)たり、其内昔の説は、多く仏道によりたりしを、百五六十年以来は、かの仏道によれる説の、非なることをばさとりて、其仏道の意をば、よくのぞきぬ れども、その輩の説は、又皆儒道の意に落入て、近世の神学者流みな然也、其中にも流々有て、すこしづゝのかはりはあれども、大抵みな同じやうなる物にて、神代紀をはじめ、もろもろの神典のとりさばき、たゞ陰陽八卦五行など、すべてからめきたるさだのみにして、いさゝかも古ヘの意にかなへることなく、説クところ悉皆儒道にて、たゞ名のみぞ神道にては有ける、されば世の儒者などの、此神道家の説を聞て、神道といふ物は、近き世に作れる事也とて、いやしめわらふは、げにことわり也、此神学者流のともがら、かの仏道によりてとけるをば、ひがこととしりながら、又おのが儒道によれるも、同じくひがことなる事をば、えさとらぬ こそ可笑(ヲカ)しけれ、かくいへば、そのともがらは、神道と儒道とは、その致(ムネ)一ツなる故に、これを仮(カリ)て説(トク)也、かの仏を牽合したる類ヒにはあらず、といふめれども、然思ふは、此道の意をえさとらざる故也、もしさやうにいはば、かの仏道によりて説ク輩も又、神道とても、仏の道の外なることなし、一致也とぞいふべき、これら共に、おのおの其道に惑へるから、然思ふ也、まことの神道は、儒仏の教ヘなどとは、いたく趣の異なる物にして、さらに一致なることなし、すべて近世の神学家は、件のごとくなれば、かの漢学者流の中の、宋学といふに似て、いさゝかもわきめをふらず、たゞ一すぢに道の事をのみ心がくめれども、ひたすら漢流の理窟にのみからめられて、古の意をば、尋ねんものとも思はず、其心を用るところ、みな儒意なれば、深く入ルほど、いよいよ道の意には遠き也、さて又かの仏の道によりて説るともがらは、その行法も、大かた仏家の行法にならひて、造れる物にして、さらに皇国の古ヘの行ひにあらず、又かの近世の儒意の神道家の、これこそ神道の行ひよとて、物する事共、葬喪祭祀等の式、其外も、世俗とかはりて、別に一種の式を立て行ふも、これ又儒意をまじへて、作れること多くして、全く古ヘの式にはあらず、すべて何事も、古ヘの御世に、漢風をしたひ用ひられて、多くかの国ざまに改められたるから、上古の式はうせて、世に伝はらざるが多ければ、そのさだかにこまかなることは、知リがたくなりぬ る、いといと歎かはしきわざ也、たまたま片田舎などには、上古の式の残れる事も有とおぼしけれども、それも猶仏家の事などのまじりて、正しく伝はれるは有がたかめり、そもそも道といふ物は、上に行ひ給ひて、下へは、上より敷キ施し給ふものにこそあれ、下たる者の、私に定めおこなふものにはあらず、されば神学者などの、神道の行ひとて、世間に異なるわざをするは、たとひ上古の行ひにかなへること有といへども、今の世にしては私なり、道は天皇の天下を治めさせ給ふ、正大公共の道なるを、一己の私の物にして、みづから狭く小(チヒサ)く説(トキ)なして、たゞ巫覡などのわざのごとく、或はあやしきわざを行ひなどして、それを神道となのるは、いともいともあさましくかなしき事也、すべて下たる者は、よくてもあしくても、その時々の上の掟のまゝに、従ひ行ふぞ、即チ古ヘの道の意には有ける、吾はかくのごとく思ひとれる故に、吾家、すべて先祖の祀リ、供仏施僧のわざ等も、たゞ親の世より為シ来りたるまゝにて、世俗とかはる事なくして、たゞこれをおろそかならざらんとするのみ也、学者はたゞ、道を尋ねて明らめしるをこそ、つとめとすべけれ、私に道を行ふべきものにはあらず、されば随分に、古の道を考へ明らめて、そのむねを、人にもをしへさとし、物にも書キ遺(ノコ)しおきて、たとひ五百年千年の後にもあれ、時至りて、上にこれを用ひ行ひ給ひて、天下にしきほどこし給はん世をまつべし、これ宣長が志シ也、
<ヘ>初学のともがらは宣長が著したる云々、 神典には、世々の注釈末書あまたあるを、さしおきて、みづから著せる書を、まづよめといふは、大に私なるに似たれども、必ズ然すべき故あり、いで其故は、注釈末書は多しといへども、まづ釈日本紀などは、道の意を示し明したる事なく、私記の説といへども、すべていまだしくをさなき事のみ也、又その後々の末書注釈どもは、仏と儒との意にして、さらに古の意にあらず、返て大に道を害することのみ也、されば今、道のために、見てよろしきは、一つもあることなし、さりとて又初学のともがら、いかほど力を用ふとも、二典の本文を見たるばかりにては、道の趣、たやすく会得しがたかるべし、こゝにわが県居ノ大人は、世の学者の、漢意のあしきことをよくさとりて、ねんごろにこれをさとし教へて、盛ンに古学を唱へ給ひしかども、其力を万葉集にむねと用ひて、道の事までは、くはしくは及ばれず、事にふれては、其事もいひ及ぼされてはあれども、力をこれにもはらと入れられざりし故に、あまねくゆきわたらず、されば道のすぢは、此大人の説も、なほたらはぬこと多ければ、まづ速に道の大意を心得んとするに、のり長が書共をおきて外に、まづ見よとをしふべき書は、世にあることなければ也、さる故に下には、古事記伝をも、おほけなく古書共にならべて、これをあげたり、かくいふをも、なほ我慢なる大言のやうに、思ひいふ人もあるべけれど、さやうに人にあしくいはれんことをはゞかりて、おもひとれるすぢを、いはざらんは、かへりて初学のために、忠実(マメ)ならざれば、あしくいはむ人には、いかにもいはれんかし、
<ロ>かのしなじなある学びのすぢすぢ云々、 これははじめにいへるしなじなの学問のことなるが、そのしなじな、いづれもよくしらではかなはざる事どもなり、そのうち律令は、皇朝の上代よりの制と、もろこしの国の制とを合せて、よきほどに定められたる物なれども、まづはもろこしによれることがちにして、皇国の古ヘの制をば、改められたる事多ければ、これを学ぶには、其心得あるべく、又此すぢのからぶみをよく明らめざれば、事ゆかぬ学問なれば、奥をきはめんとするには、から書の方に、力を用ふること多くて、こなたの学びのためには、功(テマ)の費も多き也、これらのところをもよく心得べし、さて官職儀式の事は、これももろこしによられたる事共も、おほくあれども、さのみから書に力をもちひて、考ふることはいらざれば、律令とはことかはれり、官職のことは、職員令をもととして、つぎつぎに明らむべし、世の学者、おほく職原抄を主とする事なれども、かの書は、後世のさまを、むねとしるされたる如くなるが、朝廷のもろもろの御さだめも、御世々々を経るまゝに、おのづから古ヘとは変(カハ)り来ぬ る事ども多ければ、まづその源より明らむべき也、なほ官職の事しるせる、後世の書いと多し、もろもろの儀式の事は、貞観儀式弘仁の内裏式などふるし、其外江家次第、世におしなべて用ふる書なり、されどこれも、古ヘとはやゝかはれる事ども多し、貞観儀式などと、くらべ見てしるべし、ちかく水戸の礼儀類典、めでたき書なれども、ことのほか大部なれば、たやすくよみわたしがたし、さて装束調度などのことは、世にこれをまなぶ輩、おほくは中古以来の事をのみ穿鑿して、古ヘへさかのぼりて考る人は、すくなし、これも後世の書ども、いとあまたあれども、まづ古書より考ふべし、此古書は、まづ延喜式など也、さては西宮記北山抄、此二書は、装束調度などの学のみにはかぎらず、律令官職儀式、其外の事、いづれにもわたりて、おほよそ朝廷のもろもろの事をしるされたり、かならずよくよむべき書なり、さて件のしなじなの学問いづれもいづれも、古ヘざまの事は、六国史に所々其事どもの出たるを、よく参考すべし、又中古以来のことは、諸家の記録どもなどに、散出したるを、参考すべし、さて歌まなびの事は、下に別にいへり、むかし四道の学とて、しなじなの有しは、みな漢ざまによれる学びなれば、こゝに論ずべきかぎりにあらず、四道とは、紀伝明経明法算道これ也、此中に明法道といふは、律令などの学問なれば、上にいへると同じけれど、昔のは、その実事にかゝりたれば、今の世のたゞ書のうへの学のみなるとは、かはり有リ、さてなほ外国の学は、儒学仏学其外、殊にくさぐさ多くあれども、皆よその事なれば、今論ずるに及ばず、吾は、あたら精力を、外(ヨソ)の国の事に用ひんよりは、わがみづからの国の事に用ひまほしく思ふ也、その勝劣のさだなどは、姑くさしおきて、まづよその事にのみかゝづらひて、わが内の国の事をしらざらんは、くちをしきわざならんや、
<ハ>志を高く大きにたてて云々、 すべて学問は、はじめよりその心ざしを、高く大きに立テて、その奥を究(キハ)めつくさずはやまじと、かたく思ひまうくべし、此志よわくては、学問すゝみがたく、倦怠(ウミオコタ)るもの也、
<ニ>主(ムネ)としてよるべきすぢは云々、 道を学ぶを主とすべき子細は、今さらいふにも及ばぬことなれども、いさゝかいはば、まづ人として、人の道はいかなるものぞといふことを、しらで有べきにあらず、学問の志なきものは、論のかぎりにはあらず、かりそめにもその心ざしあらむ者は、同じくは道のために、力を用ふべきこと也、然るに道の事をば、なほざりにさしおきて、たゞ末の事にのみ、かゝづらひをらむは、学問の本意にあらず、さて道を学ぶにつきては、天地の間にわたりて、殊にすぐれたる、まことの道の伝はれる、御国に生れ来つるは、幸とも幸なれば、いかにも此たふとき皇国の道を学ぶべきは、勿論のこと也、
<ホ>此道は、古事記書紀の二典に記されたる云々、 道は此二典にしるされたる、神代のもろもろの事跡のうへに備はりたれども、儒仏などの書のやうに、其道のさまを、かやうかやうと、さして教へたることなければ、かの儒仏の書の目うつしにこれを見ては、道の趣、いかなるものともしりがたく、とらへどころなきが如くなる故に、むかしより世々の物しり人も、これをえとらへず、さとらずして、或は仏道の意により、或は儒道の意にすがりて、これを説(トキ)たり、其内昔の説は、多く仏道によりたりしを、百五六十年以来は、かの仏道によれる説の、非なることをばさとりて、其仏道の意をば、よくのぞきぬ れども、その輩の説は、又皆儒道の意に落入て、近世の神学者流みな然也、其中にも流々有て、すこしづゝのかはりはあれども、大抵みな同じやうなる物にて、神代紀をはじめ、もろもろの神典のとりさばき、たゞ陰陽八卦五行など、すべてからめきたるさだのみにして、いさゝかも古ヘの意にかなへることなく、説クところ悉皆儒道にて、たゞ名のみぞ神道にては有ける、されば世の儒者などの、此神道家の説を聞て、神道といふ物は、近き世に作れる事也とて、いやしめわらふは、げにことわり也、此神学者流のともがら、かの仏道によりてとけるをば、ひがこととしりながら、又おのが儒道によれるも、同じくひがことなる事をば、えさとらぬ こそ可笑(ヲカ)しけれ、かくいへば、そのともがらは、神道と儒道とは、その致(ムネ)一ツなる故に、これを仮(カリ)て説(トク)也、かの仏を牽合したる類ヒにはあらず、といふめれども、然思ふは、此道の意をえさとらざる故也、もしさやうにいはば、かの仏道によりて説ク輩も又、神道とても、仏の道の外なることなし、一致也とぞいふべき、これら共に、おのおの其道に惑へるから、然思ふ也、まことの神道は、儒仏の教ヘなどとは、いたく趣の異なる物にして、さらに一致なることなし、すべて近世の神学家は、件のごとくなれば、かの漢学者流の中の、宋学といふに似て、いさゝかもわきめをふらず、たゞ一すぢに道の事をのみ心がくめれども、ひたすら漢流の理窟にのみからめられて、古の意をば、尋ねんものとも思はず、其心を用るところ、みな儒意なれば、深く入ルほど、いよいよ道の意には遠き也、さて又かの仏の道によりて説るともがらは、その行法も、大かた仏家の行法にならひて、造れる物にして、さらに皇国の古ヘの行ひにあらず、又かの近世の儒意の神道家の、これこそ神道の行ひよとて、物する事共、葬喪祭祀等の式、其外も、世俗とかはりて、別に一種の式を立て行ふも、これ又儒意をまじへて、作れること多くして、全く古ヘの式にはあらず、すべて何事も、古ヘの御世に、漢風をしたひ用ひられて、多くかの国ざまに改められたるから、上古の式はうせて、世に伝はらざるが多ければ、そのさだかにこまかなることは、知リがたくなりぬ る、いといと歎かはしきわざ也、たまたま片田舎などには、上古の式の残れる事も有とおぼしけれども、それも猶仏家の事などのまじりて、正しく伝はれるは有がたかめり、そもそも道といふ物は、上に行ひ給ひて、下へは、上より敷キ施し給ふものにこそあれ、下たる者の、私に定めおこなふものにはあらず、されば神学者などの、神道の行ひとて、世間に異なるわざをするは、たとひ上古の行ひにかなへること有といへども、今の世にしては私なり、道は天皇の天下を治めさせ給ふ、正大公共の道なるを、一己の私の物にして、みづから狭く小(チヒサ)く説(トキ)なして、たゞ巫覡などのわざのごとく、或はあやしきわざを行ひなどして、それを神道となのるは、いともいともあさましくかなしき事也、すべて下たる者は、よくてもあしくても、その時々の上の掟のまゝに、従ひ行ふぞ、即チ古ヘの道の意には有ける、吾はかくのごとく思ひとれる故に、吾家、すべて先祖の祀リ、供仏施僧のわざ等も、たゞ親の世より為シ来りたるまゝにて、世俗とかはる事なくして、たゞこれをおろそかならざらんとするのみ也、学者はたゞ、道を尋ねて明らめしるをこそ、つとめとすべけれ、私に道を行ふべきものにはあらず、されば随分に、古の道を考へ明らめて、そのむねを、人にもをしへさとし、物にも書キ遺(ノコ)しおきて、たとひ五百年千年の後にもあれ、時至りて、上にこれを用ひ行ひ給ひて、天下にしきほどこし給はん世をまつべし、これ宣長が志シ也、
<ヘ>初学のともがらは宣長が著したる云々、 神典には、世々の注釈末書あまたあるを、さしおきて、みづから著せる書を、まづよめといふは、大に私なるに似たれども、必ズ然すべき故あり、いで其故は、注釈末書は多しといへども、まづ釈日本紀などは、道の意を示し明したる事なく、私記の説といへども、すべていまだしくをさなき事のみ也、又その後々の末書注釈どもは、仏と儒との意にして、さらに古の意にあらず、返て大に道を害することのみ也、されば今、道のために、見てよろしきは、一つもあることなし、さりとて又初学のともがら、いかほど力を用ふとも、二典の本文を見たるばかりにては、道の趣、たやすく会得しがたかるべし、こゝにわが県居ノ大人は、世の学者の、漢意のあしきことをよくさとりて、ねんごろにこれをさとし教へて、盛ンに古学を唱へ給ひしかども、其力を万葉集にむねと用ひて、道の事までは、くはしくは及ばれず、事にふれては、其事もいひ及ぼされてはあれども、力をこれにもはらと入れられざりし故に、あまねくゆきわたらず、されば道のすぢは、此大人の説も、なほたらはぬこと多ければ、まづ速に道の大意を心得んとするに、のり長が書共をおきて外に、まづ見よとをしふべき書は、世にあることなければ也、さる故に下には、古事記伝をも、おほけなく古書共にならべて、これをあげたり、かくいふをも、なほ我慢なる大言のやうに、思ひいふ人もあるべけれど、さやうに人にあしくいはれんことをはゞかりて、おもひとれるすぢを、いはざらんは、かへりて初学のために、忠実(マメ)ならざれば、あしくいはむ人には、いかにもいはれんかし、
<ト>第一に漢意儒意を云々、 おのれ何につけても、ひたすら此事をいふは、ゆゑなくみだりに、これをにくみてにはあらず、大きに故ありていふ也、その故は、古の道の意の明らかならず、人みな大にこれを誤りしたゝめたるは、いかなるゆゑぞと尋ぬ れば、みな此漢意に心のまどはされ居て、それに妨(サマタ)げらるゝが故也、これ千有余年、世ノ中の人の心の底に染着(シミツキ)てある、痼疾なれば、とにかくに清くはのぞこりがたき物にて、近きころは、道をとくに、儒意をまじふることの、わろきをさとりて、これを破する人も、これかれ聞ゆれども、さやうの人すら、なほ清くこれをまぬ かるゝことあたはずして、その説クところ、畢竟は漢意におつるなり、かくのごとくなる故に、道をしるの要、まづこれを清くのぞき去ルにありとはいふ也、これを清くのぞきさらでは道は得がたかるべし、初学の輩、まづ此漢意を清く除き去て、やまとたましひを堅固(カタ)くすべきことは、たとへばものゝふの、戦場におもむくに、まづ具足をよくし、身をかためて立出るがごとし、もし此身の固めをよくせずして、神の御典(ミフミ)をよむときは、甲冑をも着ず、素膚(スハダ)にして戦ひて、たちまち敵のために、手を負ふがごとく、かならずからごゝろに落入べし、
<チ>道をしらんためには、殊に古事記をさきとすべし、 まづ神典は、旧事紀古事記日本紀を、昔より、三部の本書といひて、其中に世の学者の学ぶところ、日本紀をむねとし、次に旧事紀は、聖徳太子の御撰として、これを用ひて、古事記をば、さのみたふとまず、深く心を用る人もなかりし也、然るに近き世に至りてやうやう、旧事紀は真の書にあらず、後の人の撰び成せる物なることをしりそめて、今はをさをさこれを用る人はなきやうになりて、古事記のたふときことをしれる人多くなれる、これ全く吾師ノ大人の教ヘによりて、学問の道大にひらけたるが故也、まことに古事記は、漢文のかざりをまじへたることなどなく、たゞ古ヘよりの伝説のまゝにて、記しざまいといとめでたく、上代の有さまをしるに、これにしく物なく、そのうへ神代の事も、書紀よりは、つぶさに多くしるされたれば、道をしる第一の古典にして、古学のともがらの、尤尊み学ぶべきは此書也、然るゆゑに、己レ壮年より、数十年の間、心力をつくして、此記の伝四十四巻をあらはして、いにしへ学ビのしるべとせり、さて此記は、古伝説のまゝにしるせる書なるに、その文のなほ漢文ざまなるはいかにといふに、奈良の御代までは、仮字文といふことはなかりし故に、書はおしなべて、漢文に書るならひなりき、そもそも文字書籍は、もと漢国より出たる物なれば、皇国に渡り来ても、その用ひやう、かの国にて物をしるす法のまゝにならひて書キそめたるにて、こゝとかしこと、語のふりはたがへることあれども、片仮字も平仮字もなき以前は、はじめよりのならひのまゝに、物はみな漢文に書たりし也、仮字文といふ物は、いろは仮字出来て後の事也、いろは仮字は、今の京になりて後に、出来たり、されば古書のみな漢文なるは、古ヘの世のなべてのならひにこそあれ、後世のごとく、好みて漢文に書るにはあらず、さて歌は、殊に詞にあやをなして、一もじもたがへては、かなはぬ物なる故に、古書にもこれをば、別に仮字に書り、それも真仮字也、又祝詞宣命なども、詞をとゝのへかざりたるものにて、漢文ざまには書がたければ、これも別に書法有し也、然るを後世に至りては、片仮字平仮字といふ物あれば、万の事、皇国の語のまゝに、いかやうにも自由に、物はかゝるゝことなれば、古ヘのやうに、物を漢文に書べきことにはあらず、便よく正しき方をすてて、正しからず不便なるかたを用るは、いと愚也、上件の子細をわきまへざる人、古書のみな漢文なるを見て、今も物は漢文に書クをよきことと心得たるは、ひがこと也、然るに諸家の記録其外、つねの文書消息文などのたぐひは、なほ後世までも、みな漢文ざまに書クならひにて、これを男もじ男ぶみといひ、いろは仮字をば女もじ、仮字文をば、女ぶみとしもいふなるは、男はおのづからかの古ヘのならひのまゝに為シ来(キタ)り、女は便にまかせて、多くいろは仮字をのみ用ひたるから、かゝる名目も有也、
<リ>書紀をよむには大に心得あり云々、 書紀は、朝廷の正史と立られて、御世々々万の事これによらせ給ひ、世々の学者も、これをむねと学ぶこと也、まことに古事記は、しるしざまは、いとめでたく尊けれども、神武天皇よりこなたの、御代々々の事をしるされたる、甚あらくすくなくして、広からず、審ならざるを、此紀は、広く詳にしるされたるほど、たぐひなく、いともたふとき御典也、此御典なくては、上古の事どもを、ひろく知べきよしなし、然はあれども、すべて漢文の潤色多ければ、これをよむに、はじめよりその心得なくてはあるべからず、然るを世間の神学者、此わきまへなくして、たゞ文のまゝにこゝろえ、返て漢文の潤色の所を、よろこび尊みて、殊に心を用るほどに、すべての解し様(ヤウ)、ことごとく漢流の理屈にして、いたく古ヘの意にたがへり、これらの事、大抵は古事記伝の首巻にしるせり、猶又別に、神代紀のうずの山蔭といふ物を書ていへり、ひらき見るべし、
<ヌ>六国史といふ云々、 六国史のうち日本後紀は、いかにしたるにか、亡(ウセ)て伝はらず、今それとて廿巻あるは、全き物にあらず、然るに近き世、鴨ノ祐之といひし人、類聚国史をむねと取リ、かたはら他の正しき古書共をもとり加ハへて、日本逸史といふ物四十巻を撰定せる、後紀のかはりは、此書にてたれり、類聚国史は、六国史に記されたる諸の事を、部類を分ケ聚めて、菅原ノ大臣の撰給へる書也、さて三代実録の後は、正しき国史は無し、されば宇多ノ天皇よりこなたの御世御世の事は、たゞこれかれかたはらの書共を見てしること也、其書ども、国史のたぐひなるも、あまた有、近世水戸の大日本史は、神武天皇より、後小松ノ天皇の、後亀山ノ天皇の御禪(ミユヅリ)を受させ給へる御事までしるされて、めでたき書也、
<ル>御世々々の宣命には云々、 書紀に挙られたる、御世々々の詔勅は、みな漢文なるのみなるを、続紀よりこなたの史共には、皇朝詞の詔をも、載せられたる、これを分て宣命といふ也、続紀なるは、世あがりたれば、殊に古語多し、その次々の史どもなる、やうやうに古き語はすくなくなりゆきて、漢詞おほくまじれり、すべて宣命にはかぎらず、何事にもせよ、からめきたるすぢをはなれて、皇国の上代めきたるすぢの事や詞は、いづれの書にあるをも、殊に心をとどめて見るべし、古ヘをしる助ケとなること也、
<ヲ>釈日本紀、 此書は後の物にて、説もすべてをさなけれども、今の世には伝はらぬ古書どもを、これかれと引出たる中に、いとめづらかに、たふときことどもの有也、諸国の風土記なども、みな今は伝はらざるに、此書と仙覚が万葉の抄とに、引出たる所々のみぞ、世にのこれる、これ殊に古学の用なり、又むかしの私記どもも、皆亡(ウセ)ぬ るを、此釈には、多く其説をあげたり、私記の説も、すべてをさなけれども、古き故に、さすがに取ルべき事もまゝある也、さて六国史をはじめて、こゝに挙たる書共いづれも、板本も写 本も、誤字脱文等多ければ、古本を得て、校正すべし、されど古本は、たやすく得がたきものなれば、まづ人の校正したる本を、求め借りてなりとも、つぎつぎ直すべき也、さて又ついでにいはむ、今の世は、古ヘをたふとみ好む人おほくなりぬ るにつきては、おのづからめづらしき古書の、世に埋れたるも、顕れ出る有リ、又それにつきては、偽書も多く出るを、その真偽は、よく見る人は、見分れども、初学の輩などは、え見分ねば、偽書によくはからるゝ事あり、心すべし、されば初学のほどは、めづらしき書を得んことをば、さのみ好むべからず、
<ワ>古事記伝云々、 みづから著せる物を、かくやむことなき古書どもにならべて挙るは、おふけなく、つゝましくはおぼゆれども、上にいへるごとくにて、上代の事を、くはしく説キ示し、古学の心ばへを、つまびらかにいへる書は、外になければぞかし、されば同じくは此書も、二典とまじへて、はじめより見てよろしけれども、巻数多ければ、こゝへはまはしたる也、
<カ>古学の輩の、 古学とは、すべて後世の説にかゝはらず、何事も、古書によりて、その本を考へ、上代の事を、つまびらかに明らむる学問也、此学問、ちかき世に始まれり、契沖ほふし、歌書に限りてはあれど、此道すぢを開きそめたり、此人をぞ、此まなびのはじめの祖(オヤ)ともいひつべき、次にいさゝかおくれて羽倉ノ大人、荷田ノ東麻呂ノ宿祢と申せしは、歌書のみならず、すべての古書にわたりて、此こゝろばへを立テ給へりき、かくてわが師あがたゐの大人、この羽倉ノ大人の教をつぎ給ひ、東国に下り江戸に在て、さかりに此学を唱へ給へるよりぞ、世にはあまねくひろまりにける、大かた奈良ノ朝よりしてあなたの古ヘの、もろもろの事のさまを、こまかに精(クハ)しく考へしりて、手にもとるばかりになりぬ るは、もはら此大人の、此古学のをしへの功にぞ有ける、
<ヨ>初心のほどは、かたはしより文義を云々、 文義の心得がたきところを、はじめより、一々に解せんとしては、とどこほりて、すゝまぬことあれば、聞えぬところは、まづそのまゝにて過すぞよき、殊に世に難き事にしたるふしぶしを、まづしらんとするは、いといとわろし、たゞよく聞えたる所に、心をつけて、深く味ふべき也、こはよく聞えたる事也と思ひて、なほざりに見過せば、すべてこまかなる意味もしられず、又おほく心得たがひの有て、いつまでも、其誤リをえさとらざる事有也、
<タ>其末の事は、一々さとし教るに及ばず、 此こゝろをふと思ひよりてよめる歌、筆のついでに、「とる手火も今はなにせむ夜は明てほがらほがらと道見えゆくを、
<レ>ひろくも見るべく又云々、 博識とかいひて、随分ひろく見るも、よろしきことなれども、さては緊要の書を見ることの、おのづからおろそかになる物なれば、あながちに広きをよきこととのみもすべからず、その同じ力を、緊要の書に用るもよろしかるべし、又これかれにひろく心を分るは、たがひに相たすくることもあり、又たがひに害となることもあり、これらの子細をよくはからふべき也、
<ソ>五十音のとりさばき云々、 これはいはゆる仮字反シの法、音の堅横の通用の事、言の延(ノベ)つゞめの例などにつきて、古語を解キ明らむるに、要用のこと也、かならずはじめより心がくべし、仮字づかひは、古ヘのをいふ、近世風の歌よみのかなづかひは、中昔よりの事にて、古書にあはず、
<ツ>語釈は緊要にあらず、 語釈とは、もろもろの言の、然云フ本の意を考へて、釈(トク)をいふ、たとへば天(アメ)といふはいかなること、地(ツチ)といふはいかなることと、釈(ト)くたぐひ也、こは学者の、たれもまづしらまほしがることなれども、これにさのみ深く心をもちふべきにはあらず、こは大かたよき考へは出来がたきものにて、まづはいかなることとも、しりがたきわざなるが、しひてしらでも、事かくことなく、しりてもさのみ益なし、されば諸の言は、その然云フ本の意を考ヘんよりは、古人の用ひたる所をよく考へて、云々(シカシカ)の言は、云々の意に用ひたりといふことを、よく明らめ知るを、要とすべし、言の用ひたる意をしらでは、其所の文意聞えがたく、又みづから物を書クにも、言の用ひやうたがふこと也、然るを今の世古学の輩、ひたすら然云フ本の意をしらんことをのみ心がけて、用る意をば、なほざりにする故に、書をも解し誤り、みづからの歌文も、言の意用ひざまたがひて、あらぬ ひがこと多きぞかし、
<ネ>からぶみをもまじへよむべし、 漢籍を見るも、学問のために益おほし、やまと魂だによく堅固(カタ)まりて、動くことなければ、晝夜からぶみをのみよむといへども、かれに惑はさるゝうれひはなきなり、然れども世の人、とかく倭魂(ヤマトタマシヒ)かたまりにくき物にて、から書をよめば、そのことよきにまどはされて、たぢろきやすきならひ也、ことよきとは、その文辞を、麗(ウルハ)しといふにはあらず、詞の巧にして、人の思ひつきやすく、まどはされやすきさまなるをいふ也、すべてから書は、言巧にして、ものの理非を、かしこくいひまはしたれば、人のよく思ひつく也、すべて学問すぢならぬ 、よのつねの世俗の事にても、弁舌よく、かしこく物をいひまはす人の言には、人のなびきやすき物なるが、漢籍もさやうなるものと心得居べし、
<ナ>古書の注釈を作らんと云々、 書をよむに、たゞ何となくてよむときは、いかほど委く見んと思ひても、限リあるものなるに、みづから物の注釈をもせんと、こゝろがけて見るときには、何れの書にても、格別に心のとまりて、見やうのくはしくなる物にて、それにつきて、又外にも得る事の多きもの也、されば其心ざしたるすぢ、たとひ成就はせずといへども、すべて学問に大いに益あること也、是は物の注釈のみにもかぎらず、何事にもせよ、著述をこゝろがくべき也、
<ラ>万葉集をよくまなぶべし、 此書は、歌の集なるに、二典の次に挙て、道をしるに甚ダ益ありといふは、心得ぬことに、人おもふらめども、わが師ノ大人の古学のをしへ、専ラこゝにあり、其説に、古ヘの道をしらんとならば、まづいにしへの歌を学びて、古風の歌をよみ、次に古の文を学びて、古ヘぶりの文をつくりて、古言をよく知リて、古事記日本紀をよくよむべし、古言をしらでは、古意はしられず、古意をしらでは、古の道は知リがたかるべし、といふこゝろばへを、つねづねいひて、教へられたる、此教へ迂遠(マハリドホ)きやうなれども、然らず、その故は、まづ大かた人は、言(コトバ)と事(ワザ)と心(ココロ)と、そのさま大抵相かなひて、似たる物にて、たとへば心のかしこき人は、いふ言のさまも、なす事(ワザ)のさまも、それに応じてかしこく、心のつたなき人は、いふ言のさまも、なすわざのさまも、それに応じてつたなきもの也、又男は、思ふ心も、いふ言も、なす事も、男のさまあり、女は、おもふ心も、いふ言も、なす事(ワザ)も、女のさまあり、されば時代々々の差別も、又これらのごとくにて、心も言も事も、上代の人は、上代のさま、中古の人は、中古のさま、後世の人は、後世のさま有て、おのおのそのいへる言となせる事と、思へる心と、相かなひて似たる物なるを、今の世に在て、その上代の人の、言をも事をも心をも、考へしらんとするに、そのいへりし言は、歌に伝はり、なせりし事は、史に伝はれるを、その史も、言を以て記したれば、言の外ならず、心のさまも、又歌にて知ルべし、言と事と心とは其さま相かなへるものなれば、後世にして、古の人の、思へる心、なせる事(ワザ)をしりて、その世の有さまを、まさしくしるべきことは、古言古歌にある也、さて古の道は、二典の神代上代の事跡のうへに備はりたれば、古言古歌をよく得て、これを見るときは、其道の意、おのづから明らかなり、さるによりて、上にも、初学のともがら、まづ神代正語をよくよみて、古語のやうを口なれしれとはいへるぞかし、古事記は、古伝説のまゝに記されてはあれども、なほ漢文なれば、正(マサ)しく古言をしるべきことは、万葉には及ばず、書紀は、殊に漢文のかざり多ければ、さら也、さて二典に載れる歌どもは、上古のなれば、殊に古言古意をしるべき、第一の至宝也、然れどもその数多からざれば、ひろく考るに、ことたらざるを、万葉は、歌数いと多ければ、古言はをさをさもれたるなく、伝はりたる故に、これを第一に学べとは、師も教へられたる也、すべて神の道は、儒仏などの道の、善悪是非をこちたくさだせるやうなる理窟は、露ばかりもなく、たゞゆたかにおほらかに、雅(ミヤビ)たる物にて、歌のおもむきぞ、よくこれにかなへりける、さて此万葉集をよむに、今の本、誤字いと多く、訓もわろきことおほし、初学のともがら、そのこゝろえ有べし、
<ム>みづからも古風の歌をまなびてよむべし、 すべて万ヅの事、他のうへにて思ふと、みづからの事にて思ふとは、浅深の異なるものにて、他のうへの事は、いかほど深く思ふやうにても、みづからの事ほどふかくはしまぬ 物なり、歌もさやうにて、古歌をば、いかほど深く考へても、他のうへの事なれば、なほ深くいたらぬところあるを、みづからよむになりては、我ガ事なる故に、心を用ること格別にて、深き意味をしること也、さればこそ師も、みづから古風の歌をよみ、古ぶりの文をつくれとは、教へられたるなれ、文の事は、古文は、延喜式八の巻なる諸の祝詞、続紀の御世々々の宣命など、古語のまゝにのこれる文也、二典の中にも、をりをりは古語のまゝなる文有リ、其外の古書共にも、をりをりは古文まじれることあり、これかれをとりて、のりとすべし、万葉は歌にて、歌と文とは、詞の異なることなどあれども、歌と文との、詞づかひのけぢめを、よくわきまへえらびてとらば、歌の詞も、多くは文にも用ふべきものなれば、古文を作る学びにも、万葉はよく学ばでかなはぬ書也、なほ文をつくるべき学びかた、心得なども、古体近体、世々のさまなど、くさぐさいふべき事多くあれども、さのみはこゝにつくしがたし、大抵歌に准へても心得べし、そのうち文には、いろいろのしなあることにて、其品によりて、詞のつかひやう其外、すべての書キやう、かはれること多ければ、其心得有べし、いろいろのしなとは、序、或は論、或は紀事、或は消息など也、さて後世になりて、万葉ぶりの歌を、たててよめる人は、たゞ鎌倉ノ右大臣殿のみにして、外には聞えざりしを、吾師ノ大人のよみそめ給ひしより、其教によりて、世によむ人おほく出来たるを、其人どもの心ざすところ、必しも古の道を明らめんためによむにはあらず、おほくはたゞ歌を好みもてあぞぶのみにして、その心ざしは、近世風の歌よみの輩と、同じこと也、さればよき歌をよみ出むと心がくることも、近世風の歌人とかはる事なし、それにつきては、道のために学ぶすぢをば、姑くおきて、今は又ただ歌のうへにつきての心得どもをいはんとす、そもそも歌は、思ふ心をいひのぶるわざといふうちに、よのつねの言とはかはりて、必ズ詞にあやをなして、しらべをうるはしくとゝのふる道なり、これ神代のはじめより然り、詞のしらべにかゝはらず、たゞ思ふまゝにいひ出るは、つねの詞にして、歌といふものにはあらず、さてその詞のあやにつきて、よき歌とあしき歌とのけぢめあるを、上代の人は、たゞ一わたり、歌の定まりのしらべをとゝのへてよめるのみにして、後世の人のやうに、思ひめぐらして、よくよまんとかまへ、たくみてよめることはなかりし也、然れども、その出来たるうへにては、おのづからよく出来たると、よからざるとが有て、その中にすぐれてよく出来たる歌は、世間にもうたひつたへて、後ノ世までものこりて、二典に載れる歌どもなど是也、されば二典なる歌は、みな上代の歌の中にも、よにすぐれたるかぎりと知べし、古事記には、たゞ歌をのせんためのみに、其事を記されたるも、これかれ見えたるは、その歌のすぐれたるが故なり、さてかくのごとく歌は、上代よりして、よきとあしきと有て、人のあはれときゝ、神の感じ給ふも、よき歌にあること也、あしくては、人も神も、感じ給ふことなし、神代に天照大御神の、天の石屋(イハヤ)にさしこもり坐(マシ)し時、天ノ兒屋根ノ命の祝詞(ノリトゴト)に、感じ給ひしも、その辞のめでたかりし故なること、神代紀に見えたるがごとし、歌も准へて知ルべし、さればやゝ世くだりては、かまへてよき歌をよまんと、もとむるやうになりぬ るも、かならず然らではえあらぬ、おのづからの勢ヒにて、万葉に載れるころの歌にいたりては、みなかまへてよくよまんと、求めたる物にこそあれ、おのづからに出来たるは、いとすくなかるべし、万葉の歌すでに然るうへは、まして後世今の世には、よくよまんとかまふること、何かはとがむべき、これおのづからの勢ヒなれば、古風の歌をよまん人も、随分に詞をえらびて、うるはしくよろしくよむべき也、
<チ>道をしらんためには、殊に古事記をさきとすべし、 まづ神典は、旧事紀古事記日本紀を、昔より、三部の本書といひて、其中に世の学者の学ぶところ、日本紀をむねとし、次に旧事紀は、聖徳太子の御撰として、これを用ひて、古事記をば、さのみたふとまず、深く心を用る人もなかりし也、然るに近き世に至りてやうやう、旧事紀は真の書にあらず、後の人の撰び成せる物なることをしりそめて、今はをさをさこれを用る人はなきやうになりて、古事記のたふときことをしれる人多くなれる、これ全く吾師ノ大人の教ヘによりて、学問の道大にひらけたるが故也、まことに古事記は、漢文のかざりをまじへたることなどなく、たゞ古ヘよりの伝説のまゝにて、記しざまいといとめでたく、上代の有さまをしるに、これにしく物なく、そのうへ神代の事も、書紀よりは、つぶさに多くしるされたれば、道をしる第一の古典にして、古学のともがらの、尤尊み学ぶべきは此書也、然るゆゑに、己レ壮年より、数十年の間、心力をつくして、此記の伝四十四巻をあらはして、いにしへ学ビのしるべとせり、さて此記は、古伝説のまゝにしるせる書なるに、その文のなほ漢文ざまなるはいかにといふに、奈良の御代までは、仮字文といふことはなかりし故に、書はおしなべて、漢文に書るならひなりき、そもそも文字書籍は、もと漢国より出たる物なれば、皇国に渡り来ても、その用ひやう、かの国にて物をしるす法のまゝにならひて書キそめたるにて、こゝとかしこと、語のふりはたがへることあれども、片仮字も平仮字もなき以前は、はじめよりのならひのまゝに、物はみな漢文に書たりし也、仮字文といふ物は、いろは仮字出来て後の事也、いろは仮字は、今の京になりて後に、出来たり、されば古書のみな漢文なるは、古ヘの世のなべてのならひにこそあれ、後世のごとく、好みて漢文に書るにはあらず、さて歌は、殊に詞にあやをなして、一もじもたがへては、かなはぬ物なる故に、古書にもこれをば、別に仮字に書り、それも真仮字也、又祝詞宣命なども、詞をとゝのへかざりたるものにて、漢文ざまには書がたければ、これも別に書法有し也、然るを後世に至りては、片仮字平仮字といふ物あれば、万の事、皇国の語のまゝに、いかやうにも自由に、物はかゝるゝことなれば、古ヘのやうに、物を漢文に書べきことにはあらず、便よく正しき方をすてて、正しからず不便なるかたを用るは、いと愚也、上件の子細をわきまへざる人、古書のみな漢文なるを見て、今も物は漢文に書クをよきことと心得たるは、ひがこと也、然るに諸家の記録其外、つねの文書消息文などのたぐひは、なほ後世までも、みな漢文ざまに書クならひにて、これを男もじ男ぶみといひ、いろは仮字をば女もじ、仮字文をば、女ぶみとしもいふなるは、男はおのづからかの古ヘのならひのまゝに為シ来(キタ)り、女は便にまかせて、多くいろは仮字をのみ用ひたるから、かゝる名目も有也、
<リ>書紀をよむには大に心得あり云々、 書紀は、朝廷の正史と立られて、御世々々万の事これによらせ給ひ、世々の学者も、これをむねと学ぶこと也、まことに古事記は、しるしざまは、いとめでたく尊けれども、神武天皇よりこなたの、御代々々の事をしるされたる、甚あらくすくなくして、広からず、審ならざるを、此紀は、広く詳にしるされたるほど、たぐひなく、いともたふとき御典也、此御典なくては、上古の事どもを、ひろく知べきよしなし、然はあれども、すべて漢文の潤色多ければ、これをよむに、はじめよりその心得なくてはあるべからず、然るを世間の神学者、此わきまへなくして、たゞ文のまゝにこゝろえ、返て漢文の潤色の所を、よろこび尊みて、殊に心を用るほどに、すべての解し様(ヤウ)、ことごとく漢流の理屈にして、いたく古ヘの意にたがへり、これらの事、大抵は古事記伝の首巻にしるせり、猶又別に、神代紀のうずの山蔭といふ物を書ていへり、ひらき見るべし、
<ヌ>六国史といふ云々、 六国史のうち日本後紀は、いかにしたるにか、亡(ウセ)て伝はらず、今それとて廿巻あるは、全き物にあらず、然るに近き世、鴨ノ祐之といひし人、類聚国史をむねと取リ、かたはら他の正しき古書共をもとり加ハへて、日本逸史といふ物四十巻を撰定せる、後紀のかはりは、此書にてたれり、類聚国史は、六国史に記されたる諸の事を、部類を分ケ聚めて、菅原ノ大臣の撰給へる書也、さて三代実録の後は、正しき国史は無し、されば宇多ノ天皇よりこなたの御世御世の事は、たゞこれかれかたはらの書共を見てしること也、其書ども、国史のたぐひなるも、あまた有、近世水戸の大日本史は、神武天皇より、後小松ノ天皇の、後亀山ノ天皇の御禪(ミユヅリ)を受させ給へる御事までしるされて、めでたき書也、
<ル>御世々々の宣命には云々、 書紀に挙られたる、御世々々の詔勅は、みな漢文なるのみなるを、続紀よりこなたの史共には、皇朝詞の詔をも、載せられたる、これを分て宣命といふ也、続紀なるは、世あがりたれば、殊に古語多し、その次々の史どもなる、やうやうに古き語はすくなくなりゆきて、漢詞おほくまじれり、すべて宣命にはかぎらず、何事にもせよ、からめきたるすぢをはなれて、皇国の上代めきたるすぢの事や詞は、いづれの書にあるをも、殊に心をとどめて見るべし、古ヘをしる助ケとなること也、
<ヲ>釈日本紀、 此書は後の物にて、説もすべてをさなけれども、今の世には伝はらぬ古書どもを、これかれと引出たる中に、いとめづらかに、たふときことどもの有也、諸国の風土記なども、みな今は伝はらざるに、此書と仙覚が万葉の抄とに、引出たる所々のみぞ、世にのこれる、これ殊に古学の用なり、又むかしの私記どもも、皆亡(ウセ)ぬ るを、此釈には、多く其説をあげたり、私記の説も、すべてをさなけれども、古き故に、さすがに取ルべき事もまゝある也、さて六国史をはじめて、こゝに挙たる書共いづれも、板本も写 本も、誤字脱文等多ければ、古本を得て、校正すべし、されど古本は、たやすく得がたきものなれば、まづ人の校正したる本を、求め借りてなりとも、つぎつぎ直すべき也、さて又ついでにいはむ、今の世は、古ヘをたふとみ好む人おほくなりぬ るにつきては、おのづからめづらしき古書の、世に埋れたるも、顕れ出る有リ、又それにつきては、偽書も多く出るを、その真偽は、よく見る人は、見分れども、初学の輩などは、え見分ねば、偽書によくはからるゝ事あり、心すべし、されば初学のほどは、めづらしき書を得んことをば、さのみ好むべからず、
<ワ>古事記伝云々、 みづから著せる物を、かくやむことなき古書どもにならべて挙るは、おふけなく、つゝましくはおぼゆれども、上にいへるごとくにて、上代の事を、くはしく説キ示し、古学の心ばへを、つまびらかにいへる書は、外になければぞかし、されば同じくは此書も、二典とまじへて、はじめより見てよろしけれども、巻数多ければ、こゝへはまはしたる也、
<カ>古学の輩の、 古学とは、すべて後世の説にかゝはらず、何事も、古書によりて、その本を考へ、上代の事を、つまびらかに明らむる学問也、此学問、ちかき世に始まれり、契沖ほふし、歌書に限りてはあれど、此道すぢを開きそめたり、此人をぞ、此まなびのはじめの祖(オヤ)ともいひつべき、次にいさゝかおくれて羽倉ノ大人、荷田ノ東麻呂ノ宿祢と申せしは、歌書のみならず、すべての古書にわたりて、此こゝろばへを立テ給へりき、かくてわが師あがたゐの大人、この羽倉ノ大人の教をつぎ給ひ、東国に下り江戸に在て、さかりに此学を唱へ給へるよりぞ、世にはあまねくひろまりにける、大かた奈良ノ朝よりしてあなたの古ヘの、もろもろの事のさまを、こまかに精(クハ)しく考へしりて、手にもとるばかりになりぬ るは、もはら此大人の、此古学のをしへの功にぞ有ける、
<ヨ>初心のほどは、かたはしより文義を云々、 文義の心得がたきところを、はじめより、一々に解せんとしては、とどこほりて、すゝまぬことあれば、聞えぬところは、まづそのまゝにて過すぞよき、殊に世に難き事にしたるふしぶしを、まづしらんとするは、いといとわろし、たゞよく聞えたる所に、心をつけて、深く味ふべき也、こはよく聞えたる事也と思ひて、なほざりに見過せば、すべてこまかなる意味もしられず、又おほく心得たがひの有て、いつまでも、其誤リをえさとらざる事有也、
<タ>其末の事は、一々さとし教るに及ばず、 此こゝろをふと思ひよりてよめる歌、筆のついでに、「とる手火も今はなにせむ夜は明てほがらほがらと道見えゆくを、
<レ>ひろくも見るべく又云々、 博識とかいひて、随分ひろく見るも、よろしきことなれども、さては緊要の書を見ることの、おのづからおろそかになる物なれば、あながちに広きをよきこととのみもすべからず、その同じ力を、緊要の書に用るもよろしかるべし、又これかれにひろく心を分るは、たがひに相たすくることもあり、又たがひに害となることもあり、これらの子細をよくはからふべき也、
<ソ>五十音のとりさばき云々、 これはいはゆる仮字反シの法、音の堅横の通用の事、言の延(ノベ)つゞめの例などにつきて、古語を解キ明らむるに、要用のこと也、かならずはじめより心がくべし、仮字づかひは、古ヘのをいふ、近世風の歌よみのかなづかひは、中昔よりの事にて、古書にあはず、
<ツ>語釈は緊要にあらず、 語釈とは、もろもろの言の、然云フ本の意を考へて、釈(トク)をいふ、たとへば天(アメ)といふはいかなること、地(ツチ)といふはいかなることと、釈(ト)くたぐひ也、こは学者の、たれもまづしらまほしがることなれども、これにさのみ深く心をもちふべきにはあらず、こは大かたよき考へは出来がたきものにて、まづはいかなることとも、しりがたきわざなるが、しひてしらでも、事かくことなく、しりてもさのみ益なし、されば諸の言は、その然云フ本の意を考ヘんよりは、古人の用ひたる所をよく考へて、云々(シカシカ)の言は、云々の意に用ひたりといふことを、よく明らめ知るを、要とすべし、言の用ひたる意をしらでは、其所の文意聞えがたく、又みづから物を書クにも、言の用ひやうたがふこと也、然るを今の世古学の輩、ひたすら然云フ本の意をしらんことをのみ心がけて、用る意をば、なほざりにする故に、書をも解し誤り、みづからの歌文も、言の意用ひざまたがひて、あらぬ ひがこと多きぞかし、
<ネ>からぶみをもまじへよむべし、 漢籍を見るも、学問のために益おほし、やまと魂だによく堅固(カタ)まりて、動くことなければ、晝夜からぶみをのみよむといへども、かれに惑はさるゝうれひはなきなり、然れども世の人、とかく倭魂(ヤマトタマシヒ)かたまりにくき物にて、から書をよめば、そのことよきにまどはされて、たぢろきやすきならひ也、ことよきとは、その文辞を、麗(ウルハ)しといふにはあらず、詞の巧にして、人の思ひつきやすく、まどはされやすきさまなるをいふ也、すべてから書は、言巧にして、ものの理非を、かしこくいひまはしたれば、人のよく思ひつく也、すべて学問すぢならぬ 、よのつねの世俗の事にても、弁舌よく、かしこく物をいひまはす人の言には、人のなびきやすき物なるが、漢籍もさやうなるものと心得居べし、
<ナ>古書の注釈を作らんと云々、 書をよむに、たゞ何となくてよむときは、いかほど委く見んと思ひても、限リあるものなるに、みづから物の注釈をもせんと、こゝろがけて見るときには、何れの書にても、格別に心のとまりて、見やうのくはしくなる物にて、それにつきて、又外にも得る事の多きもの也、されば其心ざしたるすぢ、たとひ成就はせずといへども、すべて学問に大いに益あること也、是は物の注釈のみにもかぎらず、何事にもせよ、著述をこゝろがくべき也、
<ラ>万葉集をよくまなぶべし、 此書は、歌の集なるに、二典の次に挙て、道をしるに甚ダ益ありといふは、心得ぬことに、人おもふらめども、わが師ノ大人の古学のをしへ、専ラこゝにあり、其説に、古ヘの道をしらんとならば、まづいにしへの歌を学びて、古風の歌をよみ、次に古の文を学びて、古ヘぶりの文をつくりて、古言をよく知リて、古事記日本紀をよくよむべし、古言をしらでは、古意はしられず、古意をしらでは、古の道は知リがたかるべし、といふこゝろばへを、つねづねいひて、教へられたる、此教へ迂遠(マハリドホ)きやうなれども、然らず、その故は、まづ大かた人は、言(コトバ)と事(ワザ)と心(ココロ)と、そのさま大抵相かなひて、似たる物にて、たとへば心のかしこき人は、いふ言のさまも、なす事(ワザ)のさまも、それに応じてかしこく、心のつたなき人は、いふ言のさまも、なすわざのさまも、それに応じてつたなきもの也、又男は、思ふ心も、いふ言も、なす事も、男のさまあり、女は、おもふ心も、いふ言も、なす事(ワザ)も、女のさまあり、されば時代々々の差別も、又これらのごとくにて、心も言も事も、上代の人は、上代のさま、中古の人は、中古のさま、後世の人は、後世のさま有て、おのおのそのいへる言となせる事と、思へる心と、相かなひて似たる物なるを、今の世に在て、その上代の人の、言をも事をも心をも、考へしらんとするに、そのいへりし言は、歌に伝はり、なせりし事は、史に伝はれるを、その史も、言を以て記したれば、言の外ならず、心のさまも、又歌にて知ルべし、言と事と心とは其さま相かなへるものなれば、後世にして、古の人の、思へる心、なせる事(ワザ)をしりて、その世の有さまを、まさしくしるべきことは、古言古歌にある也、さて古の道は、二典の神代上代の事跡のうへに備はりたれば、古言古歌をよく得て、これを見るときは、其道の意、おのづから明らかなり、さるによりて、上にも、初学のともがら、まづ神代正語をよくよみて、古語のやうを口なれしれとはいへるぞかし、古事記は、古伝説のまゝに記されてはあれども、なほ漢文なれば、正(マサ)しく古言をしるべきことは、万葉には及ばず、書紀は、殊に漢文のかざり多ければ、さら也、さて二典に載れる歌どもは、上古のなれば、殊に古言古意をしるべき、第一の至宝也、然れどもその数多からざれば、ひろく考るに、ことたらざるを、万葉は、歌数いと多ければ、古言はをさをさもれたるなく、伝はりたる故に、これを第一に学べとは、師も教へられたる也、すべて神の道は、儒仏などの道の、善悪是非をこちたくさだせるやうなる理窟は、露ばかりもなく、たゞゆたかにおほらかに、雅(ミヤビ)たる物にて、歌のおもむきぞ、よくこれにかなへりける、さて此万葉集をよむに、今の本、誤字いと多く、訓もわろきことおほし、初学のともがら、そのこゝろえ有べし、
<ム>みづからも古風の歌をまなびてよむべし、 すべて万ヅの事、他のうへにて思ふと、みづからの事にて思ふとは、浅深の異なるものにて、他のうへの事は、いかほど深く思ふやうにても、みづからの事ほどふかくはしまぬ 物なり、歌もさやうにて、古歌をば、いかほど深く考へても、他のうへの事なれば、なほ深くいたらぬところあるを、みづからよむになりては、我ガ事なる故に、心を用ること格別にて、深き意味をしること也、さればこそ師も、みづから古風の歌をよみ、古ぶりの文をつくれとは、教へられたるなれ、文の事は、古文は、延喜式八の巻なる諸の祝詞、続紀の御世々々の宣命など、古語のまゝにのこれる文也、二典の中にも、をりをりは古語のまゝなる文有リ、其外の古書共にも、をりをりは古文まじれることあり、これかれをとりて、のりとすべし、万葉は歌にて、歌と文とは、詞の異なることなどあれども、歌と文との、詞づかひのけぢめを、よくわきまへえらびてとらば、歌の詞も、多くは文にも用ふべきものなれば、古文を作る学びにも、万葉はよく学ばでかなはぬ書也、なほ文をつくるべき学びかた、心得なども、古体近体、世々のさまなど、くさぐさいふべき事多くあれども、さのみはこゝにつくしがたし、大抵歌に准へても心得べし、そのうち文には、いろいろのしなあることにて、其品によりて、詞のつかひやう其外、すべての書キやう、かはれること多ければ、其心得有べし、いろいろのしなとは、序、或は論、或は紀事、或は消息など也、さて後世になりて、万葉ぶりの歌を、たててよめる人は、たゞ鎌倉ノ右大臣殿のみにして、外には聞えざりしを、吾師ノ大人のよみそめ給ひしより、其教によりて、世によむ人おほく出来たるを、其人どもの心ざすところ、必しも古の道を明らめんためによむにはあらず、おほくはたゞ歌を好みもてあぞぶのみにして、その心ざしは、近世風の歌よみの輩と、同じこと也、さればよき歌をよみ出むと心がくることも、近世風の歌人とかはる事なし、それにつきては、道のために学ぶすぢをば、姑くおきて、今は又ただ歌のうへにつきての心得どもをいはんとす、そもそも歌は、思ふ心をいひのぶるわざといふうちに、よのつねの言とはかはりて、必ズ詞にあやをなして、しらべをうるはしくとゝのふる道なり、これ神代のはじめより然り、詞のしらべにかゝはらず、たゞ思ふまゝにいひ出るは、つねの詞にして、歌といふものにはあらず、さてその詞のあやにつきて、よき歌とあしき歌とのけぢめあるを、上代の人は、たゞ一わたり、歌の定まりのしらべをとゝのへてよめるのみにして、後世の人のやうに、思ひめぐらして、よくよまんとかまへ、たくみてよめることはなかりし也、然れども、その出来たるうへにては、おのづからよく出来たると、よからざるとが有て、その中にすぐれてよく出来たる歌は、世間にもうたひつたへて、後ノ世までものこりて、二典に載れる歌どもなど是也、されば二典なる歌は、みな上代の歌の中にも、よにすぐれたるかぎりと知べし、古事記には、たゞ歌をのせんためのみに、其事を記されたるも、これかれ見えたるは、その歌のすぐれたるが故なり、さてかくのごとく歌は、上代よりして、よきとあしきと有て、人のあはれときゝ、神の感じ給ふも、よき歌にあること也、あしくては、人も神も、感じ給ふことなし、神代に天照大御神の、天の石屋(イハヤ)にさしこもり坐(マシ)し時、天ノ兒屋根ノ命の祝詞(ノリトゴト)に、感じ給ひしも、その辞のめでたかりし故なること、神代紀に見えたるがごとし、歌も准へて知ルべし、さればやゝ世くだりては、かまへてよき歌をよまんと、もとむるやうになりぬ るも、かならず然らではえあらぬ、おのづからの勢ヒにて、万葉に載れるころの歌にいたりては、みなかまへてよくよまんと、求めたる物にこそあれ、おのづからに出来たるは、いとすくなかるべし、万葉の歌すでに然るうへは、まして後世今の世には、よくよまんとかまふること、何かはとがむべき、これおのづからの勢ヒなれば、古風の歌をよまん人も、随分に詞をえらびて、うるはしくよろしくよむべき也、
<ウ>万葉の歌の中にても云々、 此集は、撰びてあつめたる集にはあらず、よきあしきえらびなく、あつめたれば、古ヘながらも、あしき歌も多し、善悪をわきまへて、よるべきなり、今の世、古風をよむともがらの、よみ出る歌を見るに、万葉の中にても、ことに耳なれぬ、あやしき詞をえり出つかひて、ひたすらにふるめかして、人の耳をおどろかさんとかまふるは、いといとよろしからぬこと也、歌も文も、しひてふるくせんとて、求め過たるは、かへすかへすうるさく、見ぐるしきものぞかし、万葉の中にても、たゞやすらかに、すがたよき歌を、手本として、詞もあやしきをば好むまじき也、さて又歌も文も、同じ古風の中にも、段々有て、いたく古きと、さもあらぬ とあれば、詞もつゞけざまも、大抵その全体の程に応ずべきことなるに、今の人のは、全体のほどに応ぜぬ 詞をつかふこと多くして、一首一編の内にも、いたくふるき詞づかひのあるかと見れば、又むげに近き世の詞もまじりなどして、其体混雑せり、すべて古風家の歌は、後世家の、あまり法度にかゝはり過るを、にくむあまりに、たゞ法度にかゝはらぬ を、心高くよき事として、そのよみかた、甚ダみだりなり、万葉のころとても、法度といふことこそなけれ、おのづから定まれる則(ノリ)は有て、みだりにはあらざりしを、法度にかゝはらぬ を、古ヘと心得るは、大にひがごと也、既に今の世にして、古ヘをまねてよむからは、古ヘのさだまりにかなはぬ事有ては、古風といふ物にはあらず、今の人は、口にはいにしへいにしへと、たけだけしくよばはりながら、古ヘの定まりを、えわきまへざるゆゑに、古ヘは定まれることはなかりし物と思ふ也、万葉風をよむことは、ちかきほど始まりたることにて、いまだその法度を示したる書などもなき故に、とかく古風家の歌は、みだりなることおほきぞかし、
<ヰ>長歌をもよむべし、 長歌は、古風のかた殊にまされり、古今集なるは、みなよくもあらず、中にいとつたなきもあり、大かた今の京になりての世には、長歌よむことは、やうやうにまれになりて、そのよみざまも、つたなくなりし也、後世にいたりては、いよいよよむことまれなりしを、万葉風の歌をよむ事おこりて、近きほどは、又皆長歌をも多くよむこととなりて、其中には、万葉集に入ルとも、をさをさはづかしかるまじきほどのも、まれには見ゆるは、いともいともめでたき大御世の栄えにぞ有ける、そもそも世の中のあらゆる諸の事の中には、歌によまんとするに、後世風にては、よみとりがたき事の多かるに、返て古風の長歌にては、よくよみとらるゝことおほし、これらにつけても、古風の長歌、必ズよみならふべきこと也、
<ノ>又後世風をもすてずして云々、 今の世、万葉風をよむ輩は、後世の歌をば、ひたすらあしきやうに、いひ破れども、そは実によきあしきを、よくこゝろみ、深く味ひしりて、然いふにはあらず、たゞ一わたりの理にまかせて、万ヅの事、古ヘはよし、後世はわろしと、定めおきて、おしこめてそらづもりにいふのみ也、又古と後世との歌の善悪を、世の治乱盛衰に係(カケ)ていふも、一わたりの理論にして、事実にはうときこと也、いと上代の歌のごとく、実情のまゝをよみいでばこそ、さることわりもあらめ、後世の歌は、みなつくりまうけてよむことなれば、たとひ治世の人なりとも、あしき風を学びてよまば、其歌あしかるべく、乱世の人にても、よき風をまなばば、其歌などかあしからん、又男ぶり女ぶりのさだも、緊要にあらず、つよき歌よわき歌の事は、別にくはしく論ぜり、大かた此古風と後世と、よしあしの論は、いといと大事にて、さらにたやすくはさだめがたき、子細どもあることなるを、古学のともがら、深きわきまへもなく、かろがろしくたやすげに、これをさだめいふは、甚ダみだりなること也、そもそも古風家の、後世の歌をわろしとするところは、まづ歌は、思ふこゝろをいひのぶるわざなるに、後世の歌は、みな実情にあらず、題をまうけて、己が心に思はぬ事を、さまざまとつくりて、意をも詞をも、むつかしくくるしく巧みなす、これみな偽リにて、歌の本意にそむけり、とやうにいふこれ也、まことに一わたりのことわりは、さることのやうなれども、これくはしきさまをわきまへざる論也、其故は、上にいへる如く、歌は、おもふまゝに、たゞにいひ出る物にあらず、かならず言にあやをなして、とゝのへいふ道にして、神代よりさる事にて、そのよく出来てめでたきに、人も神も感じ給ふわざなるがゆゑに、既に万葉にのれるころの歌とても、多くはよき歌をよまむと、求めかざりてよめる物にして、実情のまゝのみにはあらず、上代の歌にも、枕詞序詞などのあるを以てもさとるべし、枕詞や序などは、心に思ふことにはあらず、詞のあやをなさん料に、まうけたる物なるをや、もとより歌は、おもふ心をいひのべて、人に聞カれて、聞ク人のあはれと感ずるによりて、わが思ふ心は、こよなくはるくることなれば、人の聞クところを思ふも、歌の本意也、されば世のうつりもてゆくにしたがひて、いよいよ詞にあやをなし、よくよまむともとめたくむかた、次第次第に長(チヤウ)じゆくは、必ズ然らではかなはぬ 、おのづからの勢ヒにて、後世の歌に至りては、実情をよめるは、百に一ツも有がたく、皆作りことになれる也、然はあれども、その作れるは、何事を作れるぞといへば、その作りざまこそ、世々にかはれることあれ、みな世の人の思ふ心のさまを作りいへるなれば、作り事とはいへども、落るところはみな、人の実情のさまにあらずといふことなく、古ヘの雅情にあらずといふことなし、さればひたすらに後世風をきらふは、その世々に変じたるところをのみ見て、変ぜぬところのあることをばしらざる也、後世の歌といへども、上代と全く同じきところあることを思ふべし、猶いはば、今の世の人にして、万葉の古風をよむも、己が実情にはあはず、万葉をまねびたる作り事也、もしおのが今思ふ実情のまゝによむをよしとせば、今の人は、今の世俗のうたふやうなる歌をこそよむべけれ、古ヘ人のさまをまねぶべきにはあらず、万葉をまねぶも、既に作り事なるうへは、後世に題をまうけて、意を作りよむも、いかでかあしからん、よき歌をよまんとするには、数おほくよまずはあるべからず、多くよむには、題なくはあるべからず、これらもおのづから然るべきいきほひ也、そもそも後世風、わろき事もあるは、勿論のこと也、然れどもわろき事をのみえり出て、わろくいはんには、古風の方にも、わろきことは有べし、一トむきに後世をのみ、いひおとすべきにあらず、後世風の歌の中にも、又いひしらずめでたくおもしろく、さらに古風にては、よみえがたき趣どもの有ルこと也、すべてもろもろの事の中には、古ヘよりも、後世のまされる事も、なきにあらざれば、ひたぶるに後世を悪しとすべきにもあらず、歌も、古ヘと後とを、くらべていはんには、たがひに勝劣ある中に、おのれ数十年よみこゝろみて、これを考るに、万葉の歌のよきが、ゆたかにすぐれたることは、勿論なれども、今の世に、それをまなびてよむには、猶たらはぬ ことあるを、世々を経て、やうやうにたらひて、備はれる也、さればこそ、今の世に古風をよむ輩も、初心のほどこそ、何のわきまへもなく、みだりによみちらせ、すこしわきまへも出来ては、万葉風のみにては、よみとりがたき事など多き故に、やうやうと後世風の意詞をも、まじへよむほどに、いつしか後世風にちかくなりゆきて、なほをりをりは、ふるめきたる事もまじりて、さすがに全くの後世風にもあらず、しかも又古今集のふりにもあらず、おのづから別 に一風なるも多きぞかし、これ古風のみにては、事たらざるところのあるゆゑなり、すべて後世風をもよまではえあらぬ よしを、なほいはば、まづ万葉の歌を見るに、やすらかにすがたよきは、其趣いづれもいづれも、似たる事のみ多く、よめる意大抵定まれるが如くにて、或は下ノ句全く同じき歌などもおほく、すべて同じやうなる歌いと多し、まれまれにめづらしき事をよめるは、多くはいやしげにて、歌ざまよろしからず、然るを万葉の後今の世まで、千余年を経たる間ダ、歌よむ人、みなみな万葉風をのみ守りて変ぜずして、しかもよき歌をよまんとせば、皆万葉なる歌の口まねをするやうにのみ出来て、外によむべき事なくして、新タによめる詮なかるべし、されば世々を経て、古人のよみふるさぬ おもむきを、よみ出んとするには、おのづから世々に、そのさま変ぜではかなはず、次第にたくみもこまやかにふかくなりゆかではかなはぬだうり也、古人の多くよみたる事を、同じさまによみたらんには、其歌よしとても、人も神も感じ給ふことあるべからず、もし又古ヘによみふるさぬ事を、一ふしめずらしく、万葉風にてよまんとせば、いやしくあしき歌になりぬべし、かの集の歌すらさやうなれば、まして今の世をや、此事猶一ツのたとへを以ていはん、古風は白妙衣のごとく、後世風は、くれなゐ紫いろいろ染たる衣のごとし、白妙衣は、白たへにしてめでたきを、染衣も、その染色によりて、又とりどりにめでたし、然るを白妙めでたしとて、染たるをば、ひたぶるにわろしとすべきにあらず、たゞその染たる色には、よきもありあしきもあれば、そのあしきをこそ棄ツべきなれ、色よきをも、おしこめてすてんは、偏(ヒトムキ)ならずや、今の古風家の論は、紅紫などは、いかほど色よくても、白妙に似ざれば、みなわろしといはんが如し、宣長もはら古学によりて、人にもこれを教へながら、みづからよむところの歌、古風のみにあらずして、後世風をも、おほくよむことを、心得ずと難ずる人多けれども、わが思ひとれるところは、上の件のごとくなる故に、後世風をも、すてずしてよむ也、其中に古風なるは数すくなくして、返て後世風なるが多きは、古風をよむべき事すくなく、後世風をよむ事おほきが故也、すべていにしへは、事すくなかりしを、後世になりゆくまにまに、万の事しげくなるとおなじ、さて吾は、古風後世風ならべよむうちに、古と後とをば、清くこれを分ちて、たがひに混雑なきやうにと、深く心がくる也、さて又初学の輩、わがをしへにしたがひて、古風後世風ともによまんとせんに、まづいづれを先キにすべきぞといふに、万の事、本をまづよくして後に、末に及ぶべきは勿論のことなれども、又末よりさかのぼりて、本にいたるがよき事もある物にて、よく思ふに、歌も、まず後世風より入て、そを大抵得て後に、古風にかゝりてよき子細もあり、その子細を一ツ二ツいはば、後世風をまづよみならひて、その法度のくはしきをしるときは、古風をよむにも、その心得有て、つゝしむ故に、あまりみだりなることはよまず、又古風は時代遠ければ、今の世の人、いかによくまなぶといへども、なほ今の世の人なれば、その心全く古人の情のごとくには、変化しがたければ、よみ出る歌、古風とおもへども、猶やゝもすれば、近き後世の意詞のまじりやすきもの也、すべて歌も文も、古風と後世とは、全体その差別なくてはかなはざるに、今の人の歌文は、とかく古と後と、混雑することをまぬかれざるを、後世風をまづよくしるときは、是は後世ぞといふことを、わきまへしる故に、その誤リすくなし、後世風をしらざれば、そのわきまへなき故に、返て後世に落ることおほきなり、すべて古風家、後世風をば、いみしく嫌ひながら、みづから後世風の混雑することをえしらざるは、をかしきこと也、古風をよむひ人も、まづ後世風を学びて益あること、猶此外にも有也、古と後との差別をだによくわきまふるときは、後世風をよむも、害あることなし、にくむべきことにあらず、たゞ古と後と混雑するをこそ、きらふべきものなれ、これはたゞ歌文のうへのみにもあらず、古の道をあきらむる学問にも、此わきまへなくしては、おぼえず後世意にも漢意にも、落入ルこと有べし、古意と後世意と漢意とを、よくわきまふること、古学の肝要なり、
<オ>後世風の中にもさまざまよきあしきふりふりあるを云々、 かの染衣のさまざまの色には、よきも有リあしきもあるが如く、後世風の歌も、世々を経て、つぎつぎにうつり変れる間ダには、よきとあしきとさまざまの品ある、其中にまず古今集は、世もあがり、撰びも殊に精しければ、いといとめでたくして、わろき歌はすくなし、中にもよみ人しらずの歌どもには、師もつねにいはれたるごとく、殊によろしきぞ多かる、そはおほくふるき歌の、ことにすぐれたる也、さて此集は、古風と後世風との中間に在て、かのふるき歌どもになどは、万葉の中のよき歌どものさまと、をさをさかはらぬ もおほくして、殊にめでたければ、古風の歌を学ぶ輩も、これをのりとしてよろしき也、然れども大かた光孝天皇宇多天皇の御代のころよりこなたの歌は、万葉なるとはいたくかはりて、後世風の方にちかきさまなれば、此集をば、姑く後世風の始めの、めでたき歌とさだめて、明暮にこれを見て、今の京となりてよりこなたの、歌といふ物のすべてのさまを、よく心にしむべき也、次に後撰集拾遺集は、えらびやう甚ダあらくみだりにして、えもいはぬわろき歌の多き也、然れどもよき歌も又おほく、中にはすぐれたるもまじれり、さて次に後拾遺集よりこなたの、代々の撰集ども、つぎつぎに盛衰善悪さまざまあれども、そをこまかにいはむには、甚ダ事長ければ、今は省きて、その大抵をつまみていはば、其間ダに新古今集は、そのころの上手たちの歌どもは、意も詞もつゞけざまも、一首のすがたも、別に一ツのふりにて、前にも後にもたぐひなく、其中に殊によくとゝのひたるは、後世風にとりては、えもいはずおもしろく心ふかくめでたし、そもそも上代より今の世にいたるまでを、おしわたして、事のたらひ備りたる、歌の真盛(マサカリ)は、古今集ともいふべけれども、又此新古今にくらべて思へば、古今集も、なほたらはずそなはらざる事あれば、新古今を真盛といはんも、たがふべからず、然るに古風家の輩、殊に此集をわろくいひ朽(クタ)すは、みだりなる強(シヒ)ごと也、おほかた此集のよき歌をめでざるは、風雅の情をしらざるものとこそおぼゆれ、但し此時代の歌人たち、あまりに深く巧をめぐらされたるほどに、其中に又くせ有て、あしくよみ損じたるは、殊の外に心得がたく、無理なるもおほし、されどさるたぐひなるも、詞うるはしく、いひまはしの巧なる故に、無理なる聞えぬ事ながらに、うちよみあぐるに、おもしろくて捨がたくおぼゆるは、此ほどの歌共也、されどこれは、此時代の上手たちの、あやしく得たるところにて、さらに後の人の、おぼろけにまねび得べきところにはあらず、しひてこれをまねびなば、えもいはぬ すゞろごとになりぬべし、いまだしきほどの人、ゆめゆめこのさまをしたふべからず、されど又、歌のさまをくはしくえたらんうへにては、さのみいひてやむべきにもあらず、よくしたゝめなば、まねび得ることも、などかは絶てなからん、さて又玉葉風雅の二ツの集は、為兼卿流の集なるが、彼卿の流の歌は、皆ことやうなるものにして、いといやしくあしき風なり、されば此一流は、其時代よりして、異風と定めしこと也、さて件ンの二集と、新古今とをのぞきて外は、千載集より、廿一代のをはり新続古今集までのあひだ、格別にかはれることなく、おしわたして大抵同じふりなる物にて、中古以来世間普通の歌のさまこれなり、さるは世の中こぞりて、俊成卿定家卿の教ヘをたふとみ、他門の人々とても、大抵みなその掟を守りてよめる故に、よみかた大概に同じやうになりて、世々を経ても、さのみ大きにかはれる事はなく、定まれるやうになれるなるべし、世に二條家の正風体といふすがた是也、此ノ代々の集の内にも、すこしづゝは、勝劣も風のかはりもあれども、大抵はまづ同じこと也、さて初学の輩の、よむべき手本には、いづれをとるべきぞといふに、上にいへるごとく、まづ古今集をよく心にしめおきて、さて件ンの千載集より新続古今集までは、新古今と玉 葉風雅とをのぞきては、いづれをも手本としてよし、然れども件の代々の集を見渡すことも、初心のほどのつとめには、たへがたければ、まづ世間にて、頓阿ほふしの草庵集といふ物などを、会席などにもたづさへ持て、題よみのしるべとすることなるが、いかにもこれよき手本也、此人の歌、かの二條家の正風といふを、よく守りて、みだりなることなく、正しき風にして、わろき歌もさのみなければ也、其外も題よみのためには、題林愚抄やうの物を見るも、あしからず、但し歌よむ時にのぞみて、歌集を見ることは、癖(クセ)になるものなれば、なるべきたけは、書を見ずによみならふやうにすべし、たゞ集共をば、常々心がけてよく見るべき也、さてこれより近世のなべての歌人のならひの、よろしからざる事共をいひて、さとさむとす、そはまづ道統といひて、其伝来の事をいみしきわざとして、尊信し、歌も教ヘも、たゞ伝来正しき人のみ、ひたすらによき物とかたくこゝろえ、伝来なき人のは、歌も教ヘも、用ひがたきものとし、又古ヘの人の歌及び其家の宗匠の歌などをば、よきあしきを考へ見ることもなく、たゞ及ばぬ こととして、ひたぶるに仰ぎ尊み、他門の人の歌といへば、いかほどよくても、これをとらず、心をとゞめて見んともせず、すべて己が学ぶ家の法度掟を、ひたすらに神の掟の如く思ひて、動くことなく、これをかたく守ることをのみ詮とするから、その教ヘ法度にくゝられて、いたくなづめる故に、よみ出る歌みなすべて、詞のつゞけざまも、一首のすがたも、近世風又一トやうに定まりたる如くにて、わろきくせ多く、其さまいやしく窮屈にして、たとへば手も足もしばりつけられたるものの、うごくことかなはざるがごとく、いとくるしくわびしげに見えて、いさゝかもゆたかにのびらかなるところはなきを、みづからかへり見ることなく、たゞそれをよき事と、かたくおぼえたるは、いといと固陋にして、つたなく愚なること、いはんかたなし、かくのごとくにては、歌といふものの本意にたがひて、さらに雅(ミヤビ)の趣にはあらざる也、そもそも道統伝来のすぢを、重くいみしき事にするは、もと仏家のならひよりうつりて、宋儒の流なども然也、仏家には、諸宗おのおの、わが宗のよゝの祖師の説をば、よきあしきをえらぶことなく、あしきことあるをも、おしてよしと定めて尊信し、それにたがへる他の説をば、よくても用ひざるならひなるが、近世の神学者歌人などのならひも、全くこれより出たるもの也、さるは神学者歌人のみにもあらず、中昔よりこなた、もろもろの芸道なども、同じ事にて、いと愚なる世のならはしなり、たとひいかほど伝来はよくても、その教よろしからず、そのわざつたなくては、用ひがたし、其中に諸芸などは、そのわざによりては、伝来を重んずべきよしもあれども、学問や歌などは、さらにそれによることにあらず、古ヘの集共を見ても知べし、その作者の家すぢ伝来には、さらにかゝはることなく、誰にもあれ、ひろくよき歌をとれり、されば定家卿の教ヘにも、和歌に師匠なしとのたまへるにあらずや、さて又世々の先達の立チおかれたる、くさぐさの法度掟の中には、かならず守るべき事も多く、又中にはいとつたなくして、必ズかゝはるまじきも多きことなるに、ひたぶるに固くこれを守るによりて、返て歌のさまわろくなれることも、近世はおほし、すべて此道の掟は、よきとあしきとをえらびて、守るべき也、ひたすらになづむべきにはあらず、又古人の歌は、みな勝(スグ)れたる物のごとくこゝろえ、たゞ及ばぬ事とのみ思ひて、そのよしあしを考へ見んともせざるは、いと愚なること也、いにしへに歌といへども、あしきことも多く、歌仙といへども、歌ごとに勝(スグ)れたる物にもあらざれば、たとひ人まろ貫之の歌なりとも、実によき与あしき与を、考へ見て、及ばぬ までも、いろいろと評論をつけて見るべき也、すべて歌の善悪を見分る稽古、これに過たる事なし、大に益あること也、然るに近世の歌人のごとく、及ばぬ事とのみ心得居ては、すべて歌の善悪を見分べき眼の、明らかになるよしなくして、みづからの歌も、よしやあしやをわきまふることあたはず、さやうにていつまでもたゞ、宗匠にのみゆだねもたれてあらんは、いふかひなきわざならずや、すべて近世風の歌人のごとく、何事も愚につたなき学びかたにては、生涯よき歌は出来るものにあらずと知べし、さて又はじめにいへる如く、歌をよむのみにあらず、ふるき集共をはじめて、歌書に見えたる万の事を、解キ明らむる学ビ有リ、世にこれを分て歌学者といへり、歌学といへば、歌よむ事をまなぶことなれども、しばらく件のすぢを分て然いふ也、いにしへに在リては、顕昭法橋など此すぢなるが、其説はゆきたらはぬ 事多けれども、時代ふるき故に、用ふべき事もすくなからざるを、近世三百年以来の人々の説は、かの近世やうの、おろかなる癖(クセ)おほきうへに、すべてをさなきことのみなれば、いふにもたらず、然るに近く契沖ほふし出てより、此学大キにひらけそめて、歌書のとりさばきは、よろしくなれり、さて歌をよむ事をのみわざとすると、此歌学の方をむねとすると、二やうなるうちに、かの顕昭をはじめとして、今の世にいたりても、歌学のかたよろしき人は、大抵いづれも、歌よむかたつたなくて、歌は、歌学のなき人に上手がおほきもの也、こは専一にすると、然らざるとによりて、さるだうりも有ルにや、さりとて歌学のよき人のよめる歌は、皆必ズわろきものと、定めて心得るはひがこと也、此二すぢの心ばへを、よく心得わきまへたらんには、歌学いかでか歌よむ妨ゲとはならん、妨ゲとなりて、よき歌をえよまぬ は、そのわきまへのあしきが故也、然れども歌学の方は、大概にても有べし、歌よむかたをこそ、むねとはせまほしけれ、歌学のかたに深くかゝづらひては、仏書からぶみなどにも、広くわたらでは、事たらはぬわざなれば、其中に無益の書に、功(テマ)をつひやすこともおほきぞかし、
<ク>物語ぶみどもをもつねに見るべし、 此事の子細は、源氏物語の玉の小櫛に、くはしくいへれば、こゝにはもらしつ、
<ヤ>いにしへ人の風雅(ミヤビ)のおもむきをしるは云々、 すべて人は、雅(ミヤビ)の趣をしらでは有ルべからず、これをしらざるは、物のあはれをしらず、心なき人なり、かくてそのみやびの趣をしることは、歌をよみ、物語書などをよく見るにあり、然して古ヘ人のみやびたる情をしり、すべて古ヘの雅(ミヤビ)たる世の有リさまを、よくしるは、これ古の道をしるべき階梯也、然るに世間の物学びする人々のやうを見渡すに、主(ムネ)と道を学ぶ輩は、上にいへるごとくにておほくはたゞ漢流の議論理窟にのみかゝづらひて、歌などよむをば、たゞあだ事のやうに思ひすてて、歌集などは、ひらきて見ん物ともせず、古人の雅情を、夢にもしらざるが故に、その主とするところの古の道をも、しることあたはず、かくのごとくにては、名のみ神道にて、たゞ外国の意のみなれば、実には道を学ぶといふものにはあらず、さて又歌をよみ文を作りて、古をしたひ好む輩は、たゞ風流のすぢにのみまつはれて、道に事をばうちすてて、さらに心にかくることなければ、よろづにいにしへをしたひて、ふるき衣服調度などをよろこび、古き書をこのみよむたぐひなども、皆たゞ風流のための玩物にするのみ也、そもそも人としては、いかなる者も、人の道をしらでは有べからず、殊に何のすぢにもせよ、学問をもして、書をもよむほどの者の、道に心をよすることなく、神のめぐみのたふときわけなどをもしらず、なほざりに思ひて過すべきことにはあらず、古ヘをしたひたふとむとならば、かならずまづその本たる道をこそ、第一に深く心がけて、明らめしるべきわざなるに、これをさしおきて、末にのみかゝづらふは、実にいにしへを好むといふものにはあらず、さては歌をよむも、まことにあだ事にぞ有ける、のりなががをしへにしたがひて、ものまなびせんともがらは、これらのこゝろをよく思ひわきまへて、あなかしこ、道をなほざりに思ひ過すことなかれ、
こたみ此書かき出デつることは、はやくより、をしへ子どもの、ねんごろにこひもとめけるを、年ごろいとまなくなどして、聞過しきぬるを、今は古事記ノ伝もかきをへつればとて、又せちにせむるに、さのみもすぐしがたくて、物しつる也、にはかに思ひおこしたるしわざなれば、なほいふべき事どもの、もれたるなども多かりなんを、うひまなびのためには、いさゝかたすくるやうもありなんや、
いかならむうひ山ぶみのあさごろも
浅きすそ野のしるべばかりも
本 居 宣 長
寛政十年十月の廿一日のゆふべに書をへぬ
須 受 能 耶 蔵 板
<ク>物語ぶみどもをもつねに見るべし、 此事の子細は、源氏物語の玉の小櫛に、くはしくいへれば、こゝにはもらしつ、
<ヤ>いにしへ人の風雅(ミヤビ)のおもむきをしるは云々、 すべて人は、雅(ミヤビ)の趣をしらでは有ルべからず、これをしらざるは、物のあはれをしらず、心なき人なり、かくてそのみやびの趣をしることは、歌をよみ、物語書などをよく見るにあり、然して古ヘ人のみやびたる情をしり、すべて古ヘの雅(ミヤビ)たる世の有リさまを、よくしるは、これ古の道をしるべき階梯也、然るに世間の物学びする人々のやうを見渡すに、主(ムネ)と道を学ぶ輩は、上にいへるごとくにておほくはたゞ漢流の議論理窟にのみかゝづらひて、歌などよむをば、たゞあだ事のやうに思ひすてて、歌集などは、ひらきて見ん物ともせず、古人の雅情を、夢にもしらざるが故に、その主とするところの古の道をも、しることあたはず、かくのごとくにては、名のみ神道にて、たゞ外国の意のみなれば、実には道を学ぶといふものにはあらず、さて又歌をよみ文を作りて、古をしたひ好む輩は、たゞ風流のすぢにのみまつはれて、道に事をばうちすてて、さらに心にかくることなければ、よろづにいにしへをしたひて、ふるき衣服調度などをよろこび、古き書をこのみよむたぐひなども、皆たゞ風流のための玩物にするのみ也、そもそも人としては、いかなる者も、人の道をしらでは有べからず、殊に何のすぢにもせよ、学問をもして、書をもよむほどの者の、道に心をよすることなく、神のめぐみのたふときわけなどをもしらず、なほざりに思ひて過すべきことにはあらず、古ヘをしたひたふとむとならば、かならずまづその本たる道をこそ、第一に深く心がけて、明らめしるべきわざなるに、これをさしおきて、末にのみかゝづらふは、実にいにしへを好むといふものにはあらず、さては歌をよむも、まことにあだ事にぞ有ける、のりなががをしへにしたがひて、ものまなびせんともがらは、これらのこゝろをよく思ひわきまへて、あなかしこ、道をなほざりに思ひ過すことなかれ、
こたみ此書かき出デつることは、はやくより、をしへ子どもの、ねんごろにこひもとめけるを、年ごろいとまなくなどして、聞過しきぬるを、今は古事記ノ伝もかきをへつればとて、又せちにせむるに、さのみもすぐしがたくて、物しつる也、にはかに思ひおこしたるしわざなれば、なほいふべき事どもの、もれたるなども多かりなんを、うひまなびのためには、いさゝかたすくるやうもありなんや、
いかならむうひ山ぶみのあさごろも
浅きすそ野のしるべばかりも
本 居 宣 長
寛政十年十月の廿一日のゆふべに書をへぬ
須 受 能 耶 蔵 板
『玉勝間』抄
◇『玉勝間』抄
宣長の代表作の一つ『玉勝間』から、代表的な章段を抜粋した。底本には『本居宣長全集』を使用した。抜粋の基準は、『全訳玉勝間詳解』前嶋成著、大修館書店(昭和33年1月刊)に採録されたものとし、若干の追加をした。前嶋氏の著作は、学習参考書で、その選択基準には、資料編として相応しくないものがある。例えば、「54, 為兼卿の歌の事」など。今回はそれも敢えて採用した。
また、私たちが最も必要とする章段の一つ「伊勢国」は採用されていない。
>>『玉勝間』
>>「『玉勝間』って面白い本?」
【目次】
玉賀都萬一の巻
巻頭歌
初若菜
3 儒者の皇國の事をばしらずとてある事
4 古書どものこと
5 また
6 また
7 又
8 また
9 また
10 もろこしぶみをもよむべき事
11 學問して道をしる事
12 がくもん
13 からごゝろ
14 おかしとをかしと二つある事
15 東宮をたがひにゆづりて
16 漢意
17 又
18 言をもじといふ事
19 あらたなる説を出す事
20 音便の事
21 からうたのよみざま
22 大神宮の茅葺なる説
23 清水寺の敬月ほうしが歌の事
玉かつま二の巻
櫻の落葉
24 兩部唯一といふ事
25 道にかなはぬ世中のしわざ
26 道をおこなふさだ
27 から國聖人の世の祥瑞といふもの
28 姓氏の事
29 又
30 神典のときざま
31 ふみよむことのたとへ
32 あらたにいひ出たる説はとみに人のうけひかぬ事
33 又
34 儒者名をみだる事
35 松嶋の日記といふ物
36 ふみども今はえやすくなれる事
37 おのが物まなびの有しやう
38 あがたゐのうしの御さとし言
39 おのれあがたゐの大人の敎をうけしやう
40 師の説になづまざる事
41 わがをしへ子にいましめおくやう
42 五十連音をおらんだびとに唱へさせたる事
玉かつま三の巻
たちばな
43 から國にて孔丘が名をいむ事
44 から人のおやのおもひに身をやつす事
45 富貴をねがはざるをよき事にする諭ひ
46 神の御ふみをとける世々のさま
玉勝間四の巻
わすれ草
47 故郷
48 うき世
49 世の人かざりにはからるゝたとひ
50 ひとむきにかたよることの論ひ
51 前後と説のかはる事
52 人のうせたる後のわざ
53 櫻を花といふ事
54 為兼卿の歌の事
55 もろこしの經書といふものの説とりどりなる事
56 もろこし人の説こちたくくだくだしき事
57 初學の詩つくるべきやうを敎ヘたる説
58 歌は詞をえらぶべき事
59 兼好法師が詞のあげつらひ
60 うはべをつくる世のならひ
61 學者のまづかたきふしをとふ事
たまかつま五の巻
枯野のすゝき
62 あやしき事の説
63 歌の道 さくら花
64 いせ物語眞名本の事
65 いせ物がたりをよみていはまほしき事ども一つ二つ
66 業平ノ朝臣のいまはの言の葉
玉かつま六の巻
からあゐ
67 書うつし物かく事
68 手かく事
69 業平ノ朝臣の月やあらぬてふ歌のこゝろ
70 縣居大人の傳
71 花のさだめ
72 玉あられ
73 かなづかひ
74 古き名どころを尋ぬる事
75 天の下の政神事をさきとせられし事
たまかつま七の巻
ふぢなみ
76 神社の祭る神をしらまほしくする事
77 おのが仕奉る神を尊き神になさまほしくする事
78 皇孫天孫と申す御号
79 神わざのおとろへのなげかはしき事
80 よの人の神社は物さびたるをたふとしとする事
81 唐の國人あだし國あることをしらざりし事
82 おらんだといふ國のまなび
83 もろこしになきこと
84 ある人の言
85 土佐國に火葬なし
86 はまなのはし
87 おのれとり分て人につたふべきふしなき事
88 もろこしの老子の説まことの道に似たる所ある事
89 道をとくことはあだし道々の意にも世の人のとりとらざるにもかゝはるまじき事
90 香をきくといふは俗言なる事
91 もろこしに名高き物しり人の佛法を信じたりし事
92 世の人佛の道に心のよりやすき事
93 ゐなかにいにしへの雅言ののこれる事
玉かつま八の巻
萩の下葉
94 ゐなかに古ヘのわざののこれる事
95 ふるき物またそのかたをいつはり作る事
96 言の然いふ本の意をしらまほしくする事
97 今の人の歌文ひがことおほき事
98 歌もふみもよくとゝのふはかたき事
99 こうさく くわいどく 聞書
100 枕詞
101 もろこしの國に丙吉といひし人の事
102 周公旦がくひたる飯を吐出して賢人に逢たりといへる事
103 藤谷ノ成章といひし人の事
104 ある人のいへること
105 らくがき らくしゅ
玉勝間九の巻
花の雪
106 道のひめこと
107 契沖が歌をとけるやう
108 つねに異なる字音のことば
109 八百萬ノ神といふを書紀に八十萬ノ神と記されたる事
110 人ノ名を文字音にいふ事
111 神をなほざりに思ひ奉る世のならひをかなしむ事
たまかつま十の巻
山菅
112 物まなびのこゝろばへ
113 いにしへよりつたはれる事の絶るをかなしむ事
114 もろもろの物のことをよくしるしたる書あらまほしき事
115 譬ヘといふものの事
116 物をときさとす事
117 源氏物語をよむことのたとへ
118 さらしなのにきに見えたること
119 おのが帰雁のうた
120 師をとるといふ事
玉勝間十一の巻
さねかづら
121 人のうまるゝはじめ死て後の事
122 うひ学びの輩の歌よむさま
123 後の世ははづかしきものなる事
124 うたを思ふほどにあること
125 假字のさだ
126 皇國の学者のあやしき癖
127 万葉集をよむこゝろばへ
128 足ことをしるといふ事
玉かつま十二の巻
やまぶき
129 又妹背山
130 俊成卿定家卿などの歌をあしくいひなす事
131 物しり人もののことわりを論ずるやう
132 歌に六義といふ事
133 物まなびはその道をよくえらびて入そむべき事
134 八景といふ事
135 よはひの賀に歌を多く集むる事 なき跡にいしぶみをたつる事
136 金銀ほしからぬかほする事
137 雪蛍をあつめて書よみけるもろこしのふること
玉勝間十三の巻
おもひ草
138 しづかなる山林をすみよしといふ事
139 おのが京のやどりの事
140 しちすつの濁音の事
玉かつま十四の巻
つらつら椿
141 一言一行によりてひとのよしあしきをさだむる事
142 今の世の名の事
143 絵の事
144 又
145 又
146 又
147 また
148 漢ふみにしるせる事みだりに信ずまじき事
149 世の中の萬の事は皆神の御しわざなる事
150 聖人を尊む事
151 ト筮
152 から人の語かしこくいひとれること
153 論語
154 又
155 又
156 はやる
157 人のうまれつきさまざまある事
158 紙の用
159 古より後世のまされる事
160 名所
161 教誡
162 孟子
163 如是我聞
164 佛道
165 世の人まことのみちにこゝろつかざる事
166 宋の代 明の代
167 天
168 國を治むるかたの学問
169 漢籍の説と皇の古伝説とのたとへ
170 米粒を佛法ぼさつなどいひならへる事
171 世の人のこざかしきこといふをよしとする事
172 假字
173 から國の詞つかひ
174 佛經の文
175 神のめぐみ
176 道
【本文】
玉賀都萬一の巻
言草のすゞろにたまる玉がつま
つみてこゝろを野べのすさびに
初 若 菜 一
此言草よ、なにくれと数おほくつもりぬるを、いとくだくだしけれど、やりすてむもさすがにて、かきあつめむとするを、けふはむ月十八日、子ノ日なれば、よし有ておぼゆるまゝに、まづこの巻の名、かく物しつ、次々のも、又そのをりをり思ひよらんまゝに、何ともかともつけてむとす、
かたみとはのこれ野澤の水ぐきの
淺くみじかきわかななりとも
3 儒者の皇國の事をばしらずとてある事[九]
儒者に皇國の事をとふには、しらずといひて、恥とせず、から國の事をとふに、しらずといふをば、いたく恥と思ひて、しらぬ ことをもしりがほにいひまぎらはす、こはよろづをからめかさむとするあまりに、其身をも漢人めかして、皇國をばよその國のごともてなさむとするなるべし、されどなほから人にはあらず、御國人なるに、儒者とあらむものの、おのが國の事しらであるべきわざかは、但し皇國の人に對ひては、さあらむも、から人めきてよかンめれど、もし漢國人のとひたらむには、我は、そなたの國の事はよくしれれども、わが國のことはしらずとは、さすがにえいひたらじをや、もしさもいひたらむには、己が國の事をだにえしらぬ 儒者の、いかでか人の國の事をはしるべきとて、手をうちて、いたくわらひつべし、
17 又[三六]
漢國にも、神あることを、むげにしらざるにもあらず、尊みもし祀(マツ)りもすめるは、まことの傳への、かたはしは有しならむ、然れ共此天地をはじめ給ひ、國土(クニツチ)萬ノ物を造りなし給ひ、人の道をも萬の事をも始め給ひ、世ノ中のよろづの事をしり行ひ給ふ神たちのましますことをば、すべてえしらずして、これらの重(オモ)く大きなる事には、たゞ天をのみいひて、ただかたはらなる小(チイサ)き事にのみ、神をばいひて、此世を照し給ふ日ノ大御神をすら、かろがろしく、ことなることもなき物のごとくして、此神をもとも畏れ尊み奉るべきことをだにしらざるは、いとあさましきわざなりかし、
18 言をもじといふ事[三八]
歌のみそぢひともじを、近きころ古學するともがらは、字といふことをきらひて、卅一言といひ、五もじ七もじなどをも、五言七言とのみいふなれ共、古今集の序にも、みそもじあまりひともじと有て、いにしへよりかくいへり、すべてもじといふは、文字の字の音にて、御國言にはあらざれども、もんじといはずして、もじといへば、字の音共聞えず、御國言めきてきこゆる、此外にも、ほうし(ママ)ぜにふみなどのたぐひ、字の音をなほして、やがて御國言に用ひたる例多かり、されば古き物語ぶみなどにも、詞をことばといひてわろき所をば、もじといへることおほし、のもじをもじなどいふ類也、これらをも、近く古學の輩の、のの語をの語などいふなるは、中々にからめきてぞ聞ゆる、源氏物語などには、別 (ワカレ)といふことをすら、わかれといふもじといひ、葵ノ巻には、今はさるもじいませ給へなどあるも、さる詞といふこと也、かく詞といひてもよきをだに、もじといへることあれば、まして五もじ七もじのもじをもじなどのたぐひは、さら也、
19 あらたなる説を出す事[三九]
ちかき世、學問の道ひらけて、大かた萬ヅのとりまかなひ、さとくかしこくなりぬ るから、とりどりにあらたなる説を出す人おほく、其説よろしければ、世にもてはやさるゝによりて、なべての學者、いまだよくもとゝのはぬ ほどより、われおとらじと、よにことなるめづらしき説を出して、人の耳をおどろかすこと、今のよのならひ也、其中には、ずゐぶむによろしきことも、まれにはいでくめれど、大かたいまだしき學者の、心はやりていひ出ることは、たゞ人にまさらむ勝(カタ)むの心にて、かろがろしく、まへしりへをもよくも考へ合さず、思ひよれるまゝにうち出る故に、多くはなかなかなるいみしきひがことのみ也、すべて新なる説を出すは、いと大事也、いくたびもかへさひおもひて、よくたしかなるよりどころをとらへ、いづくまでもゆきとほりて、たがふ所なく、うごくまじきにあらずは、たやすくは出すまじきわざ也、その時には、うけばりてよしと思ふも、ほどへて後に、いま一たびよく思へば、なほわろかりけりと、我ながらだに思ひならるゝ事の多きぞかし、
20 音便の事[四一]
古語の中にも、いとまれまれに音便あれども、後の世のとはみな異なり、後ノ世の音便は、奈良の末つかたより、かつがつみえそめて、よゝをふるまゝに、やうやうにおほくなれり、そは漢字三音考の末にいへるごとく、おのづから定まり有て、もろもろの音便五くさをいでず、抑此音便は、みな正しき言にあらず、くづれたるものなれば、古書などをよむには、一つもまじふべきにあらざるを、後ノ世の物しり人、その本ノ語をわきまへずして、よのつねにいひなれたる音便のまゝによむは、なほざりなること也、すべて後ノ世には、音便の言いといと多くして、まどひやすし、本ノ語をよく考へて、正しくよむべき也、中にもんといふ音のことに多き、これもと古言の正しき音にあらず、ことごとく後の音便也とこゝろうべし、さてその音便のんの下は、本ノ語は清ム音なるをも、濁(ニゴ)らるゝ音なれば、皆かならず濁る例也、たとへばねもころといふ言を、後にはねんごろといふがごとし、んの下のこもじ、本ノ語は清ム音なるを、上のもをんといふにひかれて濁る、みな此格なり、然るを世の人、その音便のときの濁リに口なれて、正しくよむときも、ねもごろと、こをにごるはひがこと也、此例多し、心得おくべし、
21 からうたのよみざま[四五]
童蒙抄に、ある人北野にまうでて、東行南行雲眇々、二月三月日遲々、といふ詩を詠じけるに、すこしまどろみたる夢に、とさまにゆきかうさまにゆきてくもはるばる、きさらぎやよひ日うらうら、とこそ詠ずれと仰られけり云々とあり、むかしは詩をも、うるはしくはかくさまにこそよみあげけめ、詠(ナガ)むるはさらなり、いにしへはすべてからぶみをよむにも、よまるゝかぎりは、皇國言(ミクニコトバ)によめるは、字音(モジゴエ)は聞にくかりしが故也、然るを今はかへさまになりて、なべての詞も、皇國言よりは、字音なるをうるはしきことにし、書よむにも、よまるゝかぎりは、字音によむをよきこととすなるは、からぶみまなびのためには、字音によむかたよろしき故もあればぞかし、
22 大神宮の茅葺(カヤブキ)なる説[四七]
伊勢の大御神の宮殿(ミアラカ)の茅葺なるを、後世に質素を示す戒メなりと、ちかき世の神道者といふものなどのいふなるは、例の漢意にへつらひたる、うるさきひがこと也、質素をたふとむべきも、事にこそはよれ、すべて神の御事に、質素をよきにすること、さらになし、御殿(ミアラカ)のみならず、獻る物なども何も、力のたへたらんかぎり、うるはしくいかめしくめでたくするこそ、神を敬ひ奉るにはあれ、みあらか又獻り物などを、質素にするは、禮(ヰヤ)なく心ざし淺きしわざ也、そもそも伊勢の大宮の御殿の茅ぶきなるは、上つ代のよそひを重(オモ)みし守りて、變(カヘ)給はざる物なり、然して茅葺ながらに、その荘麗(イカメシ)きことの世にたぐひなきは、皇御孫(スメミマノ)命の、大御神を厚く尊み敬ひ奉り給ふが故也、さるを御(ミ)みづからの宮殿(ミアラカ)をば、美麗(ウルハシ)く物し給ひて、大御神の宮殿をしも、質素にし給ふべきよしあらめやは、すべてちかき世に、神道者のいふことは、皆からごゝろにして、古ヘの意にそむけりと知べし、
23 清水寺の敬月ほうしが歌の事[五七]
承久のみだれに、清水寺の敬月法師といひけるほうし、京の御方にて、官軍にくはゝり、宇治におもむきけるを、かたきにとらはれて、殺さるべかりけるに、歌をよみて、敵泰時に見せける、「勅なれば身をばすててきものゝふの八十宇治川の瀬にはたゝねど、かたき此歌にめでて、命ゆるして、遠流にぞしたりける、此事も同じ書に見ゆ、
玉かつま二の巻
櫻 の 落 葉 二
なが月の十日ごろ、せんざいの櫻の葉の、色こくなりたるが、物がなしきゆふべの風に、ほろほろとおつるを見て、よめる、
花ちりし同じ梢をもみぢにも
又ものおもふ庭ざくらかな
これをもひろひいれて、やがて巻の名としつ、
24 兩部唯一といふ事[七二]
天下の神社のうち、神人のみつかふる社を、俗(ヨ)に唯一といひ、法師のつかふる社を、兩部といふ、又兩部神道とて敎ふる一ながれもあり、兩部とは、佛の道の密敎の、胎藏界金剛界の兩部といふことを、神の道に合せたるを、兩部習合の神道といへり、かの兩部を以て、神道に合せたるよし也、部ノ字にて心得べし、神と佛とをさしていふ兩にはあらず、さて又唯一といふは、兩部神道といふもののあるにつきて、その兩部をまじへざるよし也、されば神の道の唯一なるは、もとよりの事ながら、その名は、兩部神道有ての後也、然るに此名を、兩部に對へたるにはあらず、天人唯一の義也といひなせるは、いみしきひがこと也、天と人とひとつ也とは、いかなることわりぞや、そはたゞ天をうへもなくいみしき物にすなる、漢意よりいひなしたることにて、いたく古ヘの意にそむけり、抑天は、天つ神たちのまします御國にこそあれ、人はいかでかそれと一つなることわりあらむ、世の物しり人みな、古ヘのこゝろをえさとらず、ひたぶるに漢意にまどへるから、何につけても、ことわり深げなることを説むとて、しひてかゝることをもいふにぞ有ける、
25 道にかなはぬ世中のしわざ[七三]
道にかなはずとて、世に久しく有リならひつる事を、にはかにやめむとするはわろし、たゞそのそこなひのすぢをはぶきさりて、ある物はあるにてさしおきて、まことの道を尋ぬ べき也、よろづの事を、しひて道のまゝに直しおこなはむとするは、中々にまことの道のこゝろにかなはざることあり、萬の事は、おこるもほろぶるも、さかりなるもおとろふるも、みな神の御心にしあれば、さらに人の力もて、えうごかすべきわざにはあらず、まことの道の意をさとりえたらむ人は、おのづから此ことわりはよく明らめしるべき也、
26 道をおこなふさだ[七四]
道をおこなふことは、君とある人のつとめ也、物まなぶ者のわざにはあらず、もの學ぶ者は、道を考へ尋ぬ るぞつとめなりける、吾はかくのごとく思ひとれる故に、みづから道をおこなはむとはせず、道を考へ尋ぬ ることをぞつとむる、そもそも道は、君の行ひ給ひて、天の下にしきほどこらし給ふわざにこそあれ、今のおこなひ道にかなはざらむからに、下なる者の、改め行はむは、わたくし事にして、中々に道のこゝろにあらず、下なる者はたゞ、よくもあれあしくもあれ、上の御おもむけにしたがひをる物にこそあれ、古ヘの道を考へ得たらんからに、私に定めて行ふべきものにはあらずなむ、
27 から國聖人の世の祥瑞といふもの[七六]
もろこしの國に、いにしへ聖人といひし者の世には、その德にめでて、麒麟鳳凰などいひて、ことごとしき鳥けだ物いで、又くさぐさめでたきしるしのあらはれし事をいへれども、さるたぐひのめづらしき物も、たゞ何となく、をりをりは出ることなるべきを、たまたま出ぬ れば、德にめでて、天のあたへたるごといひなして、聖人のしるしとして、世の人に、いみしき事に思はせたるもの也、よろづにかゝるぞ、かの國人のしわざなりける、
28 姓氏の事[七七]
今の世には、姓(ウヂ)のしられざる人のみぞおほかる、さるはいかなるしづ山がつといへども、みな古ヘの人の末にてはあるなれば、姓のなきはあらざンなる事なるを、中むかしよりして、いはゆる苗字をのみよびならへるまゝに、下々なるものなどは、ことごとしく姓と苗字とをならべてなのるべきにもあらざるから、おのづから姓はうづもれ行て、世々をへては、みづからだにしらずなれる也、さて後になりのぼりて、人めかしくなれる者などは、姓のなきを、物げなくあかぬ 事に思ひては、あるは藤原、あるは源平など、おのがこのめるを、みだりにつくこといと多し、すべて足利の末のみだれ世よりして、天の下の姓氏たゞしからず、皆いとみだりがはしくぞなれりける、その中に、近き世の人のなのる姓は、十に九つまでは、源藤原平也、そはいにしへのもろもろの氏々は絶て、此三氏(ミウヂ)のかぎり多くのこれるにやと思へば、さにはあらず、中昔よりして、此三うぢの人のみ、つかさ位 高きは有て、他(ホカ)のもろもろの氏人どもは、皆すぎすぎにいやしくのみなりくだれるから、其人は有リながら、其姓はおのづからかくれゆきて、をさをさしる人もなく、絶たるがごとなれる也、又ひとつには、近き世の人は、古ヘのもろもろの姓をば、しることなくして、姓はたゞ源平藤橘などのみなるがごと心得たるから、おのが好みてあらたにつくも、皆これらのうちなるが故に、古ヘもろもろの姓はきこえず、いよいよ源平藤は多くなりきぬ る也、又古ヘの名高くすぐれたる人をしたひては、その子孫ぞといひなして、學問するものは、菅原大江などになり、武士は多く源になるたぐひあり、すべて近き世は、よろしきほどの人々も、たゞ苗字をなんむねとはして、姓はかへりて、おもてにはたゝざるならひなる故に、おのが心にまかせて物する也、さて又ちかき年ごろ、萬葉ぶりの歌をよみ、古學をする輩は、又ふるき姓をおもしろく思ひて、世の人のきゝもならはぬ 、ふるめかしきを、あらたにつきてなのる者はた多かるは、かの漢學者の、からめかして、苗字をきりたちて、一字になすと同じたぐひにて、いとうるさく、その人の心のをさなさの、おしはからるゝわざぞかし、いにしへをしたふとならば、古ヘのさだめを守りて、殊にさやうに、姓などをみだりにはすまじきわざなるに、かの禍津日ノ前の探湯(クカダチ)をもおそれざンなるは、まことに古ヘを好むとはいはるべしやは、そもそも姓は、先祖より傳はる物にこそあれ、上より賜はらざるむかぎりは、心にまかせて、しかわたくしにすべき物にはあらず、まことに其姓にはあらずとも、中ごろの先祖、もしはおほぢ父の世より、なのり來(キ)てあらんは、なほさても有べきを、おのがあらたに物せむことは、いといとあるまじきわざになむ、姓しられざらんには、たゞ苗字をなのりてあらむに、なでふことかはあらん、すべて古ヘをこのまむからに、よろづをあながちに古ヘめかさむとかまふるは、中々にいにしへのこゝろにはあらざるものをや、
29 又[七八]
よに源平藤橘とならべて、四姓といふ、源平藤原は、中昔より殊に廣き姓なれば、さもいひつべきを、橘はしも、かの三うぢにくらぶれば、こよなくせばきを、此かぞへのうちに入ぬ るは、いかなるよしにかあらむ、おもふに嵯峨ノ天皇の御代に、皇后の御ゆかりに、尊みそめたりしならひにやあらむ、かくて此四姓のことは、もろこしぶみにさへいへる、そはむかしこゝの人の物せしが、語りつらむを聞て、しるしたンなるを、かしこまでしられたることと、よにいみしきわざにぞ思ふめる、すべて何事にまれ、こゝの事の、かしこの書に見えたるをば、いみしきことにおもふなるは、いとおろかなることなり、すべてかの國の書には、その國々の人の、語れる事を、きけるまゝにしるせれば、なにのめづらしくいみしきことかはあらむ、
30 神典のときざま[八五]
中昔よりこなた、神典(カミノミフミ)を説(トク)人ども、古ヘの意言(ココロコトバ)をばたづねむ物とも思ひたらず、たゞひたぶるに、外國(トツクニ)の儒佛の意にすがりて、其理をのみ思ひさだして、萬葉を見ず、むげに古ヘの意言(ココロコトバ)をしらざるが故に、かのから意(ゴコロ)のことわりの外に、別 (コト)にいにしへの旨(ムネ)ありて、明らかなることをえしらず、これによりて古ヘのむねはことごとくうづもれて、顯れず、神の御(ミ)ふみも、皆から意になりて、道明らかならざる也、かくておのが神の御書をとく趣は、よのつねの説どもとはいたく異にして、世々の人のいまだいはざることどもなる故に、世の學者、とりどりにとがむることおほし、されどそはたゞ、さきの人々の、ひたすら漢意にすがりて説(トキ)たる説(コト)をのみ聞なれて、みづからも同じく、いまだからごゝろのくせの清くさらざるから、そのわろきことをえさとらざるもの也、おのがいふおもむきは、ことごとく古事記書紀にしるされたる、古ヘの傳説(ツタヘゴト)のまゝ也、世の人々のいふは、みなそのまどひ居る漢意に説曲(トキマゲ)たるわたくしごとにて、いたく古ヘノ傳ヘ説(ゴト)と異也、此けぢめは、古事記書紀をよく見ば、おのづから分るべき物をや、もしおのが説をとがめむとならば、まづ古事記書紀をとがむべし、此御典(ミフミ)どもを信ぜんかぎりは、おのが説をとがむることえじ、
31 ふみよむことのたとへ[八九]
須賀ノ直見がいひしは、廣く大きなる書をよむは、長き旅路をゆくがごとし、おもしろからぬ 所もおほかるを經(ヘ)行ては、又おもしろくめさむるこゝちする浦山にもいたる也、又あしつよき人は、はやく、よわきはゆくことおそきも、よく似たり、とぞいひける、おかしきたとへなりかし、
32 あらたにいひ出たる説はとみに人のうけひかぬ事[九〇]
大かたよのつねにことなる、新しき説をおこすときには、よきあしきをいはず、まづ一わたりは、世中の學者ににくまれそしらるゝものなり、あるはおのがもとよりより來つる説と、いたく異なるを聞ては、よきあしきを味ひ考ふるまでもなく、始めよりひたぶるにすてて、とりあげざる者もあり、あるは心のうちには、げにと思ふふしもおほくある物から、さすがに近き人のことにしたがはむことのねたくて、よしともあしともいはで、たゞうけぬ かほして過すたぐひもあり、あるはねたむ心のすゝめるは、心にはよしと思ひながら、其中の疵をあながちにもとめ出て、すべてをいひけたむとかまふる者も有リ、大かたふるき説をば、十が中に七ツ八ツはあしきをも、あしき所をばおほひかくして、わづかに二ツ三ツのとるべき所のあるをとりたてて、力のかぎりたすけ用ひんとし、新しきは、十に八ツ九ツよくても、一ツ二ツのわろきことをいひたてて、八ツ九ツのよきことをも、おしけちて、ちからのかぎりは、我も用ひず、人にももちひさせじとする、こは大かたの學者のならひ也、然れども又まれまれには、新なる説のよきを聞ては、ふるきがあしきことをさとりて、すみやかに改めしたがふたぐひも、なきにはあらず、ふるきをいかにぞや思ひて、かくはあらじかとまでは思ひよれども、みづから定むる力なくて、疑はしながら、さてあるなどは、あらたなるよき説をきゝては、かくてこそはと、いみしくよろこびつゝ、たりまちにしたがふたぐひも有かし、大かた新なる説は、いかによくても、すみやかには用ふる人まれなるものなれど、よきは、年をへても、おのづからつひには世の人のしたがふものにて、あまねく用ひらるれば、其時にいたりては、はじめにねたみそしりしともがらも、心には悔しく思へど、おくればせにしたがはむも、猶ねたく、人わろくおぼえて、こゝろよからずながら、ふるきをまもりてやむともがらも多かり、しか世ノ中の論さだまりて、皆人のしたがふよになりては、始メよりすみやかに改めしたがひつる人は、かしこく心さとくおもはれ、ふるきにかゝづらひて、とかくとゞこほれる人は、心おそくいふかひなく思はるゝわざぞかし、
33 又[九一]
此ちかき年ごろとなりてはやうやうに古學のよきことを、世にもしれるともがらあまた出来て、物よくわきまへたる人は、おほく契沖をたふとむめり、そもそも契沖のよきことをしるものならば、かれよりもわが縣居ノ大人の、又まさりてよきことは、おのづからしるらんに、なほ契沖にしもとゞまりて、今一きざみえすゝまざるは、いかにぞや、又縣居ノ大人まではすゝめども、其後の人の説は、なほとらじとするも、同じことにて、これみな俗(ヨ)にまけをしみとかいふすぢにて、心ぎたなきわざなるを、かならず學者のこゝろは、おほくさるものなりかし、
34 儒者名をみだる事[九三]
孔丘は、名を正すをこそいみしきわざとはしつれ、此方(ココ)の近きころのじゆしやは、よろづに名をみだることをのみつとむめり、そが中に、地(トコロ)の名などを、からめかすとて、のべもつゞめもかへも心にまかせて物するなどは、なほつみかろかるべきを、おほやけざまにあづかれる、重き名どもをさへに、わたくしの心にまかせて、みだりにあらため定めて書クなるは、いともいとも可畏(カシコ)きわざならずや、近き世に或ル儒者の、今の世は、萬ヅ名正しからず、某(ソレ)をば、今はしかしかとはいふべきにあらず、しかしかいはむこそ正しけれ、などいひて、よろづを今の世のありさまにまかせて、例の私に物せるは、いかなるひが心得ぞや、そもそもかの孔丘が名を正せるやうは、諸侯どものみだりなる、當時(ソノトキ)のありさまにはかかはらずて、ひたぶるに周王のもとの定めをこそ守りつれ、かの或ル儒者のごと、古ヘよりのさだめにもかゝわらず、今の名にもしたがはず、たゞ今の世のありさまにまかせて、わたくしにあらたに物せむは、孔丘が春秋のこゝろとは、うらうへにて、ことさらに名をみだることの、いみしきものにこそ有けれ、皇國は、物のありさまは、古ヘとかはりきぬ るも、名は、物のうつりゆく、其時々のさまにはしたがはずして、今の世とても、萬ヅになほ古ヘのを守り給ふなるは、いともいとも有がたく、孔丘が心もていはば、名のいとただしきにこそありけれ、さるをかへりてただしからずとしもいふは、何につけても、あながちに皇國をいひおとさむとする心のみすゝめるからに、そのひがことなることをも、われながらおぼえざるなめり、
35 松嶋の日記といふ物[九七]
清少納言が年老て後に、おくの松嶋に下りける、道の日記とて、やがて松しまの日記と名づけたる物、一冊あり、めづらしくおぼえて、見けるに、はやくいみしき偽書(イツハリブミ)にて、むげにつたなく見どころなき物也、さるはちかきほど、古學をする者の作れる口つきとぞ聞えたる、すべて近き年ごろは、さるいつはりぶみをつくり出るたぐひの、ことに多かる、えうなきすさびに、おほくのいとまをいれ、心をもくだきて、よの人をまどはさんとするは、いかなるたぶれ心にかあらむ、よく見る人の見るには、まこといつはりは、いとよく見えわかれて、いちじるけれど、さばかりなる人は、いといとまれにして、えしも見わかぬ もののみ、世にはおほかれば、むげの偽リぶみにもあざむかれて、たふとみもてはやすなるは、いともいともかたはらいたく、かなしきわざ也、近きころは、世中にめづらしき書をえうずるともがら多きを、めづらしきは、まことの物ならぬ がおほきを、さる心して、よくえらぶべきわざぞかし、菅原ノ大臣のかき給へりといふ、須磨の記といふ物などは、やゝよにひろごりて、たれもまことと思ひたンめる、これはたいみしき偽リ書なるをや、かかるたぐひ數しらずおほし、なずらへて心すべし、
36 ふみども今はえやすくなれる事[一〇二]
二三十年あなたまでは、歌まなびする人も、たゞちかき世の歌ぶみをのみ學びて、萬葉をまなぶことなく、又神學者といふ物も、たゞ漢ざまの理をのみさだして、古ヘのまことのこゝろをえむことを思はねば、萬葉をまなぶことなくて、すべて萬葉は、歌まなびにも、道の學びにも、かならずまづまなばでかなはぬ 書なることを、しれる人なかりき、されば、契沖ほうし、むねと此集を明らめて、古ヘの意をもかつがつうかゞひそめて、はしばしいひおきつれども、歌人も神學者も、此しるべによるべきことをしれる人なかりしかば、おのがわかくて、京にありしころなどまでは、代匠記といふ物のあることをだにしれる人も、をさをさなかりければ、其書世にまれにして、いといとえがたく、かの人の書は、百人一首の改觀抄だに、えがたかりしを、そのかみおのれ京にて、始めて人にかりて見て、かはばやと思ひて、本屋(フムマキヤ)をたづねたりしに、なかりき、板本(スリマキ)なるにいかなればなきぞととひしかば、えうずる人なき故に、すり出さずとぞいへりける、さてとかくして、からくしてぞえたりける、そのころまでは、大かたかゝりけるに、此ちかき年ごろとなりては、寫本(ウツシマキ)ながら代匠記もおほく出て、さらにえがたからずなりぬ るは、古學の道のひらけて、えうずる人おほければぞかし、さるは代匠記のみにもあらず、すべてうつしまきなる物は、家々の記録などのたぐひ、その外の書どもも、いといとえがたかりしに、何も何も、今はたやすくえらるゝこととなれるは、いともいともめでたくたふとき、御代の御榮(ミサカ)えになん有ける、
37 おのが物まなびの有しやう[一〇三]
おのれいときなかりしほどより、書をよむことをなむ、よりづよりもおもしろく思ひて、よみける、さるははかばかしく師につきて、わざと學問すとにもあらず、何と心ざすこともなく、そのすぢと定めたるかたもなくて、たゞからのやまとの、くさぐさのふみを、あるにまかせ、うるにまかせて、ふるきちかきをもいはず、何くれとよみけるほどに、十七八なりしほどより、歌よままほしく思ふ心いできて、よみはじめけるを、それはた師にしたがひて、まなべるにもあらず、人に見することなどもせず、たゞひとりよみ出るばかりなりき、集どもも、古きちかきこれかれと見て、かたのごとく今の世のよみざまなりき、かくてはたちあまりなりしほど、學問しにとて、京になんのぼりける、さるは十一のとし、父におくれしにあはせて、江戸にありし、家のなりはひをさへに、うしなひたりしほどにて、母なりし人のおもむけにて、くすしのわざをならひ、又そのために、よのつねの儒學をもせむとてなりけり、さて京に在しほどに、百人一首の改觀抄を、人にかりて見て、はじめて契沖といひし人の説をしり、そのよにすぐれたるほどをもしりて、此人のあらはしたる物、餘材抄勢語臆斷などをはじめ、其外もつぎつぎに、もとめ出て見けるほどに、すべて歌まなびのすぢの、よきあしきけぢめをも、やうやうにわきまへさとりつ、さるまゝに、今の世の歌よみの思へるむねは、大かた心にかなはず、其歌のさまも、おかしからずおぼえけれど、そのかみ同じ心なる友はなかりければ、たゞよの人なみに、ここかしこの會などにも出まじらひつゝ、よみありきけり、さて人のよむふりは、おのが心には、かなはざりけれども、おのがたててよむふりは、今の世のふりにもそむかねば、人はとがめずぞ有ける、そはさるべきことわりあり、別 にいひてん、さて後、國にかへりたりしころ、江戸よりのぼれりし人の、近きころ出たりとて、冠辭考といふ物を見せたるにぞ、縣居ノ大人の御名をも、始めてしりける、かくて其ふみ、はじめに一わたり見しには、さらに思ひもかけぬ 事のみにして、あまりこととほく、あやしきやうにおぼえて、さらに信ずる心はあらざりしかど、猶あるやうあるべしと思ひて、立かへり今一たび見れば、まれまれには、げにさもやとおぼゆるふしぶしもいできければ、又立かへり見るに、いよいよげにとおぼゆることおほくなりて、見るたびに信ずる心の出來つゝ、つひにいにしへぶりのこゝろことばの、まことに然る事をさとりぬ 、かくて後に思ひくらぶれば、かの契沖が萬葉の説(トキゴト)は、なほいまだしきことのみぞ多かりける、おのが歌まなびの有リしやう、大かたかくのごとくなりき、さて又道の學びは、まづはじめより、神書といふすぢの物、ふるき近き、これやかれやとよみつるを、はたちばかりのほどより、わきて心ざし有しかど、とりたててわざとまなぶ事はなかりしに、京にのぼりては、わざとも學ばむと、こゝろざしはすゝみぬ るを、かの契沖が歌ぶみの説になずらへて、皇國のいにしへの意をおもふに、世に神道者といふものの説(トク)おもむきは、みないたくたがへりと、はやくさとりぬ れば、師と賴むべき人もなかりしほどに、われいかで古ヘのまことのむねを、かむかへ出む、と思ふこゝろざし深かりしにあはせて、かの冠辭考を得て、かへすかへすよみあぢはふほどに、いよいよ心ざしふかくなりつゝ、此大人をしたふ心、日にそへてせちなりしに、一年此うし、田安の殿の仰セ事をうけ給はり給ひて、此いせの國より、大和山城など、こゝかしこと尋ねめぐられし事の有しをり、此松坂の里にも、二日三日とゞまり給へるを、さることつゆしらで、後にきゝて、いみしくゝちをしかりしを、かへるさまにも、又一夜やどり給へるを、うかゞひまちて、いといとうれしく、いそぎやどりにまうでて、はじめて見え奉りたりき、さてつひに名簿を奉りて、敎ヘをうけ給はることにはなりたりきかし、
38 あがたゐのうしの御さとし言[一〇四]
宣長三十あまりなりしほど、縣居ノ大人のをしへをうけ給はりそめしころより、古事記の注釋を物せむのこゝろざし有て、そのことうしにもきこえけるに、さとし給へりしやうは、われももとより、神の御典(ミフミ)をとかむと思ふ心ざしあるを、そはまづからごゝろを清くはなれて、古ヘのまことの意をたづねえずはあるべからず、然るにそのいにしへのこゝろをえむことは、古言を得たるうへならではあたはず、古言をえむことは、萬葉をよく明らむるにこそあれ、さる故に、吾はまづもはら萬葉をあきらめんとする程に、すでに年老て、のこりのよはひ、今いくばくもあらざれば、神の御ふみをとくまでにいたることえざるを、いましは年さかりにて、行さき長ければ、今よりおこたることなく、いそしみ學びなば、其心ざしとぐること有べし、たゞし世ノ中の物まなぶともがらを見るに、皆ひきゝ所を經ずて、まだきに高きところにのぼらんとする程に、ひきゝところをだにうることあたはず、まして高き所は、うべきやうなければ、みなひがことのみすめり、此むねをわすれず、心にしめて、まづひきゝところよりよくかためおきてこそ、たかきところにはのぼるべきわざなれ、わがいまだ神の御ふみをえとかざるは、もはら此ゆゑぞ、ゆめしなをこえて、まだきに高き所をなのぞみそと、いとねもころになん、いましめさとし給ひたりし、此御さとし言の、いとたふとくおぼえけるまゝに、いよいよ萬葉集に心をそめて、深く考へ、くりかへし問ヒたゞして、いにしへのこゝろ詞をさとりえて見れば、まことに世の物しり人といふものの、神の御ふみ説(トケ)る趣は、みなあらぬ から意のみにして、さらにまことの意はええぬものになむ有ける、
39 おのれあがたゐの大人の敎をうけしやう[一〇五]
宣長、縣居ノ大人にあひ奉りしは、此里に一夜やどり給へりしをり、一度のみなりき、その後はたゞ、しばしば書かよはしきこえてぞ、物はとひあきらめたりける、そのたびたび給へりし御こたへのふみども、いとおほくつもりにたりしを、ひとつもちらさで、いつきもたりけるを、せちに人のこひもとむるまゝに、ひとつふたつととらせけるほどに、今はのこりすくなくなんなりぬ る、さて古事記の注釋を物せんの心ざし深き事を申せしによりて、その上つ巻をば、考へ給へる古言をもて、假字がきにし給へるをも、かし給ひ、又中ツ巻下ツ巻は、かたはらの訓を改め、所々書キ入レなどをも、てづからし給へる本をも、かし給へりき、古事記傳に、師の説とて引たるは、多く其本にある事ども也、そもそも此大人、古學の道をひらき給へる御いさをは、申すもさらなるを、かのさとし言にのたまへるごとく、よのかぎりもはら萬葉にちからをつくされしほどに、古事記書紀にいたりては、そのかむかへ、いまだあまねく深くはゆきわたらず、くはしからぬ 事どももおほし、されば道を説(トキ)給へることも、こまかなることしなければ、大むねもいまださだかにあらはれず、たゞ事のついでなどに、はしばしいさゝかづゝのたまへるのみ也、又からごゝろを去(サ)れることも、なほ清くはさりあへ給はで、おのづから猶その意におつることも、まれまれにはのこれるなり、
40 師の説になづまざる事[一〇六]
おのれ古典(イニシヘブミ)をとくに、師の説とたがへること多く、師の説のわろき事あるをば、わきまへいふこともおほかるを、いとあるまじきことと思ふ人おほかンめれど、これすなはちわが師の心にて、つねにをしへられしは、後によき考への出來たらんには、かならずしも師の説にたがふとて、なはゞかりそとなむ、敎ヘられし、こはいとたふときをしへにて、わが師の、よにすぐれ給へる一つ也、大かた古ヘをかむかふる事、さらにひとり二人の力もて、ことごとくあきらめつくすべくもあらず、又よき人の説ならんからに、多くの中には、誤リもなどかなからむ、必わろきこともまじらではえあらず、そのおのが心には、今はいにしへのこゝろことごとく明らか也、これをおきては、あるべくもあらずと、思ひ定めたることも、おもひの外に、又人のことなるよきかむかへもいでくるわざ也、あまたの手を經(フ)るまにまに、さきざきの考ヘのうへを、なほよく考へきはむるからに、つぎつぎにくはしくなりもてゆくわざなれば、師の説なりとて、かならずなづみ守るべきにもあらず、よきあしきをいはず、ひたぶるにふるきをまもるは、學問の道には、いふかひなきわざ也、又おのが師などのわろきことをいひあらはすは、いともかしこくはあれど、それもいはざれば、世の學者その説にまどひて、長くよきをしるごなし、師の説なりとして、わろきをしりながら、いはずつゝみかくして、よさまにつくろひをらんは、たゞ師をのみたふとみて、道をば思はざる也、宣長は、道を尊み古ヘを思ひて、ひたぶるに道の明らかならん事を思ひ、古ヘの意のあきらかならんことをむねと思ふが故に、わたくしに師をたふとむことわりのかけむことをば、えしもかへり見ざることあるを、猶わろしと、そしらむ人はそしりてよ、そはせんかたなし、われは人にそしられじ、よき人にならむとて、道をまげ、古ヘの意をまげて、さてあるわざはえせずなん、これすなはちわが師の心なれば、かへりては師をたふとむにもあるべくや、そはいかにもあれ、
41 わがをしへ子にいましめおくやう[一〇七]
吾にしたがひて物まなばむともがらも、わが後に、又よきかむかへのいできたらむには、かならずわが説にななづみそ、わがあしきゆゑをいひて、よき考へをひろめよ、すべておのが人ををしふるは、道を明らかにせむとなれば、かにもかくにも、道をあきらかにせむぞ、吾を用ふるには有ける、道を思はで、いたづらにわれをたふとまんは、わが心にあらざるぞかし、
42 五十連音をおらんだびとに唱へさせたる事[一〇八]
小篠大記御野(ミヌ)といふ人は、石見ノ國濱田の殿のじゆしやにて、おのが弟子(ヲシヘノコ)也、天明八年秋のころ、肥前ノ國の長崎に物して、阿蘭陀人(オランダビト)のまうで來てあるに逢いて、音韻の事どもを論じ、皇國の五十音の事をかたりて、そを其人にとなへさせて聞しに、和のくだりの音をば、みな上にうを帶て、ゐはういの如く、ゑはうえのごとく、をはうおのごとくに呼て、いえおとはひとしからず、よく分れたり、こは何をもて然るぞと問ヒしかば、はじめの和にならへば也とぞいへりける、かの國のつねの音も、このけぢめありとぞ、此事おのが字音かなづかひにいへると、全くあへりとて、いみしくよろこびおこせたりき、なほそのをりの物がたりども、何くれといひおこせたりし中に、おかしき事どもあれど、こゝにはもらしつ、
玉かつま三の巻
た ち ば な 三
立よればむかしのたれと我ながら
わが袖あやしたちばなのかげ
これは題よみのすゞろごとなるを、とり出たるは、ことされめきて、いかにぞやもおぼゆれど、例の巻の名つけむとてなむ、
43 から國にて孔丘が名をいむ事[一一二]
もろこしの國に、今の清の代に、その王が、孔子の諱(イミナ)を避(サク)とて、丘ノ字の畫を省(ハブ)きてかくことをはじめて、秦漢より明にいたるまで、夫子を尊むことをしらざりしといひて、いみしげにみづからほこれども、これいとをこなること也、もしまことに孔丘をたふとむとならば、其道をこそよく行ふべきことなれ、その道をば、全くもおこなはずして、たゞいたづらに、其人のみをたふとまんは、なにのいみしき事かあらむ、其道をだによく行ひなば、いにしへよりいむことなくて有リ來つる、其もじは、今さらいまずとて、なでふこたかあらむ、これたゞ道をたふとみがほして、世の人にいみしく思はせむためのはかりこと也、すべてかの國人のしわざは、大かたいにしへよりかくのごとくにて、聖賢といふ物をたふとむを、いみしき事にすなるは、みなまことに尊むにはあらず、名をむさぼるしわざ也、
44 から人のおやのおもひに身をやつす事[一二二]
もろこしの國の、よゝの物しり人どもの、親の喪(オモヒ)に、身のいみしくやつれたるを、孝心ふかき事にして、しるしたるがあまたある中には、まことに心のかなしさは、いとさばかりもあらざりけむを、食物をいたくへらしなどして、痩(ヤセ)さらぼひて、ことさらにかほかたりをやつして、いみしげにうはべを見せたるがおほかりげに見ゆるは、例のいといとうるさきわざなるを、いみしき事にほめたるも又をこ也、うせにし親を、まことに思ふ心ふかくは、おのが身をも、さばかりやつすべき物かは、身のやつれに、病などもおこりて、もしはからず、なくなりなどもしたらむには、孝ある子といふべしやは、たとひさまでにはいたらずとも、しかいみしくやつれたらむをば、苔の下にも、おやはさこそこゝろぐるしく思はめ、いかでかうれしとは見む、さる親の心をば思はで、たゞ世の人めをのみつくろひて、名をむさぼるは、何のよき事ならむ、すべて孝行も何わざも、世にけやけきふるまひをして、いみしき事に思はするは、かの國人のならひにぞありける、
45 富貴をねがはざるをよき事にする諭ひ[一二三]
世々の儒者、身のまづしく賤きをうれへず、とみ榮えをながはず、よろこばざるを、よき事にすれども、そは人のまことの情(ココロ)にあらず、おほくは名をむさぼる、例のいつはり也、まれまれにさる心ならむもの有とも、そは世のひがものにこそあれ、なにのよき事ならん、ことわりならぬ ふるまひをして、あながちにながはむこそは、あしからめ、ほどほどにつとむべきわざを、いそしくつとめて、なりのぼり、富(トミ)さかえむこそ、父母にも先祖にも、孝行ならめ、身おとろへ家まづしからむは、うへなき不孝にこそ有けれ、たゞおのがいさぎよき名をむさぼるあまりに、まことの孝をわするゝも、又もろこし人のつねなりかし、
46 神の御ふみをとける世々のさま[一三三]
神御典(カミノミフミ)を説(トク)事、むかしは紀傳道の儒者の職(ワザ)にて、そのとける書、弘仁より代々の、日本紀私記これ也、そはいづれも、たゞ漢學の餘力(チカラノアマリ)をもて考へたるのみにして、神御典(カミノミフミ)をまはら學びたるものにあらざるが故に、古ヘの意詞(ココロコトバ)にくらく、すべてうひうひしく淺はかにて、もとより道の趣旨(オモムキ)も、いかなるさまとも説(トキ)たることなく、たゞ文によりて、あるべきまゝにいへるばかり也、然れども皇朝のむかしの儒者は、すべてから國のやうに、己が殊にたてたる心はなかりし故に、神の御ふみをとくとても、漢意にときまげたる、わたくし説(ゴト)もをさをさ見えず、儒意(ジュゴコロ)によれる強説(シヒゴト)もなくて、やすらかにはありしを、後ノ世にいたりては、ことに神學といふ一ながれ出來て、もはらにするともがらしあれば、つぎつぎにくはしくはなりもてゆけど、なべての世の物しり人の心、なまさかしくなりて、神の御ふみをとく者も、さかしらをさきにたてて、文のまゝには物せず、おのが好むすぢに引つけて、あるは儒意に、ときまぐることとなれり、さていよいよ心さかしくなりもてゆくまゝに、近き世となりては、又やうやうに、かの佛ごゝろをまじふるが、ひがことなることをさとりて、それをば、ことごとくのぞきてとくこととなれり、然れどもそれは、まことに古ヘの意をさとりて然るにはあらず、たゞ儒意のすゝめるから、いとへるもの也、さる故に、近き世に、神の道とて説(トク)趣は、ひたすら儒にして、さらに神の道にかなはず、このともがら、かの佛に流れたることのひがことをばしりながら、みづから又儒にながるゝことを、えさとらざるは、いかにぞや、かくして又ちかき世には、しか儒によることのわろきをも、やゝしりて、つとめてこれをのぞかんとする者も、これかれとほのめくめれども、それはたいまだ清く漢意をはなるゝことあたはで、天理陰陽などいふ説をば、なほまことと心得、ともすれば、例のさかしらの立いでては、高天ノ原を帝都のこととし、天照大御神を、天つ日にあらずとし、海神(ワタツミ)ノ宮を、一つの嶋也とするたぐひ、すべてかやうに、おのがわたくしの心をもて、さまざまに説曲(トキマゲ)ることをえまぬ かれざるは、なほみな漢意なるを、みづからさもおぼえざるは、さる癖(クセ)の、世の人のこゝろの底に、しみつきたるならひぞかし、
此ちかき年ごろとなりてはやうやうに古學のよきことを、世にもしれるともがらあまた出来て、物よくわきまへたる人は、おほく契沖をたふとむめり、そもそも契沖のよきことをしるものならば、かれよりもわが縣居ノ大人の、又まさりてよきことは、おのづからしるらんに、なほ契沖にしもとゞまりて、今一きざみえすゝまざるは、いかにぞや、又縣居ノ大人まではすゝめども、其後の人の説は、なほとらじとするも、同じことにて、これみな俗(ヨ)にまけをしみとかいふすぢにて、心ぎたなきわざなるを、かならず學者のこゝろは、おほくさるものなりかし、
34 儒者名をみだる事[九三]
孔丘は、名を正すをこそいみしきわざとはしつれ、此方(ココ)の近きころのじゆしやは、よろづに名をみだることをのみつとむめり、そが中に、地(トコロ)の名などを、からめかすとて、のべもつゞめもかへも心にまかせて物するなどは、なほつみかろかるべきを、おほやけざまにあづかれる、重き名どもをさへに、わたくしの心にまかせて、みだりにあらため定めて書クなるは、いともいとも可畏(カシコ)きわざならずや、近き世に或ル儒者の、今の世は、萬ヅ名正しからず、某(ソレ)をば、今はしかしかとはいふべきにあらず、しかしかいはむこそ正しけれ、などいひて、よろづを今の世のありさまにまかせて、例の私に物せるは、いかなるひが心得ぞや、そもそもかの孔丘が名を正せるやうは、諸侯どものみだりなる、當時(ソノトキ)のありさまにはかかはらずて、ひたぶるに周王のもとの定めをこそ守りつれ、かの或ル儒者のごと、古ヘよりのさだめにもかゝわらず、今の名にもしたがはず、たゞ今の世のありさまにまかせて、わたくしにあらたに物せむは、孔丘が春秋のこゝろとは、うらうへにて、ことさらに名をみだることの、いみしきものにこそ有けれ、皇國は、物のありさまは、古ヘとかはりきぬ るも、名は、物のうつりゆく、其時々のさまにはしたがはずして、今の世とても、萬ヅになほ古ヘのを守り給ふなるは、いともいとも有がたく、孔丘が心もていはば、名のいとただしきにこそありけれ、さるをかへりてただしからずとしもいふは、何につけても、あながちに皇國をいひおとさむとする心のみすゝめるからに、そのひがことなることをも、われながらおぼえざるなめり、
35 松嶋の日記といふ物[九七]
清少納言が年老て後に、おくの松嶋に下りける、道の日記とて、やがて松しまの日記と名づけたる物、一冊あり、めづらしくおぼえて、見けるに、はやくいみしき偽書(イツハリブミ)にて、むげにつたなく見どころなき物也、さるはちかきほど、古學をする者の作れる口つきとぞ聞えたる、すべて近き年ごろは、さるいつはりぶみをつくり出るたぐひの、ことに多かる、えうなきすさびに、おほくのいとまをいれ、心をもくだきて、よの人をまどはさんとするは、いかなるたぶれ心にかあらむ、よく見る人の見るには、まこといつはりは、いとよく見えわかれて、いちじるけれど、さばかりなる人は、いといとまれにして、えしも見わかぬ もののみ、世にはおほかれば、むげの偽リぶみにもあざむかれて、たふとみもてはやすなるは、いともいともかたはらいたく、かなしきわざ也、近きころは、世中にめづらしき書をえうずるともがら多きを、めづらしきは、まことの物ならぬ がおほきを、さる心して、よくえらぶべきわざぞかし、菅原ノ大臣のかき給へりといふ、須磨の記といふ物などは、やゝよにひろごりて、たれもまことと思ひたンめる、これはたいみしき偽リ書なるをや、かかるたぐひ數しらずおほし、なずらへて心すべし、
36 ふみども今はえやすくなれる事[一〇二]
二三十年あなたまでは、歌まなびする人も、たゞちかき世の歌ぶみをのみ學びて、萬葉をまなぶことなく、又神學者といふ物も、たゞ漢ざまの理をのみさだして、古ヘのまことのこゝろをえむことを思はねば、萬葉をまなぶことなくて、すべて萬葉は、歌まなびにも、道の學びにも、かならずまづまなばでかなはぬ 書なることを、しれる人なかりき、されば、契沖ほうし、むねと此集を明らめて、古ヘの意をもかつがつうかゞひそめて、はしばしいひおきつれども、歌人も神學者も、此しるべによるべきことをしれる人なかりしかば、おのがわかくて、京にありしころなどまでは、代匠記といふ物のあることをだにしれる人も、をさをさなかりければ、其書世にまれにして、いといとえがたく、かの人の書は、百人一首の改觀抄だに、えがたかりしを、そのかみおのれ京にて、始めて人にかりて見て、かはばやと思ひて、本屋(フムマキヤ)をたづねたりしに、なかりき、板本(スリマキ)なるにいかなればなきぞととひしかば、えうずる人なき故に、すり出さずとぞいへりける、さてとかくして、からくしてぞえたりける、そのころまでは、大かたかゝりけるに、此ちかき年ごろとなりては、寫本(ウツシマキ)ながら代匠記もおほく出て、さらにえがたからずなりぬ るは、古學の道のひらけて、えうずる人おほければぞかし、さるは代匠記のみにもあらず、すべてうつしまきなる物は、家々の記録などのたぐひ、その外の書どもも、いといとえがたかりしに、何も何も、今はたやすくえらるゝこととなれるは、いともいともめでたくたふとき、御代の御榮(ミサカ)えになん有ける、
37 おのが物まなびの有しやう[一〇三]
おのれいときなかりしほどより、書をよむことをなむ、よりづよりもおもしろく思ひて、よみける、さるははかばかしく師につきて、わざと學問すとにもあらず、何と心ざすこともなく、そのすぢと定めたるかたもなくて、たゞからのやまとの、くさぐさのふみを、あるにまかせ、うるにまかせて、ふるきちかきをもいはず、何くれとよみけるほどに、十七八なりしほどより、歌よままほしく思ふ心いできて、よみはじめけるを、それはた師にしたがひて、まなべるにもあらず、人に見することなどもせず、たゞひとりよみ出るばかりなりき、集どもも、古きちかきこれかれと見て、かたのごとく今の世のよみざまなりき、かくてはたちあまりなりしほど、學問しにとて、京になんのぼりける、さるは十一のとし、父におくれしにあはせて、江戸にありし、家のなりはひをさへに、うしなひたりしほどにて、母なりし人のおもむけにて、くすしのわざをならひ、又そのために、よのつねの儒學をもせむとてなりけり、さて京に在しほどに、百人一首の改觀抄を、人にかりて見て、はじめて契沖といひし人の説をしり、そのよにすぐれたるほどをもしりて、此人のあらはしたる物、餘材抄勢語臆斷などをはじめ、其外もつぎつぎに、もとめ出て見けるほどに、すべて歌まなびのすぢの、よきあしきけぢめをも、やうやうにわきまへさとりつ、さるまゝに、今の世の歌よみの思へるむねは、大かた心にかなはず、其歌のさまも、おかしからずおぼえけれど、そのかみ同じ心なる友はなかりければ、たゞよの人なみに、ここかしこの會などにも出まじらひつゝ、よみありきけり、さて人のよむふりは、おのが心には、かなはざりけれども、おのがたててよむふりは、今の世のふりにもそむかねば、人はとがめずぞ有ける、そはさるべきことわりあり、別 にいひてん、さて後、國にかへりたりしころ、江戸よりのぼれりし人の、近きころ出たりとて、冠辭考といふ物を見せたるにぞ、縣居ノ大人の御名をも、始めてしりける、かくて其ふみ、はじめに一わたり見しには、さらに思ひもかけぬ 事のみにして、あまりこととほく、あやしきやうにおぼえて、さらに信ずる心はあらざりしかど、猶あるやうあるべしと思ひて、立かへり今一たび見れば、まれまれには、げにさもやとおぼゆるふしぶしもいできければ、又立かへり見るに、いよいよげにとおぼゆることおほくなりて、見るたびに信ずる心の出來つゝ、つひにいにしへぶりのこゝろことばの、まことに然る事をさとりぬ 、かくて後に思ひくらぶれば、かの契沖が萬葉の説(トキゴト)は、なほいまだしきことのみぞ多かりける、おのが歌まなびの有リしやう、大かたかくのごとくなりき、さて又道の學びは、まづはじめより、神書といふすぢの物、ふるき近き、これやかれやとよみつるを、はたちばかりのほどより、わきて心ざし有しかど、とりたててわざとまなぶ事はなかりしに、京にのぼりては、わざとも學ばむと、こゝろざしはすゝみぬ るを、かの契沖が歌ぶみの説になずらへて、皇國のいにしへの意をおもふに、世に神道者といふものの説(トク)おもむきは、みないたくたがへりと、はやくさとりぬ れば、師と賴むべき人もなかりしほどに、われいかで古ヘのまことのむねを、かむかへ出む、と思ふこゝろざし深かりしにあはせて、かの冠辭考を得て、かへすかへすよみあぢはふほどに、いよいよ心ざしふかくなりつゝ、此大人をしたふ心、日にそへてせちなりしに、一年此うし、田安の殿の仰セ事をうけ給はり給ひて、此いせの國より、大和山城など、こゝかしこと尋ねめぐられし事の有しをり、此松坂の里にも、二日三日とゞまり給へるを、さることつゆしらで、後にきゝて、いみしくゝちをしかりしを、かへるさまにも、又一夜やどり給へるを、うかゞひまちて、いといとうれしく、いそぎやどりにまうでて、はじめて見え奉りたりき、さてつひに名簿を奉りて、敎ヘをうけ給はることにはなりたりきかし、
38 あがたゐのうしの御さとし言[一〇四]
宣長三十あまりなりしほど、縣居ノ大人のをしへをうけ給はりそめしころより、古事記の注釋を物せむのこゝろざし有て、そのことうしにもきこえけるに、さとし給へりしやうは、われももとより、神の御典(ミフミ)をとかむと思ふ心ざしあるを、そはまづからごゝろを清くはなれて、古ヘのまことの意をたづねえずはあるべからず、然るにそのいにしへのこゝろをえむことは、古言を得たるうへならではあたはず、古言をえむことは、萬葉をよく明らむるにこそあれ、さる故に、吾はまづもはら萬葉をあきらめんとする程に、すでに年老て、のこりのよはひ、今いくばくもあらざれば、神の御ふみをとくまでにいたることえざるを、いましは年さかりにて、行さき長ければ、今よりおこたることなく、いそしみ學びなば、其心ざしとぐること有べし、たゞし世ノ中の物まなぶともがらを見るに、皆ひきゝ所を經ずて、まだきに高きところにのぼらんとする程に、ひきゝところをだにうることあたはず、まして高き所は、うべきやうなければ、みなひがことのみすめり、此むねをわすれず、心にしめて、まづひきゝところよりよくかためおきてこそ、たかきところにはのぼるべきわざなれ、わがいまだ神の御ふみをえとかざるは、もはら此ゆゑぞ、ゆめしなをこえて、まだきに高き所をなのぞみそと、いとねもころになん、いましめさとし給ひたりし、此御さとし言の、いとたふとくおぼえけるまゝに、いよいよ萬葉集に心をそめて、深く考へ、くりかへし問ヒたゞして、いにしへのこゝろ詞をさとりえて見れば、まことに世の物しり人といふものの、神の御ふみ説(トケ)る趣は、みなあらぬ から意のみにして、さらにまことの意はええぬものになむ有ける、
39 おのれあがたゐの大人の敎をうけしやう[一〇五]
宣長、縣居ノ大人にあひ奉りしは、此里に一夜やどり給へりしをり、一度のみなりき、その後はたゞ、しばしば書かよはしきこえてぞ、物はとひあきらめたりける、そのたびたび給へりし御こたへのふみども、いとおほくつもりにたりしを、ひとつもちらさで、いつきもたりけるを、せちに人のこひもとむるまゝに、ひとつふたつととらせけるほどに、今はのこりすくなくなんなりぬ る、さて古事記の注釋を物せんの心ざし深き事を申せしによりて、その上つ巻をば、考へ給へる古言をもて、假字がきにし給へるをも、かし給ひ、又中ツ巻下ツ巻は、かたはらの訓を改め、所々書キ入レなどをも、てづからし給へる本をも、かし給へりき、古事記傳に、師の説とて引たるは、多く其本にある事ども也、そもそも此大人、古學の道をひらき給へる御いさをは、申すもさらなるを、かのさとし言にのたまへるごとく、よのかぎりもはら萬葉にちからをつくされしほどに、古事記書紀にいたりては、そのかむかへ、いまだあまねく深くはゆきわたらず、くはしからぬ 事どももおほし、されば道を説(トキ)給へることも、こまかなることしなければ、大むねもいまださだかにあらはれず、たゞ事のついでなどに、はしばしいさゝかづゝのたまへるのみ也、又からごゝろを去(サ)れることも、なほ清くはさりあへ給はで、おのづから猶その意におつることも、まれまれにはのこれるなり、
40 師の説になづまざる事[一〇六]
おのれ古典(イニシヘブミ)をとくに、師の説とたがへること多く、師の説のわろき事あるをば、わきまへいふこともおほかるを、いとあるまじきことと思ふ人おほかンめれど、これすなはちわが師の心にて、つねにをしへられしは、後によき考への出來たらんには、かならずしも師の説にたがふとて、なはゞかりそとなむ、敎ヘられし、こはいとたふときをしへにて、わが師の、よにすぐれ給へる一つ也、大かた古ヘをかむかふる事、さらにひとり二人の力もて、ことごとくあきらめつくすべくもあらず、又よき人の説ならんからに、多くの中には、誤リもなどかなからむ、必わろきこともまじらではえあらず、そのおのが心には、今はいにしへのこゝろことごとく明らか也、これをおきては、あるべくもあらずと、思ひ定めたることも、おもひの外に、又人のことなるよきかむかへもいでくるわざ也、あまたの手を經(フ)るまにまに、さきざきの考ヘのうへを、なほよく考へきはむるからに、つぎつぎにくはしくなりもてゆくわざなれば、師の説なりとて、かならずなづみ守るべきにもあらず、よきあしきをいはず、ひたぶるにふるきをまもるは、學問の道には、いふかひなきわざ也、又おのが師などのわろきことをいひあらはすは、いともかしこくはあれど、それもいはざれば、世の學者その説にまどひて、長くよきをしるごなし、師の説なりとして、わろきをしりながら、いはずつゝみかくして、よさまにつくろひをらんは、たゞ師をのみたふとみて、道をば思はざる也、宣長は、道を尊み古ヘを思ひて、ひたぶるに道の明らかならん事を思ひ、古ヘの意のあきらかならんことをむねと思ふが故に、わたくしに師をたふとむことわりのかけむことをば、えしもかへり見ざることあるを、猶わろしと、そしらむ人はそしりてよ、そはせんかたなし、われは人にそしられじ、よき人にならむとて、道をまげ、古ヘの意をまげて、さてあるわざはえせずなん、これすなはちわが師の心なれば、かへりては師をたふとむにもあるべくや、そはいかにもあれ、
41 わがをしへ子にいましめおくやう[一〇七]
吾にしたがひて物まなばむともがらも、わが後に、又よきかむかへのいできたらむには、かならずわが説にななづみそ、わがあしきゆゑをいひて、よき考へをひろめよ、すべておのが人ををしふるは、道を明らかにせむとなれば、かにもかくにも、道をあきらかにせむぞ、吾を用ふるには有ける、道を思はで、いたづらにわれをたふとまんは、わが心にあらざるぞかし、
42 五十連音をおらんだびとに唱へさせたる事[一〇八]
小篠大記御野(ミヌ)といふ人は、石見ノ國濱田の殿のじゆしやにて、おのが弟子(ヲシヘノコ)也、天明八年秋のころ、肥前ノ國の長崎に物して、阿蘭陀人(オランダビト)のまうで來てあるに逢いて、音韻の事どもを論じ、皇國の五十音の事をかたりて、そを其人にとなへさせて聞しに、和のくだりの音をば、みな上にうを帶て、ゐはういの如く、ゑはうえのごとく、をはうおのごとくに呼て、いえおとはひとしからず、よく分れたり、こは何をもて然るぞと問ヒしかば、はじめの和にならへば也とぞいへりける、かの國のつねの音も、このけぢめありとぞ、此事おのが字音かなづかひにいへると、全くあへりとて、いみしくよろこびおこせたりき、なほそのをりの物がたりども、何くれといひおこせたりし中に、おかしき事どもあれど、こゝにはもらしつ、
玉かつま三の巻
た ち ば な 三
立よればむかしのたれと我ながら
わが袖あやしたちばなのかげ
これは題よみのすゞろごとなるを、とり出たるは、ことされめきて、いかにぞやもおぼゆれど、例の巻の名つけむとてなむ、
43 から國にて孔丘が名をいむ事[一一二]
もろこしの國に、今の清の代に、その王が、孔子の諱(イミナ)を避(サク)とて、丘ノ字の畫を省(ハブ)きてかくことをはじめて、秦漢より明にいたるまで、夫子を尊むことをしらざりしといひて、いみしげにみづからほこれども、これいとをこなること也、もしまことに孔丘をたふとむとならば、其道をこそよく行ふべきことなれ、その道をば、全くもおこなはずして、たゞいたづらに、其人のみをたふとまんは、なにのいみしき事かあらむ、其道をだによく行ひなば、いにしへよりいむことなくて有リ來つる、其もじは、今さらいまずとて、なでふこたかあらむ、これたゞ道をたふとみがほして、世の人にいみしく思はせむためのはかりこと也、すべてかの國人のしわざは、大かたいにしへよりかくのごとくにて、聖賢といふ物をたふとむを、いみしき事にすなるは、みなまことに尊むにはあらず、名をむさぼるしわざ也、
44 から人のおやのおもひに身をやつす事[一二二]
もろこしの國の、よゝの物しり人どもの、親の喪(オモヒ)に、身のいみしくやつれたるを、孝心ふかき事にして、しるしたるがあまたある中には、まことに心のかなしさは、いとさばかりもあらざりけむを、食物をいたくへらしなどして、痩(ヤセ)さらぼひて、ことさらにかほかたりをやつして、いみしげにうはべを見せたるがおほかりげに見ゆるは、例のいといとうるさきわざなるを、いみしき事にほめたるも又をこ也、うせにし親を、まことに思ふ心ふかくは、おのが身をも、さばかりやつすべき物かは、身のやつれに、病などもおこりて、もしはからず、なくなりなどもしたらむには、孝ある子といふべしやは、たとひさまでにはいたらずとも、しかいみしくやつれたらむをば、苔の下にも、おやはさこそこゝろぐるしく思はめ、いかでかうれしとは見む、さる親の心をば思はで、たゞ世の人めをのみつくろひて、名をむさぼるは、何のよき事ならむ、すべて孝行も何わざも、世にけやけきふるまひをして、いみしき事に思はするは、かの國人のならひにぞありける、
45 富貴をねがはざるをよき事にする諭ひ[一二三]
世々の儒者、身のまづしく賤きをうれへず、とみ榮えをながはず、よろこばざるを、よき事にすれども、そは人のまことの情(ココロ)にあらず、おほくは名をむさぼる、例のいつはり也、まれまれにさる心ならむもの有とも、そは世のひがものにこそあれ、なにのよき事ならん、ことわりならぬ ふるまひをして、あながちにながはむこそは、あしからめ、ほどほどにつとむべきわざを、いそしくつとめて、なりのぼり、富(トミ)さかえむこそ、父母にも先祖にも、孝行ならめ、身おとろへ家まづしからむは、うへなき不孝にこそ有けれ、たゞおのがいさぎよき名をむさぼるあまりに、まことの孝をわするゝも、又もろこし人のつねなりかし、
46 神の御ふみをとける世々のさま[一三三]
神御典(カミノミフミ)を説(トク)事、むかしは紀傳道の儒者の職(ワザ)にて、そのとける書、弘仁より代々の、日本紀私記これ也、そはいづれも、たゞ漢學の餘力(チカラノアマリ)をもて考へたるのみにして、神御典(カミノミフミ)をまはら學びたるものにあらざるが故に、古ヘの意詞(ココロコトバ)にくらく、すべてうひうひしく淺はかにて、もとより道の趣旨(オモムキ)も、いかなるさまとも説(トキ)たることなく、たゞ文によりて、あるべきまゝにいへるばかり也、然れども皇朝のむかしの儒者は、すべてから國のやうに、己が殊にたてたる心はなかりし故に、神の御ふみをとくとても、漢意にときまげたる、わたくし説(ゴト)もをさをさ見えず、儒意(ジュゴコロ)によれる強説(シヒゴト)もなくて、やすらかにはありしを、後ノ世にいたりては、ことに神學といふ一ながれ出來て、もはらにするともがらしあれば、つぎつぎにくはしくはなりもてゆけど、なべての世の物しり人の心、なまさかしくなりて、神の御ふみをとく者も、さかしらをさきにたてて、文のまゝには物せず、おのが好むすぢに引つけて、あるは儒意に、ときまぐることとなれり、さていよいよ心さかしくなりもてゆくまゝに、近き世となりては、又やうやうに、かの佛ごゝろをまじふるが、ひがことなることをさとりて、それをば、ことごとくのぞきてとくこととなれり、然れどもそれは、まことに古ヘの意をさとりて然るにはあらず、たゞ儒意のすゝめるから、いとへるもの也、さる故に、近き世に、神の道とて説(トク)趣は、ひたすら儒にして、さらに神の道にかなはず、このともがら、かの佛に流れたることのひがことをばしりながら、みづから又儒にながるゝことを、えさとらざるは、いかにぞや、かくして又ちかき世には、しか儒によることのわろきをも、やゝしりて、つとめてこれをのぞかんとする者も、これかれとほのめくめれども、それはたいまだ清く漢意をはなるゝことあたはで、天理陰陽などいふ説をば、なほまことと心得、ともすれば、例のさかしらの立いでては、高天ノ原を帝都のこととし、天照大御神を、天つ日にあらずとし、海神(ワタツミ)ノ宮を、一つの嶋也とするたぐひ、すべてかやうに、おのがわたくしの心をもて、さまざまに説曲(トキマゲ)ることをえまぬ かれざるは、なほみな漢意なるを、みづからさもおぼえざるは、さる癖(クセ)の、世の人のこゝろの底に、しみつきたるならひぞかし、
玉勝間四の巻
わ す れ 草 四
からぶみの中に、とみにたづぬべき事の有て、思ひめぐらすに、そのふみとばかりは、ほのかにおぼえながら、いづれの巻のあたりといふこと、さらにおぼえねは、たゞ心あてに、こゝかしことたづぬ れど、え見いでず、さりとていとあまたある巻々を、はじめよりたづねもてゆかむには、いみしくいとまいりぬ べければ、さもえ物せず、つひにむなしくてやみぬるが、いとくちをしきまゝに、思ひつゞける、
ふみみつる跡もなつ野の忘草老てはいとゞしげりそひつゝ
もとより物おぼゆること、いとともしかりけるを、此ちかきとしごろとなりては、いとゞ何事も、たゞ今見聞つるをだに、やがてわすれがちなるは、いといといふかひなきわざになむ、
47 故郷[一五五]
旅にして、國をふるさとといふは、他國(ヒトノクニ)にうつりて住る者などの、もと住し里をいへるにこそあれ、たゞゆきかへるよのつにの旅にていふは、あたらぬ 事也、されば萬葉集古今集などの歌には、しかよめるはいまだ見あたらず、萬葉などには、ゆきかへる旅にては、國をは、國又は家などこそよみたれ、然るを後の世には、おしなべて故郷といひならひて、つねのことなれば、なべては今さらとがむべきにもあらざれども、萬葉ぶりの歌には、なほ心すべきことなるに、今の人心つかで、なべてふるさととよむなるは、いかゞとこそあぼゆれ、
48 うき世[一五六]
うきよは、憂(ウ)き世といふことにて、憂(ウ)き事のあるにつきていふ詞也、古き歌どもによめるを見て知べし、然るをからぶみに、浮世(フセイ)といふこともあるにまがひて、つねに浮世(ウキヨ)とかきならひて、たゞ何となく世ノ中のことにいふは誤り也、古歌を見るにも、憂(ウ)きといふに心をつけて見べし、
49 世の人かざりにはからるゝたとひ[一六五]
皇國と外國とのやうを、物にたとへていはば、皇國の古ヘは、かほよき人の、かたち衣服(キモノ)をもかざらず、たゞありにてあるが如く、外國は、醜(ミニク)き女の、いみしく髪かほをつくり、びゝしき衣服(キモノ)を着(キ)かざりたるがごとくなるを、遠(トホ)くて見る時は、まことのかたちのよきあしきは、わかれずして、たゞそのかざりつくろへるかたぞ、まさりて見ゆめるを、世の人、ちかくよりて、まことの美醜(ヨキアシ)きを見ることをしらず、たゞ遠目(トホメ)にのみ見て、外國のかざりをしも、うるはしと思ふは、いかにぞや、すべて漢國などは、よろづの事、實(マコト)はあしきが故に、それをおほひかくさむとてこそ、さまざまにかざりつくるには有けれ、
50 ひとむきにかたよることの論ひ[一六七]
世の物しり人の、他(ヒト)の説(トキゴト)のあしきをとがめす、一(ヒト)むきにかたよらず、これをもかれをもすてぬ さまに論(アゲツラヒ)をなすは、多くはおのが思ひとりたる趣をまげて、世の人の心に、あまねくかなへむとするものにて、まことにあらず、心ぎたなし、たとひ世ノ人は、いかにそしるとも、わが思ふすぢをまげて、したがふべきことにはあらず、人のほめそしりにはかかはるまじきわざぞ、大かた一むきにかたよりて、他説(アダシトキゴト)をば、わろしととがむるをば、心せばくよからぬ こととし、ひとむきにはかたよらず、他説(アダシトキゴト)をも、わろしとはいはぬ を、心ひろくおいらかにて、よしとするは、なべての人の心なめれど、かならずそれさしもよき事にもあらず、よるところ定まりて、そを深く信ずる心ならば、かならずひとむきにこそよるべけれ、それにたがへるすぢをば、とるべきにあらず、よしとしてよる所に異(コト)なるは、みなあしきなり、これよければ、かれはかならずあしきことわりぞかし、然るをこれもよし、又かれもあしからずといふは、よるところさだまらず、信ずべきところを、深く信ぜざるもの也、よるところさだまりて、そを信ずる心の深ければ、それにことなるずぢのあしきことをば、おのづからとがめざることあたはず、これ信ずるところを信ずるまめごゝろ也、人はいかにおもふらむ、われは一むきにかたよりて、あだし説をばわろしととがむるも、かならずわろしとは思はずなむ、
51 前後と説のかはる事[一六八]
同じ人の説(トキゴト)の、こゝとかしことゆきちがひて、ひとしからざるは、いづれによるべきぞと、まどはしくて、大かた其人の説、すべてうきたるこゝちのせらるゝ、そは一わたりはさることなれ共、なほさしもあらず、はじめより終リまで、説のかはれることなきは、中々におかしからぬ かたもあるぞかし、はじめに定めおきつる事の、ほどへて後に、又ことはるよき考への出來るは、つねにある事なれば、はじめとかはれることあるこそよけれ、年をへてがくもむすゝみゆけば、説は必ズかはらでかなはず、又おのがはしめの誤リを、後にしりながらは、つゝみかくさで、きよく改めたるも、いとよき事也、殊にわが古學の道は、近きほどよりひらけそめつることなれば、すみやかにことごとくは考へつくすべきにあらず、人をへ年をへてこそ、つぎつぎに明らかには成リゆくべきわざなれば、一人のときごとの中にも、さきなると後なると異なることは、もとよりあらではえあらぬ わざ也、そは一人の生(イキ)のかぎりのほどにも、つぎつぎに明らかになりゆく也、さればそのさきのと後のとの中には、後の方をぞ、其人のさだまれる説とはすべかりける、但し又みづからこそ、初めのをばわろしと思ひて、改めつれ、又のちに人の見るには、なほはじめのかたよろしくて、後のは中々にわろきもなきにあらざれば、とにかくにえらびは、見む人のこゝろになむ、
52 人のうせたる後のわざ[一八八]
人の死(ウセ)たる後のわざ、上ツ代にはいかに有けむ、神代に天若日子(アメワカヒコ)のみうせにし時、八日八夜遊(アソブ)と有て、樂(ウタマヒ)して遊びし事などの、わづかに見えたるのみにして、こまかなる事は、すべて知がたし、但し音樂して遊びしことは、なべてのさだまり也、そのよしは古事記ノ傳にいへるがごとし、さて死(シニ)を穢(ケガレ)とすることは、神代より然り、されどそれも、日數のかぎりの定まりしは、後なるべし、又忌服は、から國をまねびたる、後の事也、書紀の仁徳天皇の御巻に、素服といふ字など見えたれど、例の漢文のかざりにこそあれ、そのかみさる事有しにあらず、仲哀天皇崩(カムアガ)りましまして、いくほどもなく、神功皇后の、重き御神わざの有しにても、服なかりけむことしられたり、そもそも漢國に、喪服といふことのかぎりを、こまやかにさだめたるは、ねもころなるに似たれども、中々に心ざし淺き、うはべのこと也、親などにおくれたらんかなしさは、その月の其ころまでと、きはやかにかぎりの有べきわざにはあらざるに、しひてかぎりをたてて、きはやかに定めたるは、かの國のなべてのくせにて、いひもてゆけば、人にいつはりを敎るわざ也、親を思ふ心の淺からむ子は、三年をまたで、はやくかなしさはさめぬ べきに、なほ服をきて、かなしきさまをもてつけ、又こゝろざし深からんは、三とせ過たらむからに、かなしさはやむべきならぬ に、ぬぎすてて、なごりなくしなさむは、ともにうはべのいつはりにあらずや、さるを皇國に比服といふことのなかりしは、きはやかなるかぎりのなきかなしさのまゝなるにて、長くもみじかくも、これぞまことにかなしむには有でる、服はきざれども、かなしきはかなしく、きても、かなしからぬ はかなしからねば、いたづらごと也、さればかの國にても、漢の文帝といひし王は、こよなく服をちゞめたりしを、儒者は、いみしくよからぬ ことに、もどきいへども、ことわりある事ぞかし、皇國にならひまねばれたるにも、ちゞめて、おやのをも、一とせと定められたり、さるはいと久しく、身のつとめをかゝむも、えうなきいたづらごとなれば、かなしながらに、出てつかへんに、なでふことかあらむ、さてかくいふは、服てふ事のありなしの、本のあげつらひにこそあれ、ふでにその御おきてのあるうへは、かたく守りて、をかすまじき物ぞかし、すべて何わざも、いにしへをたふとまむともがら、おのが心にふさはしからず思はむからに、今の上の御おきてにたがひて、まもらざらんは、いみしくかしこきわたくし也かし、
53 櫻を花といふ事[一九〇]
たゞ花といひて櫻のことにするは、古今集のころまでは、聞えぬ事なり、契沖ほうしが餘材抄に、くはしくいへるがごとし、源氏ノ物語若菜ノ上の巻に、梅の事をいふとて、花のさかりにならべて見ばやといひる事あり、これらはまさしく櫻を分て花といへり、
54 為兼卿の歌の事[二〇九]
六條ノ内大臣有房公の野守の鏡の序に云ク、此ごろ為兼ノ卿といへる人、先祖代々の風(フウ)をそむき、累世家々の義をやぶりて、よめる歌ども、すべてやまと言の葉にもあらず、と申侍しかど、かの卿は、和歌のうら風、たえず傳はりたる家にて侍れば、さだめてやうこそあらめ、と思ひ侍しほどに、くはしくとふ事もなくてやみにき、今又これをうれへ給へるにこそ、まことのあやまりとは思ひしり侍ぬ れといふにかの僧あざわらひて、堯舜の子、柳下惠がおとゝ、皆おろかなりしうへは其家なればとて、かならずしもかしこかるべきにあらず、又佛すでに、わが法をば、我弟子うしなふべしとて、獅子の身の中の蟲の、獅子をはむにたとへさせ給へり、そのむねにたがはず、内外の法みな、其道をつたふる人、其義をあやまるより、すたれゆく事にて侍れば、歌の道も、歌の家よりうせむ事、力なきことにて侍る、かの卿は、御門の御めぐみ深き人にて侍るなるに、これをそしりて、みつしほのからき罪に申シしづめられん事も、よしなかるべきわざにて侍れば、くはしく其あやまりを申しがたし、たゞこの略頌にて心得給へ、それ歌は、心をたねとして、心をたねとせず、心すなほにして、心すなほにせず、ことばをはなれて、ことばをはなれず、風情をもとめて、風情をもとめず、姿をならひて、すがたをならはず、古風をうつして、古風をうつさざる事にてなん侍る、を申すに云々、
55 もろこしの經書といふものの説とりどりなる事[二一一]
もろこしの國の、經書といふ物の注釋、漢よりよゝのじゆしやのと、宋の代の儒者のと、そのおもむきいたく異なること多く、又其後にも、宋儒の説を、ことごとくやぶりたるも有リ、そもそも經書は、かの國の道を載せたる書にて、うへもなく重き物なめれば、そのむね一ツに定まらではかなはぬ 事なるに、かくのごとく昔より定まりがたく、とりどりなれば、ましてそのほかの事の、善惡是非(ヨサアシサ)のいさゝかなるけぢめをば、いかでかよく定めうべきぞ、たゞ皇國のいにしへのごと、おほらかに定めて、くだくだしき論ひには及ばぬ こそ、かへりてまさりてはありけれ、又かの宋儒の、格物致知窮理のをしへこそ、いともいともをこなれ、うへなく重き經書のむねをだに、よく明らめつくすことあたはずして、よよに其説とりどりなるものを、萬の物の理リを、誤りなくは、いかでかよくわきまへつくす事をえん、かへすかへすをこ也、
56 もろこし人の説こちたくくだくだしき事[二一二]
すべてもろこし人の物の論ひは、あまりくだくだしくこちたくて、あぢきなきいたづら言(ゴト)多し、宋儒の論ひを、こちたしとてそしる儒者も多けれど、それもたゞいさゝか甚しからぬ のみにこそあれ、然いふものもなほこちたし、
57 初學の詩つくるべきやうを敎ヘたる説[二一七]
ちかきころあるじゆしやの書る物を見れば、初學(ウヒマナビ)の輩の、から歌を作るべきさまを敎ヘたる中にいへるやう、所詮(ショセン)作りならひに、二三百もつくる間(アヒダ)の詩は、社外の人に示すべきにまあらず、後に詩集に収録すべきにもあらざれば、古人の詩を、遠慮なく剽竊して、作りおぼえ、なほ具足しがたくは、唐詩礎明詩礎詩語碎錦などやうの物にて、補綴して、こしらゆるがよき也といへるは、まことによきをしへざま也、歌よむも、もはらさる事にて、はじめよりおのが思ふさまを、あらたによみ出むとすれば、歌のやうにもあらぬ 、ひがことのみ出來て、後までも、さるくせののぞこりがたき物なれば、うひまなびのほどは、詞のつゞきも、心のおもむきも、たゞふりたる跡によりてぞ、よみならふべきわざ也ける、
58 歌は詞をえらぶべき事[二一八]
童蒙抄に、「水のおもにてる月なみをかぞふればこよひぞ秋のもなかなりける、もなかとよめるを、時の人、和歌の詞とおぼえずと難じけるを、歌がらのよければ、えらびにいれりとあり、
59 兼好法師が詞のあげつらひ[二三一]
けんかうほうしがつれづれ草に、花はさかりに、月はくまなきをのみ見る物かはとかいへるは、いかにぞや、いにしへの歌どもに、花はさかりなる、月はくまなきを見たるよりも、花のもとには、風をかこち、月の夜は、雲をいとひ、あるはまちをしむ心づくしをよめるぞ多くて、こゝろ深きも、ことにさる歌におほかるは、みな花はさかりをのどかに見まほしく、月はくまなからむことをおもふ心のせちなるからこそ、さもえあらぬ を歎きたるなれ、いづこの歌にかは、花に風をまち、月に雲をねがひたるはあらん、さるをかのほうしがいへるごとくなるは、人の心にさかひたる、後の世のさかしら心の、つくり風流(ミヤビ)にして、まことのみやびごゝろにはあらず、かのほうしがいへる言ども、此たぐひ多し、皆同じ事也、すべてなべての人のねがふ心にたがへるを、雅(ミヤビ)とするは、つくりことぞおほかりける、戀に、あへるをよろこぶ歌は、こゝろふかゝらで、あはぬ をなげく歌のみおほくして、こゝろ深きも、逢見むことをねがふから也、人の心は、うれしき事は、さしもふかくはおぼえぬ ものにて、たゞ心にかなはぬことぞ、深く身にしみてはおぼゆるわざなるは多きぞかし、然りとて、わびしくかなしきを、みやびたりとてねがはむは、人のまことの情(ココロ)ならめや、又同じほうしの、人はよそぢにたらでしなむこそ、めやすかるべけれといへるなどは、中ごろよりこなたの人の、みな歌にもよみ、つねにもいふすぢにて、いのち長からんことをねがふをば、心ぎたなきこととし、早く死ぬ るを、めやすきことにいひ、此世をいとひすつるを、いさぎよきこととするは、これみな佛の道にへつらへるものにて、おほくはいつはり也、言にこそさもいへ、心のうちには、たれかはさは思はむ、たとひまれまれには、まことに然思ふ人のあらんも、もとよりのまごゝろにはあらず、佛のをしへにまどへる也、人のまごゝろは、いかにわびしき身も、はやくしなばやとはおもはず、命をしまぬ ものはなし、されば萬葉などのころまでの歌には、たゞ長くいきたらん事をこそねがひたれ、中ごろよりこなたの歌とは、そのこゝろうらうへなり、すべて何事も、なべての世の人のま心にさかひて、ことなるをよきことにするは、外國(トツクニ)のならひのうつれるにて、心をつくりかざれる物としるべし、
60 うはべをつくる世のならひ[二三二]
うまき物くはまほしく、よきゝぬきまほしく、よき家にすままほしく、たからえまほしく、人にたふとまれまほしく、いのちながゝらまほしくするは、みな人の眞心(マゴコロ)也、然るにこれらを皆よからぬ 事にし、ねがはざるをいみしきことにして、すべてほしからず、ねがはぬかほするものの、よにおほかるは、例のうるさきいつはりなり、又よに先生などあふがるゝ物しり人、あるは上人などたふとまるゝほうしなど、月花を見ては、あはれとめづるかほすれども、よき女を見ては、めにもかゝらぬ かほして過るは、まことに然るにや、もし月花をあはれと見る情(ココロ)しあらば、ましてよき女には、などかめのうつらざらむ、月花はあはれ也、女の色はめにもとまらずといはんは、人とあらむものの心にあらず、いみしきいつはりにこそ有けれ、しかはあれども、よろづにうはべをつくりかざるは、なべてのよのならひにしあれば、これらは、いつはりとて、さしもとがむべきにはあらずなん、
61 學者のまづかたきふしをとふ事[二三四]
物まなぶともがら、物しり人にあひて、物とふに、ともすればまづ、古書の中にも、よにかたきこととして、たれもときえぬ ふしをえり出て、とふならひ也、たとへば書紀の齋明御巻なる童謠、萬葉にては、一の巻なる莫囂圓隣云々と書る歌、などやうのたぐひなり、かうやうのかたきことを、まづ明らめまほしく思ふも、學者のなべての心なれども、しからばやすき事どもは、皆よくあきらめしれるかと、こゝろむれば、いとたやすき事どもをだに、いまだえよくもわきまへず、さるものの、さしこえて、まづかたきふしをかきらめんとするは、いとあぢきなきわざ也、よく聞えたりと思ひて、心もとゞめぬ ことに、思ひの外なるひがこゝろえの多かる物なれば、まづたやすき事を、いく度もかへさひかむかへ、とひも明らめて、よくえたらん後にこそ、かたきふしをば、思ひかくべきわざなれ、
わ す れ 草 四
からぶみの中に、とみにたづぬべき事の有て、思ひめぐらすに、そのふみとばかりは、ほのかにおぼえながら、いづれの巻のあたりといふこと、さらにおぼえねは、たゞ心あてに、こゝかしことたづぬ れど、え見いでず、さりとていとあまたある巻々を、はじめよりたづねもてゆかむには、いみしくいとまいりぬ べければ、さもえ物せず、つひにむなしくてやみぬるが、いとくちをしきまゝに、思ひつゞける、
ふみみつる跡もなつ野の忘草老てはいとゞしげりそひつゝ
もとより物おぼゆること、いとともしかりけるを、此ちかきとしごろとなりては、いとゞ何事も、たゞ今見聞つるをだに、やがてわすれがちなるは、いといといふかひなきわざになむ、
47 故郷[一五五]
旅にして、國をふるさとといふは、他國(ヒトノクニ)にうつりて住る者などの、もと住し里をいへるにこそあれ、たゞゆきかへるよのつにの旅にていふは、あたらぬ 事也、されば萬葉集古今集などの歌には、しかよめるはいまだ見あたらず、萬葉などには、ゆきかへる旅にては、國をは、國又は家などこそよみたれ、然るを後の世には、おしなべて故郷といひならひて、つねのことなれば、なべては今さらとがむべきにもあらざれども、萬葉ぶりの歌には、なほ心すべきことなるに、今の人心つかで、なべてふるさととよむなるは、いかゞとこそあぼゆれ、
48 うき世[一五六]
うきよは、憂(ウ)き世といふことにて、憂(ウ)き事のあるにつきていふ詞也、古き歌どもによめるを見て知べし、然るをからぶみに、浮世(フセイ)といふこともあるにまがひて、つねに浮世(ウキヨ)とかきならひて、たゞ何となく世ノ中のことにいふは誤り也、古歌を見るにも、憂(ウ)きといふに心をつけて見べし、
49 世の人かざりにはからるゝたとひ[一六五]
皇國と外國とのやうを、物にたとへていはば、皇國の古ヘは、かほよき人の、かたち衣服(キモノ)をもかざらず、たゞありにてあるが如く、外國は、醜(ミニク)き女の、いみしく髪かほをつくり、びゝしき衣服(キモノ)を着(キ)かざりたるがごとくなるを、遠(トホ)くて見る時は、まことのかたちのよきあしきは、わかれずして、たゞそのかざりつくろへるかたぞ、まさりて見ゆめるを、世の人、ちかくよりて、まことの美醜(ヨキアシ)きを見ることをしらず、たゞ遠目(トホメ)にのみ見て、外國のかざりをしも、うるはしと思ふは、いかにぞや、すべて漢國などは、よろづの事、實(マコト)はあしきが故に、それをおほひかくさむとてこそ、さまざまにかざりつくるには有けれ、
50 ひとむきにかたよることの論ひ[一六七]
世の物しり人の、他(ヒト)の説(トキゴト)のあしきをとがめす、一(ヒト)むきにかたよらず、これをもかれをもすてぬ さまに論(アゲツラヒ)をなすは、多くはおのが思ひとりたる趣をまげて、世の人の心に、あまねくかなへむとするものにて、まことにあらず、心ぎたなし、たとひ世ノ人は、いかにそしるとも、わが思ふすぢをまげて、したがふべきことにはあらず、人のほめそしりにはかかはるまじきわざぞ、大かた一むきにかたよりて、他説(アダシトキゴト)をば、わろしととがむるをば、心せばくよからぬ こととし、ひとむきにはかたよらず、他説(アダシトキゴト)をも、わろしとはいはぬ を、心ひろくおいらかにて、よしとするは、なべての人の心なめれど、かならずそれさしもよき事にもあらず、よるところ定まりて、そを深く信ずる心ならば、かならずひとむきにこそよるべけれ、それにたがへるすぢをば、とるべきにあらず、よしとしてよる所に異(コト)なるは、みなあしきなり、これよければ、かれはかならずあしきことわりぞかし、然るをこれもよし、又かれもあしからずといふは、よるところさだまらず、信ずべきところを、深く信ぜざるもの也、よるところさだまりて、そを信ずる心の深ければ、それにことなるずぢのあしきことをば、おのづからとがめざることあたはず、これ信ずるところを信ずるまめごゝろ也、人はいかにおもふらむ、われは一むきにかたよりて、あだし説をばわろしととがむるも、かならずわろしとは思はずなむ、
51 前後と説のかはる事[一六八]
同じ人の説(トキゴト)の、こゝとかしことゆきちがひて、ひとしからざるは、いづれによるべきぞと、まどはしくて、大かた其人の説、すべてうきたるこゝちのせらるゝ、そは一わたりはさることなれ共、なほさしもあらず、はじめより終リまで、説のかはれることなきは、中々におかしからぬ かたもあるぞかし、はじめに定めおきつる事の、ほどへて後に、又ことはるよき考への出來るは、つねにある事なれば、はじめとかはれることあるこそよけれ、年をへてがくもむすゝみゆけば、説は必ズかはらでかなはず、又おのがはしめの誤リを、後にしりながらは、つゝみかくさで、きよく改めたるも、いとよき事也、殊にわが古學の道は、近きほどよりひらけそめつることなれば、すみやかにことごとくは考へつくすべきにあらず、人をへ年をへてこそ、つぎつぎに明らかには成リゆくべきわざなれば、一人のときごとの中にも、さきなると後なると異なることは、もとよりあらではえあらぬ わざ也、そは一人の生(イキ)のかぎりのほどにも、つぎつぎに明らかになりゆく也、さればそのさきのと後のとの中には、後の方をぞ、其人のさだまれる説とはすべかりける、但し又みづからこそ、初めのをばわろしと思ひて、改めつれ、又のちに人の見るには、なほはじめのかたよろしくて、後のは中々にわろきもなきにあらざれば、とにかくにえらびは、見む人のこゝろになむ、
52 人のうせたる後のわざ[一八八]
人の死(ウセ)たる後のわざ、上ツ代にはいかに有けむ、神代に天若日子(アメワカヒコ)のみうせにし時、八日八夜遊(アソブ)と有て、樂(ウタマヒ)して遊びし事などの、わづかに見えたるのみにして、こまかなる事は、すべて知がたし、但し音樂して遊びしことは、なべてのさだまり也、そのよしは古事記ノ傳にいへるがごとし、さて死(シニ)を穢(ケガレ)とすることは、神代より然り、されどそれも、日數のかぎりの定まりしは、後なるべし、又忌服は、から國をまねびたる、後の事也、書紀の仁徳天皇の御巻に、素服といふ字など見えたれど、例の漢文のかざりにこそあれ、そのかみさる事有しにあらず、仲哀天皇崩(カムアガ)りましまして、いくほどもなく、神功皇后の、重き御神わざの有しにても、服なかりけむことしられたり、そもそも漢國に、喪服といふことのかぎりを、こまやかにさだめたるは、ねもころなるに似たれども、中々に心ざし淺き、うはべのこと也、親などにおくれたらんかなしさは、その月の其ころまでと、きはやかにかぎりの有べきわざにはあらざるに、しひてかぎりをたてて、きはやかに定めたるは、かの國のなべてのくせにて、いひもてゆけば、人にいつはりを敎るわざ也、親を思ふ心の淺からむ子は、三年をまたで、はやくかなしさはさめぬ べきに、なほ服をきて、かなしきさまをもてつけ、又こゝろざし深からんは、三とせ過たらむからに、かなしさはやむべきならぬ に、ぬぎすてて、なごりなくしなさむは、ともにうはべのいつはりにあらずや、さるを皇國に比服といふことのなかりしは、きはやかなるかぎりのなきかなしさのまゝなるにて、長くもみじかくも、これぞまことにかなしむには有でる、服はきざれども、かなしきはかなしく、きても、かなしからぬ はかなしからねば、いたづらごと也、さればかの國にても、漢の文帝といひし王は、こよなく服をちゞめたりしを、儒者は、いみしくよからぬ ことに、もどきいへども、ことわりある事ぞかし、皇國にならひまねばれたるにも、ちゞめて、おやのをも、一とせと定められたり、さるはいと久しく、身のつとめをかゝむも、えうなきいたづらごとなれば、かなしながらに、出てつかへんに、なでふことかあらむ、さてかくいふは、服てふ事のありなしの、本のあげつらひにこそあれ、ふでにその御おきてのあるうへは、かたく守りて、をかすまじき物ぞかし、すべて何わざも、いにしへをたふとまむともがら、おのが心にふさはしからず思はむからに、今の上の御おきてにたがひて、まもらざらんは、いみしくかしこきわたくし也かし、
53 櫻を花といふ事[一九〇]
たゞ花といひて櫻のことにするは、古今集のころまでは、聞えぬ事なり、契沖ほうしが餘材抄に、くはしくいへるがごとし、源氏ノ物語若菜ノ上の巻に、梅の事をいふとて、花のさかりにならべて見ばやといひる事あり、これらはまさしく櫻を分て花といへり、
54 為兼卿の歌の事[二〇九]
六條ノ内大臣有房公の野守の鏡の序に云ク、此ごろ為兼ノ卿といへる人、先祖代々の風(フウ)をそむき、累世家々の義をやぶりて、よめる歌ども、すべてやまと言の葉にもあらず、と申侍しかど、かの卿は、和歌のうら風、たえず傳はりたる家にて侍れば、さだめてやうこそあらめ、と思ひ侍しほどに、くはしくとふ事もなくてやみにき、今又これをうれへ給へるにこそ、まことのあやまりとは思ひしり侍ぬ れといふにかの僧あざわらひて、堯舜の子、柳下惠がおとゝ、皆おろかなりしうへは其家なればとて、かならずしもかしこかるべきにあらず、又佛すでに、わが法をば、我弟子うしなふべしとて、獅子の身の中の蟲の、獅子をはむにたとへさせ給へり、そのむねにたがはず、内外の法みな、其道をつたふる人、其義をあやまるより、すたれゆく事にて侍れば、歌の道も、歌の家よりうせむ事、力なきことにて侍る、かの卿は、御門の御めぐみ深き人にて侍るなるに、これをそしりて、みつしほのからき罪に申シしづめられん事も、よしなかるべきわざにて侍れば、くはしく其あやまりを申しがたし、たゞこの略頌にて心得給へ、それ歌は、心をたねとして、心をたねとせず、心すなほにして、心すなほにせず、ことばをはなれて、ことばをはなれず、風情をもとめて、風情をもとめず、姿をならひて、すがたをならはず、古風をうつして、古風をうつさざる事にてなん侍る、を申すに云々、
55 もろこしの經書といふものの説とりどりなる事[二一一]
もろこしの國の、經書といふ物の注釋、漢よりよゝのじゆしやのと、宋の代の儒者のと、そのおもむきいたく異なること多く、又其後にも、宋儒の説を、ことごとくやぶりたるも有リ、そもそも經書は、かの國の道を載せたる書にて、うへもなく重き物なめれば、そのむね一ツに定まらではかなはぬ 事なるに、かくのごとく昔より定まりがたく、とりどりなれば、ましてそのほかの事の、善惡是非(ヨサアシサ)のいさゝかなるけぢめをば、いかでかよく定めうべきぞ、たゞ皇國のいにしへのごと、おほらかに定めて、くだくだしき論ひには及ばぬ こそ、かへりてまさりてはありけれ、又かの宋儒の、格物致知窮理のをしへこそ、いともいともをこなれ、うへなく重き經書のむねをだに、よく明らめつくすことあたはずして、よよに其説とりどりなるものを、萬の物の理リを、誤りなくは、いかでかよくわきまへつくす事をえん、かへすかへすをこ也、
56 もろこし人の説こちたくくだくだしき事[二一二]
すべてもろこし人の物の論ひは、あまりくだくだしくこちたくて、あぢきなきいたづら言(ゴト)多し、宋儒の論ひを、こちたしとてそしる儒者も多けれど、それもたゞいさゝか甚しからぬ のみにこそあれ、然いふものもなほこちたし、
57 初學の詩つくるべきやうを敎ヘたる説[二一七]
ちかきころあるじゆしやの書る物を見れば、初學(ウヒマナビ)の輩の、から歌を作るべきさまを敎ヘたる中にいへるやう、所詮(ショセン)作りならひに、二三百もつくる間(アヒダ)の詩は、社外の人に示すべきにまあらず、後に詩集に収録すべきにもあらざれば、古人の詩を、遠慮なく剽竊して、作りおぼえ、なほ具足しがたくは、唐詩礎明詩礎詩語碎錦などやうの物にて、補綴して、こしらゆるがよき也といへるは、まことによきをしへざま也、歌よむも、もはらさる事にて、はじめよりおのが思ふさまを、あらたによみ出むとすれば、歌のやうにもあらぬ 、ひがことのみ出來て、後までも、さるくせののぞこりがたき物なれば、うひまなびのほどは、詞のつゞきも、心のおもむきも、たゞふりたる跡によりてぞ、よみならふべきわざ也ける、
58 歌は詞をえらぶべき事[二一八]
童蒙抄に、「水のおもにてる月なみをかぞふればこよひぞ秋のもなかなりける、もなかとよめるを、時の人、和歌の詞とおぼえずと難じけるを、歌がらのよければ、えらびにいれりとあり、
59 兼好法師が詞のあげつらひ[二三一]
けんかうほうしがつれづれ草に、花はさかりに、月はくまなきをのみ見る物かはとかいへるは、いかにぞや、いにしへの歌どもに、花はさかりなる、月はくまなきを見たるよりも、花のもとには、風をかこち、月の夜は、雲をいとひ、あるはまちをしむ心づくしをよめるぞ多くて、こゝろ深きも、ことにさる歌におほかるは、みな花はさかりをのどかに見まほしく、月はくまなからむことをおもふ心のせちなるからこそ、さもえあらぬ を歎きたるなれ、いづこの歌にかは、花に風をまち、月に雲をねがひたるはあらん、さるをかのほうしがいへるごとくなるは、人の心にさかひたる、後の世のさかしら心の、つくり風流(ミヤビ)にして、まことのみやびごゝろにはあらず、かのほうしがいへる言ども、此たぐひ多し、皆同じ事也、すべてなべての人のねがふ心にたがへるを、雅(ミヤビ)とするは、つくりことぞおほかりける、戀に、あへるをよろこぶ歌は、こゝろふかゝらで、あはぬ をなげく歌のみおほくして、こゝろ深きも、逢見むことをねがふから也、人の心は、うれしき事は、さしもふかくはおぼえぬ ものにて、たゞ心にかなはぬことぞ、深く身にしみてはおぼゆるわざなるは多きぞかし、然りとて、わびしくかなしきを、みやびたりとてねがはむは、人のまことの情(ココロ)ならめや、又同じほうしの、人はよそぢにたらでしなむこそ、めやすかるべけれといへるなどは、中ごろよりこなたの人の、みな歌にもよみ、つねにもいふすぢにて、いのち長からんことをねがふをば、心ぎたなきこととし、早く死ぬ るを、めやすきことにいひ、此世をいとひすつるを、いさぎよきこととするは、これみな佛の道にへつらへるものにて、おほくはいつはり也、言にこそさもいへ、心のうちには、たれかはさは思はむ、たとひまれまれには、まことに然思ふ人のあらんも、もとよりのまごゝろにはあらず、佛のをしへにまどへる也、人のまごゝろは、いかにわびしき身も、はやくしなばやとはおもはず、命をしまぬ ものはなし、されば萬葉などのころまでの歌には、たゞ長くいきたらん事をこそねがひたれ、中ごろよりこなたの歌とは、そのこゝろうらうへなり、すべて何事も、なべての世の人のま心にさかひて、ことなるをよきことにするは、外國(トツクニ)のならひのうつれるにて、心をつくりかざれる物としるべし、
60 うはべをつくる世のならひ[二三二]
うまき物くはまほしく、よきゝぬきまほしく、よき家にすままほしく、たからえまほしく、人にたふとまれまほしく、いのちながゝらまほしくするは、みな人の眞心(マゴコロ)也、然るにこれらを皆よからぬ 事にし、ねがはざるをいみしきことにして、すべてほしからず、ねがはぬかほするものの、よにおほかるは、例のうるさきいつはりなり、又よに先生などあふがるゝ物しり人、あるは上人などたふとまるゝほうしなど、月花を見ては、あはれとめづるかほすれども、よき女を見ては、めにもかゝらぬ かほして過るは、まことに然るにや、もし月花をあはれと見る情(ココロ)しあらば、ましてよき女には、などかめのうつらざらむ、月花はあはれ也、女の色はめにもとまらずといはんは、人とあらむものの心にあらず、いみしきいつはりにこそ有けれ、しかはあれども、よろづにうはべをつくりかざるは、なべてのよのならひにしあれば、これらは、いつはりとて、さしもとがむべきにはあらずなん、
61 學者のまづかたきふしをとふ事[二三四]
物まなぶともがら、物しり人にあひて、物とふに、ともすればまづ、古書の中にも、よにかたきこととして、たれもときえぬ ふしをえり出て、とふならひ也、たとへば書紀の齋明御巻なる童謠、萬葉にては、一の巻なる莫囂圓隣云々と書る歌、などやうのたぐひなり、かうやうのかたきことを、まづ明らめまほしく思ふも、學者のなべての心なれども、しからばやすき事どもは、皆よくあきらめしれるかと、こゝろむれば、いとたやすき事どもをだに、いまだえよくもわきまへず、さるものの、さしこえて、まづかたきふしをかきらめんとするは、いとあぢきなきわざ也、よく聞えたりと思ひて、心もとゞめぬ ことに、思ひの外なるひがこゝろえの多かる物なれば、まづたやすき事を、いく度もかへさひかむかへ、とひも明らめて、よくえたらん後にこそ、かたきふしをば、思ひかくべきわざなれ、
たまかつま五の巻
枯野のすゝき五
秋過て、草はみながらかれはてて、さびしき野べに、たゞ尾花のかぎり、心長くのこりて、むらむらたてるを、あはれと見て、よめる、
かれぬべきかれ野の尾花かれずあるをかれずこそ見めかれぬかぎりは、かゝるすゞろごとをさへに、とり出たるは、みむ人、をこに思ふべかめれど、よしやさばれとてなん、
62 あやしき事の説[二四〇]
もし人といふもの、今はなき世にて、神代にさる物ありきと記して、その人といひし物のありしやう、まづ上つかたに、首(カシラ)といふ所有て、その左リ右に、耳といふもの有て、もろもろの聲をよくきゝ、おもての上つ方に、目といふ物二つありて、よろづの物の色かたちを、のこるくまなく見あきらめ、その下に、鼻といふものも有て、物のかをかぎ、又下に、口と云フ物ありて、おくより聲の出るを、くちびるをうごかし、舌をはたらかすまゝに、その聲さまざまにかはりて、詞となりて、萬の事をいひわけ、又首(カシラ)の下の左リ右に、手といふもの有て、末に岐(マタ)ありて、指(オヨビ)といふ、此およびをはたらかして、萬ヅのわざをなし、萬の物を造り出せり、又下つかたに、足といふ物、これも二つ有て、うがかしはこべば、百重(モモヘ)の山をものぼりこえて、いづこまでもありきゆきつ、かくて又胸(ムネ)の内に隠(カク)れて、心(ココロ)といふ物の有つるこはあるが中にも、いとあやしき物にて、色も形もなきものから、上の件(クダリ)耳の聲をきゝ、目の物を見、口のものいひ、手足のはたらくも、皆此心のしわざにてぞ有ける、さるに此人といひし物、ある時いたくなやみて、やうやうに重(オモ)りもてゆくほどに、つひにかのよろづのしわざ皆やみて、いさゝかうごくこともせずなりてや(止)みにき、と記したらむ書を、じゆしやの見たらむには、例の信ぜずして、神代ならんからに、いづこのさるあやしき事かあるべき、すべてすべて理リもなく、つたなき寓言にこそはあれ、とぞいはむかし、
63 歌の道 さくら花[二六一]
しき嶋の道又歌の道といふこと、後の世には常まれど、古今集ノ序を見るに、かの御世や歌のこゝろをしろしめしたりけむ云々、こゝにいにしへのことをも、歌のこゝろをも、しれる人云々、人まろなくなりにたれど、歌のこととゞまれるかななどあるは、後の世の文なりせば、かならず歌の道とぞいはましを、かく歌のこゝろ、歌のことなどいひて、道とはいはず、眞字序には、斯(コノ)道とも吾道ともあるを、かな序には、すべて歌に道といはること見えず、又櫻の花を、さくら花といふこと、これも後の世にはつねなれど、古今集には、詞書には、いづこもいづこも、さくらの花と、のもじをそへてのみいひて、たゞにさくらばなといへることは、歌にこそあれ、詞には一つも見えず、おほかたこれらになずらへて、歌よまむにも、文かゝむにも、古ヘと後ノ世とのけぢめ、又漢文と御國文とのけぢめあること、又歌と詞とかはれることもあるなどを、いさゝかのことにも、心をどゞめて、わきまふべきわざぞ、こは古今集をよむとて、ふと心つけるまゝに、おどろかしおく也、
64 いせ物語眞名本の事[二七四]
伊勢物語に、眞名本といふ本あり、萬葉の書キざまにならひて、眞字(マナ)して書たる物也、六條ノ宮ノ御撰と、はじめにあげたれば、その親王(ミコ)の御しわざかと、見もてゆけば、あらぬ 僞(イツハリ)にて、後の物也、まづすべての字(モジ)のあてざま、いとつたなくして、しどけなく正しからず、心得ぬ ことのみぞ多かる、そが中に、闇(クラ)うを苦勞(クラウ)、指之血(オヨビノチ)を及後(オヨビノチ)などやうにかけるは、たはぶれ書キにて、萬葉にもさるたぐひあり、又東(アヅマ)を熱間(アツマ)、云々にけりを迯利(ニケリ)など書るも、清濁こそたがへれ、なほゆるさるべきを、なんといふ辭に、何ノ字を用ひ、ぞに社、とに諾ノ字を用ひたるたぐひ、こと心得ず、しかのみならず、思へるを思惠流(オモエル)、給へを給江(タマエ)、又こゝへかしこはなどのへをも、みな江(エ)とかき、身をも、これをやなどの、をもをやといふ辭を、面 親(オモオヤ)と書、忘(ワスレ)を者摺(ハスレ)と書るなど、これらの假字は、今の世とても、歌よむほどのものなどは、をさをさ誤ることなきをだに、かく誤れるは、むげに物かくやうをもわきまへしらぬ 、えせもののしわざと見えて、眞字(マナ)はすべてとりがたきもの也、然はあれども、詞は、よのつねの假字ほんとくらべて考ふるに、たがひのよきあしきところ有て、かな本のあしきに、此本のよきも、すくなからず、そを面 へば、これもむかしの一つの本なりしを、後に眞名には書キなしたるにぞ有べき、されば今も、一本にはそなふべきもの也、然るにいといと心得ぬ ことは、わが縣居ノ大人の、此物語を解(トカ)れたるには、よのつねの假字本をば、今本といひて、ひたふるにわろしとして、此眞名本をしも、古本といひて、こちたくほめて、ことごとくよろしとして用ひ、ともすれば此つたなき眞字(マナ)を、物の鐙(アカシ)にさへ引れたるは、いかなることにかあらん、さばかり古ヘの假字の事を、つねにいはるゝにも似ず、此本の、さばかり假字のいたくみだれて、よにつたなきなどをも、いかに見られけむ、かへすかへすこゝろえぬ ことぞかし、さて又ちかきころ、ある人の出せる、舊本といふなる、眞名の本も一つ有リ、それはかのもとのとは、こよなくまさりて、大かた今の京になりての世の人の、およびが
たき眞字の書キざまなる所多し、さればこれもまことのふるき本(マキ)にはあらず、やがて出せる人の、みづからのしわざにぞ有ける、然いふ故は、まづ今の京となりての書(フミ)どもは、すべて假字の清濁は、をさをさ差別 (ワキ)なく用ひたるを、此本は、ことごとく清濁を分ケて、みだりならず、こは近く古學てふこと始まりて後の人ならでは、さはえあらぬ こと也、又かきつばたといふ五言を、句の頭にすゑてとかける、これむかし人ならば、五もじとこそいふべきを、五言といひ、歌のかへしを和歌(カヘシ)、瀧を多藝(タギ)、十一日を十麻里比止日(トヲマリヒトヒ)と書るたぐひ、時代(トキヨ)のしなを思ひはからざるしわざ也、十一日など、此物語かけるころとなりては、十一日とこそ書べけれ、たとひなごめてかくとも、とをかあまりひとひとこそ書クべけれ、それをあまりのあをはぶけるは、古學者のしわざ、又とをかのかをいはざるは、さすがにいにしへのいひざまをしらざるなり、又うつの山のくだりに、よのつねの本には、修行者あひたりとあるを、此本には、修行者仁逢有(ニアヒタリ)と、仁(ニ)てふ辭をそへたるなども、古ヘの雅言(ミヤビゴト)の例をしらぬ 、今の世の俗意(サトビゴコロ)のさかしら也、かゝるひがことも、をりをりまじれるにて、いよいよいつはりはほころびたるをや、
65 いせ物がたりをよみていはまほしき事ども一つ二つ[二八〇]
初のくだり、男のきたりける云々、男ののもじひがこと也、眞名本になぞよろしき、男のとては、云々(シカシカ)して歌を書てやる事、女のしわざになる也、月やあらぬ てふ歌の條(クダリ)、ほいにはあらで、此詞聞えず、眞字本に、穗(ホ)にはとあるも、心ゆかず、ほにはいでずなどこそいへ、ほにはあらでなどは、聞つかぬ こゝちす、猶もじの誤リなどにや、うつの山のところ、わがいらむとする道は、いとくらう細きに、つたかへではしげりて云々、かへではのはは、てにをは也、上の道はのはと重ねて、かうやうにいふ、一つの格(サマ)也、「秋はきぬ 紅葉は屋どにふりしきぬ道ふみ分てとふ人はなしなど、三つも重ねていへる、此類多し、眞名本に葉と書るによりて、然心得ては、いとつたなき文になる也、「君がためたをれる枝は云々、此歌は、君にわが心ざしの深きにかなひて、春ながらも、秋のごとく色ふかく染たり、といふ意なるべし、注どもに、秋といふ言になづみて、女の心のうつろふことにこゝろえたるはいかゞ、さてはかへしの歌めづらしげなし、又女の心をうたがふべきよしも、上の詞に見えず、「いでていなば心かろしと云々、此出ていぬ るは、女とはおしはからるれども、上の文のさま、女とも男とも分りがたし、いさゝかなる事につけてといへる上に、女とあるべき文也、さて此歌の次に、云々此女とあるは、心得ず、此女といふこと、こゝに有ては、聞えず、こゝは男とあるべきところ也、かくのごとくまぎらはしきによりて、或人は、出ていにしは、女にあらず、男也といへれども、すべてのさま、男の出ていにしとは聞えず、又男にしては、かの此女とあるは、よくかなへれども、下なる「人はいさの歌の次に此女いと久しう云々とある、此女てふこと、彼ノ男とあらではかなはず、「つゝ井づゝ云々、妹見ざるまには、妹が見ざるまに也、妹を見ざるまにはあらず、上におのが長(タケ)だちの事をいへるにて、それを妹が見ざるまになること知ルべし、さて此ノ條(クダリ)は、下に、かの女やまとのかたを見やりてとも、やまと人云々ともあれば、井のもとみあそびたりしも、大和ノ國にての事也、さればはじめに、むかしやまとの國に、などあるべきことなるに、たゞゐなかわたらひしける人と、のみにては、京の人とこそ聞ゆれ、よろこびてまつに、度々過ぬ ればといへる所、詞たらず、其故は、まつにといふまでは、たゞ一度のさまをいへる文なるに、たびたび過とつゞけていひては、俄也、さればこは、よろこびてまつにこず、さること度々なりければ、などやうに有べき所なり、むかし男かたゐなかに住けり、眞名本に、昔男女とあるぞよき、男とのみにては、次なる男といふこともあまり、又まちわびたりけるにといふも、上に女といふことなくては、聞えず、「梓弓眞弓つき弓云々、此歌、初メ二句、いかなる意にか、さらにきこえず、又眞名本に、神言忠令見とかけるは、もとより借字ながら、いとつたなき書ざま也、下句は、むかしわがうるはしみせしが如く、今の男に、うるはしみせよといへる也、「見るめなきわが身を云々、此歌のこと、古今集の遠鏡にいへり、さて此歌をこゝに出せるは、下句、はしの詞にかなはず聞ゆ、又色このみなる女といふことも、こゝに有べき詞にあらず、これらによりて思ふに、これは、「秋の野にてふうたの次に、おほく詞落て、もと上とは別 條(ベツクダリ)にぞ有けむ、ええずなりにけることと、わびたりける人の云々、眞名本には、わびを慙とかけり、ともにかなへりとも聞えず、歌によりて思ふに、おぶらひたりける人の、など有べきにや、「おもほえず袖に云々、袖に湊のといふこと、聞えず、又眞名本に、袖に浪渡(ナミダ)のと書るは、下句とむげにかけあはず、ひがこと也、浪渡は、異所(コトトコロ)にもかく書て涙也、されば思ふに、こは袖の湊のなるべし、たとひ袖の湊といふ名所はなくとも、涙の深きことを、下ノ句の縁に、然いひつべきもの也、のをにに誤れるなるべし、女の手あらふところに云々、こゝの文きこえず、眞名本にて聞えたり、但しかの本も、なく影のうつりけるを見ててふ下に、女といふことなくてはいかゞ、たち聞ても、彼本にきゝつけてとあるぞよき、「水口に我や云々、此歌の初二句の注ども、いづれもいさゝかたがへり、こはさだめてわが泣(ナク)影も、ともに見えやすらんといへる也、かやうに見ざれば、下句にかなはず、わが影のみゆるにやあらむといふとはこと也、「ならはねば云々、此歌、詞たらはで、聞えぬ 歌なり、とかくなまめくあひだに、かのいたる螢を云々、かくては、なまめくは、いたるにはあらで、異(コト)人と聞えていかゞ、とかくなまめきつゝ、螢をとりて、などこそ有べけれ、此ほたるのともす火にや云々、こゝは眞名本に、此螢の、ともしびにや似(ニ)むと思ひて、けちなんとすとて、男よめる、とあるぞよろしき、但し上に、車なりける人とあれば、下なる男といふことは、なくてあらまほし、もし又、ともし火にやにんと思へるを、女の心とせば、思ひければ、などこそ有ルべけれ、思ひてといひては、かなはず、「出ていなばたれか別 れの云々、此歌、上と下と縁なし、又はしの詞にもいとうとし、眞名本に初ノ句、いとひてはとあるも聞えず、又眞名本に、此歌の次に、女辺爾付而、「いづくまでおくりは云々、此歌もをさなし、なほおもひてこそ、聞えず、眞字本に、なほざりにとあるにて聞ゆ、今の翁まさにしなんやは、為(シ)なんやにてさるすける物思ひをば為(シ)なんやの意なり、死なんやにては、からうして息出たり、といふにかなはず、「いでていなばかぎりなるべし云々、いにしへの人も、かばかりつたなき歌よみけるにや、これは上にいふべかりけるを、おとしたる也、なほはたえあらざりける中なりければ、此詞あまりて聞ゆ、眞名本には、さりとてはた、いかではえあらざりける中なりければと有、心にとゞめてよますはらに云々、聞えぬ こと也、眞字本は聞ゆ、うまのはなむけせんとて、人をまちけるに云々、人をといふこと、あまれり、眞字本にはなし、但し上なる、物へいく人にといふ詞の、なき本もあり、それは人をまちけるにてよろし、又男、「行水と過るよはいと云々、此歌此ノ條(クダリ)にかなはず、眞名本になきぞよき、又男女のしのびありきしける云々、此詞も、此くだりにかなはず、人しれぬ 物思ひけり、此詞いたづら也、むかし心つきて云々、心つきて、聞えず、眞名本に、榮而とあるも心得ず、田からんとては、男の事にて、此男の田からむとてあるを見て、といふ意也、かくてものいたくやみて云々、此事、上の詞歌に似つかず、別 條(コトクダリ)なりしが、詞共落て、亂れたるなるべし、昔としごろ音づれざりける女、昔の下に、男のといふことなくては、たらず、又よさりこの有つる云々の上にも、その男、或はその人など有べきこと也、「これやこの我に云々、此歌、あふみをといふこと、聞えず、近江にいひかけたりとせんも、しひごとなり、もし然らば、上に近江ノ國のことなくては、とゝのはず、又下句も、これやこのといへるにかなはず、むかしよごゝろつける女云々、これは、女にてはかなはず、眞名本に、嫗女(オンナ)とあるぞよろしき、假字の亂れたるより、かゝるまぎれも有也、女はを、嫗はおの假字にて、分るゝ也、又つけるといふ詞もいかゞ、眞名本に、世營とかけり、よごゝろあると訓(ヨム)べし、色好む心のある老女也、あひえてしも、同本に、あひ見てしとあるよろし、その次の詞も、かの本よろし、出たつけしきは、男のなさけ有て、嫗のがりゆかむと思ひて、出たつ也、いづくなりけん、けんといふ詞いかゞ、いづくなるらんと、などあるべきにや、もし又けんをたすけていはば、物語の地の詞として、いづくにての事なりけんと見べし、昔男いせの國なりける女云々、眞字本に、女乎(ヲ)とあるよろし、むかしそこには云々、眞字本に、昔男とあり、むかし男、いせの國にゐていきて云々、こは本トは、いせの國なる女に、京にゐていきて云々、と有しが、にもじの重なれるによりて、京にといふことの、後に落たる也、次なる歌ども、必ズ伊勢なる女とこそ聞えたれ「いはまより云々、此歌の四の句、ときえたる人なし、しほひしほみちは、とまれかくまれといふ意なるを、海の詞にていへるのみ也、今はともかくもあれ、末つひにはかひ有て、逢ふこともあらんといへる也、けふの御わざを題にてのけふのは、その日のとあるべきこと也、やよひのつごもりに、その日云々、その日といへる詞、いたづらにてつたなし、紅葉のちくさに見ゆるをり、此詞いかゞ、眞名本になきぞよき、もみぢもとあらば、有てもよからんか、板敷のしたに、したはしもなるべし、板敷のうちのしもつかたをいふなり、板じきのしたには、人の居るべきにもあらず、みちの國にいきたりけるにとは、此物語の作者(ツクリヌシ)の、みづから行たるよしにや、もし此歌よめる翁の事ならば、かの翁といふこと、みちの國にの上になくてはいかゞ也、かりはねんごろにもせで、上に狩に來ませるよしをいはざれば、此詞ゆくりなく聞ゆ、これによりて思ふに、櫻花を見ありくを、櫻がりといふなれば、此條に狩といへるは、皆櫻がりの事にやあらん、上にも下にも、たゞ櫻のことをのみいへれば、かたののなぎさの家その院の云々、こは聞えぬ 詞也、眞名本に、かたののなぎさの院のと有よろし、かのうまのかみよみて奉りける、かのうまのかみといふこと、なくてあらまほし、「思へども身をし分ねばは、分ケぬ にといふ意也、此例古き歌には多し、身を分るは、身を二つにわくる也、めかれせぬ は、雪故にえかへらで、そこにあるをいふ、さてそれを、わが本意也といへる也、「今までに云々、とてやみにけりといふ詞、上に心ざしはたさむとや思ひけむ、といへるに、かなへりとも聞えず、此くだり、眞字本はよくきこえたり、昔男ありけり、いかゞ有けむ、その男云々は、眞名本に、昔男女云々とあり、さらではたらず、さてやがて後つひに、此所詞重なりて、くだくだし、眞名本には、さてつひにと有、さてこゝは、作者(ツクリヌシ)の語なれば、けふ迄といへるもいかゞ也、然れば、さて後つひによくてやあらん云々、とこそ有べけれ、むくつけきことといふより、おはぬ ものにやあらんといふまでは、のろひごとを評(サダ)したる語也、むくつけきことは、むくつけきことよといふ意也、かくて今こそ見めといふ一句は、さかでうちたる男の、のろひていへる言なるを、評(サダ)する語の中へ引出ていへる也、よき酒ありときゝて、此下に詞落たる也、さらでは、下にその日はといへるも、より所なし、こゝろみにその落たる詞をおぎなはば、よきさけ有リときゝて、うへにありける人々、のまんとてきけり、左中弁云々、などや有けむ、あるじのはらからなるの下に、男などあらまほし、なくなりにけるを、眞名本に、なくなりたる女をと有、よろし、かへし「下ひもの云々、又かへし「戀しとは云々、かへし「下ひもの云々とあり、よろし、今はさることにげなく云々、たれともなくて、かくいへること聞えず、眞名本には、なま翁の今は云々と有リ、よろし、されど歌の上に、中將なりける翁とあるはわろし、かの翁とこそいふべけれ、又は上を、中將なりける翁いまはさること云々といひて、歌の所には、何ともいはでも有リなん、大鷹のたかがひを、眞名本に、大方之(オホカタノ)鷹飼とあるは、ひがこと也、西宮記にも、鷹飼ノ王卿、大鷹飼ハ者、着ス二地摺ノ獵衣ヲ一、綺ノ袴玉 帶、鷂飼者(コタカガヒハ)云々とある、こゝによくかなへるをや、昔みかど住吉に云々、此條すべて詞たらず、他條(コトクダリ)の例に似ず、「我見てもの歌も、たが歌ともわきまへがたく、大神の現形も俄也、他條の例にならひていはば、昔男、みかどの住吉に行幸し給ひける、御供につかうまつりてよめる、「我見ても云々、とよめりければ、大神云々、などこそ有べけれ、「むつましと云々の歌は、何事ぞや、二の句を、君はしたずやとすれば、大かた聞ゆるやうにはあれど、猶いとつたなし、むかし男久しう云々、眞名本に、いへりければの下に、女とあり、むかし女の、あだなる男の云々、女のののもじ、ひがこと也、すべてのてふ辭は、心得有て、おくべき所と、必ズおくまじきところとのあることなるを、これはさるわきまへをもしらぬ 、後の人の、何心もなくくはへたるなるべし、眞名本に、女のといふことなし、それも女といふことたらず、むかし男、女のまだ世へずと云々、此くだり詞とゝのはず、物聞えたるを、後に聞て、などこそ有べけれ、
66 業平ノ朝臣のいまはの言の葉[二八二]
古今集に、やまひして、よわくなりにける時よめる、なりひらの朝臣、「つひにゆく道とはかねて聞しかどきのふけふとは思はざりしを、契沖いはく、これ人のまことの心にて、をしへにもよき歌也、後々の人は、死なんとするきはにいたりて、ことごとしきうたをよみ、あるは道をさとれるよしなどよめる、まことしからずして、いとにくし、たゞなる時こそ、狂言綺語をもまじへめ、いまはとあらんときにだに、心のまことにかへれかし、此朝臣は、一生のまこと、此歌にあらはれ、後の人は、一生の僞リをあらはして死ぬ る也といへるは、ほうしのことばにもにず、いといとたふとし、やまとだましひなる人は、法師ながら、かくこそ有けれ、から心なる神道者歌學者、まさにかうはいはんや、契沖法師
は、よの人にまことを敎ヘ、神道者歌學者は、いつはりをぞしふなる、
枯野のすゝき五
秋過て、草はみながらかれはてて、さびしき野べに、たゞ尾花のかぎり、心長くのこりて、むらむらたてるを、あはれと見て、よめる、
かれぬべきかれ野の尾花かれずあるをかれずこそ見めかれぬかぎりは、かゝるすゞろごとをさへに、とり出たるは、みむ人、をこに思ふべかめれど、よしやさばれとてなん、
62 あやしき事の説[二四〇]
もし人といふもの、今はなき世にて、神代にさる物ありきと記して、その人といひし物のありしやう、まづ上つかたに、首(カシラ)といふ所有て、その左リ右に、耳といふもの有て、もろもろの聲をよくきゝ、おもての上つ方に、目といふ物二つありて、よろづの物の色かたちを、のこるくまなく見あきらめ、その下に、鼻といふものも有て、物のかをかぎ、又下に、口と云フ物ありて、おくより聲の出るを、くちびるをうごかし、舌をはたらかすまゝに、その聲さまざまにかはりて、詞となりて、萬の事をいひわけ、又首(カシラ)の下の左リ右に、手といふもの有て、末に岐(マタ)ありて、指(オヨビ)といふ、此およびをはたらかして、萬ヅのわざをなし、萬の物を造り出せり、又下つかたに、足といふ物、これも二つ有て、うがかしはこべば、百重(モモヘ)の山をものぼりこえて、いづこまでもありきゆきつ、かくて又胸(ムネ)の内に隠(カク)れて、心(ココロ)といふ物の有つるこはあるが中にも、いとあやしき物にて、色も形もなきものから、上の件(クダリ)耳の聲をきゝ、目の物を見、口のものいひ、手足のはたらくも、皆此心のしわざにてぞ有ける、さるに此人といひし物、ある時いたくなやみて、やうやうに重(オモ)りもてゆくほどに、つひにかのよろづのしわざ皆やみて、いさゝかうごくこともせずなりてや(止)みにき、と記したらむ書を、じゆしやの見たらむには、例の信ぜずして、神代ならんからに、いづこのさるあやしき事かあるべき、すべてすべて理リもなく、つたなき寓言にこそはあれ、とぞいはむかし、
63 歌の道 さくら花[二六一]
しき嶋の道又歌の道といふこと、後の世には常まれど、古今集ノ序を見るに、かの御世や歌のこゝろをしろしめしたりけむ云々、こゝにいにしへのことをも、歌のこゝろをも、しれる人云々、人まろなくなりにたれど、歌のこととゞまれるかななどあるは、後の世の文なりせば、かならず歌の道とぞいはましを、かく歌のこゝろ、歌のことなどいひて、道とはいはず、眞字序には、斯(コノ)道とも吾道ともあるを、かな序には、すべて歌に道といはること見えず、又櫻の花を、さくら花といふこと、これも後の世にはつねなれど、古今集には、詞書には、いづこもいづこも、さくらの花と、のもじをそへてのみいひて、たゞにさくらばなといへることは、歌にこそあれ、詞には一つも見えず、おほかたこれらになずらへて、歌よまむにも、文かゝむにも、古ヘと後ノ世とのけぢめ、又漢文と御國文とのけぢめあること、又歌と詞とかはれることもあるなどを、いさゝかのことにも、心をどゞめて、わきまふべきわざぞ、こは古今集をよむとて、ふと心つけるまゝに、おどろかしおく也、
64 いせ物語眞名本の事[二七四]
伊勢物語に、眞名本といふ本あり、萬葉の書キざまにならひて、眞字(マナ)して書たる物也、六條ノ宮ノ御撰と、はじめにあげたれば、その親王(ミコ)の御しわざかと、見もてゆけば、あらぬ 僞(イツハリ)にて、後の物也、まづすべての字(モジ)のあてざま、いとつたなくして、しどけなく正しからず、心得ぬ ことのみぞ多かる、そが中に、闇(クラ)うを苦勞(クラウ)、指之血(オヨビノチ)を及後(オヨビノチ)などやうにかけるは、たはぶれ書キにて、萬葉にもさるたぐひあり、又東(アヅマ)を熱間(アツマ)、云々にけりを迯利(ニケリ)など書るも、清濁こそたがへれ、なほゆるさるべきを、なんといふ辭に、何ノ字を用ひ、ぞに社、とに諾ノ字を用ひたるたぐひ、こと心得ず、しかのみならず、思へるを思惠流(オモエル)、給へを給江(タマエ)、又こゝへかしこはなどのへをも、みな江(エ)とかき、身をも、これをやなどの、をもをやといふ辭を、面 親(オモオヤ)と書、忘(ワスレ)を者摺(ハスレ)と書るなど、これらの假字は、今の世とても、歌よむほどのものなどは、をさをさ誤ることなきをだに、かく誤れるは、むげに物かくやうをもわきまへしらぬ 、えせもののしわざと見えて、眞字(マナ)はすべてとりがたきもの也、然はあれども、詞は、よのつねの假字ほんとくらべて考ふるに、たがひのよきあしきところ有て、かな本のあしきに、此本のよきも、すくなからず、そを面 へば、これもむかしの一つの本なりしを、後に眞名には書キなしたるにぞ有べき、されば今も、一本にはそなふべきもの也、然るにいといと心得ぬ ことは、わが縣居ノ大人の、此物語を解(トカ)れたるには、よのつねの假字本をば、今本といひて、ひたふるにわろしとして、此眞名本をしも、古本といひて、こちたくほめて、ことごとくよろしとして用ひ、ともすれば此つたなき眞字(マナ)を、物の鐙(アカシ)にさへ引れたるは、いかなることにかあらん、さばかり古ヘの假字の事を、つねにいはるゝにも似ず、此本の、さばかり假字のいたくみだれて、よにつたなきなどをも、いかに見られけむ、かへすかへすこゝろえぬ ことぞかし、さて又ちかきころ、ある人の出せる、舊本といふなる、眞名の本も一つ有リ、それはかのもとのとは、こよなくまさりて、大かた今の京になりての世の人の、およびが
たき眞字の書キざまなる所多し、さればこれもまことのふるき本(マキ)にはあらず、やがて出せる人の、みづからのしわざにぞ有ける、然いふ故は、まづ今の京となりての書(フミ)どもは、すべて假字の清濁は、をさをさ差別 (ワキ)なく用ひたるを、此本は、ことごとく清濁を分ケて、みだりならず、こは近く古學てふこと始まりて後の人ならでは、さはえあらぬ こと也、又かきつばたといふ五言を、句の頭にすゑてとかける、これむかし人ならば、五もじとこそいふべきを、五言といひ、歌のかへしを和歌(カヘシ)、瀧を多藝(タギ)、十一日を十麻里比止日(トヲマリヒトヒ)と書るたぐひ、時代(トキヨ)のしなを思ひはからざるしわざ也、十一日など、此物語かけるころとなりては、十一日とこそ書べけれ、たとひなごめてかくとも、とをかあまりひとひとこそ書クべけれ、それをあまりのあをはぶけるは、古學者のしわざ、又とをかのかをいはざるは、さすがにいにしへのいひざまをしらざるなり、又うつの山のくだりに、よのつねの本には、修行者あひたりとあるを、此本には、修行者仁逢有(ニアヒタリ)と、仁(ニ)てふ辭をそへたるなども、古ヘの雅言(ミヤビゴト)の例をしらぬ 、今の世の俗意(サトビゴコロ)のさかしら也、かゝるひがことも、をりをりまじれるにて、いよいよいつはりはほころびたるをや、
65 いせ物がたりをよみていはまほしき事ども一つ二つ[二八〇]
初のくだり、男のきたりける云々、男ののもじひがこと也、眞名本になぞよろしき、男のとては、云々(シカシカ)して歌を書てやる事、女のしわざになる也、月やあらぬ てふ歌の條(クダリ)、ほいにはあらで、此詞聞えず、眞字本に、穗(ホ)にはとあるも、心ゆかず、ほにはいでずなどこそいへ、ほにはあらでなどは、聞つかぬ こゝちす、猶もじの誤リなどにや、うつの山のところ、わがいらむとする道は、いとくらう細きに、つたかへではしげりて云々、かへではのはは、てにをは也、上の道はのはと重ねて、かうやうにいふ、一つの格(サマ)也、「秋はきぬ 紅葉は屋どにふりしきぬ道ふみ分てとふ人はなしなど、三つも重ねていへる、此類多し、眞名本に葉と書るによりて、然心得ては、いとつたなき文になる也、「君がためたをれる枝は云々、此歌は、君にわが心ざしの深きにかなひて、春ながらも、秋のごとく色ふかく染たり、といふ意なるべし、注どもに、秋といふ言になづみて、女の心のうつろふことにこゝろえたるはいかゞ、さてはかへしの歌めづらしげなし、又女の心をうたがふべきよしも、上の詞に見えず、「いでていなば心かろしと云々、此出ていぬ るは、女とはおしはからるれども、上の文のさま、女とも男とも分りがたし、いさゝかなる事につけてといへる上に、女とあるべき文也、さて此歌の次に、云々此女とあるは、心得ず、此女といふこと、こゝに有ては、聞えず、こゝは男とあるべきところ也、かくのごとくまぎらはしきによりて、或人は、出ていにしは、女にあらず、男也といへれども、すべてのさま、男の出ていにしとは聞えず、又男にしては、かの此女とあるは、よくかなへれども、下なる「人はいさの歌の次に此女いと久しう云々とある、此女てふこと、彼ノ男とあらではかなはず、「つゝ井づゝ云々、妹見ざるまには、妹が見ざるまに也、妹を見ざるまにはあらず、上におのが長(タケ)だちの事をいへるにて、それを妹が見ざるまになること知ルべし、さて此ノ條(クダリ)は、下に、かの女やまとのかたを見やりてとも、やまと人云々ともあれば、井のもとみあそびたりしも、大和ノ國にての事也、さればはじめに、むかしやまとの國に、などあるべきことなるに、たゞゐなかわたらひしける人と、のみにては、京の人とこそ聞ゆれ、よろこびてまつに、度々過ぬ ればといへる所、詞たらず、其故は、まつにといふまでは、たゞ一度のさまをいへる文なるに、たびたび過とつゞけていひては、俄也、さればこは、よろこびてまつにこず、さること度々なりければ、などやうに有べき所なり、むかし男かたゐなかに住けり、眞名本に、昔男女とあるぞよき、男とのみにては、次なる男といふこともあまり、又まちわびたりけるにといふも、上に女といふことなくては、聞えず、「梓弓眞弓つき弓云々、此歌、初メ二句、いかなる意にか、さらにきこえず、又眞名本に、神言忠令見とかけるは、もとより借字ながら、いとつたなき書ざま也、下句は、むかしわがうるはしみせしが如く、今の男に、うるはしみせよといへる也、「見るめなきわが身を云々、此歌のこと、古今集の遠鏡にいへり、さて此歌をこゝに出せるは、下句、はしの詞にかなはず聞ゆ、又色このみなる女といふことも、こゝに有べき詞にあらず、これらによりて思ふに、これは、「秋の野にてふうたの次に、おほく詞落て、もと上とは別 條(ベツクダリ)にぞ有けむ、ええずなりにけることと、わびたりける人の云々、眞名本には、わびを慙とかけり、ともにかなへりとも聞えず、歌によりて思ふに、おぶらひたりける人の、など有べきにや、「おもほえず袖に云々、袖に湊のといふこと、聞えず、又眞名本に、袖に浪渡(ナミダ)のと書るは、下句とむげにかけあはず、ひがこと也、浪渡は、異所(コトトコロ)にもかく書て涙也、されば思ふに、こは袖の湊のなるべし、たとひ袖の湊といふ名所はなくとも、涙の深きことを、下ノ句の縁に、然いひつべきもの也、のをにに誤れるなるべし、女の手あらふところに云々、こゝの文きこえず、眞名本にて聞えたり、但しかの本も、なく影のうつりけるを見ててふ下に、女といふことなくてはいかゞ、たち聞ても、彼本にきゝつけてとあるぞよき、「水口に我や云々、此歌の初二句の注ども、いづれもいさゝかたがへり、こはさだめてわが泣(ナク)影も、ともに見えやすらんといへる也、かやうに見ざれば、下句にかなはず、わが影のみゆるにやあらむといふとはこと也、「ならはねば云々、此歌、詞たらはで、聞えぬ 歌なり、とかくなまめくあひだに、かのいたる螢を云々、かくては、なまめくは、いたるにはあらで、異(コト)人と聞えていかゞ、とかくなまめきつゝ、螢をとりて、などこそ有べけれ、此ほたるのともす火にや云々、こゝは眞名本に、此螢の、ともしびにや似(ニ)むと思ひて、けちなんとすとて、男よめる、とあるぞよろしき、但し上に、車なりける人とあれば、下なる男といふことは、なくてあらまほし、もし又、ともし火にやにんと思へるを、女の心とせば、思ひければ、などこそ有ルべけれ、思ひてといひては、かなはず、「出ていなばたれか別 れの云々、此歌、上と下と縁なし、又はしの詞にもいとうとし、眞名本に初ノ句、いとひてはとあるも聞えず、又眞名本に、此歌の次に、女辺爾付而、「いづくまでおくりは云々、此歌もをさなし、なほおもひてこそ、聞えず、眞字本に、なほざりにとあるにて聞ゆ、今の翁まさにしなんやは、為(シ)なんやにてさるすける物思ひをば為(シ)なんやの意なり、死なんやにては、からうして息出たり、といふにかなはず、「いでていなばかぎりなるべし云々、いにしへの人も、かばかりつたなき歌よみけるにや、これは上にいふべかりけるを、おとしたる也、なほはたえあらざりける中なりければ、此詞あまりて聞ゆ、眞名本には、さりとてはた、いかではえあらざりける中なりければと有、心にとゞめてよますはらに云々、聞えぬ こと也、眞字本は聞ゆ、うまのはなむけせんとて、人をまちけるに云々、人をといふこと、あまれり、眞字本にはなし、但し上なる、物へいく人にといふ詞の、なき本もあり、それは人をまちけるにてよろし、又男、「行水と過るよはいと云々、此歌此ノ條(クダリ)にかなはず、眞名本になきぞよき、又男女のしのびありきしける云々、此詞も、此くだりにかなはず、人しれぬ 物思ひけり、此詞いたづら也、むかし心つきて云々、心つきて、聞えず、眞名本に、榮而とあるも心得ず、田からんとては、男の事にて、此男の田からむとてあるを見て、といふ意也、かくてものいたくやみて云々、此事、上の詞歌に似つかず、別 條(コトクダリ)なりしが、詞共落て、亂れたるなるべし、昔としごろ音づれざりける女、昔の下に、男のといふことなくては、たらず、又よさりこの有つる云々の上にも、その男、或はその人など有べきこと也、「これやこの我に云々、此歌、あふみをといふこと、聞えず、近江にいひかけたりとせんも、しひごとなり、もし然らば、上に近江ノ國のことなくては、とゝのはず、又下句も、これやこのといへるにかなはず、むかしよごゝろつける女云々、これは、女にてはかなはず、眞名本に、嫗女(オンナ)とあるぞよろしき、假字の亂れたるより、かゝるまぎれも有也、女はを、嫗はおの假字にて、分るゝ也、又つけるといふ詞もいかゞ、眞名本に、世營とかけり、よごゝろあると訓(ヨム)べし、色好む心のある老女也、あひえてしも、同本に、あひ見てしとあるよろし、その次の詞も、かの本よろし、出たつけしきは、男のなさけ有て、嫗のがりゆかむと思ひて、出たつ也、いづくなりけん、けんといふ詞いかゞ、いづくなるらんと、などあるべきにや、もし又けんをたすけていはば、物語の地の詞として、いづくにての事なりけんと見べし、昔男いせの國なりける女云々、眞字本に、女乎(ヲ)とあるよろし、むかしそこには云々、眞字本に、昔男とあり、むかし男、いせの國にゐていきて云々、こは本トは、いせの國なる女に、京にゐていきて云々、と有しが、にもじの重なれるによりて、京にといふことの、後に落たる也、次なる歌ども、必ズ伊勢なる女とこそ聞えたれ「いはまより云々、此歌の四の句、ときえたる人なし、しほひしほみちは、とまれかくまれといふ意なるを、海の詞にていへるのみ也、今はともかくもあれ、末つひにはかひ有て、逢ふこともあらんといへる也、けふの御わざを題にてのけふのは、その日のとあるべきこと也、やよひのつごもりに、その日云々、その日といへる詞、いたづらにてつたなし、紅葉のちくさに見ゆるをり、此詞いかゞ、眞名本になきぞよき、もみぢもとあらば、有てもよからんか、板敷のしたに、したはしもなるべし、板敷のうちのしもつかたをいふなり、板じきのしたには、人の居るべきにもあらず、みちの國にいきたりけるにとは、此物語の作者(ツクリヌシ)の、みづから行たるよしにや、もし此歌よめる翁の事ならば、かの翁といふこと、みちの國にの上になくてはいかゞ也、かりはねんごろにもせで、上に狩に來ませるよしをいはざれば、此詞ゆくりなく聞ゆ、これによりて思ふに、櫻花を見ありくを、櫻がりといふなれば、此條に狩といへるは、皆櫻がりの事にやあらん、上にも下にも、たゞ櫻のことをのみいへれば、かたののなぎさの家その院の云々、こは聞えぬ 詞也、眞名本に、かたののなぎさの院のと有よろし、かのうまのかみよみて奉りける、かのうまのかみといふこと、なくてあらまほし、「思へども身をし分ねばは、分ケぬ にといふ意也、此例古き歌には多し、身を分るは、身を二つにわくる也、めかれせぬ は、雪故にえかへらで、そこにあるをいふ、さてそれを、わが本意也といへる也、「今までに云々、とてやみにけりといふ詞、上に心ざしはたさむとや思ひけむ、といへるに、かなへりとも聞えず、此くだり、眞字本はよくきこえたり、昔男ありけり、いかゞ有けむ、その男云々は、眞名本に、昔男女云々とあり、さらではたらず、さてやがて後つひに、此所詞重なりて、くだくだし、眞名本には、さてつひにと有、さてこゝは、作者(ツクリヌシ)の語なれば、けふ迄といへるもいかゞ也、然れば、さて後つひによくてやあらん云々、とこそ有べけれ、むくつけきことといふより、おはぬ ものにやあらんといふまでは、のろひごとを評(サダ)したる語也、むくつけきことは、むくつけきことよといふ意也、かくて今こそ見めといふ一句は、さかでうちたる男の、のろひていへる言なるを、評(サダ)する語の中へ引出ていへる也、よき酒ありときゝて、此下に詞落たる也、さらでは、下にその日はといへるも、より所なし、こゝろみにその落たる詞をおぎなはば、よきさけ有リときゝて、うへにありける人々、のまんとてきけり、左中弁云々、などや有けむ、あるじのはらからなるの下に、男などあらまほし、なくなりにけるを、眞名本に、なくなりたる女をと有、よろし、かへし「下ひもの云々、又かへし「戀しとは云々、かへし「下ひもの云々とあり、よろし、今はさることにげなく云々、たれともなくて、かくいへること聞えず、眞名本には、なま翁の今は云々と有リ、よろし、されど歌の上に、中將なりける翁とあるはわろし、かの翁とこそいふべけれ、又は上を、中將なりける翁いまはさること云々といひて、歌の所には、何ともいはでも有リなん、大鷹のたかがひを、眞名本に、大方之(オホカタノ)鷹飼とあるは、ひがこと也、西宮記にも、鷹飼ノ王卿、大鷹飼ハ者、着ス二地摺ノ獵衣ヲ一、綺ノ袴玉 帶、鷂飼者(コタカガヒハ)云々とある、こゝによくかなへるをや、昔みかど住吉に云々、此條すべて詞たらず、他條(コトクダリ)の例に似ず、「我見てもの歌も、たが歌ともわきまへがたく、大神の現形も俄也、他條の例にならひていはば、昔男、みかどの住吉に行幸し給ひける、御供につかうまつりてよめる、「我見ても云々、とよめりければ、大神云々、などこそ有べけれ、「むつましと云々の歌は、何事ぞや、二の句を、君はしたずやとすれば、大かた聞ゆるやうにはあれど、猶いとつたなし、むかし男久しう云々、眞名本に、いへりければの下に、女とあり、むかし女の、あだなる男の云々、女のののもじ、ひがこと也、すべてのてふ辭は、心得有て、おくべき所と、必ズおくまじきところとのあることなるを、これはさるわきまへをもしらぬ 、後の人の、何心もなくくはへたるなるべし、眞名本に、女のといふことなし、それも女といふことたらず、むかし男、女のまだ世へずと云々、此くだり詞とゝのはず、物聞えたるを、後に聞て、などこそ有べけれ、
66 業平ノ朝臣のいまはの言の葉[二八二]
古今集に、やまひして、よわくなりにける時よめる、なりひらの朝臣、「つひにゆく道とはかねて聞しかどきのふけふとは思はざりしを、契沖いはく、これ人のまことの心にて、をしへにもよき歌也、後々の人は、死なんとするきはにいたりて、ことごとしきうたをよみ、あるは道をさとれるよしなどよめる、まことしからずして、いとにくし、たゞなる時こそ、狂言綺語をもまじへめ、いまはとあらんときにだに、心のまことにかへれかし、此朝臣は、一生のまこと、此歌にあらはれ、後の人は、一生の僞リをあらはして死ぬ る也といへるは、ほうしのことばにもにず、いといとたふとし、やまとだましひなる人は、法師ながら、かくこそ有けれ、から心なる神道者歌學者、まさにかうはいはんや、契沖法師
は、よの人にまことを敎ヘ、神道者歌學者は、いつはりをぞしふなる、
玉かつま六の巻
か ら あ ゐ 六
おのが歌に、からあゐの末つむ花、とよめりければ、ある人、すゑつむ花は、くれなゐのとこそよみたれ、からあゐのとはいかゞ、といへるに、おのれこたへけらく、萬葉集の歌に、くれなゐを、からあゐともよめり、そもそもくれなゐといふは、此物もと呉(クレ)の國より渡りまうできたるよしにて、呉(クレ)の藍(アヰ)といふを、つゞめたる名
なるを、そは韓(カラ)國よりつたへつる故に、又韓藍(カラアヰ)ともいへるなり、といへる説のごとし、但しからといふは、西の方の國々のなべての名なれば、これは呉ノ國をさしていへるにて、呉藍(クレナヰ)といふと同じことにもあるべし、さるを萬葉の十一の巻には、鷄冠草(カラアヰ)とも書るにつきて、鴨頭草(ツキクサ)也とも、鷄頭花(ケイトウゲ)也ともいふ、説どもの有てまぎらはしきやうなれども、つき草とも、鷄頭花ともいふは、みなひがことにて、紅花(クレナヰ)まること疑ひなし、さればからあゐるなはち紅花(クレナヰ)なることを、さとしがてら、ことさらにかくはよめるぞ、ついでにいはむ、同七の巻に、「秋さらば移(ウツ)しもせんとわがまきしからあゐの花をたれかつみけん、移(ウツ)すとは、おろして染るをいふ、此移ノ字を、本に影に誤れり、といへりければ、うなづきてやみぬ、其おのが歌は
からあゐの末摘花の末つひに色にや出ん忍びかねてば
寄草戀といふ題にてよめる也、古今集なる、「我戀をしのびかねてばあしひきの山たちばなの色に出ぬべし、といふ歌にぞよくにたると、又いふ人もありなんか、
67 書うつし物かく事[二八七]
ふみをうつすに、同じくだりのうち、あるはならべるくだりなどに、同じ詞のあるときは、見まがへて、そのあひだなる詞どもを、寫しもらすこと、つねによくあるわざ也、又一ひらと思ひて、二ひら重(カサ)ねてかへしては、其ノ間ダ一ひらを、みながらおとすことも有リ、これらつねに心すべきわざ也、又よく似て、見まがへやすきもじなどは、ことにまがふまじく、たしかに書クべき也、これは寫しがきのみにもあらず、おほかた物かくに、心得べき事ぞ、すべて物をかくは、事のこゝろをしめさむとてなれば、おふなおふなもじさだかにこそかゝまほしけれ、さるをひたすら、筆のいきほひを見せむとのみしたるは、いかなることとも、よみときがたきが、よにおほかる、あぢきなきわざ也、常にかきかはす、消息文(セウソコブミ)なども、もじよみがたくては、いひやるすぢ、ゆきとほらず、よむ人はたくるしみて、かしらかたぶけつゝ、かへさひよめども、つひによみえずなどしては、こゝよみがたしと、かへしとはんも、さすがになめしきやうなれば、たゞおしはかりに心得ては、事たがひもするぞかし、
68 手かく事[二八八]
よろづよりも、手はよくかゝまほしきわざ也、歌よみがくもんなどする人は、ことに手あしくては、心おとりのせらるるを、それ何かはくるしからんといふも、一わたりことわりはさることながら、なほあかず、うちあはぬこゝちぞするや、のり長いとつたなくて、つねに筆とるたびに、いとくちをしう、いふかひなくおぼゆるを、人のこふまゝにおもなくたんざく一ひらなど、かき出て見るにも、我ながらだに、いとかたはに見ぐるしう、かたくななるを、人いかに見るらんと、はづかしくむねいたくて、わかゝりしほどに、などててならひはせざりけむと、いみしうくやしくなん、
69 業平ノ朝臣の月やあらぬてふ歌のこゝろ[二八九]
「月やあらぬ春やむかしの春ならぬ我身ひとつはもとの身にして、此歌、とりどりに解(トキ)たれども、いづれも其意くだくだしくして、一首(ヒトウタ)の趣とほらず、これによりて、今おのが思ひえたる趣をいはんには、まづ二つのやもじは、やはてふ意にて、月も春も、去年にかはらざるよし也、さて一首の意は、月やは昔の月にあらぬ月もむかしのまゝ也、春やは昔の春にあらざる、春もむかしのまゝの春なり、然るにたゞ我身ひとつのみは、本の昔のまゝの身ながら、むかしのやうにもあらぬことよ、といふ意をふくめたる物也、にしてといへる語のいきほひ、上ノ句に、月も春もむかしのまゝなるに、といへるとあひ照(テラ)して、おのづからふくめたる意は聞ゆる也、此人の歌、こゝろあまりて、詞たらずといへるは、かゝるをいへるなるべし、いせ物語のはしの詞に、立て見ゐて見見れど、こぞに似るべくもあらず、といへるは、此ふくめたる意を、あらはしたるもの也、去年ににぬとは、月春のにぬにはあらず、見るわがこゝちの、去年に似ぬ也、新古今集雜上に、清原ノ深養父の、「むかし見し春は昔の春ながら我身ひとつのあらずも有かな、とよめる歌は、此ノ業平ノ朝臣の歌を、註したるがごとし、これにて、よく聞えたる物をや、
70 縣居大人の傳[三〇三]
あがたゐの大人は、賀茂ノ縣主氏にて、遠祖(トホツオヤ)は、神魂(カミムスビノ)神の孫、鴨武津之身(カモタケツノミノ)命にて、八咫烏(ヤタガラス)と化(ナリ)て、神武天皇を導き奉り給ひし神なること、姓氏録に見えたるがごとし、此神の末、山城ノ國相樂ノ郡岡田ノ賀茂ノ大神を以齋(モテイツ)く、師朝といひし人、文永十一年に、遠江ノ國敷智ノ郡濱松ノ庄岡部ノ鄕なる、賀茂の新宮をいつきまつるべきよしの詔を蒙りて、彼ノ鄕を賜はり、すなはち彼ノ新宮の神主になさる、此事引馬草に見え、又綸旨の如くなる物あり、又乾元元年にも、詔とかうぶりて、かの岡部の地を領ぜる、これは正しき綸旨有て、家に傳はれり、かくて世々かの神主たりしを、大人の五世の祖、政定といひし、引馬原の御軍に功有て、東照神御祖ノ君より、來國行がうちたる刀と、丸龍の具足とを賜はりぬ、此事は三河記にも見えたり、さて大人は、元禄十年に、此岡部ノ鄕に生れ給ひて、わかゝりしほどより、古ヘ學ビにふかく心をよせて、享保十八年に、京にのぼりて、稻荷の荷田ノ宿禰東麻呂ノ大人の教をうけ給ひ、寛延三年に、江戸に下り給ひて、其後田安ノ殿に仕奉り給ふ、かの殿より、葵の文の御衣を賜はり給へる時の歌、「あふへてふあやの御衣をも氏人のかづかむものと神やしりけん、明和六年十月晦の日、とし七十三にて、みまかり給ひぬ、武藏ノ國荏原ノ郡品川の、東海寺の中、少林院の山に葬、こは大人の弟子(ヲシヘコ)なる某が、しるしたるまゝに、とりてしるせり、なほ父ぬし母とじなどをも、しるすべきものなるに、もれたるは、又よくしりたらむ人にとひきゝて、しるすべくなん、
71 花のさだめ[三〇四]
花はさくら、櫻は、山櫻の、葉あかくてりて、ほそきが、まばらにまじりて、花しげく咲たるは、又たぐふべき物もなく、うき世のものとも思はれず、葉青くて、花のまばらなるは、こよなくおくれたり、大かた山ざくらといふ中にも、しなじなの有て、こまかに見れば、一木ごとに、いさゝかかはれるところ有て、またく同じきはなきやう也、又今の世に、桐がやつ八重一重などいふも、やうかはりて、いとめでたし、すべてくもれる日の空に見あげたるは、花の色あざやかならず、松も何も、あをやかにしげりたるこなたに咲るは、色はえて、ことに見ゆ、空きよくはれたる日、日影のさすかたより見たるは、にほひこよなくて、おなじ花ともおぼえぬまでなん、朝日はさら也、夕ばえも、梅は紅梅、ひらけさしたるほどぞ、いとめでたきを、さかりになるまゝに、やうやうしらけゆきて、見どころなくなるこそ、いとくちをしけれ、さくらの咲るころまでも、ちることしらで、むげににほひなく、ねべれしぼみて、のこりたるをみれば、げに有てよの中は、何事もみなかくこそと、見る春ごとに、思ひしらるかし、白きはすべて香こそあれ、見るめはしなおくれたり、大かた梅の花は、ちひさき枝を、物にさして、ちかく見たるぞ、梢ながらよりは、まされる、桃の花は、あまた咲つゞきたるを、遠く見たるはよし、ちかくては、ひなびたり、山ぶきかきつばたなでしこ萩すゝき女郎花など、とりどりにめでたし、菊も、よきほどにつくろひたるこそよけれ、あまりうるはしく、したゝかにつくりなしたるは、中々にしななく、なつかしからず、つゝじ、野山に多く咲たるは、めさむるこゝちす、かいだうといふ物、からめきて、こまやかにうるはしき花也、そもそもかくいふは、みなおのが思ふ心にこそあれ、人は又おもふこゝろことなンべければ、一(ヒト)やうにさだむべきわざにはあらず、又いまやうの、よの人のもてはやすめる花どもも、よにおほかるを、かぞへいでぬは、ことされめきたるやうなれど、歌にもよみたらず、ふるき物にも、見えたることなきは、心のなしにや、なつかしからずおぼゆかし、されどそれはた、ひとやうなるひがこゝろにやあらむ、
72 玉あられ[三四六]
宣長ちかきころ玉あられといふ書をかきて、近き世にあまねく誤りならへることどもをあげて、うひ學のともがらをさとせるを、のりなががをしへ子として、何事も宣長が言にしたがふともがらの、其後の此ごろの歌文に、此書に出せる事どもを、なほ誤ることのおほかるは、いかなるひがことぞや、此書用ひぬよそ人は、いふべきかぎりにあらざるを、それだに心さときは、うはべこそ用ひざるかほつくれ、げにとおぼゆるふしぶしは、たちまちにさとりて、ひそかに改むるたぐひもあるを、ましてのりながが敎をよしとて、したがひながら、改めざるは、此ふみよみても、心にとまらず、やがてわすれたるにて、そはもとより心にしまず、なほざりに思へるから也、つねに心にしめたるすぢは、一たび聞ては、しかたちまちにわするゝ物にはあらざるを、よそ人の思はむ心も、はづかしからずや、これは玉あられのみにもあらず、何(イヅ)れの書見むも、おなじことぞかし、
73 かなづかひ[三四七]
假字づかひは、近き世明らかになりて、古ヘ學ビするかぎりの人は、心すめれば、をさをさあやまることなきを、宣長が弟子(ヲシヘコ)共の、つねに歌かきつらねて見するを見るに、誤リのみ多かるは、又いかにぞや、抑てにをはのとゝのへなどは、うひまなびの力及ばぬふしある物なれば、あやまるも、つみゆるさるゝを、かなづかひは、今は正濫抄もしは古言梯などをだに見ば、むげに物しらぬわらはべも、いとよくわきまふべきわざなるを、猶とりはづして、書キひがむるは、かへすかへすいかにぞや、これはた心とゞめず、又ひたぶるにまなびおやにすがりて、たがへらむは、直さるべしと、思ひおこたりて、おのが力いれざるからのわざにしあれば、かつはにくゝさへぞおぼゆる、しか人にのみすがりたらんには、つひにかなづかひをば、しるよなくてぞやみぬべかりける、さればいゐえゑおを、又はひふへほわゐうゑを又しちすつの濁音(ニゴリコヱ)など、いさゝかもうたがはしくおぼえむ假字は、わづらはしくとも、それしるせるむみを、かゝむたびごとにひらき見て、たしかにうかべずは、やむべきにあらず、何わざも、おのがちからをいれずては、しうることかたかンべきわざぞ、人の子の、としたくるまで、おやのてはなるゝことしらざらむは、いといといふかひなからじやは、
74 古き名どころを尋ぬる事[三四八]
ふるき神の社の、今は絶たる、又絶ざれども、さだかならずなりぬるなど、いづくにも多かるは、いとかなしきわざ也、神祇官の帳にのれるなどは、かけてもさはあるまじきわざなるを、中ごろの世のみだれに、天ノ下のよろづの事も、古ヘのおきても、皆みだれにみだれ、たえうせにたえうせにたる、萬ヅにつけて、いともいともかなしきは、亂れ世のしわざなりけり、さるを今の御世は、いにしへにもまれなるまで、よく治まりて、いともめでたく、天の下榮えにさかゆるまゝに、よろづに古ヘをたづねて、絶たるをおこし、おとろへたるを直し給ふ御世にしあれば、神の社どもは、殊に古ヘに立かへりて、榮ゆべき時なりけり、然あるにつけては、絶たるは、跡をだにさだかにたづねまほしく、又今も有リながら、さだかならず、疑はしきをば、よく考へ尋ねて、たしかにそれと、定めしらまほしきわざになむありける、次には神ノ社ならぬも、いにしへに名あるところどころ、歌枕なども、今はさだかならぬが多かるは、かゝるめでたき時世(トキヨ)にあたりて、尋ねおかまほしきわざ也、かくて神の社にまれ、御陵にまれ、歌まくらにまれ、何にまれ、はるかなるいにしへのを、中ごろとめうしなひたるを、今の世にして、たづね定めむことは、大かたたやすからぬわざになむ有ける、其ゆゑをいはむには、まづ此ふるき所をたづぬるわざは、たゞに古ヘの書どもを考へたるのみにては、知リがたし、いかにくはしく考へたるも、書(フミ)もて考へ定めたることは、其所にいたりて見聞けば、いたく違ふことの多き物也、よそながらは、さだかならぬ所も、其國にては、さすがに書(カキ)もつたへ、かたりも傳へて、まがひなきことも有リ、さればみづから其地(トコロ)にいたりて、見もし、そこの事よくしれる人に、とひきゝなどもせでは、事たらはず、又たゞ一たび物して、見聞キたるのみにても、猶たらはず、ゆきて見聞て、立かへりて、又ふみどもと考へ合せて、又々もゆきて、よく見聞たるうへならでは、定めがたかるべし、さて又其ところの人にあひて、とひきくにも、心得べきことくさぐさあり、いにしへの事を、あまりたしかにしりがほにかたるは、おほくは、書のかたはしを、なまなまにかむかへなどしたるものの、おのがさかしらもて、さだめいふが多ければ、そはいと頼みがたく、なかなかのものぞこなひなり、又世に名高き所などをば、外なるをも、しひておのが國おのが里のにせまほしがるならひにて、たゞいさゝかのよりどころめきたることをも、かたくとらへて、しひてこゝぞといひなして、しるしを作るたぐひなどはた、よに多きを、さる心して、まどふべからず、ふみなどは、むげに見たることなき、ひたぶるのしづのをの、おぼえゐてかたることは、しり口あはず、しどけなく、ひがことのみおほかれど、其中には、かへりておかしき事もまじるわざなれば、さるたぐひをも、心とゞめてきくべきわざ也、されぢ又、むかしなまなまの物しり人などの、尋ねきたるが、ひがさだめして、こゝはしかしかの跡ぞなど、をしへおきたるをきゝをりて、里人は、まことにさることと信じて、子うまごなどにも、かたりつたへたるたぐひもあンなれば、うべうべしくきこゆることも、なほひたぶるにはうけがたし、又みづからそのところのさまをゆき見てさだむるにも、くさぐさこゝろうべきことどもあり、おほかた所のさまかみさびて、木立しげく、物ふりなどしたるを見れば、こゝこそはと、めとまる物なれど、それはたうちつけには頼みがたし、大かたなにならぬ所にも、ふるめきたる森はやしなどは、多くおるもの也、木だちなど、二三百年をもへぬるは、いといと物ふりて見ゆるものなれば、ふるく見ゆるにつきても、たやすくは定めがたきわざなりかし、村の名、山川浦磯などの名に、心をつけて尋ぬべし、田どころなどのあざなといふ物などをも、よく尋ぬべし、寺の名に、古きがのこれるがよくあること也、しかはあれども又、すべて名によりて、誤ることもあるわざ也、又寺々の縁起といふ物、おほかた例のほうしのそらごとがちなれど、其中に、まれまれにはとるべきこともまじれるものなれば、これはたひたぶるにはすつべきにあらず、ふるきあとは、中ごろほうしどもの、國人をあざむきて、佛どころにしなしたるが、いづれの國にも多ければ、ほとけどころをも、其心してたづぬべし、ふるき寺には、ふるき書キ物など有て、古き事ののこれるおほし、むげに尋ぬべきたづきなき所も、思ひかけぬところより、たしかなるしるしの出來るやうもあれば、いたらぬくまなく、よろづに思ひめぐらして、くはしく尋ぬべし、かくて尋ねえたりと思ふところも、なほたしかには定(サダ)むべからず、よにさるべき人の定めおきつる所などは、ひがさだめなるも、つひにそこにさだまりて、後のまどひとなるわざ也かし、そもそも此くだりは、名所(ナドコロ)をたづぬるわざのみにもあらず、よろづのかむかへにもわたることどもありぬべくなむ、
75 天の下の政神事をさきとせられし事[三五三]
職員令に、神祇官を、もろもろの官のはじめに、まづあげて、それが次に、太政官を擧られたり、延喜式も、同くはじめに神祇式、次に太政官式也、後の世ながら、北畠ノ准后の職原抄も、令にならひて、ついでられたり、そもそもよろづの事、さばかり唐の國ぶりをならひ給へりし御世にしも、かく有しは、さすがに神の御國のしるしにて、いともいともたふとく、めでたきわざになむ有ける、世ノ中は何につけても、此こゝろばへこそあらまほしへれ、
か ら あ ゐ 六
おのが歌に、からあゐの末つむ花、とよめりければ、ある人、すゑつむ花は、くれなゐのとこそよみたれ、からあゐのとはいかゞ、といへるに、おのれこたへけらく、萬葉集の歌に、くれなゐを、からあゐともよめり、そもそもくれなゐといふは、此物もと呉(クレ)の國より渡りまうできたるよしにて、呉(クレ)の藍(アヰ)といふを、つゞめたる名
なるを、そは韓(カラ)國よりつたへつる故に、又韓藍(カラアヰ)ともいへるなり、といへる説のごとし、但しからといふは、西の方の國々のなべての名なれば、これは呉ノ國をさしていへるにて、呉藍(クレナヰ)といふと同じことにもあるべし、さるを萬葉の十一の巻には、鷄冠草(カラアヰ)とも書るにつきて、鴨頭草(ツキクサ)也とも、鷄頭花(ケイトウゲ)也ともいふ、説どもの有てまぎらはしきやうなれども、つき草とも、鷄頭花ともいふは、みなひがことにて、紅花(クレナヰ)まること疑ひなし、さればからあゐるなはち紅花(クレナヰ)なることを、さとしがてら、ことさらにかくはよめるぞ、ついでにいはむ、同七の巻に、「秋さらば移(ウツ)しもせんとわがまきしからあゐの花をたれかつみけん、移(ウツ)すとは、おろして染るをいふ、此移ノ字を、本に影に誤れり、といへりければ、うなづきてやみぬ、其おのが歌は
からあゐの末摘花の末つひに色にや出ん忍びかねてば
寄草戀といふ題にてよめる也、古今集なる、「我戀をしのびかねてばあしひきの山たちばなの色に出ぬべし、といふ歌にぞよくにたると、又いふ人もありなんか、
67 書うつし物かく事[二八七]
ふみをうつすに、同じくだりのうち、あるはならべるくだりなどに、同じ詞のあるときは、見まがへて、そのあひだなる詞どもを、寫しもらすこと、つねによくあるわざ也、又一ひらと思ひて、二ひら重(カサ)ねてかへしては、其ノ間ダ一ひらを、みながらおとすことも有リ、これらつねに心すべきわざ也、又よく似て、見まがへやすきもじなどは、ことにまがふまじく、たしかに書クべき也、これは寫しがきのみにもあらず、おほかた物かくに、心得べき事ぞ、すべて物をかくは、事のこゝろをしめさむとてなれば、おふなおふなもじさだかにこそかゝまほしけれ、さるをひたすら、筆のいきほひを見せむとのみしたるは、いかなることとも、よみときがたきが、よにおほかる、あぢきなきわざ也、常にかきかはす、消息文(セウソコブミ)なども、もじよみがたくては、いひやるすぢ、ゆきとほらず、よむ人はたくるしみて、かしらかたぶけつゝ、かへさひよめども、つひによみえずなどしては、こゝよみがたしと、かへしとはんも、さすがになめしきやうなれば、たゞおしはかりに心得ては、事たがひもするぞかし、
68 手かく事[二八八]
よろづよりも、手はよくかゝまほしきわざ也、歌よみがくもんなどする人は、ことに手あしくては、心おとりのせらるるを、それ何かはくるしからんといふも、一わたりことわりはさることながら、なほあかず、うちあはぬこゝちぞするや、のり長いとつたなくて、つねに筆とるたびに、いとくちをしう、いふかひなくおぼゆるを、人のこふまゝにおもなくたんざく一ひらなど、かき出て見るにも、我ながらだに、いとかたはに見ぐるしう、かたくななるを、人いかに見るらんと、はづかしくむねいたくて、わかゝりしほどに、などててならひはせざりけむと、いみしうくやしくなん、
69 業平ノ朝臣の月やあらぬてふ歌のこゝろ[二八九]
「月やあらぬ春やむかしの春ならぬ我身ひとつはもとの身にして、此歌、とりどりに解(トキ)たれども、いづれも其意くだくだしくして、一首(ヒトウタ)の趣とほらず、これによりて、今おのが思ひえたる趣をいはんには、まづ二つのやもじは、やはてふ意にて、月も春も、去年にかはらざるよし也、さて一首の意は、月やは昔の月にあらぬ月もむかしのまゝ也、春やは昔の春にあらざる、春もむかしのまゝの春なり、然るにたゞ我身ひとつのみは、本の昔のまゝの身ながら、むかしのやうにもあらぬことよ、といふ意をふくめたる物也、にしてといへる語のいきほひ、上ノ句に、月も春もむかしのまゝなるに、といへるとあひ照(テラ)して、おのづからふくめたる意は聞ゆる也、此人の歌、こゝろあまりて、詞たらずといへるは、かゝるをいへるなるべし、いせ物語のはしの詞に、立て見ゐて見見れど、こぞに似るべくもあらず、といへるは、此ふくめたる意を、あらはしたるもの也、去年ににぬとは、月春のにぬにはあらず、見るわがこゝちの、去年に似ぬ也、新古今集雜上に、清原ノ深養父の、「むかし見し春は昔の春ながら我身ひとつのあらずも有かな、とよめる歌は、此ノ業平ノ朝臣の歌を、註したるがごとし、これにて、よく聞えたる物をや、
70 縣居大人の傳[三〇三]
あがたゐの大人は、賀茂ノ縣主氏にて、遠祖(トホツオヤ)は、神魂(カミムスビノ)神の孫、鴨武津之身(カモタケツノミノ)命にて、八咫烏(ヤタガラス)と化(ナリ)て、神武天皇を導き奉り給ひし神なること、姓氏録に見えたるがごとし、此神の末、山城ノ國相樂ノ郡岡田ノ賀茂ノ大神を以齋(モテイツ)く、師朝といひし人、文永十一年に、遠江ノ國敷智ノ郡濱松ノ庄岡部ノ鄕なる、賀茂の新宮をいつきまつるべきよしの詔を蒙りて、彼ノ鄕を賜はり、すなはち彼ノ新宮の神主になさる、此事引馬草に見え、又綸旨の如くなる物あり、又乾元元年にも、詔とかうぶりて、かの岡部の地を領ぜる、これは正しき綸旨有て、家に傳はれり、かくて世々かの神主たりしを、大人の五世の祖、政定といひし、引馬原の御軍に功有て、東照神御祖ノ君より、來國行がうちたる刀と、丸龍の具足とを賜はりぬ、此事は三河記にも見えたり、さて大人は、元禄十年に、此岡部ノ鄕に生れ給ひて、わかゝりしほどより、古ヘ學ビにふかく心をよせて、享保十八年に、京にのぼりて、稻荷の荷田ノ宿禰東麻呂ノ大人の教をうけ給ひ、寛延三年に、江戸に下り給ひて、其後田安ノ殿に仕奉り給ふ、かの殿より、葵の文の御衣を賜はり給へる時の歌、「あふへてふあやの御衣をも氏人のかづかむものと神やしりけん、明和六年十月晦の日、とし七十三にて、みまかり給ひぬ、武藏ノ國荏原ノ郡品川の、東海寺の中、少林院の山に葬、こは大人の弟子(ヲシヘコ)なる某が、しるしたるまゝに、とりてしるせり、なほ父ぬし母とじなどをも、しるすべきものなるに、もれたるは、又よくしりたらむ人にとひきゝて、しるすべくなん、
71 花のさだめ[三〇四]
花はさくら、櫻は、山櫻の、葉あかくてりて、ほそきが、まばらにまじりて、花しげく咲たるは、又たぐふべき物もなく、うき世のものとも思はれず、葉青くて、花のまばらなるは、こよなくおくれたり、大かた山ざくらといふ中にも、しなじなの有て、こまかに見れば、一木ごとに、いさゝかかはれるところ有て、またく同じきはなきやう也、又今の世に、桐がやつ八重一重などいふも、やうかはりて、いとめでたし、すべてくもれる日の空に見あげたるは、花の色あざやかならず、松も何も、あをやかにしげりたるこなたに咲るは、色はえて、ことに見ゆ、空きよくはれたる日、日影のさすかたより見たるは、にほひこよなくて、おなじ花ともおぼえぬまでなん、朝日はさら也、夕ばえも、梅は紅梅、ひらけさしたるほどぞ、いとめでたきを、さかりになるまゝに、やうやうしらけゆきて、見どころなくなるこそ、いとくちをしけれ、さくらの咲るころまでも、ちることしらで、むげににほひなく、ねべれしぼみて、のこりたるをみれば、げに有てよの中は、何事もみなかくこそと、見る春ごとに、思ひしらるかし、白きはすべて香こそあれ、見るめはしなおくれたり、大かた梅の花は、ちひさき枝を、物にさして、ちかく見たるぞ、梢ながらよりは、まされる、桃の花は、あまた咲つゞきたるを、遠く見たるはよし、ちかくては、ひなびたり、山ぶきかきつばたなでしこ萩すゝき女郎花など、とりどりにめでたし、菊も、よきほどにつくろひたるこそよけれ、あまりうるはしく、したゝかにつくりなしたるは、中々にしななく、なつかしからず、つゝじ、野山に多く咲たるは、めさむるこゝちす、かいだうといふ物、からめきて、こまやかにうるはしき花也、そもそもかくいふは、みなおのが思ふ心にこそあれ、人は又おもふこゝろことなンべければ、一(ヒト)やうにさだむべきわざにはあらず、又いまやうの、よの人のもてはやすめる花どもも、よにおほかるを、かぞへいでぬは、ことされめきたるやうなれど、歌にもよみたらず、ふるき物にも、見えたることなきは、心のなしにや、なつかしからずおぼゆかし、されどそれはた、ひとやうなるひがこゝろにやあらむ、
72 玉あられ[三四六]
宣長ちかきころ玉あられといふ書をかきて、近き世にあまねく誤りならへることどもをあげて、うひ學のともがらをさとせるを、のりなががをしへ子として、何事も宣長が言にしたがふともがらの、其後の此ごろの歌文に、此書に出せる事どもを、なほ誤ることのおほかるは、いかなるひがことぞや、此書用ひぬよそ人は、いふべきかぎりにあらざるを、それだに心さときは、うはべこそ用ひざるかほつくれ、げにとおぼゆるふしぶしは、たちまちにさとりて、ひそかに改むるたぐひもあるを、ましてのりながが敎をよしとて、したがひながら、改めざるは、此ふみよみても、心にとまらず、やがてわすれたるにて、そはもとより心にしまず、なほざりに思へるから也、つねに心にしめたるすぢは、一たび聞ては、しかたちまちにわするゝ物にはあらざるを、よそ人の思はむ心も、はづかしからずや、これは玉あられのみにもあらず、何(イヅ)れの書見むも、おなじことぞかし、
73 かなづかひ[三四七]
假字づかひは、近き世明らかになりて、古ヘ學ビするかぎりの人は、心すめれば、をさをさあやまることなきを、宣長が弟子(ヲシヘコ)共の、つねに歌かきつらねて見するを見るに、誤リのみ多かるは、又いかにぞや、抑てにをはのとゝのへなどは、うひまなびの力及ばぬふしある物なれば、あやまるも、つみゆるさるゝを、かなづかひは、今は正濫抄もしは古言梯などをだに見ば、むげに物しらぬわらはべも、いとよくわきまふべきわざなるを、猶とりはづして、書キひがむるは、かへすかへすいかにぞや、これはた心とゞめず、又ひたぶるにまなびおやにすがりて、たがへらむは、直さるべしと、思ひおこたりて、おのが力いれざるからのわざにしあれば、かつはにくゝさへぞおぼゆる、しか人にのみすがりたらんには、つひにかなづかひをば、しるよなくてぞやみぬべかりける、さればいゐえゑおを、又はひふへほわゐうゑを又しちすつの濁音(ニゴリコヱ)など、いさゝかもうたがはしくおぼえむ假字は、わづらはしくとも、それしるせるむみを、かゝむたびごとにひらき見て、たしかにうかべずは、やむべきにあらず、何わざも、おのがちからをいれずては、しうることかたかンべきわざぞ、人の子の、としたくるまで、おやのてはなるゝことしらざらむは、いといといふかひなからじやは、
74 古き名どころを尋ぬる事[三四八]
ふるき神の社の、今は絶たる、又絶ざれども、さだかならずなりぬるなど、いづくにも多かるは、いとかなしきわざ也、神祇官の帳にのれるなどは、かけてもさはあるまじきわざなるを、中ごろの世のみだれに、天ノ下のよろづの事も、古ヘのおきても、皆みだれにみだれ、たえうせにたえうせにたる、萬ヅにつけて、いともいともかなしきは、亂れ世のしわざなりけり、さるを今の御世は、いにしへにもまれなるまで、よく治まりて、いともめでたく、天の下榮えにさかゆるまゝに、よろづに古ヘをたづねて、絶たるをおこし、おとろへたるを直し給ふ御世にしあれば、神の社どもは、殊に古ヘに立かへりて、榮ゆべき時なりけり、然あるにつけては、絶たるは、跡をだにさだかにたづねまほしく、又今も有リながら、さだかならず、疑はしきをば、よく考へ尋ねて、たしかにそれと、定めしらまほしきわざになむありける、次には神ノ社ならぬも、いにしへに名あるところどころ、歌枕なども、今はさだかならぬが多かるは、かゝるめでたき時世(トキヨ)にあたりて、尋ねおかまほしきわざ也、かくて神の社にまれ、御陵にまれ、歌まくらにまれ、何にまれ、はるかなるいにしへのを、中ごろとめうしなひたるを、今の世にして、たづね定めむことは、大かたたやすからぬわざになむ有ける、其ゆゑをいはむには、まづ此ふるき所をたづぬるわざは、たゞに古ヘの書どもを考へたるのみにては、知リがたし、いかにくはしく考へたるも、書(フミ)もて考へ定めたることは、其所にいたりて見聞けば、いたく違ふことの多き物也、よそながらは、さだかならぬ所も、其國にては、さすがに書(カキ)もつたへ、かたりも傳へて、まがひなきことも有リ、さればみづから其地(トコロ)にいたりて、見もし、そこの事よくしれる人に、とひきゝなどもせでは、事たらはず、又たゞ一たび物して、見聞キたるのみにても、猶たらはず、ゆきて見聞て、立かへりて、又ふみどもと考へ合せて、又々もゆきて、よく見聞たるうへならでは、定めがたかるべし、さて又其ところの人にあひて、とひきくにも、心得べきことくさぐさあり、いにしへの事を、あまりたしかにしりがほにかたるは、おほくは、書のかたはしを、なまなまにかむかへなどしたるものの、おのがさかしらもて、さだめいふが多ければ、そはいと頼みがたく、なかなかのものぞこなひなり、又世に名高き所などをば、外なるをも、しひておのが國おのが里のにせまほしがるならひにて、たゞいさゝかのよりどころめきたることをも、かたくとらへて、しひてこゝぞといひなして、しるしを作るたぐひなどはた、よに多きを、さる心して、まどふべからず、ふみなどは、むげに見たることなき、ひたぶるのしづのをの、おぼえゐてかたることは、しり口あはず、しどけなく、ひがことのみおほかれど、其中には、かへりておかしき事もまじるわざなれば、さるたぐひをも、心とゞめてきくべきわざ也、されぢ又、むかしなまなまの物しり人などの、尋ねきたるが、ひがさだめして、こゝはしかしかの跡ぞなど、をしへおきたるをきゝをりて、里人は、まことにさることと信じて、子うまごなどにも、かたりつたへたるたぐひもあンなれば、うべうべしくきこゆることも、なほひたぶるにはうけがたし、又みづからそのところのさまをゆき見てさだむるにも、くさぐさこゝろうべきことどもあり、おほかた所のさまかみさびて、木立しげく、物ふりなどしたるを見れば、こゝこそはと、めとまる物なれど、それはたうちつけには頼みがたし、大かたなにならぬ所にも、ふるめきたる森はやしなどは、多くおるもの也、木だちなど、二三百年をもへぬるは、いといと物ふりて見ゆるものなれば、ふるく見ゆるにつきても、たやすくは定めがたきわざなりかし、村の名、山川浦磯などの名に、心をつけて尋ぬべし、田どころなどのあざなといふ物などをも、よく尋ぬべし、寺の名に、古きがのこれるがよくあること也、しかはあれども又、すべて名によりて、誤ることもあるわざ也、又寺々の縁起といふ物、おほかた例のほうしのそらごとがちなれど、其中に、まれまれにはとるべきこともまじれるものなれば、これはたひたぶるにはすつべきにあらず、ふるきあとは、中ごろほうしどもの、國人をあざむきて、佛どころにしなしたるが、いづれの國にも多ければ、ほとけどころをも、其心してたづぬべし、ふるき寺には、ふるき書キ物など有て、古き事ののこれるおほし、むげに尋ぬべきたづきなき所も、思ひかけぬところより、たしかなるしるしの出來るやうもあれば、いたらぬくまなく、よろづに思ひめぐらして、くはしく尋ぬべし、かくて尋ねえたりと思ふところも、なほたしかには定(サダ)むべからず、よにさるべき人の定めおきつる所などは、ひがさだめなるも、つひにそこにさだまりて、後のまどひとなるわざ也かし、そもそも此くだりは、名所(ナドコロ)をたづぬるわざのみにもあらず、よろづのかむかへにもわたることどもありぬべくなむ、
75 天の下の政神事をさきとせられし事[三五三]
職員令に、神祇官を、もろもろの官のはじめに、まづあげて、それが次に、太政官を擧られたり、延喜式も、同くはじめに神祇式、次に太政官式也、後の世ながら、北畠ノ准后の職原抄も、令にならひて、ついでられたり、そもそもよろづの事、さばかり唐の國ぶりをならひ給へりし御世にしも、かく有しは、さすがに神の御國のしるしにて、いともいともたふとく、めでたきわざになむ有ける、世ノ中は何につけても、此こゝろばへこそあらまほしへれ、
たまかつま七の巻
ふ ぢ な み 七
あるところにて、藤の花のいとおもしろく咲りけるを見て、あかずおぼえければ、かへらん人にといふ歌を思ひ出て、
藤の花わが玉のをも松が枝にまつはれたみむ千世の春迄
とよみたるを、そのまたの日、此巻をかくとて、例のなづけつ、
76 神社の祭る神をしらまほしくする事[三五五]
古き神社どもにはいかなる神を祭れるにか、しられぬぞおほかる、神名帳にも、すべてまつれる神の御名は、しるされずたゞ其社號(ヤシロノナ)のみを擧られたり、出雲風土記の、神社をしるせるやうも、同じことなり、社號すなはち其神の御名なれば、さも有べきことにて、古ヘはさしも祭る神をば、しひてはしらでも有けむ、然るを後の世には、かならず祭る神をしらでは、あるまじきことのごと心得て、しられぬをも、しひてしらむとするから、よろづにもとめて、或は社號につきて、神代のふみに、いさゝかも似よれる神ノ名あれば、おしあてに其神と地(クニ)にも、其數かぎりなくおはしますことなれば、天の下の社々には、其中のいづれの神を祭れるも、しるべからぬぞおほかるべき、神代紀などに出たる神は、その千萬の中の一つにもたらざンめるを、必ズ其中にて、其神と定めむとするは、八百萬の神の御名は、神代紀に、ことごとく出たりと思ふひや、古書に御名の出ざる神の多かることを、思ひわきまへざるは、いかにぞや、さればもとより某(ソノ)神といふ、古きつたへのなきを、しひて後に考へて、あらぬ神に定めむは、中々のひがこと也、もしその社ノ號によりて定めむとせば、たとへば伊勢の大神宮は、五十鈴ノ宮と申せば、祭る神は五十鈴姫ノ命にて、鈴の神、外宮は、わたらひの宮と申せば、綿津見(ワタツミノ)命にて、海神也とせんか、近き世に、物しり人の考へて定むるは、大かたこれに似たるものにて、いとうきたることのみなれば、すべて信(ウケ)がたし、しられぬをしへてもとめて、あらぬ神となさむよりは、たゞその社ノ號を、神の御名としてあらんこそ、古ヘの意なるべきを、社ノ號のみにては、とらへどころなきがごと思ふは、近き世の俗心(ツタナキココロ)にこそあれ、今の世とても、よに廣くいひならへる社號は、そをやがて神の御名と心得居て、八幡宮春日明神稲荷明神などいへば、かならずしもその神は、いかなる神ぞとまでは、たづねず、たゞ八幡春日いなりにてあるにあらずや、もろもろのやしろも、皆同じことにて、社ノ號すなはち其神の御名なるものをや、
77 おのが仕奉る神を尊き神になさまほしくする事[三五六]
中昔よりして、神主祝部のともがら、己が仕奉る社の神を、あるが中にも尊き神にせまほしく思ひては、古き傳へのある御名をば、隠(カク)して、あるは國常立ノ尊をまつれり、天照大神を祭れり、神武天皇をまつれりなどいひて、例の神祕のむねありげに、似つかはしく作りなして偽るたぐひ、世に多し、おのれ尊き神につかふる者にならむとて、その仕奉る神を、わたくしに心にまかせて、いつはり奉るは、いともかしこき、みだりごとならずや、
78 皇孫天孫と申す[三五七]
邇々藝ノ命より始め奉りて、御代々々の天皇を、皇(スメミマノ)命とも、天神御子(アマツカミノミコ)とも申すを、書紀の神代ノ巻に、皇孫又天孫と書れたるは、ともに古言にあらず、皇孫とは、皇御孫ノ命と申す御號(ミナ)を、例の漢文ざまに、つくられたる也、他(ホカ)の古書どもにはみな、皇御孫ノ命と見えて、續紀の歌に、皇(スメ)をはぶきて、御孫(ミマノ)命とはよみたることあれども、命(ミコト)をはぶきて申せることは見えず、まして天孫と申せることは、古き文には、すべて見えず、天孫とは、天神御子(アマツカミノミコ)と申すを、つくりかへられたる文字と見えたり、然るを世の人、ひたぶるに漢文ざまのうるはしき方を好むならひとなりては、此皇孫天孫と申す御號(ミナ)のみひろまりて、かへりて皇御孫ノ命天ツ神ノ御子と申す、いにしへのまことのうるはしき御號はかくれたるが如し、皇孫はすめみま、天孫はあめみまと訓たれども、文字になづまで、皇孫をば、すめみまのみこととよみ奉るべく、天孫をば、あまつかみのみことよみ奉りて古ヘのまことの御號(ミナ)を、ひろくせまほしきわざ也、あめみまといふは、殊につたなく、よしなき訓なるをや、
79 神わざのおとろへのなげかはしき事[三六九]
よろづよりも、世ノ中に願はしきは、いかでもろもろの神ノ社のおとろへを、もて直し、もろもろの神わざを、おこさまほしくこそ、今の世の神ノ社神事のさまは、おほかた中ごろのみだれ世に、いたくおとろへすたれたるまゝなるを、今の世の人は、たゞ今のさまをのみ見て、いにしへよりかゝるものとぞ思ひたンめる、まれまれ書をよむ人なども、たゞからぶみをのみむねとはよみて、其心もて、よろづをさだして、皇國のふるきふみどもをば、をさをさよむ人もなければ、古の御世には、神社神事を、むねと重くし給ひしことをばしらず、又まれにはしれる人もあれども、なほ今の世のならひにまぎれては、いにしへを思ひくらべて、これを深く歎く人のなきこそ、いと悲しけれ、
80 よの人の神社は物さびたるをたふとしとする事[三七〇]
今の世の人、神の御社は、さびしく物さびたるを、たふとしとおもふは、いにしへ神社の盛(サカリ)なりし世のさまをば、しらずして、たゞ今のよに、大かたふるく尊き神社どもは、いみしく衰へて、あれたるを見なれて、ふるく尊き神社は、もとよりかくある物と、心得たるからのひがことなり、
81 唐の國人あだし國あることをしらざりし事[三七二]
もろこしの國のいにしへの人、すべて他國(アダシクニ)あることをしらず、おほかた國を治め、身ををさむる道よりはじめて、萬の事、みな其國のいにしへの聖人といひし物の、はじめたるごとく心得て、天地の間に、國はたゞわれひとり尊(タフト)しと、よろづにほこりならひたり、然るをやゝ後に、天竺といふ國より、佛法といふ物わたり來ては、いさゝかあだし國のあることをも、しれるさま也、かくて近き世にいたりては、かの天竺よりも、はるかに西のかたなる國々の事も、やうやうしられて、おほかた今は、天地の間の、萬の國の事、をさをさしられざるはなきを、そのはるかの西の國々にも、もろこしにあるかぎりの事は、皆むかしより有て、もろこしにはなき物も多くあり、もろこしよりはるかにまされる事も有リ、その國々は、みな近き世まで、もろこしと通ひはなかりしかども、本よりしか何事も、たらひてあるぞかし、そもそももろこしの古ヘは、たゞその近きほとりなる、胡國などいふ國の事のみを、わづかによくはしりて、其外は、さしも遠からぬ國々の事も、こまかにはしらず、おぼおぼしくて、すべて他國の事いへるは、みだりごとのみ也、かくてそのよくしれる胡國などは、いたづらに廣きのみにして、いといやしくわろき國なるを、つねに見しり聞しりては、他國はいづれも皆、かゝる物とのみ思へりしから、何事もたゞたふときは吾ひとりと、みだりにほこれる也、いにしへあだし國の事を、ひろくしらざりしほどこそ、さもあらめ、近き世になりて、遠き國々の事も、まなよくしられても、猶古ヘよりのくせを、あらたむることなく、今に同じさまに、ほこりをるなるを、皇國にても、學問をもする人は、今は萬ヅの國國のことをも、大かた知リたるべきに、なほむかしよりの癖(クセ)にて、もろこし人のみだりごとを信じて、ひたぶるにかの國を尊みて、何事もみな、かの國より始まれるやうに思ひ、かの國より外に、國はなきごと心得居るは、いかなるまどひぞや、
82 おらんだといふ國のまなび[三七三]
ちかきとしごろ、於蘭陀といふ國の學問をする事、はじまりて、江戸などに、そのともがら、かれこれとあめり、ある人、もはらそのまなびをするが、いひけるおもむきをきくに、於蘭陀は、其國人、物かへに、遠き國々を、あまねくわたりありく國なれば、其國の學問をすれば、遠き國々のやうを、よくしる故に、漢學者の、かの國にのみなづめるくせの、あしきことのしらるゝ也、あめつちのあひだ、いづれの國も、おのおの其國なれば、必ズ一トむきにかたよりなづむべきにあらず、とやうにおもむけいふめり、そはかのもろこしにのみなづめるよりは、まさりて一わたりさることとは聞ゆれども、なほ皇國の、萬の國にすぐれて、尊きことをば、しらざるにや、萬の國の事をしらば、皇國のすぐれたるほどは、おのづからしるらむものを、なほ皇國を尊むことをしらざるは、かのなづめるをわろしとするから、たゞなづまぬをよしとして、又それになづめるにこそあらめ、おらんだのにはあらぬ、よのつねの學者にも、今は此たぐひも有也、
83 もろこしになきこと[三七四]
もろこしのまなびする人、かの國になき事の、御國にあるをば、文盲(モンマウ)なる事と、おとしむるを、もろこしにもあることとだにいへば、さてゆるすは、いかにぞや、もろこしには、すべて文盲なる事は、なき物とやこゝろえたるらむ、かの國の學びするともがらは、よろづにかしこげに、物はいへども、かゝるおろかなることも有けり、
84 ある人の言[三九三]
櫻の花ざかりに、歌よむ友だち、これかれかいつらねて、そこかしこと、見ありきける、かへるさに、見し花どもの事、かたりつゝ來(ク)るに、ひとりがいふやう、まろは、歌よまむと、思ひめぐらしける程に、けふの花は、いかに有けむ、こまやかにも見ずなりぬといへるは、をこがましきやうなれど、まことはたれもさもあることと、をかしくぞ聞し、
85 土佐國に火葬なし[三九五]
土佐國には、火葬といふわざなし、さる故に、かの國人は、他國の、火葬にすることをかたれば、あやしきわざに思へりとぞ、これもかの國人のかたりけるに、そは近き世のさだめかととひしに、いにしへより然りとぞいへる、
86 はまなのはし[四〇一]
さらしなの日記にいはく、濱名の橋、くだりし時は、黒木をわたしたりし、此度はあとだに見えねば、舟にて渡る、入江に渡せし橋也、との海は、いといみしく浪高くて、入江のいたづらなる洲どもに、こと物もなく、松原のしげれる名かより、浪のよせかへるも、いろいろの玉やうに見え、まことに松の末より、浪はこゆるやうにみえて、いみしくおもしろし、それよりかみは、ゐのはなといふ坂の、えもいはぬわびしきを、のぼりぬれば、三河ノ國の高師の濱といふ、
87 おのれとり分て人につたふべきふしなき事[四〇九]
おのれは、道の事も歌の事も、あがたゐのうしの敎のおもむきによりて、たゞ古の書共を、かむかへさとれるのみこそあれ、其家の傳へごととては、うけつたへたることさらになければ、家々のひめことなどいふかぎりは、いかなる物にか、一ツだにしれることなし、されば又、人にとりわきて殊に傳ふべきふしもなし、すべてよき事は、いかにもいかにも、世にひろくせまほしく思へば、いにしへの書共を考へて、さたりえたりと思ふかぎりは、みな書にかきあらはして、露ものこしこめたることはなきぞかし、おのづからも、おのれにしたがひて、物まなばむと思はむ人あらば、たゞあらはせるふみどもを、よく見てありぬべし、そをはなちて外には、さらにをしふべきふしはなきぞとよ、
88 もろこしの老子の説まことの道に似たる所ある事[四一〇]
おのれ今まことの道のおもむきを見明らめて、ときあらはせるを、漢學(カラマナビ)のともがら、かの國の老子といふものの説(トキゴト)によれり、と思ひいふ人、これかれあり、そもそもおのが道をとく趣は、いさゝかも私のさかしらをばまじへず、神典(カミノミフミ)に見えたるまゝなること、あだし注釋どもと、くらべ見て知べし、かくてそ
の趣の、たまたまかの老子といふものの言と、にたるところどころのあるを見て、ゆくりなく、それによりていへりとは、例のかのもろこしの國をおきて外に國はなく、かの國ならでは、何事も始まらぬことと、ひたおもむきにおもひとれる、ひが心より、さは思ふなンめり、いにしへより、漢ノ國と通へることなく、たがひに聞キも及ばざりし國々にも、ほどほどにつけつゝ、有べきかぎりの事は、おのおの本よりありける中にも、殊に皇國は、萬ヅの國の本、よろづの國の宗(オヤ)とある御國なれば、萬ノ國々わたりて、正しきまことの道は、たゞ皇國にこそ傳はりたれ、他國(アダシクニ)には、傳はれることなければ、此道をしることあたはず、然るにもろこしの國に、かの老子といひしは、すぐれてかしこく、たどりふかき人にこそ有けめ、世のこちたくさかしだちたる敎ヘは、うはべこそよろしきにたれ、まことには、いとよろしからず、中々の物害(モノソコナ)ひとなることをさとりて、まことの道はかくこそあるべきものなれと、はしばしみづから考ヘ出たることの中に、かむかへあてて、たまたま此まことの道に似たるふし、合へることもあるなりけり、さるはまことの道は、もとより人のさかしらをくはへたることなく、皇神(スメカミ)の定めおき給へるまゝなる道にしあれば、そのおもむきをとかむには、かれが、さかしらをにくめる説は、おのづから似たるところ、あへるところ有べきことわり也、しかはあれども、かれがいへるは、たゞおのが智慮(サトリ)もて、考へ出たるかぎりにこそあれ、皇國に生れて、正しく此道を聞るにあらざれば、その主(ムネ)とある本のこゝろは、しることあたはず、いたくたがひて、さらに似もつかぬことなるを、かの漢學のともがら、しかたがへるところをがしらで、たまたまかたはし似たることのあるをとらへてそれによれりとしもいひなすは、いとをこ也かし、大かたよろづの事、おのづからこれにもかれにも、かよひてにたることは、かならずまじる物にて、此道も、儒のおもむきかよけるところもまじり、佛の道とも似たることはまじれゝが、おのづからかの老子とも、かたはし似たるところ過へるところは、などかまじらではあらむ、
89 道をとくことはあだし道々の意にも世の人のとりとらざるにもかゝはるまじき事[四一一]
道をとかむに、儒にまれ老にまれ佛にまれ、まれまれに心ばへのかよへるところのあるをとらへて、おのが心のひくかたにまかせて、かよはぬところをも、すべてそのすぢに引よせてときなし、あるは又他(アダシ)道と同じからんことを、いとひさけて、ことさらにけぢめを見せ、さまをかへて説(トカ)むとする、これらみないとあぢきなくしひたるわざ也、似ざらむもにたらむも、異(コト)ならむも同じからむも、とにかくに異道(アダシミチ)の意には、いさゝかもかゝはるべきわざにあらず、又かくときたらむには、世にうけひかじ、かくいひてこそ、人は信ぜめなど、世の人の心をとりて、いさゝかもときまげむことは、又いとあるまじく、心ぎたなきわざ也、すべて世ノ人のほめそしりをも、思ふべきにはあらず、たとひあだし道々とは、うらうへのたがひあり、世にも絶えて信ずる人なからむにても、ただ神の御ふみのおもむきのまゝにこそはとくべきわざなりけれ、
90 香をきくといふは俗言なる事[四一二]
香(カウ)を聞クといふは、もとからことにて、古ヘの詞にあらず、すべて物の香(カ)は、薫物(タキモノ)などをも、かぐといふぞ雅言(ミヤビコト)にて、古今集の歌などにも、花たちばなの香をかげばと見え、源氏物語の梅枝ノ巻に、たき物共のおとりまさりを、兵部卿ノ宮の論(サダ)め給ふところにも、人々の心々に合せ給へる、深さ淺さを、かぎあはせ給へるに、などこそ見えたれ、聞(キク)といへる事は、昔の書に見えたることなし、今の世の人は、そをばしらで、香(カウ)などをかぐといはむは、いやしき詞のごと心得ためるは中々のひがこと也、きくといふぞ、俗言(サトビコト)には有ける、
91 もろこしに名高き物しり人の佛法を信じたりし事[四一三]
佛の道は、もろこしの國にて、よゝに名高き儒者などの中にも、信じ尊みたるが、あまた聞とゆるによりては、まことにすてがたき物にこそ、と思ふ人あンめれど、かのもろこしにて、しか名高き物しり人どもの、佛をしんじ尊みたるやうなくは、まことの心に信じたふとみたるは、いとすくなくて、おほくはたゞもてあそびたるにこそあれ、さるはかの道の説(トケ)るやう、あやしく廣く大きにして、此世のほかを、とほく深く、さとり明らめたるさま、すべて心のおきてなど、めづらかにおかしきものなるが故に、詩作る人などは、さらにもいはず、さらぬも、これをもてあそびて、風流(ミヤビ)のたすけにぞしたンめる、又その諸宗に、高僧と聞ゆるほうしどもの中にも、實に尊み信じて、おこなひたるにあらで、世の中の人にたふとまれ、いさぎよくいみしき名をとゞめて、後の世まであふがれむために、その道のふみを深く學び、もろもろの欲をも忍び、たへがたき行ひをもして、まことしげにふるまひたるぞ、多く見えたンめる、そもそも利のため名のためには、命をさへに、をしまぬたぶひもあるわざなれば、何かは、それはたあやしむべきことにもあらずかし、
92 世の人佛の道に心のよりやすき事[四一四]
ほとけの道には、さばかりさかしだちたる、今の世の人の心も、うつりやすきは、かならず其道よろしと、思ひとれるにしもあらねど、むかしよりあまねくさかりにて、おしなべて世ノ中の人の、皆おこなふわざなるに、かたへはもよほさるゝぞ多かりける、すべてなにわざも、世にあまねく、人のみなする事には、たれもすゞろに心のよりやすきならひぞかし、
93 ゐなかにいにしへの雅言(ミヤビゴト)ののこれる事[四一五]
すべてゐなかには、いにしへの言ののこれること多し、殊にとほき國人のいふ言の中には、おもしろきことどもぞまじれる、おのれとしごろ心をつけて、遠き國人の、とぶらひきたるには、必ズその国の詞をとひきゝもし、その人のいふ言をも、心とゞめてきゝもするを、なほ國々の詞共を、あまねく聞あつめなば、いかにおもしろきことおほからん、ちかきころ、肥後ノ國人のきたるが、いふことをきけば、世に見える聞えるなどいふたぐひを、見ゆる聞ゆるなどぞいふなる、こは今の世にはたえて聞えぬ、雅(ミヤ)びたることばづかひなるを、其國にては、なべてかくいふにやととひければ、ひたぶるの賤(シヅ)山がつは皆、見ゆるきこゆるさゆるたゆる、などやうにいふを、すこしことばをもつくろふほどの者は、多くは見える聞えるとやうにいふ也、とぞ語りける、そは中々今のよの俗(イヤシ)きいひざまなるを、なべて國々の人のいふから、そをよきことと心得たるなンめり、いづれの國にても、しづ山がつのいふ言は、よこなまりながらも、おほくむかしの言をいひつたへたるを、人しげくにぎはゝしき里などは、他(コト)國人も入まじり、都の人なども、ことにふれてきかよひなどするほどに、おのづからこゝかしこの詞をきゝならひては、おのれもことえりして、なまさかしき今やうにうつりやすくて、昔ざまにとほく、中々にいやしくなんなりもてゆくめる、まことや同じひごの國の、又の人のいへる、かの國にて、ひきがへるといふ物を、たんがくといふなるは、古ヘのたにぐゝの訛(ヨコナマ)りなるべくおぼゆ、とかたりしは、もことに然なるべし、此たぐひのこと、國々になほ聞ることおほかるを、いまはふと思ひ出たることをいふ也、なほおもひいでむまゝに、又もいふべし、
ふ ぢ な み 七
あるところにて、藤の花のいとおもしろく咲りけるを見て、あかずおぼえければ、かへらん人にといふ歌を思ひ出て、
藤の花わが玉のをも松が枝にまつはれたみむ千世の春迄
とよみたるを、そのまたの日、此巻をかくとて、例のなづけつ、
76 神社の祭る神をしらまほしくする事[三五五]
古き神社どもにはいかなる神を祭れるにか、しられぬぞおほかる、神名帳にも、すべてまつれる神の御名は、しるされずたゞ其社號(ヤシロノナ)のみを擧られたり、出雲風土記の、神社をしるせるやうも、同じことなり、社號すなはち其神の御名なれば、さも有べきことにて、古ヘはさしも祭る神をば、しひてはしらでも有けむ、然るを後の世には、かならず祭る神をしらでは、あるまじきことのごと心得て、しられぬをも、しひてしらむとするから、よろづにもとめて、或は社號につきて、神代のふみに、いさゝかも似よれる神ノ名あれば、おしあてに其神と地(クニ)にも、其數かぎりなくおはしますことなれば、天の下の社々には、其中のいづれの神を祭れるも、しるべからぬぞおほかるべき、神代紀などに出たる神は、その千萬の中の一つにもたらざンめるを、必ズ其中にて、其神と定めむとするは、八百萬の神の御名は、神代紀に、ことごとく出たりと思ふひや、古書に御名の出ざる神の多かることを、思ひわきまへざるは、いかにぞや、さればもとより某(ソノ)神といふ、古きつたへのなきを、しひて後に考へて、あらぬ神に定めむは、中々のひがこと也、もしその社ノ號によりて定めむとせば、たとへば伊勢の大神宮は、五十鈴ノ宮と申せば、祭る神は五十鈴姫ノ命にて、鈴の神、外宮は、わたらひの宮と申せば、綿津見(ワタツミノ)命にて、海神也とせんか、近き世に、物しり人の考へて定むるは、大かたこれに似たるものにて、いとうきたることのみなれば、すべて信(ウケ)がたし、しられぬをしへてもとめて、あらぬ神となさむよりは、たゞその社ノ號を、神の御名としてあらんこそ、古ヘの意なるべきを、社ノ號のみにては、とらへどころなきがごと思ふは、近き世の俗心(ツタナキココロ)にこそあれ、今の世とても、よに廣くいひならへる社號は、そをやがて神の御名と心得居て、八幡宮春日明神稲荷明神などいへば、かならずしもその神は、いかなる神ぞとまでは、たづねず、たゞ八幡春日いなりにてあるにあらずや、もろもろのやしろも、皆同じことにて、社ノ號すなはち其神の御名なるものをや、
77 おのが仕奉る神を尊き神になさまほしくする事[三五六]
中昔よりして、神主祝部のともがら、己が仕奉る社の神を、あるが中にも尊き神にせまほしく思ひては、古き傳へのある御名をば、隠(カク)して、あるは國常立ノ尊をまつれり、天照大神を祭れり、神武天皇をまつれりなどいひて、例の神祕のむねありげに、似つかはしく作りなして偽るたぐひ、世に多し、おのれ尊き神につかふる者にならむとて、その仕奉る神を、わたくしに心にまかせて、いつはり奉るは、いともかしこき、みだりごとならずや、
78 皇孫天孫と申す[三五七]
邇々藝ノ命より始め奉りて、御代々々の天皇を、皇(スメミマノ)命とも、天神御子(アマツカミノミコ)とも申すを、書紀の神代ノ巻に、皇孫又天孫と書れたるは、ともに古言にあらず、皇孫とは、皇御孫ノ命と申す御號(ミナ)を、例の漢文ざまに、つくられたる也、他(ホカ)の古書どもにはみな、皇御孫ノ命と見えて、續紀の歌に、皇(スメ)をはぶきて、御孫(ミマノ)命とはよみたることあれども、命(ミコト)をはぶきて申せることは見えず、まして天孫と申せることは、古き文には、すべて見えず、天孫とは、天神御子(アマツカミノミコ)と申すを、つくりかへられたる文字と見えたり、然るを世の人、ひたぶるに漢文ざまのうるはしき方を好むならひとなりては、此皇孫天孫と申す御號(ミナ)のみひろまりて、かへりて皇御孫ノ命天ツ神ノ御子と申す、いにしへのまことのうるはしき御號はかくれたるが如し、皇孫はすめみま、天孫はあめみまと訓たれども、文字になづまで、皇孫をば、すめみまのみこととよみ奉るべく、天孫をば、あまつかみのみことよみ奉りて古ヘのまことの御號(ミナ)を、ひろくせまほしきわざ也、あめみまといふは、殊につたなく、よしなき訓なるをや、
79 神わざのおとろへのなげかはしき事[三六九]
よろづよりも、世ノ中に願はしきは、いかでもろもろの神ノ社のおとろへを、もて直し、もろもろの神わざを、おこさまほしくこそ、今の世の神ノ社神事のさまは、おほかた中ごろのみだれ世に、いたくおとろへすたれたるまゝなるを、今の世の人は、たゞ今のさまをのみ見て、いにしへよりかゝるものとぞ思ひたンめる、まれまれ書をよむ人なども、たゞからぶみをのみむねとはよみて、其心もて、よろづをさだして、皇國のふるきふみどもをば、をさをさよむ人もなければ、古の御世には、神社神事を、むねと重くし給ひしことをばしらず、又まれにはしれる人もあれども、なほ今の世のならひにまぎれては、いにしへを思ひくらべて、これを深く歎く人のなきこそ、いと悲しけれ、
80 よの人の神社は物さびたるをたふとしとする事[三七〇]
今の世の人、神の御社は、さびしく物さびたるを、たふとしとおもふは、いにしへ神社の盛(サカリ)なりし世のさまをば、しらずして、たゞ今のよに、大かたふるく尊き神社どもは、いみしく衰へて、あれたるを見なれて、ふるく尊き神社は、もとよりかくある物と、心得たるからのひがことなり、
81 唐の國人あだし國あることをしらざりし事[三七二]
もろこしの國のいにしへの人、すべて他國(アダシクニ)あることをしらず、おほかた國を治め、身ををさむる道よりはじめて、萬の事、みな其國のいにしへの聖人といひし物の、はじめたるごとく心得て、天地の間に、國はたゞわれひとり尊(タフト)しと、よろづにほこりならひたり、然るをやゝ後に、天竺といふ國より、佛法といふ物わたり來ては、いさゝかあだし國のあることをも、しれるさま也、かくて近き世にいたりては、かの天竺よりも、はるかに西のかたなる國々の事も、やうやうしられて、おほかた今は、天地の間の、萬の國の事、をさをさしられざるはなきを、そのはるかの西の國々にも、もろこしにあるかぎりの事は、皆むかしより有て、もろこしにはなき物も多くあり、もろこしよりはるかにまされる事も有リ、その國々は、みな近き世まで、もろこしと通ひはなかりしかども、本よりしか何事も、たらひてあるぞかし、そもそももろこしの古ヘは、たゞその近きほとりなる、胡國などいふ國の事のみを、わづかによくはしりて、其外は、さしも遠からぬ國々の事も、こまかにはしらず、おぼおぼしくて、すべて他國の事いへるは、みだりごとのみ也、かくてそのよくしれる胡國などは、いたづらに廣きのみにして、いといやしくわろき國なるを、つねに見しり聞しりては、他國はいづれも皆、かゝる物とのみ思へりしから、何事もたゞたふときは吾ひとりと、みだりにほこれる也、いにしへあだし國の事を、ひろくしらざりしほどこそ、さもあらめ、近き世になりて、遠き國々の事も、まなよくしられても、猶古ヘよりのくせを、あらたむることなく、今に同じさまに、ほこりをるなるを、皇國にても、學問をもする人は、今は萬ヅの國國のことをも、大かた知リたるべきに、なほむかしよりの癖(クセ)にて、もろこし人のみだりごとを信じて、ひたぶるにかの國を尊みて、何事もみな、かの國より始まれるやうに思ひ、かの國より外に、國はなきごと心得居るは、いかなるまどひぞや、
82 おらんだといふ國のまなび[三七三]
ちかきとしごろ、於蘭陀といふ國の學問をする事、はじまりて、江戸などに、そのともがら、かれこれとあめり、ある人、もはらそのまなびをするが、いひけるおもむきをきくに、於蘭陀は、其國人、物かへに、遠き國々を、あまねくわたりありく國なれば、其國の學問をすれば、遠き國々のやうを、よくしる故に、漢學者の、かの國にのみなづめるくせの、あしきことのしらるゝ也、あめつちのあひだ、いづれの國も、おのおの其國なれば、必ズ一トむきにかたよりなづむべきにあらず、とやうにおもむけいふめり、そはかのもろこしにのみなづめるよりは、まさりて一わたりさることとは聞ゆれども、なほ皇國の、萬の國にすぐれて、尊きことをば、しらざるにや、萬の國の事をしらば、皇國のすぐれたるほどは、おのづからしるらむものを、なほ皇國を尊むことをしらざるは、かのなづめるをわろしとするから、たゞなづまぬをよしとして、又それになづめるにこそあらめ、おらんだのにはあらぬ、よのつねの學者にも、今は此たぐひも有也、
83 もろこしになきこと[三七四]
もろこしのまなびする人、かの國になき事の、御國にあるをば、文盲(モンマウ)なる事と、おとしむるを、もろこしにもあることとだにいへば、さてゆるすは、いかにぞや、もろこしには、すべて文盲なる事は、なき物とやこゝろえたるらむ、かの國の學びするともがらは、よろづにかしこげに、物はいへども、かゝるおろかなることも有けり、
84 ある人の言[三九三]
櫻の花ざかりに、歌よむ友だち、これかれかいつらねて、そこかしこと、見ありきける、かへるさに、見し花どもの事、かたりつゝ來(ク)るに、ひとりがいふやう、まろは、歌よまむと、思ひめぐらしける程に、けふの花は、いかに有けむ、こまやかにも見ずなりぬといへるは、をこがましきやうなれど、まことはたれもさもあることと、をかしくぞ聞し、
85 土佐國に火葬なし[三九五]
土佐國には、火葬といふわざなし、さる故に、かの國人は、他國の、火葬にすることをかたれば、あやしきわざに思へりとぞ、これもかの國人のかたりけるに、そは近き世のさだめかととひしに、いにしへより然りとぞいへる、
86 はまなのはし[四〇一]
さらしなの日記にいはく、濱名の橋、くだりし時は、黒木をわたしたりし、此度はあとだに見えねば、舟にて渡る、入江に渡せし橋也、との海は、いといみしく浪高くて、入江のいたづらなる洲どもに、こと物もなく、松原のしげれる名かより、浪のよせかへるも、いろいろの玉やうに見え、まことに松の末より、浪はこゆるやうにみえて、いみしくおもしろし、それよりかみは、ゐのはなといふ坂の、えもいはぬわびしきを、のぼりぬれば、三河ノ國の高師の濱といふ、
87 おのれとり分て人につたふべきふしなき事[四〇九]
おのれは、道の事も歌の事も、あがたゐのうしの敎のおもむきによりて、たゞ古の書共を、かむかへさとれるのみこそあれ、其家の傳へごととては、うけつたへたることさらになければ、家々のひめことなどいふかぎりは、いかなる物にか、一ツだにしれることなし、されば又、人にとりわきて殊に傳ふべきふしもなし、すべてよき事は、いかにもいかにも、世にひろくせまほしく思へば、いにしへの書共を考へて、さたりえたりと思ふかぎりは、みな書にかきあらはして、露ものこしこめたることはなきぞかし、おのづからも、おのれにしたがひて、物まなばむと思はむ人あらば、たゞあらはせるふみどもを、よく見てありぬべし、そをはなちて外には、さらにをしふべきふしはなきぞとよ、
88 もろこしの老子の説まことの道に似たる所ある事[四一〇]
おのれ今まことの道のおもむきを見明らめて、ときあらはせるを、漢學(カラマナビ)のともがら、かの國の老子といふものの説(トキゴト)によれり、と思ひいふ人、これかれあり、そもそもおのが道をとく趣は、いさゝかも私のさかしらをばまじへず、神典(カミノミフミ)に見えたるまゝなること、あだし注釋どもと、くらべ見て知べし、かくてそ
の趣の、たまたまかの老子といふものの言と、にたるところどころのあるを見て、ゆくりなく、それによりていへりとは、例のかのもろこしの國をおきて外に國はなく、かの國ならでは、何事も始まらぬことと、ひたおもむきにおもひとれる、ひが心より、さは思ふなンめり、いにしへより、漢ノ國と通へることなく、たがひに聞キも及ばざりし國々にも、ほどほどにつけつゝ、有べきかぎりの事は、おのおの本よりありける中にも、殊に皇國は、萬ヅの國の本、よろづの國の宗(オヤ)とある御國なれば、萬ノ國々わたりて、正しきまことの道は、たゞ皇國にこそ傳はりたれ、他國(アダシクニ)には、傳はれることなければ、此道をしることあたはず、然るにもろこしの國に、かの老子といひしは、すぐれてかしこく、たどりふかき人にこそ有けめ、世のこちたくさかしだちたる敎ヘは、うはべこそよろしきにたれ、まことには、いとよろしからず、中々の物害(モノソコナ)ひとなることをさとりて、まことの道はかくこそあるべきものなれと、はしばしみづから考ヘ出たることの中に、かむかへあてて、たまたま此まことの道に似たるふし、合へることもあるなりけり、さるはまことの道は、もとより人のさかしらをくはへたることなく、皇神(スメカミ)の定めおき給へるまゝなる道にしあれば、そのおもむきをとかむには、かれが、さかしらをにくめる説は、おのづから似たるところ、あへるところ有べきことわり也、しかはあれども、かれがいへるは、たゞおのが智慮(サトリ)もて、考へ出たるかぎりにこそあれ、皇國に生れて、正しく此道を聞るにあらざれば、その主(ムネ)とある本のこゝろは、しることあたはず、いたくたがひて、さらに似もつかぬことなるを、かの漢學のともがら、しかたがへるところをがしらで、たまたまかたはし似たることのあるをとらへてそれによれりとしもいひなすは、いとをこ也かし、大かたよろづの事、おのづからこれにもかれにも、かよひてにたることは、かならずまじる物にて、此道も、儒のおもむきかよけるところもまじり、佛の道とも似たることはまじれゝが、おのづからかの老子とも、かたはし似たるところ過へるところは、などかまじらではあらむ、
89 道をとくことはあだし道々の意にも世の人のとりとらざるにもかゝはるまじき事[四一一]
道をとかむに、儒にまれ老にまれ佛にまれ、まれまれに心ばへのかよへるところのあるをとらへて、おのが心のひくかたにまかせて、かよはぬところをも、すべてそのすぢに引よせてときなし、あるは又他(アダシ)道と同じからんことを、いとひさけて、ことさらにけぢめを見せ、さまをかへて説(トカ)むとする、これらみないとあぢきなくしひたるわざ也、似ざらむもにたらむも、異(コト)ならむも同じからむも、とにかくに異道(アダシミチ)の意には、いさゝかもかゝはるべきわざにあらず、又かくときたらむには、世にうけひかじ、かくいひてこそ、人は信ぜめなど、世の人の心をとりて、いさゝかもときまげむことは、又いとあるまじく、心ぎたなきわざ也、すべて世ノ人のほめそしりをも、思ふべきにはあらず、たとひあだし道々とは、うらうへのたがひあり、世にも絶えて信ずる人なからむにても、ただ神の御ふみのおもむきのまゝにこそはとくべきわざなりけれ、
90 香をきくといふは俗言なる事[四一二]
香(カウ)を聞クといふは、もとからことにて、古ヘの詞にあらず、すべて物の香(カ)は、薫物(タキモノ)などをも、かぐといふぞ雅言(ミヤビコト)にて、古今集の歌などにも、花たちばなの香をかげばと見え、源氏物語の梅枝ノ巻に、たき物共のおとりまさりを、兵部卿ノ宮の論(サダ)め給ふところにも、人々の心々に合せ給へる、深さ淺さを、かぎあはせ給へるに、などこそ見えたれ、聞(キク)といへる事は、昔の書に見えたることなし、今の世の人は、そをばしらで、香(カウ)などをかぐといはむは、いやしき詞のごと心得ためるは中々のひがこと也、きくといふぞ、俗言(サトビコト)には有ける、
91 もろこしに名高き物しり人の佛法を信じたりし事[四一三]
佛の道は、もろこしの國にて、よゝに名高き儒者などの中にも、信じ尊みたるが、あまた聞とゆるによりては、まことにすてがたき物にこそ、と思ふ人あンめれど、かのもろこしにて、しか名高き物しり人どもの、佛をしんじ尊みたるやうなくは、まことの心に信じたふとみたるは、いとすくなくて、おほくはたゞもてあそびたるにこそあれ、さるはかの道の説(トケ)るやう、あやしく廣く大きにして、此世のほかを、とほく深く、さとり明らめたるさま、すべて心のおきてなど、めづらかにおかしきものなるが故に、詩作る人などは、さらにもいはず、さらぬも、これをもてあそびて、風流(ミヤビ)のたすけにぞしたンめる、又その諸宗に、高僧と聞ゆるほうしどもの中にも、實に尊み信じて、おこなひたるにあらで、世の中の人にたふとまれ、いさぎよくいみしき名をとゞめて、後の世まであふがれむために、その道のふみを深く學び、もろもろの欲をも忍び、たへがたき行ひをもして、まことしげにふるまひたるぞ、多く見えたンめる、そもそも利のため名のためには、命をさへに、をしまぬたぶひもあるわざなれば、何かは、それはたあやしむべきことにもあらずかし、
92 世の人佛の道に心のよりやすき事[四一四]
ほとけの道には、さばかりさかしだちたる、今の世の人の心も、うつりやすきは、かならず其道よろしと、思ひとれるにしもあらねど、むかしよりあまねくさかりにて、おしなべて世ノ中の人の、皆おこなふわざなるに、かたへはもよほさるゝぞ多かりける、すべてなにわざも、世にあまねく、人のみなする事には、たれもすゞろに心のよりやすきならひぞかし、
93 ゐなかにいにしへの雅言(ミヤビゴト)ののこれる事[四一五]
すべてゐなかには、いにしへの言ののこれること多し、殊にとほき國人のいふ言の中には、おもしろきことどもぞまじれる、おのれとしごろ心をつけて、遠き國人の、とぶらひきたるには、必ズその国の詞をとひきゝもし、その人のいふ言をも、心とゞめてきゝもするを、なほ國々の詞共を、あまねく聞あつめなば、いかにおもしろきことおほからん、ちかきころ、肥後ノ國人のきたるが、いふことをきけば、世に見える聞えるなどいふたぐひを、見ゆる聞ゆるなどぞいふなる、こは今の世にはたえて聞えぬ、雅(ミヤ)びたることばづかひなるを、其國にては、なべてかくいふにやととひければ、ひたぶるの賤(シヅ)山がつは皆、見ゆるきこゆるさゆるたゆる、などやうにいふを、すこしことばをもつくろふほどの者は、多くは見える聞えるとやうにいふ也、とぞ語りける、そは中々今のよの俗(イヤシ)きいひざまなるを、なべて國々の人のいふから、そをよきことと心得たるなンめり、いづれの國にても、しづ山がつのいふ言は、よこなまりながらも、おほくむかしの言をいひつたへたるを、人しげくにぎはゝしき里などは、他(コト)國人も入まじり、都の人なども、ことにふれてきかよひなどするほどに、おのづからこゝかしこの詞をきゝならひては、おのれもことえりして、なまさかしき今やうにうつりやすくて、昔ざまにとほく、中々にいやしくなんなりもてゆくめる、まことや同じひごの國の、又の人のいへる、かの國にて、ひきがへるといふ物を、たんがくといふなるは、古ヘのたにぐゝの訛(ヨコナマ)りなるべくおぼゆ、とかたりしは、もことに然なるべし、此たぐひのこと、國々になほ聞ることおほかるを、いまはふと思ひ出たることをいふ也、なほおもひいでむまゝに、又もいふべし、
玉かつま八の巻
萩 の 下 葉 八
人はこず萩の下葉もかつちりて嵐は寒し秋の山ざと、はもじを重ねたる、いにしへのうたどもを見て、ふとおかしきふしにおぼえたるまゝにわれもいかでとよみ出たる也、きこえてやあらむ、聞えずやあらむ、われは聞えたりと思ふとも、人の見たらんには、いかゞあらん、きこえずやあらむ、しらずかし、
94 ゐなかに古ヘのわざののこれる事[四一九]
詞のみにもあらず、よろづのしわざにも、かたゐなかには、いにしへざまの、みやびたることの、のこれるたぐひ多し、さるを例のなまさかしき心ある者の、立まじりては、かへりてをこがましくおぼえて、あらたむるから、いづこにも、やうやうにふるき事のうせゆくは、いとくちをしきわざ也、葬禮婚禮(ハフリワザトツギワザ)など、ことに田舎(ヰナカ)には、ふるくおもしろきことおほし、すべてかゝるたぐひの事共をも、國々のやうを、海づら山がくれの里々まで、あまねく尋ね、聞あつめて、物にもしるしおかまほしきわざなり、葬祭(ハフリマツリ)などのわざ、後ノ世の物しり人の、考え定めたるは、中々にからごゝろのさかしらのみ、多くまじりて、ふさはしからず、うるさしかし、
95 ふるき物またそのかたをいつはり作る事[四二二]
ちかきころは、いにしへをしのぶともがら、よにおほくして、何物にまれ、こだいの物といへば、もてはやしめづるから、国々より、あるはふるきやしろ、ふるき寺などに、つたはりきたる物、あるは土の中よりほりいでなど、八百年(ヤホトセ)千とせに、久しくうづもれたりし物共も、つぎつぎにあらはれ出来る類ヒおほし、さてしかふるくめづらしきものの出来れば、その物はさらにもいはず、圖(カタ)をさへにうつして、つぎつぎとほきさかひまでも、寫しつたへて、もえあそぶを、又世には、あやしく偽リする、をこのものの有て、これはその國のその社に、をさまれる物ぞ、その國のなにがしの山より、ほり出たる、なにのかたぞなど、古き物をも圖(カタ)をも、つきつぎしくおのれ造りいでて、人をまどはすたぐひも、又多きは、いといとあぢきなく、心うきわざ也、さいつころ、いにしへかひの國の酒折宮(サカオリノミヤ)にして、倭建ノ命の御歌の末をつぎたりし、火ともしの翁のかた、火揚ノ命ノ像としるしたる物を、かの酒折ノ社の、屋根の板のはざまより、近き年出たる也とて、うつしたる人の見せたる、げに上ツ代の人のしわざと見えて其さまいみしくふるめきたりければ、めづらかにおぼえて、おのれうつしおきたりしを、なほいかにぞや、うたがはしくはたおぼえしかば、かの國に、その社ちかき里に、弟子(オシヘコ)のあるが許へ、しかしかのものえたるは、いかなるにかと、とひにやりたりしもしるく、はやくいつはりにて、すなはちかのやしろの神主飯田氏にもとひしに、さらにかたもなき事也と、いひおこせたりき、又同じころ、檜垣嫗(ヒカキノオウナ)が、みづからきざみたる、ちひさき木の像(カタ)の、肥後ノ國の、わすれたり、何とかいふところより、ちかく掘出たる、うつしとて、こゝかしこに寫しつたへて、ひろまりたる、これはた、出たる本を尋ぬるに、たしかなるやうにはきこゆれど、なほ心得ぬこと有て、うたがはしくなむ、すべてかうやうのたぐひ、今はゆくりかにはうけがたきわざ也、心すべし、
96 言の然いふ本の意をしらまほしくする事[四二三]
物まなびするともがら、古言の、しかいふもとの意を、しらまほしくして、人にもまづとふこと、常也、然いふ本のこころとは、たとへば天(アメ)といふは、いかなる意ぞ、地(ツチ)といふは、いかなる意ぞ、といふたぐひ也、これも學びの一ツにて、さもあるべきことにはあれども、さしあたりて、むねとすべきわざにはあらず、大かたいにしへの言は、然いふ本の意をしらむよりは、古人の用ひたる意を、よく明らめしるべきなり、用ひたる意をだに、よくあきらめなば、然いふ本の意は、しらでもあるべき也、そもそも萬ヅの事、まづその本をよく明らめて、末をば後にすべきは、論なけれど、然のみにもあらぬわざにて、事のさまによりては、末よりまづ物して、後に本へはさかのぼるべきもあるぞかし、大かた言の本の意は、しりがたきわざにて、われ考へえたりと思ふも、あたれりやあらずや、さだめがたく、多くはあたりがたきわざ也、されば言のはのがくもんは、その本の意をしることおば、のどめおきて、かへすがへすも、いにしへひとのつかひたる意を、心をつけて、よく明らむべきわざなり、たとひ其もとの意は、よく明らめてたらむにても、いかなるところにつかひたりといふことをしらでは、何のかひもなく、おのが歌文に用ふるにも、ひがことの有也、今の世古學をするともがらなど殊に、すこしとほき言といへば、まづ然いふ本の意をしらむとのみして、用ひたる意をば、考へむともせざる故に、おのがつかふに、いみしきひがことのみ多きぞかし、すべて言は、しかいふ本の意と、用ひたる意とは、多くはひとしからぬもの也、たとへばなかなかにといふ言はもと、こなたへもかなたへもつかず、中間(ナカラ)なる意の言なれども、用ひたるいはたゞ、なまじひにといふ意、又うつりては、かへりてといふ意にも用ひたり、然たるを言の本によりて、うちまかせて、中間(ナカラ)なる意に用ひては、たがふ也、又こゝろぐるしといふ言は、今の俗言(ヨノコト)に、気毒(キノドク)なるといふ意に用ひたるを、げんのまゝに、心の苦(クルシ)きことに用ひては、たがへり、さればこれらにて、萬の言をも、なずらへ心得て、まずいにしへに用ひたるやうを、さきとして、明らめしるべし、言の本にのみよりては、中々にいにしへにたがふことおほかるべしかし、
97 今の人の歌文ひがことおほき事[四二五]
ちかきよの人のは、うたも文も、大かたはよろしと見ゆるにも、なほひがことのおほきぞかし、されどそのたがへるふしを、見しれる人はたよになければ、たゞかひなでに、こゝかしこえんなることばをつかひ、よしめきて、よみえなしかきちらしたるをば、まことによしと見て、人のもてはやし、ほめたつれば、心をやりて、したりがほすめる、いとかたはらいたく、をこがましくさへぞおもはるゝ、さるにつけては、かくいふおのが物することも、なほいかにひがことあらむと、物よくみしれらむ人のこゝろぞ、はづかしかりける、人のひがことの、よく見えわかるゝにつけては、我はよくわきまへたれば、ひがことはせずと、思ひほこれど、いにしへのことのこゝろをさとりしるすぢは、かぎりなきわざにしあれば、此外あらじとは、いとなんさだめがたきわざまりける、
98 歌もふみもよくとゝのふはかたき事[四二六]
ちかきよの人の歌ども文どもを、見あつむるに、一ふしおかしとめとまることは、ほどほどにあまたあンめれど、それはたいかにぞやおぼゆるところはまじりて、大かたきずなくとゝののひたるは、をさをさ見えず、これを思へば、後の世にして、いにしへをまねぶことは、いといとかたきわざになむ有ける、いにしへのかしこき人々のだに、これはしも、露のきずなしとおぼゆるは、多かる中にも、すくなくなんあれば、まして今の人のは、いさゝかなるきずをさへに、いひたてむは、あながちなるにやあらむ、されど同じくは、ひとのいさゝかもなんずべきふしまぜぬさまにこそはあらまほしけれ、よきほどにて、心をやるをば、もろこしのいにしへのひとも、よからぬことにいひおきけるをや、
99 こうさく くわいどく 聞書[四二七]
いづれの道のまなびにも、講釋とて、古き書のこゝろをとききかするを、きくことつね也、中昔には、これを談義となんいひけるを、今はだんぎとは、法師のおろかなるもの共あつめて、佛の道をいひきかするをのみいひて、こうさくといふは、さまことなり、さて此こうさくといふわざは、師のいふことのみたのみて、己が心もて、考ふることなければ、物まなびのために、やくなしとて、今やうの儒者(ズサ)などは、よろしからぬわざとして、會讀といふことをぞすなる、そはこうさくとはやうかはりて、おのおのみづからかむかへて、思ひえたるさまをも、いひこゝろみ、心得がたきふしは聞えたれど、それさしもえあらず、よの中に此わざするを見るに、大かたはじめのほどこそ、こゝかしこかへさひ、あげつらひなどさるべきさまに見ゆれ、度かさなれば、おのづからおこたりつゝ、一ひらにても、多くよみもてゆかむとするほどに、いかにぞやおぼゆるふしぶしをも、おほくなほざりに過すならひにて、おほかたひとりゐてよむにも、かはることなければ、殊に集ひたるかひもなき中に、うひまなびのともがらなどは、いさゝかもみづから考へうるちからはなきに、これもかれも聞えぬことがちなるを、ことごとにとひ出むことつゝましくて、聞えぬながらに、さてすぐしやるめれば、さるともがらなどのためには、猶講釋ぞまさりては有ける、されどこうさくも、たゞ師のいふことをのみ頼みて、己レちからいれむとも思はず、聞クことをのみむねとせむは、いふかひなくくちおしきわざ也、まず下見(シタミ)といふことをよくして、はじめより、力のかぎりは、みづからとかく思ひめぐらし、きこえがたきところどころは、殊に心をいれて、かへさひよみおけば、きく時に、心のとまる故に、さとることも、こよなくして、わすれぬもの也、さて聞て、家にかへりたらむにも、やがてかへり見といふことをして、きゝたりしおもむきを、思ひ出て味ふべし、また聞書といひて、きくきくその趣をかきしるすわざ有リ、そは中にわすれもしぬべきふしなどを、をりをりはいさゝかづゝしるしおかむは、さも有べきわざなるを、はじめより師のいふまゝに、一言ももらさじと、筆はなたず、ことごとにかきつゞくるかし、そもそもこうさくは、よく心をしずめて、ことのこゝろを、こまやかにきゝうべきわざなるに、此きゝがきすとては、きくかたよりも、おくれじとかく方に、心はいそがれて、あわたゝしきに、殊によくきくべきふしも、かいまぎれて、きゝもらい、あるはあらぬすぢに、きゝひがめもするぞかし、然るにこれをしも、いみしきわざに思ひて、いかでわれこまかにしるしとらむと、たゞこれのみ心をいれて、つとむるほどに、もはら聞書のためのこうさくになるたぐひもおほかるは、いといとあぢきなきならひになん有ける、
100 枕詞[四三二]
天又月日などいはむとて、まづひさかたのといひ、山といはむとて、まづあしひきの、といふたぐひの詞を、よに枕詞といふ、此名、ふるくは聞も及ばず、中昔の末よりいふことなめり、是を枕としもいふは、かしらにおく故と、たれも思ふめれど、さにはあらず、枕はかしらにおくものにはあらず、かしらをさゝゆるものにこそあれ、さるはかしらのみにもあらず、すべて物のうきて、間(アヒダ)のあきたる所を、ささゆる物を、何にもまくらとはいへば、名所を歌枕といふも、一句言葉のたらで、明(アキ)たるところにおくよしの名と聞ゆれば、枕詞といふも、そのでうにてぞ、いひそめけんかし、梅の花それとも見えずひさかたの云々、しのぶれど戀しき時はあしひきの云々などのごとし、そもそもこれらは、一つのさまにこそあれ、なべて然るには荒ザルを、後の世人の心にて、さる一かたにつきてぞ、名づけたりけむ、なべてはかしらにおく詞なれば、吾師の、冠詞(カウブリコトバ)といはれたるぞ、ことわりかなひては有ける、しかはあれども、今はあまねく、いひならひたれば、ことわりはいかにまれ、さてもありぬべくこそ、
101 もろこしの國に丙吉といひし人の事[四四一]
わらはべの蒙求といふからぶみよむをきけば、かの國の漢といひし代に、丙吉といふ大臣有けり、春のころ、物へゆく道に、牛の人にひかれてくるが、舌を出して、いみしく苦しげに、あへぐを見て、いま夏にもあらざるに、此うしいたく暑ければこそ、かくは喘(アヘ)ぐなれ、すべて寒さぬるさの、時にかなはぬは、わがうれふべきこと也、といひければ、みな人げにとかしこまりて、よにいみしきことに思ひあへりとぞ、今おもふに、こはいとをこがましきこと也、暑きころならずとて、ことによりては、などかしかあへぐこともなからん、又さばかり陰陽のとゝのひを、心にかけたらむには、つねにみづからこゝろむべきわざなるに、たまたま道かひに、此牛のさまを見て、ゆくりなくさとりたるは、いかにぞや、もし此うしのあへぐを見ずは、しらでやむべきにや、さればこは、まことにさ思ひていへるにはあらで、人にいみしきことに思はせむとての、つくりことにこそ有けれ、もしまことにしか心得たらんには、いふかひなきしれものなるを、よにいみしきことにしるしつたへたるも、いとをこなり、又もとより陰陽をとゝのふなどいふこと、あるべくもあらず、すべて世の中の事は、時々の天地のあるやうも何も、みな神の御しわざにて、時の氣(ケ)のかなひかなはぬなど、さらに人のしるべきわざにはあらぬを、かくことごとしげにいひなすは、すべてかの國人のならひにて、いといとこちたく、うるさきわざ也かし、
102 周公旦がくひたる飯を吐出して賢人に逢たりといへる事[四四二]
又きけば、周公旦といひける聖人の、子をいましめたる詞に、我一タビ沐スルニ三タビ髪ヲ握リ、一タビ飯(クフ)ニ三タビ哺ヲ吐テ、起テ以テ士ヲ待テ、猶天下ノ之賢人ヲ失ハムコトヲ恐ルといへり、もしまことに然したりけむには、これもよの人にいみしきことに思はせむための、はかりこと也、いかに賢人を思へばとて、口に入たらむ飯を、呑(ノミ)いるゝまを、またぬやうやは有べき、出迎へむ道のほどにても、のみいれむことは、いとやすかるべきを、ことさらに吐出して、人に見せたるは、何事ぞや、すべてかの國には、かくさまに、甚しくけやけきふるまひをしたるたぐひの、何事につけても多きは、みな名をむさぼりたる物にして、例のいとうるさきならひ也、
103 藤谷ノ成章といひし人の事[四四三]
ちかきころ京に、藤谷ノ專右衛門成章といふ人有ける、それがつくれる、かざし抄あゆひ抄六運圖略などいふふみどもを見て、おどろかれぬ、それよりさきにも、さる人有とは、ほの聞たりしかど、例の今やうの、かいなでの歌よみならんと、みゝもたゝざりしを、此ふみどもを見てぞ、しれる人に、あるやうとひしかば、此ちかきほど、みまかりぬと聞て、又おどろかれぬ、そもそも此ごろのうたよみどもは、すこし人にもまさりて、もちひらるゝばかりにもなれば、おのれひとり此道えたるかほして、心やりたかぶるめれど、よめる歌かける文いへる説などをきけば、ひがことのみ多く、みないとまだしきものにて、これはとおぼゆるは、いとかたく、ましてぬけ出たるは、たえてなきよにこの藤谷は、さるたぐひにあらず、又ふるきすぢをとらへてみだりに高きことのみいふともがらはた、よにおほかるを、さるたぐひにもあらず、萬葉よりあなたのことは、いかゞあらむ、しらず、六運の辨にいへるおもむきを見るに、古今集よりこなたざまの歌のやうを、よく見しれることは、大かたちかき世に、ならぶ人あらじとぞおぼゆる、北邉集といひて歌の集もあるを、見たるに、よめるうたは、さしもすぐれたりとはなけれど、いまのよの歌よみのやうなる、ひがことは、をさをさ見えずなん有ける、さもあたらしき人の、はやくもうせぬることよ、その子の專右衛門といふも、まだとしわかけれど、心いれて、わざと此道ものすときくは、ちゝの氣はひもそはりたらむと、たのもしくおぼゆかし、それが物したる書どもも、これかれと、見えしらがふめり、
104 ある人のいへること[四八三]
ある人の、古學を、儒の古文辭家の言にさそはれていできたる物なりといへるは、ひがこと也、わが古學は、契沖はやくそのはしをひらけり、かの儒の古學といふことの始めなる、伊藤氏など、契沖と大かた同じころといふうちに、契沖はいさゝか先(サキ)だち、かれはおくれたり、荻生氏は、又おくれたり、いかでかかれにならへることあらむ、
105 らくがき らくしゅ[五一六]
いはまほしき事の、あらはにいひがたきを、たがしわざとも、しらるまじく書て、おとしおくを、落し書(ブミ)と今もいへり、ふるくより有しことにて、そを又門屏などやうのところに、おしもし、たゞにかきもしけむ、かくてそのおとしぶみを、もじごゑに、らくしよともいひならひしを、後に其もじにつきて、らくがきともいひて、又後には、たゞなにとなく、たはぶれに、さるところに物かくを、らくがきとはいふ也、又たはぶれのさとび歌に、らくしゅといふ一くさ有リ、これもかのおとしぶみよりうつりて、もとは落書(ラクショ)なりけんを、訛りてらくしゅとはいふなンめり、愚問賢注に、童謡落書の歌とある、これ也、
萩 の 下 葉 八
人はこず萩の下葉もかつちりて嵐は寒し秋の山ざと、はもじを重ねたる、いにしへのうたどもを見て、ふとおかしきふしにおぼえたるまゝにわれもいかでとよみ出たる也、きこえてやあらむ、聞えずやあらむ、われは聞えたりと思ふとも、人の見たらんには、いかゞあらん、きこえずやあらむ、しらずかし、
94 ゐなかに古ヘのわざののこれる事[四一九]
詞のみにもあらず、よろづのしわざにも、かたゐなかには、いにしへざまの、みやびたることの、のこれるたぐひ多し、さるを例のなまさかしき心ある者の、立まじりては、かへりてをこがましくおぼえて、あらたむるから、いづこにも、やうやうにふるき事のうせゆくは、いとくちをしきわざ也、葬禮婚禮(ハフリワザトツギワザ)など、ことに田舎(ヰナカ)には、ふるくおもしろきことおほし、すべてかゝるたぐひの事共をも、國々のやうを、海づら山がくれの里々まで、あまねく尋ね、聞あつめて、物にもしるしおかまほしきわざなり、葬祭(ハフリマツリ)などのわざ、後ノ世の物しり人の、考え定めたるは、中々にからごゝろのさかしらのみ、多くまじりて、ふさはしからず、うるさしかし、
95 ふるき物またそのかたをいつはり作る事[四二二]
ちかきころは、いにしへをしのぶともがら、よにおほくして、何物にまれ、こだいの物といへば、もてはやしめづるから、国々より、あるはふるきやしろ、ふるき寺などに、つたはりきたる物、あるは土の中よりほりいでなど、八百年(ヤホトセ)千とせに、久しくうづもれたりし物共も、つぎつぎにあらはれ出来る類ヒおほし、さてしかふるくめづらしきものの出来れば、その物はさらにもいはず、圖(カタ)をさへにうつして、つぎつぎとほきさかひまでも、寫しつたへて、もえあそぶを、又世には、あやしく偽リする、をこのものの有て、これはその國のその社に、をさまれる物ぞ、その國のなにがしの山より、ほり出たる、なにのかたぞなど、古き物をも圖(カタ)をも、つきつぎしくおのれ造りいでて、人をまどはすたぐひも、又多きは、いといとあぢきなく、心うきわざ也、さいつころ、いにしへかひの國の酒折宮(サカオリノミヤ)にして、倭建ノ命の御歌の末をつぎたりし、火ともしの翁のかた、火揚ノ命ノ像としるしたる物を、かの酒折ノ社の、屋根の板のはざまより、近き年出たる也とて、うつしたる人の見せたる、げに上ツ代の人のしわざと見えて其さまいみしくふるめきたりければ、めづらかにおぼえて、おのれうつしおきたりしを、なほいかにぞや、うたがはしくはたおぼえしかば、かの國に、その社ちかき里に、弟子(オシヘコ)のあるが許へ、しかしかのものえたるは、いかなるにかと、とひにやりたりしもしるく、はやくいつはりにて、すなはちかのやしろの神主飯田氏にもとひしに、さらにかたもなき事也と、いひおこせたりき、又同じころ、檜垣嫗(ヒカキノオウナ)が、みづからきざみたる、ちひさき木の像(カタ)の、肥後ノ國の、わすれたり、何とかいふところより、ちかく掘出たる、うつしとて、こゝかしこに寫しつたへて、ひろまりたる、これはた、出たる本を尋ぬるに、たしかなるやうにはきこゆれど、なほ心得ぬこと有て、うたがはしくなむ、すべてかうやうのたぐひ、今はゆくりかにはうけがたきわざ也、心すべし、
96 言の然いふ本の意をしらまほしくする事[四二三]
物まなびするともがら、古言の、しかいふもとの意を、しらまほしくして、人にもまづとふこと、常也、然いふ本のこころとは、たとへば天(アメ)といふは、いかなる意ぞ、地(ツチ)といふは、いかなる意ぞ、といふたぐひ也、これも學びの一ツにて、さもあるべきことにはあれども、さしあたりて、むねとすべきわざにはあらず、大かたいにしへの言は、然いふ本の意をしらむよりは、古人の用ひたる意を、よく明らめしるべきなり、用ひたる意をだに、よくあきらめなば、然いふ本の意は、しらでもあるべき也、そもそも萬ヅの事、まづその本をよく明らめて、末をば後にすべきは、論なけれど、然のみにもあらぬわざにて、事のさまによりては、末よりまづ物して、後に本へはさかのぼるべきもあるぞかし、大かた言の本の意は、しりがたきわざにて、われ考へえたりと思ふも、あたれりやあらずや、さだめがたく、多くはあたりがたきわざ也、されば言のはのがくもんは、その本の意をしることおば、のどめおきて、かへすがへすも、いにしへひとのつかひたる意を、心をつけて、よく明らむべきわざなり、たとひ其もとの意は、よく明らめてたらむにても、いかなるところにつかひたりといふことをしらでは、何のかひもなく、おのが歌文に用ふるにも、ひがことの有也、今の世古學をするともがらなど殊に、すこしとほき言といへば、まづ然いふ本の意をしらむとのみして、用ひたる意をば、考へむともせざる故に、おのがつかふに、いみしきひがことのみ多きぞかし、すべて言は、しかいふ本の意と、用ひたる意とは、多くはひとしからぬもの也、たとへばなかなかにといふ言はもと、こなたへもかなたへもつかず、中間(ナカラ)なる意の言なれども、用ひたるいはたゞ、なまじひにといふ意、又うつりては、かへりてといふ意にも用ひたり、然たるを言の本によりて、うちまかせて、中間(ナカラ)なる意に用ひては、たがふ也、又こゝろぐるしといふ言は、今の俗言(ヨノコト)に、気毒(キノドク)なるといふ意に用ひたるを、げんのまゝに、心の苦(クルシ)きことに用ひては、たがへり、さればこれらにて、萬の言をも、なずらへ心得て、まずいにしへに用ひたるやうを、さきとして、明らめしるべし、言の本にのみよりては、中々にいにしへにたがふことおほかるべしかし、
97 今の人の歌文ひがことおほき事[四二五]
ちかきよの人のは、うたも文も、大かたはよろしと見ゆるにも、なほひがことのおほきぞかし、されどそのたがへるふしを、見しれる人はたよになければ、たゞかひなでに、こゝかしこえんなることばをつかひ、よしめきて、よみえなしかきちらしたるをば、まことによしと見て、人のもてはやし、ほめたつれば、心をやりて、したりがほすめる、いとかたはらいたく、をこがましくさへぞおもはるゝ、さるにつけては、かくいふおのが物することも、なほいかにひがことあらむと、物よくみしれらむ人のこゝろぞ、はづかしかりける、人のひがことの、よく見えわかるゝにつけては、我はよくわきまへたれば、ひがことはせずと、思ひほこれど、いにしへのことのこゝろをさとりしるすぢは、かぎりなきわざにしあれば、此外あらじとは、いとなんさだめがたきわざまりける、
98 歌もふみもよくとゝのふはかたき事[四二六]
ちかきよの人の歌ども文どもを、見あつむるに、一ふしおかしとめとまることは、ほどほどにあまたあンめれど、それはたいかにぞやおぼゆるところはまじりて、大かたきずなくとゝののひたるは、をさをさ見えず、これを思へば、後の世にして、いにしへをまねぶことは、いといとかたきわざになむ有ける、いにしへのかしこき人々のだに、これはしも、露のきずなしとおぼゆるは、多かる中にも、すくなくなんあれば、まして今の人のは、いさゝかなるきずをさへに、いひたてむは、あながちなるにやあらむ、されど同じくは、ひとのいさゝかもなんずべきふしまぜぬさまにこそはあらまほしけれ、よきほどにて、心をやるをば、もろこしのいにしへのひとも、よからぬことにいひおきけるをや、
99 こうさく くわいどく 聞書[四二七]
いづれの道のまなびにも、講釋とて、古き書のこゝろをとききかするを、きくことつね也、中昔には、これを談義となんいひけるを、今はだんぎとは、法師のおろかなるもの共あつめて、佛の道をいひきかするをのみいひて、こうさくといふは、さまことなり、さて此こうさくといふわざは、師のいふことのみたのみて、己が心もて、考ふることなければ、物まなびのために、やくなしとて、今やうの儒者(ズサ)などは、よろしからぬわざとして、會讀といふことをぞすなる、そはこうさくとはやうかはりて、おのおのみづからかむかへて、思ひえたるさまをも、いひこゝろみ、心得がたきふしは聞えたれど、それさしもえあらず、よの中に此わざするを見るに、大かたはじめのほどこそ、こゝかしこかへさひ、あげつらひなどさるべきさまに見ゆれ、度かさなれば、おのづからおこたりつゝ、一ひらにても、多くよみもてゆかむとするほどに、いかにぞやおぼゆるふしぶしをも、おほくなほざりに過すならひにて、おほかたひとりゐてよむにも、かはることなければ、殊に集ひたるかひもなき中に、うひまなびのともがらなどは、いさゝかもみづから考へうるちからはなきに、これもかれも聞えぬことがちなるを、ことごとにとひ出むことつゝましくて、聞えぬながらに、さてすぐしやるめれば、さるともがらなどのためには、猶講釋ぞまさりては有ける、されどこうさくも、たゞ師のいふことをのみ頼みて、己レちからいれむとも思はず、聞クことをのみむねとせむは、いふかひなくくちおしきわざ也、まず下見(シタミ)といふことをよくして、はじめより、力のかぎりは、みづからとかく思ひめぐらし、きこえがたきところどころは、殊に心をいれて、かへさひよみおけば、きく時に、心のとまる故に、さとることも、こよなくして、わすれぬもの也、さて聞て、家にかへりたらむにも、やがてかへり見といふことをして、きゝたりしおもむきを、思ひ出て味ふべし、また聞書といひて、きくきくその趣をかきしるすわざ有リ、そは中にわすれもしぬべきふしなどを、をりをりはいさゝかづゝしるしおかむは、さも有べきわざなるを、はじめより師のいふまゝに、一言ももらさじと、筆はなたず、ことごとにかきつゞくるかし、そもそもこうさくは、よく心をしずめて、ことのこゝろを、こまやかにきゝうべきわざなるに、此きゝがきすとては、きくかたよりも、おくれじとかく方に、心はいそがれて、あわたゝしきに、殊によくきくべきふしも、かいまぎれて、きゝもらい、あるはあらぬすぢに、きゝひがめもするぞかし、然るにこれをしも、いみしきわざに思ひて、いかでわれこまかにしるしとらむと、たゞこれのみ心をいれて、つとむるほどに、もはら聞書のためのこうさくになるたぐひもおほかるは、いといとあぢきなきならひになん有ける、
100 枕詞[四三二]
天又月日などいはむとて、まづひさかたのといひ、山といはむとて、まづあしひきの、といふたぐひの詞を、よに枕詞といふ、此名、ふるくは聞も及ばず、中昔の末よりいふことなめり、是を枕としもいふは、かしらにおく故と、たれも思ふめれど、さにはあらず、枕はかしらにおくものにはあらず、かしらをさゝゆるものにこそあれ、さるはかしらのみにもあらず、すべて物のうきて、間(アヒダ)のあきたる所を、ささゆる物を、何にもまくらとはいへば、名所を歌枕といふも、一句言葉のたらで、明(アキ)たるところにおくよしの名と聞ゆれば、枕詞といふも、そのでうにてぞ、いひそめけんかし、梅の花それとも見えずひさかたの云々、しのぶれど戀しき時はあしひきの云々などのごとし、そもそもこれらは、一つのさまにこそあれ、なべて然るには荒ザルを、後の世人の心にて、さる一かたにつきてぞ、名づけたりけむ、なべてはかしらにおく詞なれば、吾師の、冠詞(カウブリコトバ)といはれたるぞ、ことわりかなひては有ける、しかはあれども、今はあまねく、いひならひたれば、ことわりはいかにまれ、さてもありぬべくこそ、
101 もろこしの國に丙吉といひし人の事[四四一]
わらはべの蒙求といふからぶみよむをきけば、かの國の漢といひし代に、丙吉といふ大臣有けり、春のころ、物へゆく道に、牛の人にひかれてくるが、舌を出して、いみしく苦しげに、あへぐを見て、いま夏にもあらざるに、此うしいたく暑ければこそ、かくは喘(アヘ)ぐなれ、すべて寒さぬるさの、時にかなはぬは、わがうれふべきこと也、といひければ、みな人げにとかしこまりて、よにいみしきことに思ひあへりとぞ、今おもふに、こはいとをこがましきこと也、暑きころならずとて、ことによりては、などかしかあへぐこともなからん、又さばかり陰陽のとゝのひを、心にかけたらむには、つねにみづからこゝろむべきわざなるに、たまたま道かひに、此牛のさまを見て、ゆくりなくさとりたるは、いかにぞや、もし此うしのあへぐを見ずは、しらでやむべきにや、さればこは、まことにさ思ひていへるにはあらで、人にいみしきことに思はせむとての、つくりことにこそ有けれ、もしまことにしか心得たらんには、いふかひなきしれものなるを、よにいみしきことにしるしつたへたるも、いとをこなり、又もとより陰陽をとゝのふなどいふこと、あるべくもあらず、すべて世の中の事は、時々の天地のあるやうも何も、みな神の御しわざにて、時の氣(ケ)のかなひかなはぬなど、さらに人のしるべきわざにはあらぬを、かくことごとしげにいひなすは、すべてかの國人のならひにて、いといとこちたく、うるさきわざ也かし、
102 周公旦がくひたる飯を吐出して賢人に逢たりといへる事[四四二]
又きけば、周公旦といひける聖人の、子をいましめたる詞に、我一タビ沐スルニ三タビ髪ヲ握リ、一タビ飯(クフ)ニ三タビ哺ヲ吐テ、起テ以テ士ヲ待テ、猶天下ノ之賢人ヲ失ハムコトヲ恐ルといへり、もしまことに然したりけむには、これもよの人にいみしきことに思はせむための、はかりこと也、いかに賢人を思へばとて、口に入たらむ飯を、呑(ノミ)いるゝまを、またぬやうやは有べき、出迎へむ道のほどにても、のみいれむことは、いとやすかるべきを、ことさらに吐出して、人に見せたるは、何事ぞや、すべてかの國には、かくさまに、甚しくけやけきふるまひをしたるたぐひの、何事につけても多きは、みな名をむさぼりたる物にして、例のいとうるさきならひ也、
103 藤谷ノ成章といひし人の事[四四三]
ちかきころ京に、藤谷ノ專右衛門成章といふ人有ける、それがつくれる、かざし抄あゆひ抄六運圖略などいふふみどもを見て、おどろかれぬ、それよりさきにも、さる人有とは、ほの聞たりしかど、例の今やうの、かいなでの歌よみならんと、みゝもたゝざりしを、此ふみどもを見てぞ、しれる人に、あるやうとひしかば、此ちかきほど、みまかりぬと聞て、又おどろかれぬ、そもそも此ごろのうたよみどもは、すこし人にもまさりて、もちひらるゝばかりにもなれば、おのれひとり此道えたるかほして、心やりたかぶるめれど、よめる歌かける文いへる説などをきけば、ひがことのみ多く、みないとまだしきものにて、これはとおぼゆるは、いとかたく、ましてぬけ出たるは、たえてなきよにこの藤谷は、さるたぐひにあらず、又ふるきすぢをとらへてみだりに高きことのみいふともがらはた、よにおほかるを、さるたぐひにもあらず、萬葉よりあなたのことは、いかゞあらむ、しらず、六運の辨にいへるおもむきを見るに、古今集よりこなたざまの歌のやうを、よく見しれることは、大かたちかき世に、ならぶ人あらじとぞおぼゆる、北邉集といひて歌の集もあるを、見たるに、よめるうたは、さしもすぐれたりとはなけれど、いまのよの歌よみのやうなる、ひがことは、をさをさ見えずなん有ける、さもあたらしき人の、はやくもうせぬることよ、その子の專右衛門といふも、まだとしわかけれど、心いれて、わざと此道ものすときくは、ちゝの氣はひもそはりたらむと、たのもしくおぼゆかし、それが物したる書どもも、これかれと、見えしらがふめり、
104 ある人のいへること[四八三]
ある人の、古學を、儒の古文辭家の言にさそはれていできたる物なりといへるは、ひがこと也、わが古學は、契沖はやくそのはしをひらけり、かの儒の古學といふことの始めなる、伊藤氏など、契沖と大かた同じころといふうちに、契沖はいさゝか先(サキ)だち、かれはおくれたり、荻生氏は、又おくれたり、いかでかかれにならへることあらむ、
105 らくがき らくしゅ[五一六]
いはまほしき事の、あらはにいひがたきを、たがしわざとも、しらるまじく書て、おとしおくを、落し書(ブミ)と今もいへり、ふるくより有しことにて、そを又門屏などやうのところに、おしもし、たゞにかきもしけむ、かくてそのおとしぶみを、もじごゑに、らくしよともいひならひしを、後に其もじにつきて、らくがきともいひて、又後には、たゞなにとなく、たはぶれに、さるところに物かくを、らくがきとはいふ也、又たはぶれのさとび歌に、らくしゅといふ一くさ有リ、これもかのおとしぶみよりうつりて、もとは落書(ラクショ)なりけんを、訛りてらくしゅとはいふなンめり、愚問賢注に、童謡落書の歌とある、これ也、
玉勝間九の巻
花 の 雪 九
やよひのころ、あるところにて、さくらの花の、木ノ本にちりしけるを見て、一とせよし野にものせし時も、おほくはかうやうにこそ、散ぬるほどなりしかと、ふと思ひ出られけるまゝに、
ふみ分し昔恋しきみよしのの山つくらばや花の白雪、かきあつめて、例の巻の名としつ、雪の山つくられし事は、物に見えたり、
106 道のひめこと[五六九]
いづれの道にも、その大事とて、世にひろくもらさず、ひめかくす事おほし、まことに其道大事ならば、殊に世に広くこそせまほしけれ、あまりに重くして、たやしく伝へざれば、せばくなりて、絶やすきわざぞかし、そもみだりにひろくしぬれば、其道かろがろしくなることといふなるも、一わたりは、ことわりあるやうなれども、たとひかるがるしくなるかたはありとても、なほ世にひろまるこしはよけれ、広ければ、おのづから重きかたはあるぞかし、いかにおもおもしければとても、せばくかすかならむは、よきことにあらず、まして絶もせむには、何のいふかひかあらむ、されどちかき世に、道々に秘伝口決などいふなるすぢ、おほくは、道をおもくすといふは、たゞ名のみにて、まことは、ひとにしらさずて、おのれひとりの物にして、世にほこらむとする、わたくしのきたなき心、又それよりもまさりて、きたなき心なるぞおほかる、さるたぐひも、もろもろのはかなき技芸の道などは、とてもかくてもありぬべけれど、うるはしくはかばかしき道には、さること有べくもあらず、
107 契沖が歌をとけるやう[五七一]
歌の注は、むつかしきわざにて、いさゝかのいひざまによりて、意もいきほひも、いたくたがふこと多きを、契沖は、歌をとくこと、上手にて、よくもあしくも、いへることのすぢうよくとほりて、聞えやすし、しかるにをりをり、くだくだしき解(トキ)ざまのまじれるは、いかにぞや、たとへば遍昭僧正の、天津風の歌の注に、もとより風雲ともに、うきたる物なれば、久しく吹とづべきものにはあらざるによりて、しばしといへる詞、よくかなへり、といへるたぐひ也、すべてかのころなどの歌は、よみぬしの心には、さることまでを思へるものにはあらず、然るをかくさまに、こまかに意をそへてとどけるたぐひは、思ふに、佛ぶみの注釈どもを、見なれたるくせなめり、すべてほとけぶみの注尺といふ物は、深くせむとて、えみいはずくだくだしき意をくはへて、こちたくときなせる物ぞかし、
108 つねに異なる字音のことば[五七五]
字音(モジゴエ)の言の、みかしよりいひなれたるに、常の音とことなる多し、周禮をしゅうらい、檀弓をだんぐう、淮南子をゑなんじ、玉篇をごくへん、鄭玄をぢやうげん、孔頴達をくえうだつといふたぐひは、呉音なれば、こともなし、越王句践を、ゑつとうこうせんとよむは、たゞ引つめていふ也、子昂をすかうといふは、扇子銀子鑵子などのたぐひにて、これもと唐音(カラコエ)なるべし、子ノ字今の唐音にては、つうと呼(イフ)なれど、すといふは、宋元などのころの音にぞありけむ、又天子の物へ行幸の時、さきざきにて、おはします所を、行在所といふを、あんざいしょとよむは、此とき別(コト)にあんの音になるにはあらず、行灯行脚(アンドンアンギャ)などといふあんと同じことにて、これもむかしの唐音なるべし、今の唐音は、平声の時も、去声の時も、いんといへり、又もろこしの國の、明の代の明を、みんと呼(イフ)も、唐音也、今の代の清を、しんといふは、唐音の訛也、清ノ字の唐音は、ついんと呼(イヘ)り、又明の代のとぢめに、鄭成功といひし人を、國姓爺と称ふ、この姓ノ字をせんといふも、唐音にすいんといふを訛れる也、さてこの國姓爺といふ称(ナ)は、國姓とは、当時(ソノトキ)の王の姓をいひて、此人、明の姓を賜はれるよし也、爺は、某(ナニ)老某(ナニ)丈などいふ、老丈のたぐひにて、たふとめる称(ナ)也、ちかき代かの國にて、ことによくつかふもじ也、こは筆のついでにいへり、
109 八百萬ノ神といふを書紀に八十萬ノ神と記されたる事[五八五]
もろもろの神たちを、すべていふには、古事記をはじめて、そのほかの古き書どもにもみな、八百萬(ヤホヨロヅノ)ノ神といへるぞつねなるに、たゞ書紀にのみは、いづこにもいづこにも、八十萬(ヤソヨロヅノ)ノ神とのみありて、八百萬神とあるところは見えず、こはいかさまにも、撰者の心あることと見えたり、神の御名に、日高(ヒタカ)と申すをも、彼ノ紀には、みなかへて、彦としるされたるは、当代(ソノコロ)の天皇の御名をさけられたりとおぼしきを、此八十萬ノ神は、いかなるよしにかあらむ、いまだ思ひえず、さてかようのたぐひも、神の御名の文字なども、何も、後の世の書どもは、おほかた書紀にのみよれるをたまたま此称は書紀によらず、今の世にいたるまでも、八十萬ノ神とのみいひならへるは、めづらし、
110 人ノ名を文字音(モジコエ)にいふ事[五八六]
人の名を、世に文字の音にて呼ならへる事、ふるくは、時平(ジヘイ)大臣、多田ノ満仲(マンヂウ)、源ノ頼光(ライクワウ)、安倍ノ清明(セイメイ)などのごときあり、やゝ後には、俊成卿、定家卿、家隆卿、鴨ノ長明など、もはらもじこゑにのみいひならへり、琵琶ほうしの、平家物語をかたるをきくに、つねにはさもあらぬ、もろもろの人の名どもも、おほくはもじこゑに物すなるは、当時(ソノカミ)ことに、よの中にさかりなりしことなめり、
111 神をなほざりに思ひ奉る世のならひをかなしむ事[五九八]
世の人の、神をなほざりに思ひ奉るは、かへすかへすこゝろうきわざなり、さるはほどほどに、たふとみ奉らぬにしもあらざンめれど、たゞよのならひの、人なみ人なみのかいなでのたふとみのみこそあれ、まことに心にしめて尊みたてまつるべきことを、思ひわきまへず、たゞおろそかにぞ思干たンめる、目にこそ見えね、此天地萬の物の、出来はじめしも、又むかし今の、世ノ中の大き小きもろもろの事も、人の身のうへ、くひ物き物居どころなにくれ、もろもろのことも、ことごとく神の御めぐみにかゝらざることはなきを、さるゆゑよしをばわすれはてて、なべての人、ただまがつひのまがことにのみまじこり、心をかたむけて、よろづにさかしだつひとはた、からぶみごゝろを、心とはして、まれまれに神代のおのが身々のうへにかゝれる、本なることをおもひたどらず、よろづよりもかなしきは、神の社神事(カムワザ)のおとろへなるを、かばかりめでたき御代にしも、もろもろのふるき神の御社どもの、いみしくおとろへませるを、なほしたて奉らんの心ざしある人はうるさしとも思ふらめど、此事のうれしさの、あけくれ心にわすらるゝ間もなくおぼゆるから、筆だにとれば、かきいでまほしくてなん、
治まれる御代のしるしを千木たかく
神のやしろに見るよしもがな
花 の 雪 九
やよひのころ、あるところにて、さくらの花の、木ノ本にちりしけるを見て、一とせよし野にものせし時も、おほくはかうやうにこそ、散ぬるほどなりしかと、ふと思ひ出られけるまゝに、
ふみ分し昔恋しきみよしのの山つくらばや花の白雪、かきあつめて、例の巻の名としつ、雪の山つくられし事は、物に見えたり、
106 道のひめこと[五六九]
いづれの道にも、その大事とて、世にひろくもらさず、ひめかくす事おほし、まことに其道大事ならば、殊に世に広くこそせまほしけれ、あまりに重くして、たやしく伝へざれば、せばくなりて、絶やすきわざぞかし、そもみだりにひろくしぬれば、其道かろがろしくなることといふなるも、一わたりは、ことわりあるやうなれども、たとひかるがるしくなるかたはありとても、なほ世にひろまるこしはよけれ、広ければ、おのづから重きかたはあるぞかし、いかにおもおもしければとても、せばくかすかならむは、よきことにあらず、まして絶もせむには、何のいふかひかあらむ、されどちかき世に、道々に秘伝口決などいふなるすぢ、おほくは、道をおもくすといふは、たゞ名のみにて、まことは、ひとにしらさずて、おのれひとりの物にして、世にほこらむとする、わたくしのきたなき心、又それよりもまさりて、きたなき心なるぞおほかる、さるたぐひも、もろもろのはかなき技芸の道などは、とてもかくてもありぬべけれど、うるはしくはかばかしき道には、さること有べくもあらず、
107 契沖が歌をとけるやう[五七一]
歌の注は、むつかしきわざにて、いさゝかのいひざまによりて、意もいきほひも、いたくたがふこと多きを、契沖は、歌をとくこと、上手にて、よくもあしくも、いへることのすぢうよくとほりて、聞えやすし、しかるにをりをり、くだくだしき解(トキ)ざまのまじれるは、いかにぞや、たとへば遍昭僧正の、天津風の歌の注に、もとより風雲ともに、うきたる物なれば、久しく吹とづべきものにはあらざるによりて、しばしといへる詞、よくかなへり、といへるたぐひ也、すべてかのころなどの歌は、よみぬしの心には、さることまでを思へるものにはあらず、然るをかくさまに、こまかに意をそへてとどけるたぐひは、思ふに、佛ぶみの注釈どもを、見なれたるくせなめり、すべてほとけぶみの注尺といふ物は、深くせむとて、えみいはずくだくだしき意をくはへて、こちたくときなせる物ぞかし、
108 つねに異なる字音のことば[五七五]
字音(モジゴエ)の言の、みかしよりいひなれたるに、常の音とことなる多し、周禮をしゅうらい、檀弓をだんぐう、淮南子をゑなんじ、玉篇をごくへん、鄭玄をぢやうげん、孔頴達をくえうだつといふたぐひは、呉音なれば、こともなし、越王句践を、ゑつとうこうせんとよむは、たゞ引つめていふ也、子昂をすかうといふは、扇子銀子鑵子などのたぐひにて、これもと唐音(カラコエ)なるべし、子ノ字今の唐音にては、つうと呼(イフ)なれど、すといふは、宋元などのころの音にぞありけむ、又天子の物へ行幸の時、さきざきにて、おはします所を、行在所といふを、あんざいしょとよむは、此とき別(コト)にあんの音になるにはあらず、行灯行脚(アンドンアンギャ)などといふあんと同じことにて、これもむかしの唐音なるべし、今の唐音は、平声の時も、去声の時も、いんといへり、又もろこしの國の、明の代の明を、みんと呼(イフ)も、唐音也、今の代の清を、しんといふは、唐音の訛也、清ノ字の唐音は、ついんと呼(イヘ)り、又明の代のとぢめに、鄭成功といひし人を、國姓爺と称ふ、この姓ノ字をせんといふも、唐音にすいんといふを訛れる也、さてこの國姓爺といふ称(ナ)は、國姓とは、当時(ソノトキ)の王の姓をいひて、此人、明の姓を賜はれるよし也、爺は、某(ナニ)老某(ナニ)丈などいふ、老丈のたぐひにて、たふとめる称(ナ)也、ちかき代かの國にて、ことによくつかふもじ也、こは筆のついでにいへり、
109 八百萬ノ神といふを書紀に八十萬ノ神と記されたる事[五八五]
もろもろの神たちを、すべていふには、古事記をはじめて、そのほかの古き書どもにもみな、八百萬(ヤホヨロヅノ)ノ神といへるぞつねなるに、たゞ書紀にのみは、いづこにもいづこにも、八十萬(ヤソヨロヅノ)ノ神とのみありて、八百萬神とあるところは見えず、こはいかさまにも、撰者の心あることと見えたり、神の御名に、日高(ヒタカ)と申すをも、彼ノ紀には、みなかへて、彦としるされたるは、当代(ソノコロ)の天皇の御名をさけられたりとおぼしきを、此八十萬ノ神は、いかなるよしにかあらむ、いまだ思ひえず、さてかようのたぐひも、神の御名の文字なども、何も、後の世の書どもは、おほかた書紀にのみよれるをたまたま此称は書紀によらず、今の世にいたるまでも、八十萬ノ神とのみいひならへるは、めづらし、
110 人ノ名を文字音(モジコエ)にいふ事[五八六]
人の名を、世に文字の音にて呼ならへる事、ふるくは、時平(ジヘイ)大臣、多田ノ満仲(マンヂウ)、源ノ頼光(ライクワウ)、安倍ノ清明(セイメイ)などのごときあり、やゝ後には、俊成卿、定家卿、家隆卿、鴨ノ長明など、もはらもじこゑにのみいひならへり、琵琶ほうしの、平家物語をかたるをきくに、つねにはさもあらぬ、もろもろの人の名どもも、おほくはもじこゑに物すなるは、当時(ソノカミ)ことに、よの中にさかりなりしことなめり、
111 神をなほざりに思ひ奉る世のならひをかなしむ事[五九八]
世の人の、神をなほざりに思ひ奉るは、かへすかへすこゝろうきわざなり、さるはほどほどに、たふとみ奉らぬにしもあらざンめれど、たゞよのならひの、人なみ人なみのかいなでのたふとみのみこそあれ、まことに心にしめて尊みたてまつるべきことを、思ひわきまへず、たゞおろそかにぞ思干たンめる、目にこそ見えね、此天地萬の物の、出来はじめしも、又むかし今の、世ノ中の大き小きもろもろの事も、人の身のうへ、くひ物き物居どころなにくれ、もろもろのことも、ことごとく神の御めぐみにかゝらざることはなきを、さるゆゑよしをばわすれはてて、なべての人、ただまがつひのまがことにのみまじこり、心をかたむけて、よろづにさかしだつひとはた、からぶみごゝろを、心とはして、まれまれに神代のおのが身々のうへにかゝれる、本なることをおもひたどらず、よろづよりもかなしきは、神の社神事(カムワザ)のおとろへなるを、かばかりめでたき御代にしも、もろもろのふるき神の御社どもの、いみしくおとろへませるを、なほしたて奉らんの心ざしある人はうるさしとも思ふらめど、此事のうれしさの、あけくれ心にわすらるゝ間もなくおぼゆるから、筆だにとれば、かきいでまほしくてなん、
治まれる御代のしるしを千木たかく
神のやしろに見るよしもがな
たまかつま十の巻
山 菅 十
はてもなしいふびきことはいへどいへど
なほやますげのみだれあひつゝ
此野べのすさびよ、いとかくはかなき手奈良ひを、ものものしく、巻ごとに名つけて、歌をさへにそへたるは、我ながらだに、あやしくおぼゆるを、おのづからも見む人は、ましていかにことごとしと思ふらん、さるははじめの巻のはしに、ゆくりかに歌ひとつ物して、巻の名つけるまゝに、つぎつぎも一つ二つそかせしが、おのづからならひになりて、かならずさらではえあらぬわざのごとなりもてきぬるを、今さらにたがへむも、さくがにて、例のごと物するになむ、そもそのをりをり、思ひうるまゝに、よみいでもし、あるは他事(コトコト)によみたるがあるをも、とりいでなどするを、につかはしくおぼゆるも、なきをりなど、今かゝむとすとては、筆とりながら、思ひめぐらすに、例の口おそさは、とみにもいでこで、しりくはへがちなるも、あぢきなく物ぐるほしきわざになん、此山菅も、からうじてほりいでたる、さる歌のきたなげさよ、
112 物まなびのこゝろばへ[五九九]
むかしは、皇國(ミクニ)のまなびとて、ことにすることはなくて、たゞからまなびをのみしけるほどに、世々をふるまゝに、いにしへの事は、やうやうにうとくのみなりゆき、から國の事は、やうやうにしたしくなりもてきつゝ、つひにそのこゝろは、もはらからざまにうつりはてて、上つ代の事は、物の意はさらにもいはず、言葉だに、聞しらぬ異国(ヒトクニ)のさへづりをきくがごと、ものうとくぞなりにける、かくて後にいたりて、皇國の学(マナビ)を、もはらとすることもはじまりつれども、しか漢意(カラゴコロ)の、久しくしみつきたる人心にしあればたゞ名のみこそ、みくにのまなびには有けれ、いひといひ、おもひと思ふことは、猶みなからにぞ有けるを、みづからも、さはおぼえざるなめり、されば近き世、まなびの道ひらけて、よろづさかしくなりぬるにつけても、なかなかにそのからごゝろのみ、深くさかりにはなりて、古の意は、いよいよはるかになむなりにけるを、此ちかきころになりてぞ、そこに心つきぬる人の出来そめて、世はみなからなることをさとりて、人も我も、いにしへのこゝろをたづぬる道の、明(アカ)りそめぬる、しかすがに神直毘大直毘(カムナホビオホナホビ)の神のましましける世は、なほゆくさきいとたのもしくなむ、
113 いにしへよりつたはれる事の絶るをかなしむ事[六〇〇]
よの中に、いにしへの事の、いたくおとろへたる、又ひたぶるに絶ぬるなどもおほかるを、かゝるめでたき御代にあたりて、何事もおこしたてまほしき中に、たえたるも、あとをたづねて、又かじめむに、はじめづべきは、おそくもとくも、直毘ノ神の頼みの、なほのこれるを、一たび絶ては、またつぐべきよしなく、又はじむべきたよりなき事どもこそ、殊にいふかひなく、くちをしきわざには有けれ、ふるき氏々など、神代のゆゑよし重(オモ)きなどは、さらにもいはず、さらぬも、はやく末のたえはてぬるがおほき、今はいかに思ひても、二たびつぎおこすべきよしなくなん、これらをおもふに、萬のふるきことは、わづかにも残りて、絶ざるをだに、おとしあぶさず、よくとりしたゝめて、今より後、たゆまじきさまに、いかにもいかにも、つよくかたくなしおかまほしきわざぞかし、
114 もろもろの物のことをよくしるしたる書あらまほしき事[六〇二]
よろずの草木鳥獣、なにくれもろもろの物の事を、上の代よりひろめ委しく考へて、しるしたる書こそ、あらまほしけれ、もろこしの國には、本草などいふ、さるすぢのふみどもも、いにしへよりこゝらあンなるを、御國には、わづかに源ノ順の和名抄のみこそはあれ、かの書のさま、すべていとしどけなく、からぶみを引出たるやうなども正しからず、いにしへさまのことにうとく、すべてたらはぬことのみ也、されどこれをおきては、ふるくよるべき書のなきまゝに、人も我も、もはら萬の物の考へのよりどころにはする也、ちかきころ、新撰字鏡といふもの出て、ふるくはあれども、事ひろからずかりそめなるうへに、あやしきもじども多くなどして、ことさまなるふみなるを、さすがに和名抄をたすくべき事どもは、おほくぞ有ける、これらをおきて、後の世に作れるどもは、あまたあれども、たゞみな例のからまなびのかたによれるのみにて、皇國のまなびのためには、おさおさ用もなきを、今いかで古事記書紀万葉集など、すべてふるきふみどもをまづよく考へ、中むかしのふみども、今の世のうつゝの物まで、よく考へ合せて、和名抄のかはりにも用ふべきさまの書を、作り出む人もがな、おのれはやくより、せちに此心ざしあれど、たやすからぬわざにて、物のかたてには、えしも物せず、いまはのこりのよはひも、いとすくなきこゝちすれば、思ひたえにたれば、今より後の人をだにと、いざなひおくになん、此六七年ばかりさきに、越前ノ國の府中の人とて、伊藤東四郎多羅といへる、まだわかきをのこなりけるが、とふ(ム)らひきて、かたりけるは、多羅が父は、いはゆる物産の学を好みて、ものしけるまゝに、多羅も、わらはなりしほどより、其すぢに心よせけるを、もろこしさまの事は、たれもたれも物するわざにて、人のふみはたよにともしからぬを、皇國の此すぢの事、よくしるしたるは、いまだ見え聞えざンなれば、多羅は、今より皇國のこのまなびを、物してんと心ざして、かつがつ考へたる事どももある也とて、一巻二巻かきあつめたるをも、とうでて見せけるを、はしばしいさゝか見たりしに、おのが思ふにかなへるさまにて、考へも、よろしく見えしかば、これいかでおこたらずつとめて、しはててよと、ねんごろに、かへすかへすすゝめやりしを、さて後いかになりぬらむ、音もなし、ちかきころ、しのちかき國の人にあへりしに、この事かたりて、とひけるに、たしかにはしらぬさまにて、かのをのこは、みまかりぬとか、ほのかに聞しよしいひたりし、それまことならば、いとあたらしくくちをしきわざにぞ有ける、
115 譬ヘといふものの事[六〇五]
たゞにいひては、ことゆきがたきこゝろも、萬の物のうへにたとへていへば、こともなくよく聞ゆること、多くあるわざ也、されば、このたとへといふ事、神代より有て、歌にも見え、今の世の人も、常にものすること也、皇國のみにもあらず、戎(カラ)の國々にも、古より有けるを、もろこし人は、すべて物のたとへをとること、いち上手にて、言すくなくて、いとよく聞えて、げによく譬(タト)ヘたりとおぼゆることのおほかるを、佛の經どもに、殊に多く見えたるたとへは、おほくは物どほくして、よくあたれりとも聞えぬ事をくだくだしくながながといへるなど、いといとつたなし、佛といへる人のいへることも、かゝるものにや、
116 物をときさとす事[六〇六]
すべて物の色形、又事のこゝろを、いひさとすの、いかにくはしくいひても、なほさだかにさとりがたきこと、つねにあるわざ也、そはその同じたぐひの物をあげて、其の色に同じきぞ、某のかたちのごとくなるぞといひ、ことの意をさとすには、その例を一つ二つ引出ヅれば、言おほらかで、よくわかるゝものなり、
117 源氏物語をよむことのたとへ[六一〇]
源氏物語とて、世にもて興ずる、五十四帖の草子とやらむ、心みに、なにことぞと、くりひろげて見しかば、みだれたる糸すじの、口なきやうにて、さらによみとかれ侍らぬは、いかにと問、さかし、たゞなれよ、のちのち見もてゆかば、さながらまどひはてじ、ととへていはば、六月ばかり、いと暑き日かげをしのぎきたらむ人の、内に入ては、やみのうつゝのさだかならで、物のいろふし、あやめもわかれねど、をること久しくなれば、じねんに、かのうつは物此調度と、こまかに見わかるゝが如し、と同集の文にあり、この集は、長嘯子の歌又文をあつめたるふみ也、
118 さらしなのにきに見えたること[六一八]
さらしなの日記にいはく、二むらの山の中に、とまりたる夜、大きなる柿の木の下に、いほをつくりたれば、よひとよいほのうへに、柿のおちかゝりたるを、人々ひろいなどすといへり、これは菅原ノ孝標といひける人の女のかける物にて、さしもとほき世の事にもあらぬを、そのかみなほ旅の屋どりは、かゝる事も有けるをおもへば、つねに歌によむなる、草の枕もあがれりし世には、まことにさることにぞ有けむかし、
119 おのが帰雁のうた[六一九]
帰雁の題にておのれ、「春くれば霞を見てやかへる雁われもとそらに子ひたつらむ、いまひとつ、「かへるかりこれもこしぢの梅香や風のたよりにさそひそめけむ、とよめりける後なるをよく思へば、末の二句に、雁の縁なくて、いかにぞやおぼえければ、またとかく思ひめぐらして、「うめがかやさそひそめけむかへる雁これも越路の風のたよりに、となんよみなほしける、これはしも、こしぢを末の句にうつしたるにて、雁の緑はさることながら、歌ざまは、いさゝかおとりておぼゆるは、いかならむ、歌よく見しれらむ人、さだめてよ、
120 師をとるといふ事[六二二]
源氏物がたりの紅葉賀ノ巻に、舞の師どもなど、よになべてならぬをとりつゝ、おのおのこもりてなんならひけるとあり、世の言に、師匠をとる、弟子をとるといふも、ふるきことなりけり、
山 菅 十
はてもなしいふびきことはいへどいへど
なほやますげのみだれあひつゝ
此野べのすさびよ、いとかくはかなき手奈良ひを、ものものしく、巻ごとに名つけて、歌をさへにそへたるは、我ながらだに、あやしくおぼゆるを、おのづからも見む人は、ましていかにことごとしと思ふらん、さるははじめの巻のはしに、ゆくりかに歌ひとつ物して、巻の名つけるまゝに、つぎつぎも一つ二つそかせしが、おのづからならひになりて、かならずさらではえあらぬわざのごとなりもてきぬるを、今さらにたがへむも、さくがにて、例のごと物するになむ、そもそのをりをり、思ひうるまゝに、よみいでもし、あるは他事(コトコト)によみたるがあるをも、とりいでなどするを、につかはしくおぼゆるも、なきをりなど、今かゝむとすとては、筆とりながら、思ひめぐらすに、例の口おそさは、とみにもいでこで、しりくはへがちなるも、あぢきなく物ぐるほしきわざになん、此山菅も、からうじてほりいでたる、さる歌のきたなげさよ、
112 物まなびのこゝろばへ[五九九]
むかしは、皇國(ミクニ)のまなびとて、ことにすることはなくて、たゞからまなびをのみしけるほどに、世々をふるまゝに、いにしへの事は、やうやうにうとくのみなりゆき、から國の事は、やうやうにしたしくなりもてきつゝ、つひにそのこゝろは、もはらからざまにうつりはてて、上つ代の事は、物の意はさらにもいはず、言葉だに、聞しらぬ異国(ヒトクニ)のさへづりをきくがごと、ものうとくぞなりにける、かくて後にいたりて、皇國の学(マナビ)を、もはらとすることもはじまりつれども、しか漢意(カラゴコロ)の、久しくしみつきたる人心にしあればたゞ名のみこそ、みくにのまなびには有けれ、いひといひ、おもひと思ふことは、猶みなからにぞ有けるを、みづからも、さはおぼえざるなめり、されば近き世、まなびの道ひらけて、よろづさかしくなりぬるにつけても、なかなかにそのからごゝろのみ、深くさかりにはなりて、古の意は、いよいよはるかになむなりにけるを、此ちかきころになりてぞ、そこに心つきぬる人の出来そめて、世はみなからなることをさとりて、人も我も、いにしへのこゝろをたづぬる道の、明(アカ)りそめぬる、しかすがに神直毘大直毘(カムナホビオホナホビ)の神のましましける世は、なほゆくさきいとたのもしくなむ、
113 いにしへよりつたはれる事の絶るをかなしむ事[六〇〇]
よの中に、いにしへの事の、いたくおとろへたる、又ひたぶるに絶ぬるなどもおほかるを、かゝるめでたき御代にあたりて、何事もおこしたてまほしき中に、たえたるも、あとをたづねて、又かじめむに、はじめづべきは、おそくもとくも、直毘ノ神の頼みの、なほのこれるを、一たび絶ては、またつぐべきよしなく、又はじむべきたよりなき事どもこそ、殊にいふかひなく、くちをしきわざには有けれ、ふるき氏々など、神代のゆゑよし重(オモ)きなどは、さらにもいはず、さらぬも、はやく末のたえはてぬるがおほき、今はいかに思ひても、二たびつぎおこすべきよしなくなん、これらをおもふに、萬のふるきことは、わづかにも残りて、絶ざるをだに、おとしあぶさず、よくとりしたゝめて、今より後、たゆまじきさまに、いかにもいかにも、つよくかたくなしおかまほしきわざぞかし、
114 もろもろの物のことをよくしるしたる書あらまほしき事[六〇二]
よろずの草木鳥獣、なにくれもろもろの物の事を、上の代よりひろめ委しく考へて、しるしたる書こそ、あらまほしけれ、もろこしの國には、本草などいふ、さるすぢのふみどもも、いにしへよりこゝらあンなるを、御國には、わづかに源ノ順の和名抄のみこそはあれ、かの書のさま、すべていとしどけなく、からぶみを引出たるやうなども正しからず、いにしへさまのことにうとく、すべてたらはぬことのみ也、されどこれをおきては、ふるくよるべき書のなきまゝに、人も我も、もはら萬の物の考へのよりどころにはする也、ちかきころ、新撰字鏡といふもの出て、ふるくはあれども、事ひろからずかりそめなるうへに、あやしきもじども多くなどして、ことさまなるふみなるを、さすがに和名抄をたすくべき事どもは、おほくぞ有ける、これらをおきて、後の世に作れるどもは、あまたあれども、たゞみな例のからまなびのかたによれるのみにて、皇國のまなびのためには、おさおさ用もなきを、今いかで古事記書紀万葉集など、すべてふるきふみどもをまづよく考へ、中むかしのふみども、今の世のうつゝの物まで、よく考へ合せて、和名抄のかはりにも用ふべきさまの書を、作り出む人もがな、おのれはやくより、せちに此心ざしあれど、たやすからぬわざにて、物のかたてには、えしも物せず、いまはのこりのよはひも、いとすくなきこゝちすれば、思ひたえにたれば、今より後の人をだにと、いざなひおくになん、此六七年ばかりさきに、越前ノ國の府中の人とて、伊藤東四郎多羅といへる、まだわかきをのこなりけるが、とふ(ム)らひきて、かたりけるは、多羅が父は、いはゆる物産の学を好みて、ものしけるまゝに、多羅も、わらはなりしほどより、其すぢに心よせけるを、もろこしさまの事は、たれもたれも物するわざにて、人のふみはたよにともしからぬを、皇國の此すぢの事、よくしるしたるは、いまだ見え聞えざンなれば、多羅は、今より皇國のこのまなびを、物してんと心ざして、かつがつ考へたる事どももある也とて、一巻二巻かきあつめたるをも、とうでて見せけるを、はしばしいさゝか見たりしに、おのが思ふにかなへるさまにて、考へも、よろしく見えしかば、これいかでおこたらずつとめて、しはててよと、ねんごろに、かへすかへすすゝめやりしを、さて後いかになりぬらむ、音もなし、ちかきころ、しのちかき國の人にあへりしに、この事かたりて、とひけるに、たしかにはしらぬさまにて、かのをのこは、みまかりぬとか、ほのかに聞しよしいひたりし、それまことならば、いとあたらしくくちをしきわざにぞ有ける、
115 譬ヘといふものの事[六〇五]
たゞにいひては、ことゆきがたきこゝろも、萬の物のうへにたとへていへば、こともなくよく聞ゆること、多くあるわざ也、されば、このたとへといふ事、神代より有て、歌にも見え、今の世の人も、常にものすること也、皇國のみにもあらず、戎(カラ)の國々にも、古より有けるを、もろこし人は、すべて物のたとへをとること、いち上手にて、言すくなくて、いとよく聞えて、げによく譬(タト)ヘたりとおぼゆることのおほかるを、佛の經どもに、殊に多く見えたるたとへは、おほくは物どほくして、よくあたれりとも聞えぬ事をくだくだしくながながといへるなど、いといとつたなし、佛といへる人のいへることも、かゝるものにや、
116 物をときさとす事[六〇六]
すべて物の色形、又事のこゝろを、いひさとすの、いかにくはしくいひても、なほさだかにさとりがたきこと、つねにあるわざ也、そはその同じたぐひの物をあげて、其の色に同じきぞ、某のかたちのごとくなるぞといひ、ことの意をさとすには、その例を一つ二つ引出ヅれば、言おほらかで、よくわかるゝものなり、
117 源氏物語をよむことのたとへ[六一〇]
源氏物語とて、世にもて興ずる、五十四帖の草子とやらむ、心みに、なにことぞと、くりひろげて見しかば、みだれたる糸すじの、口なきやうにて、さらによみとかれ侍らぬは、いかにと問、さかし、たゞなれよ、のちのち見もてゆかば、さながらまどひはてじ、ととへていはば、六月ばかり、いと暑き日かげをしのぎきたらむ人の、内に入ては、やみのうつゝのさだかならで、物のいろふし、あやめもわかれねど、をること久しくなれば、じねんに、かのうつは物此調度と、こまかに見わかるゝが如し、と同集の文にあり、この集は、長嘯子の歌又文をあつめたるふみ也、
118 さらしなのにきに見えたること[六一八]
さらしなの日記にいはく、二むらの山の中に、とまりたる夜、大きなる柿の木の下に、いほをつくりたれば、よひとよいほのうへに、柿のおちかゝりたるを、人々ひろいなどすといへり、これは菅原ノ孝標といひける人の女のかける物にて、さしもとほき世の事にもあらぬを、そのかみなほ旅の屋どりは、かゝる事も有けるをおもへば、つねに歌によむなる、草の枕もあがれりし世には、まことにさることにぞ有けむかし、
119 おのが帰雁のうた[六一九]
帰雁の題にておのれ、「春くれば霞を見てやかへる雁われもとそらに子ひたつらむ、いまひとつ、「かへるかりこれもこしぢの梅香や風のたよりにさそひそめけむ、とよめりける後なるをよく思へば、末の二句に、雁の縁なくて、いかにぞやおぼえければ、またとかく思ひめぐらして、「うめがかやさそひそめけむかへる雁これも越路の風のたよりに、となんよみなほしける、これはしも、こしぢを末の句にうつしたるにて、雁の緑はさることながら、歌ざまは、いさゝかおとりておぼゆるは、いかならむ、歌よく見しれらむ人、さだめてよ、
120 師をとるといふ事[六二二]
源氏物がたりの紅葉賀ノ巻に、舞の師どもなど、よになべてならぬをとりつゝ、おのおのこもりてなんならひけるとあり、世の言に、師匠をとる、弟子をとるといふも、ふるきことなりけり、
玉勝間十一の巻
さ ね か づ ら 十一
こぬものを思ひたえなでさねかづら
まつもくるしやくるゝ夜ごとに
これは夜毎にまつといふ、題よみのなるを、巻の名つけむとて、例のひきいでたるになん、
121 人のうまるゝはじめ死て後の事[六七二]
人の生れ来るはじめ、また死(シニ)て後、いかなるものぞといふこと、たれも心にかけて、明らめしらまほしくするならひなるを、佛ぶみに説たる、生死(うまれしに)の趣、心性のさだ、いとくはしきやうなれど、みな人の考へたるつくりことなれば、よくさとりあきらめたらむも、つひに何の用もなき、いたづらわざ也、たゞ儒者の説に、死(シニ)て身ほろびぬれば、心神もともに消うせて、のこることなしといへるぞ、よく思ひめぐらせば、まことにさるべしことわりとは聞こえたる、然はあれども、これも又たのみがたし、すべてものの理は、かぎりなきものにて、火の色は赤きに、所焼(やけ)たる物は、黒くなり、又灰になれば、白くこそなれ、すべてかく思ひのほかなること有て、思ひはかれるとは、いたくたがへることのおほければ也、されば人の死て後のやうも、さらに人の智(サトリ)もて、一わたりのことわりによりて、はかりしるべきわざにはあらず、思ひのほかなるものにぞ有べき、これを思ふにも、皇國の神代の神のつたへ説(ごと)に夜見(ヨミノ)國にまかるといへるこそ、いといとたふとけれ、から國のことわりふかげなる、さかしき説どもは、なかなかにいとあさはかなること也かし、
122 うひ学びの輩の歌よむさま[六七四]
今の世にうひまなびのともがらの、よみ出たる歌は、きこえぬところを、聞ゆるさまにとりなほせば、古人の歌と、もはら同じくなること、つねにあり、これさるべきこと也、いかにといふに、うひまなびのほどは、おほかた題をとりぬれば、まづ昔のよき歌の集の中の、その題の歌どもを見て、その中の一つによりて、こゝかしこすこしづゝ詞をかへて、つゞりなすならひなるを、大かた古ヘ人のよき歌は、其詞みな、かならず然いはではかなはぬさまにて、おほかた一もじかへがたきものなるを、いまだしきものの、心もえず、こゝかしことかへぬれば、かへたる所の、必ズとゝのはぬわざなるゆゑに、歌よく心得たる人の見て、そをとゝのふさまに引なほせば、かならず又本の古歌とひとしくはなる也、さてさやうに古歌ともはら同じくては、新によめるかひなきやうなれども、うひまなびのほどのは、後まで、よめる歌数に入びきにもあらざれば、そはとてもかくてもありぬべし、歌のさまこゝろえむまなびのためには、しばらくただおいらかにて、上の件のごとしたらむどよかるべき、さるをはじめよりさかしだちて、人のふるさぬめづらしきふしをやまむとせば、中々によこさまなるあしき道にぞ、まどひいりぬべき、
123 後の世ははづかしきものなる事[六九三]
安藤ノ為章が千年山集といふ物に、契沖の万葉の注釈をほめて、かの顕昭仙覚がともがらを、此大とこになぞらへば、あたかも駑胎にひとしといふべしといへる、まことにさることなりかし、そのかみ顕昭などの説にくらべては、かの契沖の釈は、くはふべきふしなく、事つきたりとぞ、たれもおぼえけむを、今又吾ガ県居ノ大人にくらべてみれば、契沖のともがらも又、駑胎にひとしとぞいふべかりける、何事もつぎつぎに後の世は、いとはづかしきものにこそありけれ、
124 うたを思ふほどにあること[六九四]
歌よまむとて、思ひめぐらすほど、一ふし思ひたえたる事のあるに、心のごといひとゝのへがたくて、時うつるまで思ひ、あるは日をかさねても、同じすぢにかゝづらひて、とかくつゞけみれども、つひに事ゆかぬことあるものなり、さるをりは、そのふしをば、きよくすてて、さらにほかにもとむべきわざなるを、さすがにをしく、すてがたくて、あいあずはおぼえながら、いかゞはせむに、しひてつゞり出たる、いと心ぎたなきわざにはあれども、たれもよくあること也、又さように久しく思ひわずらひたるほどに、そのかゝづらへるすぢにはあらで、思ひかけぬよき事の、ふとかたはらより出来て、たやすくよみ出らるゝこともありかし、されどそれも、深く思ひ入たるから、さるよきことも出来るにて、はじめよりのいたつきの、いたずらになれるにはあらずなむ、そもそもこれらは、えうもなきあだことなれども、おもひ出たるまゝに、書出たるなり、
125 假字のさだ[七〇六]
源氏物語梅枝巻に、よろづの事、むかしのはおとりざまに、浅くなりゆく世の末なれど、かんなのみなむ、今の世は、いときはなくなりたる、ふるきあとは、さだまれるやうにはあれど、ひろきこゝろゆたかならづ、ひとすぢに通ひてなむ有ける、たへにおかしきことは、とよりてこそ、書いづる人々有けれといへり、此ノかんなといへるは、いろは假字のこと也、此かたは、空海ほうしの作れりといふを、萬の事、はじめはうひうひしきを思ふに、これも、出来つるはじめのほどは、たゞ用ふるにたよりよきかたをのみこととはして、その書キざまのよきあしきをいふことなどまでは及ばざりけんを、やうやうに世にひろくかきならひて、年をふるまゝに、書キざまのよさあしさをも、さだすることにはなれりけむを、源氏物語つくりしころは、此假字出来て、まだいとしも遠からぬほどなりければ、げにやうやうにおかしくたへにかきいづるひとのいでくべきころほひ也、
126 皇國の学者のあやしき癖[七〇六]
すべて何事も、おのが國のことにこそしたがふべけれ、そをすてて、他ヒトの國のことにしたがふべきにはあらざるを、かへりて他ヒトの國のことにしたがふを、かしこきわざとして、皇國のことにしたがふをば、つたなきわざとこゝろえためるは、皇國の学者の、あやしきくせ也、はかなきことながらたとえば、もろこしの國を、もろこしともからともいひ、漢文には、漢とも唐ともかくぞ、皇國のことなるを、しかいふをばつたなしとして、中華中国などいふを、かしこきこと心得たるひがことは、馭戎慨言にくはしく論ひたれば、今さらにいはず、又中華中国などは、いふままじきことと、物のこゝろをわきまへたるひとはた、猶漢もし唐などいふをば、つたなしとやおもふらむ、震旦支那など書クたぐひもあンなるは、中華中国などいふにくらぶれば、よろしけれども、震旦支那などは、西の方なる國より、つけたる名なれば、そもなほおのが國のことをすてて、人の國のことにしたがふにぞ有ける、もし漢といひ唐ともいはむを、おかしからずとおもはば、漢文にも、諸越とも、毛虜胡鴟とも書むに、何事かあらむ、かく己が國のことをたてたらむこそは、雄々(ヲヲ)しき文ならめ、他(ヒト)の國のことにへつらひよりて書むは、めゝしくつたなきわざにぞ有ける、こはもろこしの國の名のみにもあらず、よろずにわたれる事ぞかし、なほ此たぐひなる事を、一ツ 二ツ いはば、遥なる西の國々にて此大地にあらゆる國々をすべて、五ツに分たるも、つけたる名どもも、もとより他(ヒト)國のことにて、殊に近き世に聞えきつることなるを、神代より皇國に伝はりたる説のごと、うちまかせてしたがいよるは、これはた他(ヒト)の國のことといへば、たふとみ信ずる、例のあやしき癖にぞありける、又もろこしの國の音(コエ)は、他國の音を訳(ウツ)すに、いと便リあしくて、いにしえに天竺の國の佛ぶみを訳(ウツ)せるにも、多くはまさしくはあたりがたかりしことなるを、近く明の世のほどなどに、かの遥なる西の國國の名ども、又そのよろづの詞を、訳(ウツ)せるどもを見るに、其字の音、十に七八は、かの言にあたらず、いたくたがへるがおほければ、假字づけなくては、其言しりがたく、訳字(ウツシモジ)はいたづらなるがごとし、かくいふは、皇國の漢音呉音によりてにはあらず、ちかき世の唐音といふ音によりていふ也、かゝればもろこしの國國の言をおぼえたらむは、皆誤りてぞ有べきを、皇國の假字は、他國の音を訳(ウツ)すに、いとたよりよければ、おさおさたがふことなし、さればこうこくにては、かのもろこしの訳字をば、みな廃て、此方(ココ)の訳(ウツシ)をのみ用ふべきこと也、それも片假字は、しどけなくて、漢文などには書キがたくは、眞假字(マガナ)を用ふべし、眞假字ちは、いはゆる万葉假字にて、伊呂波爾保閇登とやうにかくをいふ、すべてあらたに此假字を用ひて、かの五つの洲の名の、亜細亜をば阿自夜(アジヤ)、欧羅巴をば要呂波(エウロハ)とやうに、萬ヅの言を、みなかくさまに訳(ウツ)しなば、いとよろしかるべきに、よろしくたよりよき、己が國のことを用ひずして、かのみろこしの、ものどほくたよりあしく、あたらぬ訳字を、大事と守りて用るは、いといとつたなく愚なることにて、これはた例の、他國(ヒトノクニ)のことにしたがふを、かしこきわざと心得たる、あやしき学者のくせなりけり、
127 万葉集をよむこゝろばへ[七一〇]
万葉集今の本、もじを誤れるところいと多し、こは近き世のことにはあらで、いとはやくより、久しく誤り来ぬるものとぞ見えたる、然るにちかきころは、古学おこりて、むねと此集を心にかくるともがら、おほきが故につぎつぎによきかむかへ出来て、誤れる字(モジ)も、やうやうにしられたること多し、されど猶しられざるもおほきなり、その心してよむべき也、むげに聞えぬところどころなどは、大かた誤字にぞ有りける、さて又すべて訓(ヨミ)も、誤いと多し、さるは此集はじめは、訓はなかりしを、やゝ後に始めて附ケたりし、その訓は、いといとをさなくて、えもいはぬひがことのみにして、さらに用ひがたきものなりしを、中むかしまでさて有しを、仙覚といひけるほうし、力を用ひて、多く訓を改めたる、今の本は、此仙覚が訓にて、もとのにくらぶれば、こよなくまさりてぞ有ける、然れどもなほよからざること多きを、ちかき世に、契沖法師があらためたるにて、又こよなくよくなれり、然れども誤字なるをしらずして、本のまゝによめるなどには、強(シヒ)たることおほく、そのほかすべてのよみざまも、なほよからざること多きを、その後又此集の事、いよいよくは敷くなり茂木塗るまにまに、訓もいとよくなれれども、なほいまだ清く直(ナホ)りはてたりとはいひがたし、まづ誤字のことごとくしられざるほどは、訓もことごとくよろしくは直りがたきわざ也、誤字のなほいとおほかるを、その字のままによむとせぬには、かへりてしひごとになるたぐひ多かンべきを、よく心得べし、又すべての訓ざま、假字書キのところをよく考へて、その例をもてよむべきなり、おほかたこれら、此集をよむに、むねと心得べき事ども也かし、
128 足ことをしるといふ事[七一一]
たることをしるといふは、もろこし人のつねに、いみしきわざにすめることなるを、これまことにいとよきことにて、しか思ひとらば、ほどほどにつけて、たれもたれも、心はいと安(ヤス)かりぬべきわざにぞ有ける、然はあれども、高きみじかき、ほどほどにのぞみねがふことのつきせぬぞ、世の人の真情(マゴコロ)にて、今はたりぬとおぼゆるよはなきものなるを、世には足(タル)ことしれるさまにいひて、さるかほする人の多かるは、例のからやうのつくりことにこそはあれ、まことにきよく然思ひとれる人は、千万の中にも、有がたかるべきわざにこそ、
さ ね か づ ら 十一
こぬものを思ひたえなでさねかづら
まつもくるしやくるゝ夜ごとに
これは夜毎にまつといふ、題よみのなるを、巻の名つけむとて、例のひきいでたるになん、
121 人のうまるゝはじめ死て後の事[六七二]
人の生れ来るはじめ、また死(シニ)て後、いかなるものぞといふこと、たれも心にかけて、明らめしらまほしくするならひなるを、佛ぶみに説たる、生死(うまれしに)の趣、心性のさだ、いとくはしきやうなれど、みな人の考へたるつくりことなれば、よくさとりあきらめたらむも、つひに何の用もなき、いたづらわざ也、たゞ儒者の説に、死(シニ)て身ほろびぬれば、心神もともに消うせて、のこることなしといへるぞ、よく思ひめぐらせば、まことにさるべしことわりとは聞こえたる、然はあれども、これも又たのみがたし、すべてものの理は、かぎりなきものにて、火の色は赤きに、所焼(やけ)たる物は、黒くなり、又灰になれば、白くこそなれ、すべてかく思ひのほかなること有て、思ひはかれるとは、いたくたがへることのおほければ也、されば人の死て後のやうも、さらに人の智(サトリ)もて、一わたりのことわりによりて、はかりしるべきわざにはあらず、思ひのほかなるものにぞ有べき、これを思ふにも、皇國の神代の神のつたへ説(ごと)に夜見(ヨミノ)國にまかるといへるこそ、いといとたふとけれ、から國のことわりふかげなる、さかしき説どもは、なかなかにいとあさはかなること也かし、
122 うひ学びの輩の歌よむさま[六七四]
今の世にうひまなびのともがらの、よみ出たる歌は、きこえぬところを、聞ゆるさまにとりなほせば、古人の歌と、もはら同じくなること、つねにあり、これさるべきこと也、いかにといふに、うひまなびのほどは、おほかた題をとりぬれば、まづ昔のよき歌の集の中の、その題の歌どもを見て、その中の一つによりて、こゝかしこすこしづゝ詞をかへて、つゞりなすならひなるを、大かた古ヘ人のよき歌は、其詞みな、かならず然いはではかなはぬさまにて、おほかた一もじかへがたきものなるを、いまだしきものの、心もえず、こゝかしことかへぬれば、かへたる所の、必ズとゝのはぬわざなるゆゑに、歌よく心得たる人の見て、そをとゝのふさまに引なほせば、かならず又本の古歌とひとしくはなる也、さてさやうに古歌ともはら同じくては、新によめるかひなきやうなれども、うひまなびのほどのは、後まで、よめる歌数に入びきにもあらざれば、そはとてもかくてもありぬべし、歌のさまこゝろえむまなびのためには、しばらくただおいらかにて、上の件のごとしたらむどよかるべき、さるをはじめよりさかしだちて、人のふるさぬめづらしきふしをやまむとせば、中々によこさまなるあしき道にぞ、まどひいりぬべき、
123 後の世ははづかしきものなる事[六九三]
安藤ノ為章が千年山集といふ物に、契沖の万葉の注釈をほめて、かの顕昭仙覚がともがらを、此大とこになぞらへば、あたかも駑胎にひとしといふべしといへる、まことにさることなりかし、そのかみ顕昭などの説にくらべては、かの契沖の釈は、くはふべきふしなく、事つきたりとぞ、たれもおぼえけむを、今又吾ガ県居ノ大人にくらべてみれば、契沖のともがらも又、駑胎にひとしとぞいふべかりける、何事もつぎつぎに後の世は、いとはづかしきものにこそありけれ、
124 うたを思ふほどにあること[六九四]
歌よまむとて、思ひめぐらすほど、一ふし思ひたえたる事のあるに、心のごといひとゝのへがたくて、時うつるまで思ひ、あるは日をかさねても、同じすぢにかゝづらひて、とかくつゞけみれども、つひに事ゆかぬことあるものなり、さるをりは、そのふしをば、きよくすてて、さらにほかにもとむべきわざなるを、さすがにをしく、すてがたくて、あいあずはおぼえながら、いかゞはせむに、しひてつゞり出たる、いと心ぎたなきわざにはあれども、たれもよくあること也、又さように久しく思ひわずらひたるほどに、そのかゝづらへるすぢにはあらで、思ひかけぬよき事の、ふとかたはらより出来て、たやすくよみ出らるゝこともありかし、されどそれも、深く思ひ入たるから、さるよきことも出来るにて、はじめよりのいたつきの、いたずらになれるにはあらずなむ、そもそもこれらは、えうもなきあだことなれども、おもひ出たるまゝに、書出たるなり、
125 假字のさだ[七〇六]
源氏物語梅枝巻に、よろづの事、むかしのはおとりざまに、浅くなりゆく世の末なれど、かんなのみなむ、今の世は、いときはなくなりたる、ふるきあとは、さだまれるやうにはあれど、ひろきこゝろゆたかならづ、ひとすぢに通ひてなむ有ける、たへにおかしきことは、とよりてこそ、書いづる人々有けれといへり、此ノかんなといへるは、いろは假字のこと也、此かたは、空海ほうしの作れりといふを、萬の事、はじめはうひうひしきを思ふに、これも、出来つるはじめのほどは、たゞ用ふるにたよりよきかたをのみこととはして、その書キざまのよきあしきをいふことなどまでは及ばざりけんを、やうやうに世にひろくかきならひて、年をふるまゝに、書キざまのよさあしさをも、さだすることにはなれりけむを、源氏物語つくりしころは、此假字出来て、まだいとしも遠からぬほどなりければ、げにやうやうにおかしくたへにかきいづるひとのいでくべきころほひ也、
126 皇國の学者のあやしき癖[七〇六]
すべて何事も、おのが國のことにこそしたがふべけれ、そをすてて、他ヒトの國のことにしたがふべきにはあらざるを、かへりて他ヒトの國のことにしたがふを、かしこきわざとして、皇國のことにしたがふをば、つたなきわざとこゝろえためるは、皇國の学者の、あやしきくせ也、はかなきことながらたとえば、もろこしの國を、もろこしともからともいひ、漢文には、漢とも唐ともかくぞ、皇國のことなるを、しかいふをばつたなしとして、中華中国などいふを、かしこきこと心得たるひがことは、馭戎慨言にくはしく論ひたれば、今さらにいはず、又中華中国などは、いふままじきことと、物のこゝろをわきまへたるひとはた、猶漢もし唐などいふをば、つたなしとやおもふらむ、震旦支那など書クたぐひもあンなるは、中華中国などいふにくらぶれば、よろしけれども、震旦支那などは、西の方なる國より、つけたる名なれば、そもなほおのが國のことをすてて、人の國のことにしたがふにぞ有ける、もし漢といひ唐ともいはむを、おかしからずとおもはば、漢文にも、諸越とも、毛虜胡鴟とも書むに、何事かあらむ、かく己が國のことをたてたらむこそは、雄々(ヲヲ)しき文ならめ、他(ヒト)の國のことにへつらひよりて書むは、めゝしくつたなきわざにぞ有ける、こはもろこしの國の名のみにもあらず、よろずにわたれる事ぞかし、なほ此たぐひなる事を、一ツ 二ツ いはば、遥なる西の國々にて此大地にあらゆる國々をすべて、五ツに分たるも、つけたる名どもも、もとより他(ヒト)國のことにて、殊に近き世に聞えきつることなるを、神代より皇國に伝はりたる説のごと、うちまかせてしたがいよるは、これはた他(ヒト)の國のことといへば、たふとみ信ずる、例のあやしき癖にぞありける、又もろこしの國の音(コエ)は、他國の音を訳(ウツ)すに、いと便リあしくて、いにしえに天竺の國の佛ぶみを訳(ウツ)せるにも、多くはまさしくはあたりがたかりしことなるを、近く明の世のほどなどに、かの遥なる西の國國の名ども、又そのよろづの詞を、訳(ウツ)せるどもを見るに、其字の音、十に七八は、かの言にあたらず、いたくたがへるがおほければ、假字づけなくては、其言しりがたく、訳字(ウツシモジ)はいたづらなるがごとし、かくいふは、皇國の漢音呉音によりてにはあらず、ちかき世の唐音といふ音によりていふ也、かゝればもろこしの國國の言をおぼえたらむは、皆誤りてぞ有べきを、皇國の假字は、他國の音を訳(ウツ)すに、いとたよりよければ、おさおさたがふことなし、さればこうこくにては、かのもろこしの訳字をば、みな廃て、此方(ココ)の訳(ウツシ)をのみ用ふべきこと也、それも片假字は、しどけなくて、漢文などには書キがたくは、眞假字(マガナ)を用ふべし、眞假字ちは、いはゆる万葉假字にて、伊呂波爾保閇登とやうにかくをいふ、すべてあらたに此假字を用ひて、かの五つの洲の名の、亜細亜をば阿自夜(アジヤ)、欧羅巴をば要呂波(エウロハ)とやうに、萬ヅの言を、みなかくさまに訳(ウツ)しなば、いとよろしかるべきに、よろしくたよりよき、己が國のことを用ひずして、かのみろこしの、ものどほくたよりあしく、あたらぬ訳字を、大事と守りて用るは、いといとつたなく愚なることにて、これはた例の、他國(ヒトノクニ)のことにしたがふを、かしこきわざと心得たる、あやしき学者のくせなりけり、
127 万葉集をよむこゝろばへ[七一〇]
万葉集今の本、もじを誤れるところいと多し、こは近き世のことにはあらで、いとはやくより、久しく誤り来ぬるものとぞ見えたる、然るにちかきころは、古学おこりて、むねと此集を心にかくるともがら、おほきが故につぎつぎによきかむかへ出来て、誤れる字(モジ)も、やうやうにしられたること多し、されど猶しられざるもおほきなり、その心してよむべき也、むげに聞えぬところどころなどは、大かた誤字にぞ有りける、さて又すべて訓(ヨミ)も、誤いと多し、さるは此集はじめは、訓はなかりしを、やゝ後に始めて附ケたりし、その訓は、いといとをさなくて、えもいはぬひがことのみにして、さらに用ひがたきものなりしを、中むかしまでさて有しを、仙覚といひけるほうし、力を用ひて、多く訓を改めたる、今の本は、此仙覚が訓にて、もとのにくらぶれば、こよなくまさりてぞ有ける、然れどもなほよからざること多きを、ちかき世に、契沖法師があらためたるにて、又こよなくよくなれり、然れども誤字なるをしらずして、本のまゝによめるなどには、強(シヒ)たることおほく、そのほかすべてのよみざまも、なほよからざること多きを、その後又此集の事、いよいよくは敷くなり茂木塗るまにまに、訓もいとよくなれれども、なほいまだ清く直(ナホ)りはてたりとはいひがたし、まづ誤字のことごとくしられざるほどは、訓もことごとくよろしくは直りがたきわざ也、誤字のなほいとおほかるを、その字のままによむとせぬには、かへりてしひごとになるたぐひ多かンべきを、よく心得べし、又すべての訓ざま、假字書キのところをよく考へて、その例をもてよむべきなり、おほかたこれら、此集をよむに、むねと心得べき事ども也かし、
128 足ことをしるといふ事[七一一]
たることをしるといふは、もろこし人のつねに、いみしきわざにすめることなるを、これまことにいとよきことにて、しか思ひとらば、ほどほどにつけて、たれもたれも、心はいと安(ヤス)かりぬべきわざにぞ有ける、然はあれども、高きみじかき、ほどほどにのぞみねがふことのつきせぬぞ、世の人の真情(マゴコロ)にて、今はたりぬとおぼゆるよはなきものなるを、世には足(タル)ことしれるさまにいひて、さるかほする人の多かるは、例のからやうのつくりことにこそはあれ、まことにきよく然思ひとれる人は、千万の中にも、有がたかるべきわざにこそ、
玉かつま十二の巻
や ま ぶ き 十二
われとひとしき人しなければ、といひける人も有けれど、よしやさばれおのれは
思ふこといはではやまじやまぶきも
さればぞ花の露けかるらむ
129 又妹背山[七二九]
寛政十一年春、又紀の国に物しけるをり、妹背山の事、なほよくたづねむと思ひて、ゆくさには、きの川を船よりくだりけるを、しばし、陸におりて、批山をこえ、かえるさにもこえて、くはしき尋ねける、そは紀の国ノ伊都ノ郡橋本の駅より、四里ばかり西に、背山村といふ有て、其村の山ぞ、すなわち背山なりける、いとしも高からぬ山にて紀の川の北の邊に在て、南のかたの尾さきは、川の岸までせまれり、村は、批山の東おもての腹にあり、大道は、川岸のかの尾さきのやゝ高きところを、村を北にみてこゆる、道のかたわらにも、屋どもある、それも背山村の民の屋也、批山までは伊都の郡なるを、その西は那賀の郡にて、名手の駅にちかし、かくて花の雪の巻にも、既にいへるごとく、妹山といふ山はなし、批背ノ山の南のふもとの河中に、ほそく長き嶋ある、妹山とはそれをいふにやと思へど、批嶋は、たゞ岩のめぐりたてる中に、木の生ヒしげるたるのみにて、いさゝかも山といふばかり高きところはなし、又批嶋を背ノ山也といふも、ひがごと也、そは川の瀬にある故に、背の山とはいふと、心得誤りて、背山村といふも、批嶋によれる名と思ひためれど、然にはあらず、万葉に、せの山をこゆとあれば、かの村の山なること明らけし、川中の嶋は、いかでかこゆることあらむ、さて、又川の南にも、岸まで出たる山有りて、背ノ山と相対ひたれば、これや妹山ならむともいふべけれど、其山は、背ノ山よりやゝ高くて、山のさまも、背の山よりをゝしく見えて、妹山とはいふべくもあらず、そのうへ河のあなたにて、大道にあらず、こゆる山にあらざれば、妹の山せの山こえてといへるにも、かなはざるをや、とにかくに妹山といへるは、たゞ背の山といふ名につきての、詞のあやのみにて、いはゆる序枕詞のたぐひにぞ有ける、
130 俊成卿定家卿などの歌をあしくいひなす事[七六〇]
ちかきころ、万葉ぶりの歌をものするともがら、みだりにこゝろ高きことをいひて俊成ノ卿定家ノ卿などの歌をば、いたくつたなきやうに、たやすげにいひおとすなるは、世の歌よみどもおしなべて、神のごとたふとみかしこむを、ねたみて、あながちにいひくたさむとする、みだりごと也、そもそも批卿たちの歌、あしきことも、たえてなきにはあらざめれど、すべてのやう、いにしへより世々のあひだに、ぬけ出たるところ有て、まことにいとめでたし、しかいひおとすともがら、いかによむとも、あしもとへもよることあたはじをや、
131 物しり人もののことわりを論ずるやう[七六二]
世のものしり人、人の身のうへ、よの中のことわりなどを、さまざま心たかく、いとかしこげには論へども、といふもかくいふも、みなからぶみのおもむきにて、その垣内を出ることあたはざるは、いかにぞや、
132 歌に六義といふ事[七六三]
歌に六義といふことを、やむことなきことにするは、いと愚かなることなり、六義は、もろこしの国にて、上代の詩にさだせることにこそあれ、歌にはさらにさることなし、歌にいふは、古今集の序に、歌のさまむつ也とて、その六くさを分て、あてたるよりおこれる事なるを、そはかのもろのこしの詩にならひて、六くさには分たれども、さらにかなはぬことどもにて、そへ歌といひ、なずらへ歌といひ、たとへ歌といへるなど、此三つは、皆同じことなるを、かの詩の六義の名どもにあてむとて、しひて分たるもの也、又いはひ歌を、此うちに入レたるも、あたらず、もしいはひ歌をいれば、恋歌かなしびの歌などをも、いれずはあるべからず、そもそも此古今集の序は、すべて歌のことをば、よくも尋ねずして、たゞもろこしにて、上代の詩の事をいへるを、そのまゝにとりて書ること多くして、歌にはさらにかなはぬことがちなる中に、此六義は、殊にあたらぬことにしあれば、深く心をいれて、とかく論ふは、やくなきいたづらごと也、もろこしにて、詩のうへの六義だに、さまざま説有て、さだめがたきことなるに、いはむや歌にうつしあてては、いかでかよくかなふやうのあらむ、いはゆる古注に、おほよそむくさにわかれむことは、えあるまじきことになむといへるぞ、よくあたれる論ヒには有ける。此ノ一ト言にて、六義の論はつきたるべし、
133 物まなびはその道をよくえらびて入そむべき事[七八五]
ものまなびに心ざしたらむには、まづ師をよくえらびて、その立たるやう、教ヘのさまを、よくかむかへて、したか゛ひそむべきわざ也、さとりにぶき人は、さらにもいはず、もとより智とき人といへども、大かたはじめにしたがひそめたるかたに、おのづから心はひかるゝわざにて、その道のすぢわろけれど、わろきことをえさとらず、又後にはさとりながらも、としごろのならひは、さすがにすてがたきわざなるに、我とかいふ禍神さへ立そて、とにかくにしひごとして、なほそのすぢをたすけむとするほどに、終によき事はえ物せで、よのかぎりひがごとのみして、身ををふるたぐひなど、世におほし、かゝるたぐひの人は、つとめて深くまなべば、まなぶまにまに、いよいよわろきことのみさかりになりて、おのれまどへるのみならず、世の人をさへにまどはすことぞかし、かへすかえすはじめより、師をよくえらぶべきわざになむ、此事は、うひやまぶみにいふべかりしを、もらしてければ、こゝにはいふ也、
134 八景といふ事[七八六]
世に八景といふことの、こゝにもかしこにも多かるは、もともろこしの国の、なにがしの八景といいふをならひて、さだめたる、近江八景ぞはじめなめるを又それにならひてなりけり、さるはむげに見どころもなきところをさへに、しひて入れなどしたるがおほかるは、いかにぞや、まことにその景を賞とならば、けしきよきかぎりをとりてこそ、さだむべけれ、その数にはさらにかゝはるまじく、いくつにても有べきに、数をかたく守りて、かならず八にとゝのへむとしたるこそ、こちなくおぼゆれ、
135 よはひの賀に歌を多く集むる事 なき跡にいしぶみをたつる事[七八七]
よはひの賀に、やまともろこしくさぐさの歌を、ひろくこひももとめて集むる事、今の世に、人のおほくすることなり、みやびわざとはいへど、さる心もなきものの、みだりにふくつけく物して、たゞ数おほくあつまれるを、たけきことにすなるは、中々にこちなくぞおぼゆる、又さしもあるまじききはの人の、墓にもこと所にも、ことごとしきいしぶみをたつることも、今の世にはいと多かる、これはたあまりたぐひおほくて、めづらしげなく、中々にこゝろおとりせられて、うるさくさへこそおぼゆれ、
136 金銀ほしからぬかほする事[七八八]
金銀ほしからずといふは、例の漢やうの偽にぞ有ける、学問する人など、好書をせちに得まほしがる物から、金銀はほしからぬかほするにて、そのいつはりはあらはなるをや、いまの世よろづの物、金銀をだに出せば、心にまかせてえらるゝものを好書ほしからむには、などか金銀ほしからざらむ、燃はあれども、はゞかることなくむさぼる世のならひにくらぶれば偽ながらも、さるたぐひは、なほはるかにまさりてぞ有べき、
137 雪蛍をあつめて書よみけるもろこしのふること[八〇二]
もろこしの国に、むかし孫康といひける人は、いたくがくもんを好みけるに、家まずしくて、油をえかはざりければ、夜は、雪のひかりにて、ふみをよみ、又同じ国に、車胤といひし人も、いたく書よむ事をこのみけるを、これも同じやうにいと貧くて、油をええざりければ、夏のころは、蛍を多くあつめてなむよみける、此二つの故事は、いといと名高くして、しらぬ人なく、歌にさへなむおほくよむことなりける、今思ふに、これらもかの国人の、例の名をむさぼりたる、つくりことにぞ有ける、其故は、もし油をええずは、よるよるは、ちかどなりなどの家にものして、そのともし火の光をこひかりても、書はよむべし、たとひそのあかり心にまかせず、はつはつなりとも、雪蛍には、こよなくまさりたるべし、又年のうちに、雪蛍のあるは、しばしのほどなるに、それがなきほどは、夜ルは書よまでありけるにや、いとおかし、
や ま ぶ き 十二
われとひとしき人しなければ、といひける人も有けれど、よしやさばれおのれは
思ふこといはではやまじやまぶきも
さればぞ花の露けかるらむ
129 又妹背山[七二九]
寛政十一年春、又紀の国に物しけるをり、妹背山の事、なほよくたづねむと思ひて、ゆくさには、きの川を船よりくだりけるを、しばし、陸におりて、批山をこえ、かえるさにもこえて、くはしき尋ねける、そは紀の国ノ伊都ノ郡橋本の駅より、四里ばかり西に、背山村といふ有て、其村の山ぞ、すなわち背山なりける、いとしも高からぬ山にて紀の川の北の邊に在て、南のかたの尾さきは、川の岸までせまれり、村は、批山の東おもての腹にあり、大道は、川岸のかの尾さきのやゝ高きところを、村を北にみてこゆる、道のかたわらにも、屋どもある、それも背山村の民の屋也、批山までは伊都の郡なるを、その西は那賀の郡にて、名手の駅にちかし、かくて花の雪の巻にも、既にいへるごとく、妹山といふ山はなし、批背ノ山の南のふもとの河中に、ほそく長き嶋ある、妹山とはそれをいふにやと思へど、批嶋は、たゞ岩のめぐりたてる中に、木の生ヒしげるたるのみにて、いさゝかも山といふばかり高きところはなし、又批嶋を背ノ山也といふも、ひがごと也、そは川の瀬にある故に、背の山とはいふと、心得誤りて、背山村といふも、批嶋によれる名と思ひためれど、然にはあらず、万葉に、せの山をこゆとあれば、かの村の山なること明らけし、川中の嶋は、いかでかこゆることあらむ、さて、又川の南にも、岸まで出たる山有りて、背ノ山と相対ひたれば、これや妹山ならむともいふべけれど、其山は、背ノ山よりやゝ高くて、山のさまも、背の山よりをゝしく見えて、妹山とはいふべくもあらず、そのうへ河のあなたにて、大道にあらず、こゆる山にあらざれば、妹の山せの山こえてといへるにも、かなはざるをや、とにかくに妹山といへるは、たゞ背の山といふ名につきての、詞のあやのみにて、いはゆる序枕詞のたぐひにぞ有ける、
130 俊成卿定家卿などの歌をあしくいひなす事[七六〇]
ちかきころ、万葉ぶりの歌をものするともがら、みだりにこゝろ高きことをいひて俊成ノ卿定家ノ卿などの歌をば、いたくつたなきやうに、たやすげにいひおとすなるは、世の歌よみどもおしなべて、神のごとたふとみかしこむを、ねたみて、あながちにいひくたさむとする、みだりごと也、そもそも批卿たちの歌、あしきことも、たえてなきにはあらざめれど、すべてのやう、いにしへより世々のあひだに、ぬけ出たるところ有て、まことにいとめでたし、しかいひおとすともがら、いかによむとも、あしもとへもよることあたはじをや、
131 物しり人もののことわりを論ずるやう[七六二]
世のものしり人、人の身のうへ、よの中のことわりなどを、さまざま心たかく、いとかしこげには論へども、といふもかくいふも、みなからぶみのおもむきにて、その垣内を出ることあたはざるは、いかにぞや、
132 歌に六義といふ事[七六三]
歌に六義といふことを、やむことなきことにするは、いと愚かなることなり、六義は、もろこしの国にて、上代の詩にさだせることにこそあれ、歌にはさらにさることなし、歌にいふは、古今集の序に、歌のさまむつ也とて、その六くさを分て、あてたるよりおこれる事なるを、そはかのもろのこしの詩にならひて、六くさには分たれども、さらにかなはぬことどもにて、そへ歌といひ、なずらへ歌といひ、たとへ歌といへるなど、此三つは、皆同じことなるを、かの詩の六義の名どもにあてむとて、しひて分たるもの也、又いはひ歌を、此うちに入レたるも、あたらず、もしいはひ歌をいれば、恋歌かなしびの歌などをも、いれずはあるべからず、そもそも此古今集の序は、すべて歌のことをば、よくも尋ねずして、たゞもろこしにて、上代の詩の事をいへるを、そのまゝにとりて書ること多くして、歌にはさらにかなはぬことがちなる中に、此六義は、殊にあたらぬことにしあれば、深く心をいれて、とかく論ふは、やくなきいたづらごと也、もろこしにて、詩のうへの六義だに、さまざま説有て、さだめがたきことなるに、いはむや歌にうつしあてては、いかでかよくかなふやうのあらむ、いはゆる古注に、おほよそむくさにわかれむことは、えあるまじきことになむといへるぞ、よくあたれる論ヒには有ける。此ノ一ト言にて、六義の論はつきたるべし、
133 物まなびはその道をよくえらびて入そむべき事[七八五]
ものまなびに心ざしたらむには、まづ師をよくえらびて、その立たるやう、教ヘのさまを、よくかむかへて、したか゛ひそむべきわざ也、さとりにぶき人は、さらにもいはず、もとより智とき人といへども、大かたはじめにしたがひそめたるかたに、おのづから心はひかるゝわざにて、その道のすぢわろけれど、わろきことをえさとらず、又後にはさとりながらも、としごろのならひは、さすがにすてがたきわざなるに、我とかいふ禍神さへ立そて、とにかくにしひごとして、なほそのすぢをたすけむとするほどに、終によき事はえ物せで、よのかぎりひがごとのみして、身ををふるたぐひなど、世におほし、かゝるたぐひの人は、つとめて深くまなべば、まなぶまにまに、いよいよわろきことのみさかりになりて、おのれまどへるのみならず、世の人をさへにまどはすことぞかし、かへすかえすはじめより、師をよくえらぶべきわざになむ、此事は、うひやまぶみにいふべかりしを、もらしてければ、こゝにはいふ也、
134 八景といふ事[七八六]
世に八景といふことの、こゝにもかしこにも多かるは、もともろこしの国の、なにがしの八景といいふをならひて、さだめたる、近江八景ぞはじめなめるを又それにならひてなりけり、さるはむげに見どころもなきところをさへに、しひて入れなどしたるがおほかるは、いかにぞや、まことにその景を賞とならば、けしきよきかぎりをとりてこそ、さだむべけれ、その数にはさらにかゝはるまじく、いくつにても有べきに、数をかたく守りて、かならず八にとゝのへむとしたるこそ、こちなくおぼゆれ、
135 よはひの賀に歌を多く集むる事 なき跡にいしぶみをたつる事[七八七]
よはひの賀に、やまともろこしくさぐさの歌を、ひろくこひももとめて集むる事、今の世に、人のおほくすることなり、みやびわざとはいへど、さる心もなきものの、みだりにふくつけく物して、たゞ数おほくあつまれるを、たけきことにすなるは、中々にこちなくぞおぼゆる、又さしもあるまじききはの人の、墓にもこと所にも、ことごとしきいしぶみをたつることも、今の世にはいと多かる、これはたあまりたぐひおほくて、めづらしげなく、中々にこゝろおとりせられて、うるさくさへこそおぼゆれ、
136 金銀ほしからぬかほする事[七八八]
金銀ほしからずといふは、例の漢やうの偽にぞ有ける、学問する人など、好書をせちに得まほしがる物から、金銀はほしからぬかほするにて、そのいつはりはあらはなるをや、いまの世よろづの物、金銀をだに出せば、心にまかせてえらるゝものを好書ほしからむには、などか金銀ほしからざらむ、燃はあれども、はゞかることなくむさぼる世のならひにくらぶれば偽ながらも、さるたぐひは、なほはるかにまさりてぞ有べき、
137 雪蛍をあつめて書よみけるもろこしのふること[八〇二]
もろこしの国に、むかし孫康といひける人は、いたくがくもんを好みけるに、家まずしくて、油をえかはざりければ、夜は、雪のひかりにて、ふみをよみ、又同じ国に、車胤といひし人も、いたく書よむ事をこのみけるを、これも同じやうにいと貧くて、油をええざりければ、夏のころは、蛍を多くあつめてなむよみける、此二つの故事は、いといと名高くして、しらぬ人なく、歌にさへなむおほくよむことなりける、今思ふに、これらもかの国人の、例の名をむさぼりたる、つくりことにぞ有ける、其故は、もし油をええずは、よるよるは、ちかどなりなどの家にものして、そのともし火の光をこひかりても、書はよむべし、たとひそのあかり心にまかせず、はつはつなりとも、雪蛍には、こよなくまさりたるべし、又年のうちに、雪蛍のあるは、しばしのほどなるに、それがなきほどは、夜ルは書よまでありけるにや、いとおかし、
玉勝間十三の巻
お も ひ 草 十三
末ひろくしげるけりかな思ひ草
を花が本は一もとにして
かくよめるこゝろは、恋の歌につねに、尾花がもとの思ひ草とよむなるは、そのはじめを尋ぬれば、万葉集の十の巻に、「道のべのをばなが本の思草、今さらに何物か思はむ、といへる歌たゞ一ツあるのみにて、これをおきては見えぬ事なるを、此一本によりてなむ、後にはひろくよむこととなれるよしをよめるにぞ有ける、そもそも此思ひ草といふ草は、いかなる草にか、さだかならぬを、一とせ尾張の名古屋の、田中ノ道麻呂が許より、文のたよりに、今の世にも、思ひ草といひて、すゝきの中に生る、小き草なむあるを高さ三四寸、あるは五六寸ばかりにて、秋の末に花さくを、其色紫の黒みたるにて、うち見たるは、菫の花に似て、すみれのごと、色のにほひはなし、花さくころは、葉はなし、此草薄の中ならでは、ほかには生ず、花のはしつかたなる所の中に、黒大豆ばかりの大キさる実のあるを、とりてまけば、よく生る也、されどそれも、薄の下ならでは、まけども植れども、生ることなし、古ヘの思ひ草も、これにやあらむ、されどすゝきの中にのみ生るから、近き世に事好むものの、おしてそれと名づけたるにもあらむかといひて、其草のカタをも書て、見せにおこせたる、そのかたは、かくぞ有ける、其後に又あるとき、花の咲たるころ、一もとほりて、薄のきりくひごめに、竹の筒の中にうゑて、たゞに其草をも、見せにおこせたるを、うつしうゑて見けるに、しばしは生つきたるさまにて有しを、ほどなく冬枯にける、又のとしの春、もえや出ると、まちけるに、つひにかれて、薄ながらに芽も出ずなりにきかし、さるは後にたづね見れば、此わたりの野山なる、すゝきの中にも、ある草にぞ有ける、これ古の思草ならむことはしも、げにいとおほつかなくなむ、
138 しづかなる山林をすみよしといふ事[八五〇]
世々の物しり人、又今の世に学問する人などもみな、すみかは、里とほくしづかなる山林を、住よくこのましくするさまにのみいふなるを、われはいかなるにか、さらにさはおぼえず、たゞ人げしげくにぎはゝしきところの、好ましくて、さる世ばなれたるところなどは、さびしくて、心もしをるゝやうにぞおぼゆる、さるはまれまれにものして、一夜たびねしたるなどこそは、めづらかなるかたに、おかしくもおぼゆれ、さる所に、つねにすままほしくは、さらにおぼえずなむ、人の心はさまざまなれば、人うとくしづかならむところを、すみよくおぼえむもさることにて、まことにさ思はむ人も、よには多かりぬべけれど、又例のつくりことの、漢ぶりの人まねに、さいひなして、なべての世の人の心と、ことなるさまに、もてなすたぐひも、中には有ぬべくや、かく疑はるゝも、おのが俗情のならひにこそ、
139 おのが京のやどりの事[八五一]
のりなが、享和のはじめのとし、京にのぼりて在しほど、やどれりしところは、四條大路の南づらの、烏丸のひむかしなる所にぞ有けるを、家はやゝおくまりてなむ有けれど朝のほど夕ぐれなどには、門に立出つゝ見るに、道もひろくはればれしきに、ゆきかふ人しげく、いとにぎはゝしきは、ゐなかに住なれたるめうつし、こよなくて、めさむるこゝちなむしける、京といへど、なべてはかくしもあらぬを、此四條大路などは、ことににぎはゝしくなむありける、天の下三ところの大都の中に、江戸大坂は、あまり人のゆきゝぬ多く、らうがはしきを、よきほどのにぎはひにて、よろづの社々寺々など、古のよしあるおほく、思ひなしたふとく、すべて物きよらに、よろづの事みやびたるなど、天ノ下に、すままほしき里は、さはいへど京をおきて、外にはなかりけり、
140 しちすつの濁音の事[九〇一]
土佐ノ国の人の言には、しとちと、すとつとのにごり声、おのづからよく分れて、混ふことなし、さればわづかにいろはもじをかくほどの童といへども、此仮字をば、書キ誤ることなしと、かの国人かたれり、
お も ひ 草 十三
末ひろくしげるけりかな思ひ草
を花が本は一もとにして
かくよめるこゝろは、恋の歌につねに、尾花がもとの思ひ草とよむなるは、そのはじめを尋ぬれば、万葉集の十の巻に、「道のべのをばなが本の思草、今さらに何物か思はむ、といへる歌たゞ一ツあるのみにて、これをおきては見えぬ事なるを、此一本によりてなむ、後にはひろくよむこととなれるよしをよめるにぞ有ける、そもそも此思ひ草といふ草は、いかなる草にか、さだかならぬを、一とせ尾張の名古屋の、田中ノ道麻呂が許より、文のたよりに、今の世にも、思ひ草といひて、すゝきの中に生る、小き草なむあるを高さ三四寸、あるは五六寸ばかりにて、秋の末に花さくを、其色紫の黒みたるにて、うち見たるは、菫の花に似て、すみれのごと、色のにほひはなし、花さくころは、葉はなし、此草薄の中ならでは、ほかには生ず、花のはしつかたなる所の中に、黒大豆ばかりの大キさる実のあるを、とりてまけば、よく生る也、されどそれも、薄の下ならでは、まけども植れども、生ることなし、古ヘの思ひ草も、これにやあらむ、されどすゝきの中にのみ生るから、近き世に事好むものの、おしてそれと名づけたるにもあらむかといひて、其草のカタをも書て、見せにおこせたる、そのかたは、かくぞ有ける、其後に又あるとき、花の咲たるころ、一もとほりて、薄のきりくひごめに、竹の筒の中にうゑて、たゞに其草をも、見せにおこせたるを、うつしうゑて見けるに、しばしは生つきたるさまにて有しを、ほどなく冬枯にける、又のとしの春、もえや出ると、まちけるに、つひにかれて、薄ながらに芽も出ずなりにきかし、さるは後にたづね見れば、此わたりの野山なる、すゝきの中にも、ある草にぞ有ける、これ古の思草ならむことはしも、げにいとおほつかなくなむ、
138 しづかなる山林をすみよしといふ事[八五〇]
世々の物しり人、又今の世に学問する人などもみな、すみかは、里とほくしづかなる山林を、住よくこのましくするさまにのみいふなるを、われはいかなるにか、さらにさはおぼえず、たゞ人げしげくにぎはゝしきところの、好ましくて、さる世ばなれたるところなどは、さびしくて、心もしをるゝやうにぞおぼゆる、さるはまれまれにものして、一夜たびねしたるなどこそは、めづらかなるかたに、おかしくもおぼゆれ、さる所に、つねにすままほしくは、さらにおぼえずなむ、人の心はさまざまなれば、人うとくしづかならむところを、すみよくおぼえむもさることにて、まことにさ思はむ人も、よには多かりぬべけれど、又例のつくりことの、漢ぶりの人まねに、さいひなして、なべての世の人の心と、ことなるさまに、もてなすたぐひも、中には有ぬべくや、かく疑はるゝも、おのが俗情のならひにこそ、
139 おのが京のやどりの事[八五一]
のりなが、享和のはじめのとし、京にのぼりて在しほど、やどれりしところは、四條大路の南づらの、烏丸のひむかしなる所にぞ有けるを、家はやゝおくまりてなむ有けれど朝のほど夕ぐれなどには、門に立出つゝ見るに、道もひろくはればれしきに、ゆきかふ人しげく、いとにぎはゝしきは、ゐなかに住なれたるめうつし、こよなくて、めさむるこゝちなむしける、京といへど、なべてはかくしもあらぬを、此四條大路などは、ことににぎはゝしくなむありける、天の下三ところの大都の中に、江戸大坂は、あまり人のゆきゝぬ多く、らうがはしきを、よきほどのにぎはひにて、よろづの社々寺々など、古のよしあるおほく、思ひなしたふとく、すべて物きよらに、よろづの事みやびたるなど、天ノ下に、すままほしき里は、さはいへど京をおきて、外にはなかりけり、
140 しちすつの濁音の事[九〇一]
土佐ノ国の人の言には、しとちと、すとつとのにごり声、おのづからよく分れて、混ふことなし、さればわづかにいろはもじをかくほどの童といへども、此仮字をば、書キ誤ることなしと、かの国人かたれり、
玉かつま十四の巻
つ ら つ ら 椿 十四
萬葉集の一の巻に、巨勢山のつらつら椿つらつらに、といふ歌をおもひ出て、われもよめるは、
世中をつらつらつばきつらつらに
思へばおもふことぞおほかる
さるはわがみのうへのうれへにもあらず、なべての世のたゝずまひ、人のありさまの、よきあしきことにつけて、おふけなく思ふすぢの、心にこめがたきは、おりおり此巻々にも、もらせるふしもおほかれど、猶いひてもいひても、つきすべくもあらずなむ、
141 一言一行によりてひとのよしあしきをさだむる事[九三五]
人のたゞ一言(ヒトコト)たゞ一行(ヒトワザ)によりて、其人のすべての善(ヨ)き悪きを、定めいふは、から書のつねなれども、これいとあたらぬこと也すべてよきひとといへども、まれにはことわりにかなはぬしわざも、まじらざるにあらず、あしき人といへども、よきしわざみまじるものにて、生(イケ)るかぎりのしわざ、ことごとに善き悪き一かたにさだまれる人は、をさをさなきものなるを、いかでかはたゞ一言一行によりては定むべき、
142 今の世の名の事[九三六]
近き世の人の名には、名に似つかはしからぬ字をつくこと多し、又すべて名の訓は、よのつねならぬがおほきうちに、近きころの名には、ことにあやしき字、あやしき訓有て、いかにともよみがたきぞ多く見ゆる、すべて名は、いかにもやすらかなるもじの、訓のよくしられたるこそよけれ、これに名といふは、いはゆる名乗実名也、某(ナニ)右衛門某(ナニ)兵衛のたぐひの名のことにあらず、さてまた其人の性(シヤウ)といふ物にあはせて、名をつくるは、いふにもたらぬ、愚なるならひ也、すべて人に、火性水性など、性といふことは、さらなきことなり、又名のもじの、反切といふことをえらぶも、いと愚也、反切といふものは、たゞ字の音をさとさむ料にこそあれ、いかでかは人の名、これにあづからむ、
143 絵の事[九五二]
人の像を写すことは、つとめてその人の形に似むことを要す、面やうはさらにもいはず、そのなりすがた衣服のさまにいたるまで、よく似たらむと心すべし、されば人の像は、つとめてくはしくこまかにうつすべきことなり、然るに今の世には、人の像を写すとても、ただおのが筆のいきおひを見せんとし、絵のさまを雅にせむとするほどに、まことの形にはさらに似ず、又真の形に似むことをば要せず、ただ筆の勢ひを見せ、絵のさまを雅にせんとすることをむねとするから、すべてことそぎてくはしからず、さらさらとかくゆに、面やうなど、その人に似ざるのみならず、甚いやしき賎やまがつのかほやうにて、さらに君子有徳の人のかほつきにあらず、これいとにくむべきことなり、
144 又[九五三]
古人の像をかくには、その面やういかにありけむ知がたければ、たゞその人の位にかなへ、徳にかなへて、位たかき人のかたは、面ようすべてのさまけたかく、まことにたかき人と見ゆるように書クべく、徳ありし人は、又その徳にかなへてかくべし、然るに後の絵師、この意を思はず、たゞおのが筆の勢ひを見せむとのみするほどに、位たかき人、徳ある人も、ただしず山がつの如く、愚味なる人の如くかきなせり、
145 又[九五四]
かほよき女のかたちをかくとても、例のたゞおのが筆のいきほいおのみをのみむねとしてかくほどに、そのかほ見にくやかなり、あまりなまめかしくかほよくかけば、絵のさまいやしくなるといふめれど、そはおのが絵のつたなきなり、かほよくてゑのさまいやしからぬやうにこそ書べけれ、己が絵がらのいやしくなるをいとひて、かほよき人を見にくゝかくべきいはれなし、美女のかほは、いかにもいかにもかほよくかくべきなり、みにくやかなるはいといと心づきなし、但し今の世に、江戸絵といふゑなどは、しひてあながちにかほよくせんとするほどに、ゑのさまのいやしき事はさらにもいはず、中々にかほ見にくゝ見えて、いとつたなきことおほし、
146 又[九五五]
世に武者絵といひて、たけき人の戦ひのさまをかく、其かほやう人とも見えず、目丸く大きに、鼻いかり口大きにて、すべて鬼のごとし、いかにたけきさまを見せむとすればとて、人にもあらず、しか鬼のやうには書べきわざかは、ただおだやかに人と見えて、しかもたけきいきほひあるさまにこそかくべけれ、或から書に、皇國の絵の事をいへるに、その人夜叉羅刹の如しといへり、思ふにこの鬼の如くかける武者絵を見ていへるなるべし、されどかの國人は皇國人のさまおば見しらねば、さいへる書をよみては、日本人のかほはすべてみな、鬼の如くなる物とぞ心得らむ、すべての事、皇國人は、もろこしの事は、から國のもろもろの書をよむゆゑに、よくしれるを、もろこし人は、皇國の書をよむことなければ、皇國の事はしらず、まれまれには、かに國の書の中にいへることあれば、それを定(デウ)として心得ることぞかし、皇國の人物の絵も、異國の人の見ては、それをでうとすることなれば、かの位高き人のかほを山がつのごとくいやしく書キなし、かほよき女のかほを見にくゝかきなせるなどを、異國人の見たらむには、日本人の形いやしく女もみな見にくきことぞとぞ心得べき、こは異國人のみにもあらず、同じ皇國人にても、しらぬ昔の人のかほは、絵にかけるを一度見れば、おのづからそのおもかげを、その人のかほと思はるゝ物ぞかし、
147 また[九五六]
おのれ、絵のことはさらにしらねば、とかくいふべきにあらざるに似たれども、よろずのことおのがよきあしきはえしらで、かたはらよりはよく見ゆるものなり、もろもろの藝などもそのでうにて、その道の人は、なかなかにえしらで、かへりて他よりよきあしきさまのよく見ゆることあり、絵もさる心ばへあれば、今おのが思ふすぢをいふなり、まづやまともろこしの古より、代々の絵の事は、あまたも見あつめず、くはしくしらねば、さしおきて、たゞ今の世につねに見およぶところをもていはん、そはまづ、墨絵、うすざいしき、ごくざいしきなど、さまざまある中に、墨絵といふは、たゞ墨をべたべたと書て、筆数すくなく、よろづをことそぎて、かろがろとかきて、その物と見ゆる、こはたゞ筆の力いきほひを見せたる物なれば、至りて上手のかけるは、げにかうも書べしとおぼえて、見どころあるもあれど、おしなべての絵師のかけるは、見どころなく心づきなきものなり、さるを世の人、たゞ此墨絵をことにいみしきことにしてめづるは、世のならひにしたがふ心にて、まことにはみどころなきものなり、近き世に茶の湯といふわざを好むともがらなど、殊に此墨絵をのみめでて、さいしき絵はすべてとらず、これもその人々、まことにしか思ひとれるにはあらず、たゞその道の祖のさだめおきつる心ばへを守りて、しかるなり、すべて此茶の湯にめづる筋は、絵も、書も、さらに見どころなくおかしからなるを、かたくまもりてたふとむは、いといとかたくななることなり、さてうすざいしきは、なつかしくやはらびておかし、ごくさいしきいといふにいたりては、物によりてめでたきもあり、又まれにはあまりこちたく見えてうるさき所もあるなり、水を紺青といふ物にしてかけるたぐひ、ことにこちたし、さて絵の流、さまざまある中に、むかしよりこれを業とたてたる家々あり、大かた此家々の絵は、その家々の伝ありて、法をのみ重くまもりて、必しもその物のまこともさまをばとはず、此家といふすぢの絵に、よきことありあしきことあり、まずかの位たかき人のかほのいやしげに見え、美女のかほふくらかにて見にくきなど、いといとこゝろづきなし、又人の衣服のきは、折目などの筋を、いとふとくかけるもかたはなり、これみな、筆の力を見せむとするしわざなり、もろこしの松をかくに、一種から松といひて、必ことなる松をかくは、思ふにむかしかの國人のかける絵に、さるさまの松ありけむをならひつたへたるならむ、これから國にさやうのまつの、一種あるにはあらず、たゞ世のつねの松なるを、かきさまのつづきなきは、つたなくかける墨絵、このからまつ、人物の衣の折目の筋ふとき、さてはだるま、布袋、福禄寿などいふもののかた、すべて是ら、一目見るもうるさく、二度と見やらんとおぼえずなん、大かた旧き定めをばまもるは、いとよきことなれども、そは事により、物にこそよるべけれ、絵などは必しも然るべからず、他のよきを見て、うつることあたはざるはいとかたくななり、されど又、家の法といふ中に、いといとよろしく、まことに、屋上を去て内を見する事、雲をへだてて遠近をわかつこと、さるべきことにて、その法にはずれては、いとあやしきこともおほくして、今時のこゝろにまかせれかきちらすゑどもの、及びがたき事もおほかりかし、又今の世に、もろこしのふりとてまねびたるさまざまあり、その大かたは、まづ何をかくにも、まことの物のやうをよく見てまねびかく、これを生(シヤウ)うつしとかいふ、こはまことによろしかるべくおぼゆることなり、しかれども、まことの物と絵とはことなることもありて、まことのあるまゝにかきては、かへりて其物に似ずして、あしきこともある物なり、故にかの家々には法ありて、かならずしもその物のまことのまゝにはかゝはらぬ事あるなり、こは法のいみしくしてすてがたき物なり、まづ山水といふ絵、すべてこゝの家々の絵よろし、もろこそやうはいといとわろくこちなく見ぐるしきことおほし、これその法によらずして、心にまかせてかくゆゑなり、あるひは道あるまじき所に道をかき、橋あるまじき所に橋をかき、その外いはほ草木など、かきてわろき所にかき、おほくてよき所にはすくなく、おほくてわろきところにおほくかくたぐひ、すべてもののかきどころわろく、草木岩根のたゝずまひ、さかしきみねのさまなど、つたなく見ぐるしきこと、大かたこれらは上手の絵の中にも此なむはあるなり、かの家々のはかゝることもみな法ありてかくゆゑにつたなからず、又から絵に舟をかくに斜めにかくことおほきもいたくわろし、大かた船のゆくゆくことはなゝめにみゆることつねにあれども、ゑにかきてはわろきなり、なゝめによらず、たゞまことの物のまゝにかくゆゑの失なり、又鳥虫をかくにこまかにくはしくはあれども、飛動くさまの勢ひなきがおほし、草木をかくに葉も茎も地との際の筋をかゝず、これわろし、是また際の筋は実はなき物なればじつによれるなれども、絵にかくときはすじなくてはあざやかにわかれず、すべてよろずの物、その実の物は、何もなき所が地にて、何もなき所は色なき物なるを、絵は白きが地にして、何もなき所が白し、その白き所へかくことなれば、実の何もなき空の地とは異なれば、きはの筋なきことあたはず、から絵に此筋のなきは此わきまへをしらざるなり、人の面をかくにはから絵といへども、地とのきはの筋をかゝざる事を得ず、又から絵は、木の枝ざし、草花のもとだち、葉のあり所など、法なきが如くにて、心にまかせてかくゆゑに、とりしまりなし、家の画はみな法ありとおぼしくて、とりしまりよくつたなきことなし、大かたこれらなべての唐画のつたなき所なり、しかれども唐絵は、鳥獣蟲魚草木など、すべて此方の家の画とくらぶれば、甚くはしここまかにかくゆゑに、じょうずのかけるはまことに、上手のかけるはまことに眞のその物のごとく見ゆるを、此方の家々の絵は、獣の毛のさま、草木の花のしべ、葉のあやなど、すべてあらくかける故に、くらべて見ればからゑにけおさるゝ事おほし、こは広き家の屏風壁などの絵は、やゝ遠く見ゆる物なる故に、あまりこまかにくはしくかけるは詮なく、中々によろしからざる事として、さらさらと書るをよしとするなるべけれど、猶こまかにくはしき唐画の方ぞまさりて見ゆる、大かた此家々の画と、唐絵とたがひにえたる所、得ぬ所ありて、勝劣をいひがたき事上件の如し、又ちかきころは、家の法にも菜づ先ず、唐絵のかきざまにもかたよらず、たゞおのが心もて、いづかたにまれよしとおぼゆるところをとりてかくたぐひも多き、そのすぢはよきをえらびわろきをすてて画ゆゑに、いづれもいみしきなんはをさをさ見えざるなり、
つ ら つ ら 椿 十四
萬葉集の一の巻に、巨勢山のつらつら椿つらつらに、といふ歌をおもひ出て、われもよめるは、
世中をつらつらつばきつらつらに
思へばおもふことぞおほかる
さるはわがみのうへのうれへにもあらず、なべての世のたゝずまひ、人のありさまの、よきあしきことにつけて、おふけなく思ふすぢの、心にこめがたきは、おりおり此巻々にも、もらせるふしもおほかれど、猶いひてもいひても、つきすべくもあらずなむ、
141 一言一行によりてひとのよしあしきをさだむる事[九三五]
人のたゞ一言(ヒトコト)たゞ一行(ヒトワザ)によりて、其人のすべての善(ヨ)き悪きを、定めいふは、から書のつねなれども、これいとあたらぬこと也すべてよきひとといへども、まれにはことわりにかなはぬしわざも、まじらざるにあらず、あしき人といへども、よきしわざみまじるものにて、生(イケ)るかぎりのしわざ、ことごとに善き悪き一かたにさだまれる人は、をさをさなきものなるを、いかでかはたゞ一言一行によりては定むべき、
142 今の世の名の事[九三六]
近き世の人の名には、名に似つかはしからぬ字をつくこと多し、又すべて名の訓は、よのつねならぬがおほきうちに、近きころの名には、ことにあやしき字、あやしき訓有て、いかにともよみがたきぞ多く見ゆる、すべて名は、いかにもやすらかなるもじの、訓のよくしられたるこそよけれ、これに名といふは、いはゆる名乗実名也、某(ナニ)右衛門某(ナニ)兵衛のたぐひの名のことにあらず、さてまた其人の性(シヤウ)といふ物にあはせて、名をつくるは、いふにもたらぬ、愚なるならひ也、すべて人に、火性水性など、性といふことは、さらなきことなり、又名のもじの、反切といふことをえらぶも、いと愚也、反切といふものは、たゞ字の音をさとさむ料にこそあれ、いかでかは人の名、これにあづからむ、
143 絵の事[九五二]
人の像を写すことは、つとめてその人の形に似むことを要す、面やうはさらにもいはず、そのなりすがた衣服のさまにいたるまで、よく似たらむと心すべし、されば人の像は、つとめてくはしくこまかにうつすべきことなり、然るに今の世には、人の像を写すとても、ただおのが筆のいきおひを見せんとし、絵のさまを雅にせむとするほどに、まことの形にはさらに似ず、又真の形に似むことをば要せず、ただ筆の勢ひを見せ、絵のさまを雅にせんとすることをむねとするから、すべてことそぎてくはしからず、さらさらとかくゆに、面やうなど、その人に似ざるのみならず、甚いやしき賎やまがつのかほやうにて、さらに君子有徳の人のかほつきにあらず、これいとにくむべきことなり、
144 又[九五三]
古人の像をかくには、その面やういかにありけむ知がたければ、たゞその人の位にかなへ、徳にかなへて、位たかき人のかたは、面ようすべてのさまけたかく、まことにたかき人と見ゆるように書クべく、徳ありし人は、又その徳にかなへてかくべし、然るに後の絵師、この意を思はず、たゞおのが筆の勢ひを見せむとのみするほどに、位たかき人、徳ある人も、ただしず山がつの如く、愚味なる人の如くかきなせり、
145 又[九五四]
かほよき女のかたちをかくとても、例のたゞおのが筆のいきほいおのみをのみむねとしてかくほどに、そのかほ見にくやかなり、あまりなまめかしくかほよくかけば、絵のさまいやしくなるといふめれど、そはおのが絵のつたなきなり、かほよくてゑのさまいやしからぬやうにこそ書べけれ、己が絵がらのいやしくなるをいとひて、かほよき人を見にくゝかくべきいはれなし、美女のかほは、いかにもいかにもかほよくかくべきなり、みにくやかなるはいといと心づきなし、但し今の世に、江戸絵といふゑなどは、しひてあながちにかほよくせんとするほどに、ゑのさまのいやしき事はさらにもいはず、中々にかほ見にくゝ見えて、いとつたなきことおほし、
146 又[九五五]
世に武者絵といひて、たけき人の戦ひのさまをかく、其かほやう人とも見えず、目丸く大きに、鼻いかり口大きにて、すべて鬼のごとし、いかにたけきさまを見せむとすればとて、人にもあらず、しか鬼のやうには書べきわざかは、ただおだやかに人と見えて、しかもたけきいきほひあるさまにこそかくべけれ、或から書に、皇國の絵の事をいへるに、その人夜叉羅刹の如しといへり、思ふにこの鬼の如くかける武者絵を見ていへるなるべし、されどかの國人は皇國人のさまおば見しらねば、さいへる書をよみては、日本人のかほはすべてみな、鬼の如くなる物とぞ心得らむ、すべての事、皇國人は、もろこしの事は、から國のもろもろの書をよむゆゑに、よくしれるを、もろこし人は、皇國の書をよむことなければ、皇國の事はしらず、まれまれには、かに國の書の中にいへることあれば、それを定(デウ)として心得ることぞかし、皇國の人物の絵も、異國の人の見ては、それをでうとすることなれば、かの位高き人のかほを山がつのごとくいやしく書キなし、かほよき女のかほを見にくゝかきなせるなどを、異國人の見たらむには、日本人の形いやしく女もみな見にくきことぞとぞ心得べき、こは異國人のみにもあらず、同じ皇國人にても、しらぬ昔の人のかほは、絵にかけるを一度見れば、おのづからそのおもかげを、その人のかほと思はるゝ物ぞかし、
147 また[九五六]
おのれ、絵のことはさらにしらねば、とかくいふべきにあらざるに似たれども、よろずのことおのがよきあしきはえしらで、かたはらよりはよく見ゆるものなり、もろもろの藝などもそのでうにて、その道の人は、なかなかにえしらで、かへりて他よりよきあしきさまのよく見ゆることあり、絵もさる心ばへあれば、今おのが思ふすぢをいふなり、まづやまともろこしの古より、代々の絵の事は、あまたも見あつめず、くはしくしらねば、さしおきて、たゞ今の世につねに見およぶところをもていはん、そはまづ、墨絵、うすざいしき、ごくざいしきなど、さまざまある中に、墨絵といふは、たゞ墨をべたべたと書て、筆数すくなく、よろづをことそぎて、かろがろとかきて、その物と見ゆる、こはたゞ筆の力いきほひを見せたる物なれば、至りて上手のかけるは、げにかうも書べしとおぼえて、見どころあるもあれど、おしなべての絵師のかけるは、見どころなく心づきなきものなり、さるを世の人、たゞ此墨絵をことにいみしきことにしてめづるは、世のならひにしたがふ心にて、まことにはみどころなきものなり、近き世に茶の湯といふわざを好むともがらなど、殊に此墨絵をのみめでて、さいしき絵はすべてとらず、これもその人々、まことにしか思ひとれるにはあらず、たゞその道の祖のさだめおきつる心ばへを守りて、しかるなり、すべて此茶の湯にめづる筋は、絵も、書も、さらに見どころなくおかしからなるを、かたくまもりてたふとむは、いといとかたくななることなり、さてうすざいしきは、なつかしくやはらびておかし、ごくさいしきいといふにいたりては、物によりてめでたきもあり、又まれにはあまりこちたく見えてうるさき所もあるなり、水を紺青といふ物にしてかけるたぐひ、ことにこちたし、さて絵の流、さまざまある中に、むかしよりこれを業とたてたる家々あり、大かた此家々の絵は、その家々の伝ありて、法をのみ重くまもりて、必しもその物のまこともさまをばとはず、此家といふすぢの絵に、よきことありあしきことあり、まずかの位たかき人のかほのいやしげに見え、美女のかほふくらかにて見にくきなど、いといとこゝろづきなし、又人の衣服のきは、折目などの筋を、いとふとくかけるもかたはなり、これみな、筆の力を見せむとするしわざなり、もろこしの松をかくに、一種から松といひて、必ことなる松をかくは、思ふにむかしかの國人のかける絵に、さるさまの松ありけむをならひつたへたるならむ、これから國にさやうのまつの、一種あるにはあらず、たゞ世のつねの松なるを、かきさまのつづきなきは、つたなくかける墨絵、このからまつ、人物の衣の折目の筋ふとき、さてはだるま、布袋、福禄寿などいふもののかた、すべて是ら、一目見るもうるさく、二度と見やらんとおぼえずなん、大かた旧き定めをばまもるは、いとよきことなれども、そは事により、物にこそよるべけれ、絵などは必しも然るべからず、他のよきを見て、うつることあたはざるはいとかたくななり、されど又、家の法といふ中に、いといとよろしく、まことに、屋上を去て内を見する事、雲をへだてて遠近をわかつこと、さるべきことにて、その法にはずれては、いとあやしきこともおほくして、今時のこゝろにまかせれかきちらすゑどもの、及びがたき事もおほかりかし、又今の世に、もろこしのふりとてまねびたるさまざまあり、その大かたは、まづ何をかくにも、まことの物のやうをよく見てまねびかく、これを生(シヤウ)うつしとかいふ、こはまことによろしかるべくおぼゆることなり、しかれども、まことの物と絵とはことなることもありて、まことのあるまゝにかきては、かへりて其物に似ずして、あしきこともある物なり、故にかの家々には法ありて、かならずしもその物のまことのまゝにはかゝはらぬ事あるなり、こは法のいみしくしてすてがたき物なり、まづ山水といふ絵、すべてこゝの家々の絵よろし、もろこそやうはいといとわろくこちなく見ぐるしきことおほし、これその法によらずして、心にまかせてかくゆゑなり、あるひは道あるまじき所に道をかき、橋あるまじき所に橋をかき、その外いはほ草木など、かきてわろき所にかき、おほくてよき所にはすくなく、おほくてわろきところにおほくかくたぐひ、すべてもののかきどころわろく、草木岩根のたゝずまひ、さかしきみねのさまなど、つたなく見ぐるしきこと、大かたこれらは上手の絵の中にも此なむはあるなり、かの家々のはかゝることもみな法ありてかくゆゑにつたなからず、又から絵に舟をかくに斜めにかくことおほきもいたくわろし、大かた船のゆくゆくことはなゝめにみゆることつねにあれども、ゑにかきてはわろきなり、なゝめによらず、たゞまことの物のまゝにかくゆゑの失なり、又鳥虫をかくにこまかにくはしくはあれども、飛動くさまの勢ひなきがおほし、草木をかくに葉も茎も地との際の筋をかゝず、これわろし、是また際の筋は実はなき物なればじつによれるなれども、絵にかくときはすじなくてはあざやかにわかれず、すべてよろずの物、その実の物は、何もなき所が地にて、何もなき所は色なき物なるを、絵は白きが地にして、何もなき所が白し、その白き所へかくことなれば、実の何もなき空の地とは異なれば、きはの筋なきことあたはず、から絵に此筋のなきは此わきまへをしらざるなり、人の面をかくにはから絵といへども、地とのきはの筋をかゝざる事を得ず、又から絵は、木の枝ざし、草花のもとだち、葉のあり所など、法なきが如くにて、心にまかせてかくゆゑに、とりしまりなし、家の画はみな法ありとおぼしくて、とりしまりよくつたなきことなし、大かたこれらなべての唐画のつたなき所なり、しかれども唐絵は、鳥獣蟲魚草木など、すべて此方の家の画とくらぶれば、甚くはしここまかにかくゆゑに、じょうずのかけるはまことに、上手のかけるはまことに眞のその物のごとく見ゆるを、此方の家々の絵は、獣の毛のさま、草木の花のしべ、葉のあやなど、すべてあらくかける故に、くらべて見ればからゑにけおさるゝ事おほし、こは広き家の屏風壁などの絵は、やゝ遠く見ゆる物なる故に、あまりこまかにくはしくかけるは詮なく、中々によろしからざる事として、さらさらと書るをよしとするなるべけれど、猶こまかにくはしき唐画の方ぞまさりて見ゆる、大かた此家々の画と、唐絵とたがひにえたる所、得ぬ所ありて、勝劣をいひがたき事上件の如し、又ちかきころは、家の法にも菜づ先ず、唐絵のかきざまにもかたよらず、たゞおのが心もて、いづかたにまれよしとおぼゆるところをとりてかくたぐひも多き、そのすぢはよきをえらびわろきをすてて画ゆゑに、いづれもいみしきなんはをさをさ見えざるなり、
148 漢ふみにしるせる事みだりに信ずまじき事[九五七]
世の学者、ことの疑はしきを、から画にしかしか見えたりといへば、疑はず信ずるはいとをこなり、すべて漢籍、うきたる事、ひがこと、そら言いと多し、その言よきにまどひて、みだりに信ずべきにあらず、
149 世の中の萬の事は皆神の御しわざなる事[九五九]
世の中のよろづのことはみなあやしきを、これ奇しく妙なる神の御しわざなることをえしらずして、己がおしはかりの理を以ていふはいとをこなり、いかにともしられぬ事を理を以てとかくいふは、から人のくせなり、そのいふところの理は、いかさまにもいへばいはるゝ物ぞ、かれいにしへのから人のいひおける理、後世にいたりてひがことなることのあらはれたる事おほし、またつひに理のはかりがたきことにあへば、これを天といひてのがるゝ、みな神ある事をしらざるゆゑなり、
150 聖人を尊む事[九六〇]
世々のもろこし人おしなべて、かの國の聖人といふ物を尊み信ずる中には、実に尊みしんずるひともあるべく、又こゝろにはいかにぞや思ふことあれども、聖人にたがひては世の人のそしりてうけぬことなるによりて、尊み信ずるかほして、世にしたがへるもありげに見ゆるなり、又もろもろの聖人どものなかに、孔子は、かの國の王にあらず、もはらその道の人なるがゆゑに、あるが中に此人をばことに尊み信ずめるは、これつとめてこれをほめたてて、その道を張むとするなり、
151 ト筮[九六一]
もろこしの國とても、いと上代には、後世のごとく、萬の事、己がおしはかりの理を以て定むる事は、さしもあらざりしこと、ト筮といふ物あるをもてしるべし、ト筮は己が心にさだめがたき事を、神にこひてその教えをうけて定むるわざなり、ト筮にいづるは、かみのをしへなり、然るを後世のごとく、己がこころをもて、物の理をはかりて、さだむることは、大かた周公旦といふさかしら人より、盛んにその風になれるなり、
152 から人の語かしこくいひとれること[九六三]
むかしより、世々に、もろこしひとのいへる、名たかき語どもをおもふに、たゞかしこく物にたとへもし、又たゞにても、おかしくいひとれるのみにこそあれ、そのこゝろは、学文もせぬつねの人も、心かしこきは、大かたみなもとよりよく心得たる事にて、さしもこゝろに及ばずめづらしき事はなし、されどよくいひとれるがかしこさに、げにさこそはあれと、みな人は感ずるなり、
153 論語[九六四]
論語の雍也篇の朱注に、仲弓蓋シ未喩夫子可字可字之意云々といへり、朱熹、つねに格物致知を教ふ、しかるに仲弓は孔丘が高弟なるに、いまだ可の字の意をだに喩らぬは、いかでか致知えを得む、孔丘が高弟すら、かくに如くならむには、常人はいかでかこれを得ん、大かた朱学の牽強付会みなかくの如し、
154 又[九六七]
同書に子曰、孰レカ謂微生高ヲ直シト、或乞ヘルニ醯ヲ焉、乞テ諸其隣ニ而与フ之ヲとあり、聖人の教えの刻酷なることかくの如し、これらはたゞいさゝかの事にて、さしも不直といふべきほどの事にあらず、かほどの事さえ、不直といひてとがむるは、あまりのことなり、又たとひ此事は、実に不直にもせよ、いさゝかなる此一事によりてその人を不直なりと定むるも、いといとあたらぬ事なり、すべてよき人にもあやまちわろき事はあるものなり、あしき人にもよき事もあるものなるを、たゞ一事の善悪によりて、その人のよしあしを定むるは、聖人の道のくせにて、ひがことなり、
155 又[九六八]
同書に、厩焚タリ、子退テ朝ヨリ曰、傷人乎、不問馬ヲ、これ甚いかがなり、すべての人の家の焚んにも、人はさしもやかるゝ物にあらず、馬はよくやかるゝものなり、まして馬屋のやけんには、ひとはあやふきことなし、うまこそいとあやふけれ、されば馬をこそ問ふべけれ、これ人情なり、しかるにまづ人をとふらいかゞなるに、馬をとはざるはいと心なき人なり、但し人をとへるはさることなれば記しもすべきを、うまをとはぬが何のよきことがある、是まなびの子どもの、孔丘が不情をあらはせり、不問馬の三字を削りてよろし、
156 はやる[九六九]
時ありて世に盛にものすることを、俗言にはやるといふ、疫病のはやる、医師のはやるなど、よろづの物にも、事にもいへり、この言中昔の書にも見えて、抄出しおきたり、それは今時にいふとはいさゝか心ばへかはりて聞ゆ、其人のはやり給ひし時とあり、これはたゞ時にあひて栄え給ひし時といふことなり、今医師などのはやるといふは、その産業の盛に用ひらるゝをいふを、かれはたゞその身の栄えをいへるなり、
157 人のうまれつきさまざまある事[九七一]
人のうまれつきさまざまあるものなり、物の義理、事の利害など、すべて萬の事を、心にはよく思ひわきまへながら、口にはえいはぬ人もあり、また口にはよくいへども、しか行ふ事はえせぬひともあり、又口には得いはねども、よく行ふ人もあり、又口にはよくいへども、ふみには得かきいでぬひとあり、又口にはえいはねども、文にはよく書いづるひともあるなり、
158 紙の用[九七二]
紙の用、物をかく外にいと多し、まづ物をつゝむこと、拭ふこと、また箱籠のたぐひに張て器となす事、又かうより、かんでうよりといふ物にして、物を結ふことなどなり、これらのほかにも猶ことにふれて多かるべし、しかるにもろこしの紙はたゞ物かくにのみ宣しくて、件の事どもにはいといと不便にぞありける、かくて皇國には國々より出る紙の品いといと多くて、厚きうすき、強(コハ)きやはらかなる、さまざまあげもつくしがたけれど、物かくにはなほ唐の紙に及(シク)ものなし、人はいかゞおぼゆらむしらず、我はしかおぼゆるなり、
159 古より後世のまされる事[九七三]
古よりも、後世のまされること、萬の物にも、事にもおほし、其一つをいはむに、いにしへは、橘をならびなき物にしてめでつるを、近き世には、みかんといふ物ありて、此みかんにくらぶれば、橘は数にもあらずおされたり、その外かうじ、ゆ、くねんぼ、だいだいなどの、たぐひおほき中に、蜜柑ぞ味ことにすぐれて、中にも橘によく似てこよなくまされる物なり、此一つにておしはかるべし、或は古にはなくて、今はある物もおほく、いにしへはわろくて、今のはよきたぐひ多し、こりをもておもへば、今より後も又いかにあらむ、今に勝れる物おほく出来べし、今の心にて思へば、古はよろづに事たらずあかぬ事おほかりけむ、されどその世には、さはおぼえずやありけん、今より後なた、物の多くよきがいでこん世には、今をもしか思ふべけど、今の人、事たらずとおぼえぬが如し、
160 名所[九七五]
歌枕の國郡を論ずるに、ふるき歌によめるをよく考へて、その國郡を定むべし、後世の歌は、たゞ歌の趣意により来れる所をよむ故に、その国所をばしらずそらによめる故に、後世の歌はさらに據とするにたらず、題詠のみならず、後世の歌は、その所にいたりてよめるも取がたきことあり、いかにといふに、ふるき歌枕を、中昔の書に某国にありと注せるには、いみしく誤れる事のみ多きを、後の人、その誤れる注によりて、その國に其名所をつくりかまへて、或は萬葉によめる某山はこれなりなどいふたぐひおほきを、それも年を経ればその名のひろまりて、もとよりその所の如くなれるを、他国の歌人そこにいたりて、その名をきゝてよめるたぐひおほければなり、
161 教誡[九八〇]
もろこしの古書、ひたすら教誡をのみこちたくいへるは、いといとうるさし、人は教によりてよくなるものにあらず、みとより教をまつものにはあらぬを、あまりこちたくいましめ教るから、中々に姦曲詐偽のみまさる事をしらず、周公旦、あまりにこちたく定めたるゆゑに、周の末の乱をおこせり、戦国のころのひとの邪智ふかきは、みな周公がをしへたることなり、皇国の古書には、露ばかりもをしへがましき事見えず、此けじめをよく考ふべし、教誡の厳なるをよきことと心得たるは愚なり、
162 孟子[九八一]
孟子に、不孝ニ有三、無ヲ後為大ナリトといへり、然る時は、後あるが孝ならば、身を富貴にせむこそ大孝ならめ、しかるを、儒者の富貴を願はざるは、たゞおのが身を潔くせむとして、親を思はざるなり、これ又不孝といふべし、
163 如是我聞[九八三]
もろもろの佛經のはじめに、如是我聞といへること、さまざま故ある事のごといひなせれども、末々の文にかなはず、はじめにかくいへるは、いずれにしてもひがことにて、つたなきことなり、又如是我聞とこそいふべけれ、言のついでも、いとつたなし、これらのこと、天竺のなべてのならひにもあるべけれど、なほ翻訳者も拙し、すべて漢学びする人の、手をかけるにも、詩文を作れるにも、和習々々と、つねにいふことなるを、佛書の文には、又天竺習の多きなり、
164 佛道[九八五]
佛道は、たゞ悟と迷ひとをわきまへて、その悟を得るのみにして、その余の事はみな枝葉のみなり、かくてその悟といふ物、また無用の空論にして、露も世に益ある事なし、しかるを、世の人、その枝葉の方便にまどへるは、いかなる愚なる心ぞや、
165 世の人まことのみちにこゝろつかざる事[九八六]
もろこしの國には、道教といふもの、世々に盛に行はれて、大かた佛道とひとしきばかりなり、此道、老子を祖とはたつれども、老子が意とはいたく異にして、たゞあやしきたはふれわざのやうなることにて、そのむねをきはむれば、やうなきいたづらぎとなり、皇國に、此道のわたりまうでこざるは幸ひなり、しかはあれども、天ノ下の人の心、佛道と儒道とに、ことごとく奪はれてたるは、又なげかしき事なり、大かた天下の人、上中下、さかしき愚なる、おしなべて、奥山の山賤(ヤマガツ)までも、佛を信ぜざるは一人もなく、その中に、まれまれさすがに己が家の業と思ひ得て、神の道を尊ぶもあれど、さる人も、多くは佛意儒意なり、又神の道といふも、皆儒佛によりて設キまげたる物なれば、まことのみちは、大かた絶はてたるも同じなり、天ノ下大かた、件の如くなれば、たゞ何國も何國も、佛寺のみ栄えて、神社はいたく衰へまして、その衰へをうれふる人もなく、神はたゞ、病その外の祈りことのみに用ひられて、此道もたゞ、世ノ中の無用の物のごとく、たゞいにしへより有来れる事として、ひたふるに廃られぬといふのみなり、此道は、これ天下を治め、國を治め、先務要道なることをしれる人は、われいまだ、夢にも見きかず、いともいともかなしき事ならずや、
166 宋の代 明の代[九八七]
もろこしの國、宋の代にいたりては、よろづの事理屈三昧にして、國政につけても、何につけても、無用の空論のみなり、明の代の人は、又見識ひらけて、宋の理屈のわろき事をしり、又古より世々の物しり人の説の、誤り、心もつかざりしことなどをも、見つけたる人多きは、めずらしき事なり、されどつひにまことの道をばしる人なくして、その代終りぬるは、神の御國にあらざるがゆえなり、
167 天[九九〇]
から人の、何につけても天天といふは、神あることをしらざる故のひがごとなり、天は、たゞ神のまします國にこそあれ、心も、行ひも、道も、何も、ある物にはあらず、いはゆる天命、天道などといふは、みな神のなし賜ふことにこそあれ、又天地は、萬物を生育するものと思ふもひがごとなり、萬物の生育するも、みな神の御しわざなり、天地は、たゞ、神のこれを生育し給ふ場所のみなり、天地のこれを生育するにはあらず、から人の云く、天聖人に命じて、暴を征伐して、民を安ジせしむといへり、しからば、天のしわざは、正しき物にして、ひがことはなき物と聞えたるに、世ノ中には、理にたがひたる事の多きはいかに、その理にたがひたることあれども、たゞ天の命なればせんかたなしとのみいひて、その天のひがことするをば、とがめざるはいとをかい、天もひがことするならば、かの聖人に命じて、君を亡して、天下をとらせたるも、店のひがことといふべし、
168 國を治むるかたの学問[九九一]
國を治むる人の、がくもんし給はんとならば、をさまれる世には、宋学のかた、ものどほけれど、全てそこなひなし、近き世の古文辞家の学問は、ようせずは、いみしきあやまちを引いづべし、さて乱れたる世には、しばらく、もろもろの書はさしおきて、たゞ近昔の戦を記したる、軍書といふものをつねによく読べし、その世の人々の、よしあしさ、かしこきおろかなる、こゝろしわざ、たゝかひのしやうなどを、よくよく考ふべし、
169 漢籍の説と皇の古伝説とのたとへ[九九五]
漢ぶみの説は、まのあたり近き山を見るがごとく、皇國の上代の伝説は、十里廿里もかさなりたる、遠き山を見るがごとし、漢ぶみの説は、人情にかなひて、みな尤と思はるゝ事なり、皇國の上代神代などの故事は何の味もなく、たゞ浅はかに聞ゆるは、凡人の思ひはかる智の及ぶかぎりとは、はるかに遠きゆゑ、その理の聞えず、たゞ浅はかに聞ゆるなり、これかのとほき山は、たゞほかに山と見ゆるのみにて、その景色も何もみえず、見どころなきが如し、これ景色なきにあらず、人の目力の及ばぬ故なり、又漢籍の理ふかく尤に聞ゆるは、ひとのいへる説にて、人の情に近きなり、是かの近き山は、けしきよく見えわかれて、おもしろき見所あるがごとし、
170 米粒を佛法ぼさつなどいひならへる事[九九九]
穀物をおろそかにすまじきよしをいふ時に、米粒などを、佛法といひ、東國にては、菩薩といふ、これ大切にして、おろそかにすまじきよしなれば、然いふ心はいとありがたけれども、佛菩薩より尊き物はなしと心得たる心よりしかいふなれば、言はいとひがことなり、神とこそいふべけれ、まことに穀はうへもなき尊きものなれば、神とも神と申すべきものなり、
171 世の人のこざかしきこといふをよしとする事[一〇〇〇]
世の中のこざかしき人は、いはゆる道歌のさまなる俗歌をよみて、さとりがましき事をよくいふものなり、或は身こそやすけれなどいひて、わが心のさとりにて身のやすきよしをよむこと、みな儒佛にへつらひたる偽ごとなり、まことには、わが身を安しとして、足事をしれるものはなきものなり、たとへば人の齢など、七十に及ぶは、まことにまれなる事なれば、七十までも長らへては、はやく足れりと思ふべきことなれども、人みな猶たれりとは思はず、末のみじかき事をのみ歎きて、九十までも、百歳までも生(イカ)まほしくしふぞ、まことの情なりける、
172 假字[一〇〇一]
皇國の言を、古書どもに、漢文ざまにかけるは、假字といふものなくして、せむかたなく止事を得ざる故なり、今はかなといふ物ありて、自由にかゝるゝに、それを捨てて、不自由なる漢文をもて、かゝむとするは、いかなるひがこゝろえぞや、
173 から國の詞つかひ[一〇〇二]
皇國の言語にくらぶれば、唐の言語はいとあらき物なり、たとへば罕言といふこと、皇國言にては、まれにいふといふと、いふことまれなりといふと、心ばへ異なり、まれにいふは、言(イフ)といふこと主となりて、罕ながらもいふことのあることなり、いふことまれなりは、罕といふこと主となりて、いふことのまれなるなり、他の言も此たぐひ多し、すべてのことみなかくの如し、
174 佛經の文[一〇〇三]
すべての佛經は、文のいとつたなきものなり、一つに短くいひとらるゝ事を、くだくだしく同じことを長々おいへるなど、天竺國の物いひにてもあるべけれど、いとわづらはしうつたなし、
175 神のめぐみ[一〇〇四]
上は位たかく、一國一郡をもしりて、多くの人をしたがへ、世の人にうやまはれ、萬ゆたかにたのしくてすぐし、下はうゑず食ひ、さむからず着、やすく家(ヲ)る、これらみな、君のめぐみ、先祖のめぐみ、父母のめぐみなることはさるものにて、その本をたづぬれば、件の事どもよりはじめ、世にありとあるもろもろのこと、みなかみのみたまにあらずといふことなし、しかれば、世にあらむ人、神を尊まではわえあらぬ事なるを、平日(ツネ)になりぬることは、さしも心にとめず、忘れをるならひにて、君のめぐみ、先祖のめぐみをもさしもおもはず、もとより神の御たまなることは、みなわすれはてて、思ひもやらぬは、いといとかしこくあるまじき事なり、一日も、食物なくはいかにせむ、衣物なくはいかにせむ、これを思はば、君のめぐみ、先祖父母のめぐみをつねにわするべきにあらず、しかるを世の人、さることをばしらずおもはず、神をばたゞよそげに思ひ奉りて、たまたまさしあたりて祈る事などかなはねば、その神をうらみ奉りなどするは、いといとかたじけなきことなり、生れいづるより死ぬるまで、神の恵の中に居ながら、いさゝか心にかなはぬ事ありとても、これをうらみ奉るべきことかは、又祈ることきゝ給はねば、神は尊みてやくなき物のごと思ひなどするは、いかにぞや、かへすかえすも萬の事、ことごとく神のみたまなることを、平日(ツネ)にわするゝ事なくは、おのづからかみのたふとまではかなはぬ事を知べし、たとへば百両の金ほしき時に、秘との九十九両あたへて、一両たらざるが如し、そのあたへる人をば悦ぶべきか、恨むべきか、祈ることかなはねばとて、神をえうなき物にうらみ奉るは、九十九両あたへたらむ人を、えうなきものに思ひてうらむるがごとし、九十九両のめぐみを忘れて、今一両あたへざるをうらむるはいかに、
176 道[一〇〇五]
神の道は、世にすぐれたるまことの道なり、みな人しらではかなはぬ皇國のみちなるに、わづかに糸筋ばかりよにのこりて、たゞまことならぬ、他の國の道々のみはびこれるは、いかなることにか、まがつひの神の御こゝろは、すべなき物なりけり、
世の学者、ことの疑はしきを、から画にしかしか見えたりといへば、疑はず信ずるはいとをこなり、すべて漢籍、うきたる事、ひがこと、そら言いと多し、その言よきにまどひて、みだりに信ずべきにあらず、
149 世の中の萬の事は皆神の御しわざなる事[九五九]
世の中のよろづのことはみなあやしきを、これ奇しく妙なる神の御しわざなることをえしらずして、己がおしはかりの理を以ていふはいとをこなり、いかにともしられぬ事を理を以てとかくいふは、から人のくせなり、そのいふところの理は、いかさまにもいへばいはるゝ物ぞ、かれいにしへのから人のいひおける理、後世にいたりてひがことなることのあらはれたる事おほし、またつひに理のはかりがたきことにあへば、これを天といひてのがるゝ、みな神ある事をしらざるゆゑなり、
150 聖人を尊む事[九六〇]
世々のもろこし人おしなべて、かの國の聖人といふ物を尊み信ずる中には、実に尊みしんずるひともあるべく、又こゝろにはいかにぞや思ふことあれども、聖人にたがひては世の人のそしりてうけぬことなるによりて、尊み信ずるかほして、世にしたがへるもありげに見ゆるなり、又もろもろの聖人どものなかに、孔子は、かの國の王にあらず、もはらその道の人なるがゆゑに、あるが中に此人をばことに尊み信ずめるは、これつとめてこれをほめたてて、その道を張むとするなり、
151 ト筮[九六一]
もろこしの國とても、いと上代には、後世のごとく、萬の事、己がおしはかりの理を以て定むる事は、さしもあらざりしこと、ト筮といふ物あるをもてしるべし、ト筮は己が心にさだめがたき事を、神にこひてその教えをうけて定むるわざなり、ト筮にいづるは、かみのをしへなり、然るを後世のごとく、己がこころをもて、物の理をはかりて、さだむることは、大かた周公旦といふさかしら人より、盛んにその風になれるなり、
152 から人の語かしこくいひとれること[九六三]
むかしより、世々に、もろこしひとのいへる、名たかき語どもをおもふに、たゞかしこく物にたとへもし、又たゞにても、おかしくいひとれるのみにこそあれ、そのこゝろは、学文もせぬつねの人も、心かしこきは、大かたみなもとよりよく心得たる事にて、さしもこゝろに及ばずめづらしき事はなし、されどよくいひとれるがかしこさに、げにさこそはあれと、みな人は感ずるなり、
153 論語[九六四]
論語の雍也篇の朱注に、仲弓蓋シ未喩夫子可字可字之意云々といへり、朱熹、つねに格物致知を教ふ、しかるに仲弓は孔丘が高弟なるに、いまだ可の字の意をだに喩らぬは、いかでか致知えを得む、孔丘が高弟すら、かくに如くならむには、常人はいかでかこれを得ん、大かた朱学の牽強付会みなかくの如し、
154 又[九六七]
同書に子曰、孰レカ謂微生高ヲ直シト、或乞ヘルニ醯ヲ焉、乞テ諸其隣ニ而与フ之ヲとあり、聖人の教えの刻酷なることかくの如し、これらはたゞいさゝかの事にて、さしも不直といふべきほどの事にあらず、かほどの事さえ、不直といひてとがむるは、あまりのことなり、又たとひ此事は、実に不直にもせよ、いさゝかなる此一事によりてその人を不直なりと定むるも、いといとあたらぬ事なり、すべてよき人にもあやまちわろき事はあるものなり、あしき人にもよき事もあるものなるを、たゞ一事の善悪によりて、その人のよしあしを定むるは、聖人の道のくせにて、ひがことなり、
155 又[九六八]
同書に、厩焚タリ、子退テ朝ヨリ曰、傷人乎、不問馬ヲ、これ甚いかがなり、すべての人の家の焚んにも、人はさしもやかるゝ物にあらず、馬はよくやかるゝものなり、まして馬屋のやけんには、ひとはあやふきことなし、うまこそいとあやふけれ、されば馬をこそ問ふべけれ、これ人情なり、しかるにまづ人をとふらいかゞなるに、馬をとはざるはいと心なき人なり、但し人をとへるはさることなれば記しもすべきを、うまをとはぬが何のよきことがある、是まなびの子どもの、孔丘が不情をあらはせり、不問馬の三字を削りてよろし、
156 はやる[九六九]
時ありて世に盛にものすることを、俗言にはやるといふ、疫病のはやる、医師のはやるなど、よろづの物にも、事にもいへり、この言中昔の書にも見えて、抄出しおきたり、それは今時にいふとはいさゝか心ばへかはりて聞ゆ、其人のはやり給ひし時とあり、これはたゞ時にあひて栄え給ひし時といふことなり、今医師などのはやるといふは、その産業の盛に用ひらるゝをいふを、かれはたゞその身の栄えをいへるなり、
157 人のうまれつきさまざまある事[九七一]
人のうまれつきさまざまあるものなり、物の義理、事の利害など、すべて萬の事を、心にはよく思ひわきまへながら、口にはえいはぬ人もあり、また口にはよくいへども、しか行ふ事はえせぬひともあり、又口には得いはねども、よく行ふ人もあり、又口にはよくいへども、ふみには得かきいでぬひとあり、又口にはえいはねども、文にはよく書いづるひともあるなり、
158 紙の用[九七二]
紙の用、物をかく外にいと多し、まづ物をつゝむこと、拭ふこと、また箱籠のたぐひに張て器となす事、又かうより、かんでうよりといふ物にして、物を結ふことなどなり、これらのほかにも猶ことにふれて多かるべし、しかるにもろこしの紙はたゞ物かくにのみ宣しくて、件の事どもにはいといと不便にぞありける、かくて皇國には國々より出る紙の品いといと多くて、厚きうすき、強(コハ)きやはらかなる、さまざまあげもつくしがたけれど、物かくにはなほ唐の紙に及(シク)ものなし、人はいかゞおぼゆらむしらず、我はしかおぼゆるなり、
159 古より後世のまされる事[九七三]
古よりも、後世のまされること、萬の物にも、事にもおほし、其一つをいはむに、いにしへは、橘をならびなき物にしてめでつるを、近き世には、みかんといふ物ありて、此みかんにくらぶれば、橘は数にもあらずおされたり、その外かうじ、ゆ、くねんぼ、だいだいなどの、たぐひおほき中に、蜜柑ぞ味ことにすぐれて、中にも橘によく似てこよなくまされる物なり、此一つにておしはかるべし、或は古にはなくて、今はある物もおほく、いにしへはわろくて、今のはよきたぐひ多し、こりをもておもへば、今より後も又いかにあらむ、今に勝れる物おほく出来べし、今の心にて思へば、古はよろづに事たらずあかぬ事おほかりけむ、されどその世には、さはおぼえずやありけん、今より後なた、物の多くよきがいでこん世には、今をもしか思ふべけど、今の人、事たらずとおぼえぬが如し、
160 名所[九七五]
歌枕の國郡を論ずるに、ふるき歌によめるをよく考へて、その國郡を定むべし、後世の歌は、たゞ歌の趣意により来れる所をよむ故に、その国所をばしらずそらによめる故に、後世の歌はさらに據とするにたらず、題詠のみならず、後世の歌は、その所にいたりてよめるも取がたきことあり、いかにといふに、ふるき歌枕を、中昔の書に某国にありと注せるには、いみしく誤れる事のみ多きを、後の人、その誤れる注によりて、その國に其名所をつくりかまへて、或は萬葉によめる某山はこれなりなどいふたぐひおほきを、それも年を経ればその名のひろまりて、もとよりその所の如くなれるを、他国の歌人そこにいたりて、その名をきゝてよめるたぐひおほければなり、
161 教誡[九八〇]
もろこしの古書、ひたすら教誡をのみこちたくいへるは、いといとうるさし、人は教によりてよくなるものにあらず、みとより教をまつものにはあらぬを、あまりこちたくいましめ教るから、中々に姦曲詐偽のみまさる事をしらず、周公旦、あまりにこちたく定めたるゆゑに、周の末の乱をおこせり、戦国のころのひとの邪智ふかきは、みな周公がをしへたることなり、皇国の古書には、露ばかりもをしへがましき事見えず、此けじめをよく考ふべし、教誡の厳なるをよきことと心得たるは愚なり、
162 孟子[九八一]
孟子に、不孝ニ有三、無ヲ後為大ナリトといへり、然る時は、後あるが孝ならば、身を富貴にせむこそ大孝ならめ、しかるを、儒者の富貴を願はざるは、たゞおのが身を潔くせむとして、親を思はざるなり、これ又不孝といふべし、
163 如是我聞[九八三]
もろもろの佛經のはじめに、如是我聞といへること、さまざま故ある事のごといひなせれども、末々の文にかなはず、はじめにかくいへるは、いずれにしてもひがことにて、つたなきことなり、又如是我聞とこそいふべけれ、言のついでも、いとつたなし、これらのこと、天竺のなべてのならひにもあるべけれど、なほ翻訳者も拙し、すべて漢学びする人の、手をかけるにも、詩文を作れるにも、和習々々と、つねにいふことなるを、佛書の文には、又天竺習の多きなり、
164 佛道[九八五]
佛道は、たゞ悟と迷ひとをわきまへて、その悟を得るのみにして、その余の事はみな枝葉のみなり、かくてその悟といふ物、また無用の空論にして、露も世に益ある事なし、しかるを、世の人、その枝葉の方便にまどへるは、いかなる愚なる心ぞや、
165 世の人まことのみちにこゝろつかざる事[九八六]
もろこしの國には、道教といふもの、世々に盛に行はれて、大かた佛道とひとしきばかりなり、此道、老子を祖とはたつれども、老子が意とはいたく異にして、たゞあやしきたはふれわざのやうなることにて、そのむねをきはむれば、やうなきいたづらぎとなり、皇國に、此道のわたりまうでこざるは幸ひなり、しかはあれども、天ノ下の人の心、佛道と儒道とに、ことごとく奪はれてたるは、又なげかしき事なり、大かた天下の人、上中下、さかしき愚なる、おしなべて、奥山の山賤(ヤマガツ)までも、佛を信ぜざるは一人もなく、その中に、まれまれさすがに己が家の業と思ひ得て、神の道を尊ぶもあれど、さる人も、多くは佛意儒意なり、又神の道といふも、皆儒佛によりて設キまげたる物なれば、まことのみちは、大かた絶はてたるも同じなり、天ノ下大かた、件の如くなれば、たゞ何國も何國も、佛寺のみ栄えて、神社はいたく衰へまして、その衰へをうれふる人もなく、神はたゞ、病その外の祈りことのみに用ひられて、此道もたゞ、世ノ中の無用の物のごとく、たゞいにしへより有来れる事として、ひたふるに廃られぬといふのみなり、此道は、これ天下を治め、國を治め、先務要道なることをしれる人は、われいまだ、夢にも見きかず、いともいともかなしき事ならずや、
166 宋の代 明の代[九八七]
もろこしの國、宋の代にいたりては、よろづの事理屈三昧にして、國政につけても、何につけても、無用の空論のみなり、明の代の人は、又見識ひらけて、宋の理屈のわろき事をしり、又古より世々の物しり人の説の、誤り、心もつかざりしことなどをも、見つけたる人多きは、めずらしき事なり、されどつひにまことの道をばしる人なくして、その代終りぬるは、神の御國にあらざるがゆえなり、
167 天[九九〇]
から人の、何につけても天天といふは、神あることをしらざる故のひがごとなり、天は、たゞ神のまします國にこそあれ、心も、行ひも、道も、何も、ある物にはあらず、いはゆる天命、天道などといふは、みな神のなし賜ふことにこそあれ、又天地は、萬物を生育するものと思ふもひがごとなり、萬物の生育するも、みな神の御しわざなり、天地は、たゞ、神のこれを生育し給ふ場所のみなり、天地のこれを生育するにはあらず、から人の云く、天聖人に命じて、暴を征伐して、民を安ジせしむといへり、しからば、天のしわざは、正しき物にして、ひがことはなき物と聞えたるに、世ノ中には、理にたがひたる事の多きはいかに、その理にたがひたることあれども、たゞ天の命なればせんかたなしとのみいひて、その天のひがことするをば、とがめざるはいとをかい、天もひがことするならば、かの聖人に命じて、君を亡して、天下をとらせたるも、店のひがことといふべし、
168 國を治むるかたの学問[九九一]
國を治むる人の、がくもんし給はんとならば、をさまれる世には、宋学のかた、ものどほけれど、全てそこなひなし、近き世の古文辞家の学問は、ようせずは、いみしきあやまちを引いづべし、さて乱れたる世には、しばらく、もろもろの書はさしおきて、たゞ近昔の戦を記したる、軍書といふものをつねによく読べし、その世の人々の、よしあしさ、かしこきおろかなる、こゝろしわざ、たゝかひのしやうなどを、よくよく考ふべし、
169 漢籍の説と皇の古伝説とのたとへ[九九五]
漢ぶみの説は、まのあたり近き山を見るがごとく、皇國の上代の伝説は、十里廿里もかさなりたる、遠き山を見るがごとし、漢ぶみの説は、人情にかなひて、みな尤と思はるゝ事なり、皇國の上代神代などの故事は何の味もなく、たゞ浅はかに聞ゆるは、凡人の思ひはかる智の及ぶかぎりとは、はるかに遠きゆゑ、その理の聞えず、たゞ浅はかに聞ゆるなり、これかのとほき山は、たゞほかに山と見ゆるのみにて、その景色も何もみえず、見どころなきが如し、これ景色なきにあらず、人の目力の及ばぬ故なり、又漢籍の理ふかく尤に聞ゆるは、ひとのいへる説にて、人の情に近きなり、是かの近き山は、けしきよく見えわかれて、おもしろき見所あるがごとし、
170 米粒を佛法ぼさつなどいひならへる事[九九九]
穀物をおろそかにすまじきよしをいふ時に、米粒などを、佛法といひ、東國にては、菩薩といふ、これ大切にして、おろそかにすまじきよしなれば、然いふ心はいとありがたけれども、佛菩薩より尊き物はなしと心得たる心よりしかいふなれば、言はいとひがことなり、神とこそいふべけれ、まことに穀はうへもなき尊きものなれば、神とも神と申すべきものなり、
171 世の人のこざかしきこといふをよしとする事[一〇〇〇]
世の中のこざかしき人は、いはゆる道歌のさまなる俗歌をよみて、さとりがましき事をよくいふものなり、或は身こそやすけれなどいひて、わが心のさとりにて身のやすきよしをよむこと、みな儒佛にへつらひたる偽ごとなり、まことには、わが身を安しとして、足事をしれるものはなきものなり、たとへば人の齢など、七十に及ぶは、まことにまれなる事なれば、七十までも長らへては、はやく足れりと思ふべきことなれども、人みな猶たれりとは思はず、末のみじかき事をのみ歎きて、九十までも、百歳までも生(イカ)まほしくしふぞ、まことの情なりける、
172 假字[一〇〇一]
皇國の言を、古書どもに、漢文ざまにかけるは、假字といふものなくして、せむかたなく止事を得ざる故なり、今はかなといふ物ありて、自由にかゝるゝに、それを捨てて、不自由なる漢文をもて、かゝむとするは、いかなるひがこゝろえぞや、
173 から國の詞つかひ[一〇〇二]
皇國の言語にくらぶれば、唐の言語はいとあらき物なり、たとへば罕言といふこと、皇國言にては、まれにいふといふと、いふことまれなりといふと、心ばへ異なり、まれにいふは、言(イフ)といふこと主となりて、罕ながらもいふことのあることなり、いふことまれなりは、罕といふこと主となりて、いふことのまれなるなり、他の言も此たぐひ多し、すべてのことみなかくの如し、
174 佛經の文[一〇〇三]
すべての佛經は、文のいとつたなきものなり、一つに短くいひとらるゝ事を、くだくだしく同じことを長々おいへるなど、天竺國の物いひにてもあるべけれど、いとわづらはしうつたなし、
175 神のめぐみ[一〇〇四]
上は位たかく、一國一郡をもしりて、多くの人をしたがへ、世の人にうやまはれ、萬ゆたかにたのしくてすぐし、下はうゑず食ひ、さむからず着、やすく家(ヲ)る、これらみな、君のめぐみ、先祖のめぐみ、父母のめぐみなることはさるものにて、その本をたづぬれば、件の事どもよりはじめ、世にありとあるもろもろのこと、みなかみのみたまにあらずといふことなし、しかれば、世にあらむ人、神を尊まではわえあらぬ事なるを、平日(ツネ)になりぬることは、さしも心にとめず、忘れをるならひにて、君のめぐみ、先祖のめぐみをもさしもおもはず、もとより神の御たまなることは、みなわすれはてて、思ひもやらぬは、いといとかしこくあるまじき事なり、一日も、食物なくはいかにせむ、衣物なくはいかにせむ、これを思はば、君のめぐみ、先祖父母のめぐみをつねにわするべきにあらず、しかるを世の人、さることをばしらずおもはず、神をばたゞよそげに思ひ奉りて、たまたまさしあたりて祈る事などかなはねば、その神をうらみ奉りなどするは、いといとかたじけなきことなり、生れいづるより死ぬるまで、神の恵の中に居ながら、いさゝか心にかなはぬ事ありとても、これをうらみ奉るべきことかは、又祈ることきゝ給はねば、神は尊みてやくなき物のごと思ひなどするは、いかにぞや、かへすかえすも萬の事、ことごとく神のみたまなることを、平日(ツネ)にわするゝ事なくは、おのづからかみのたふとまではかなはぬ事を知べし、たとへば百両の金ほしき時に、秘との九十九両あたへて、一両たらざるが如し、そのあたへる人をば悦ぶべきか、恨むべきか、祈ることかなはねばとて、神をえうなき物にうらみ奉るは、九十九両あたへたらむ人を、えうなきものに思ひてうらむるがごとし、九十九両のめぐみを忘れて、今一両あたへざるをうらむるはいかに、
176 道[一〇〇五]
神の道は、世にすぐれたるまことの道なり、みな人しらではかなはぬ皇國のみちなるに、わづかに糸筋ばかりよにのこりて、たゞまことならぬ、他の國の道々のみはびこれるは、いかなることにか、まがつひの神の御こゝろは、すべなき物なりけり、